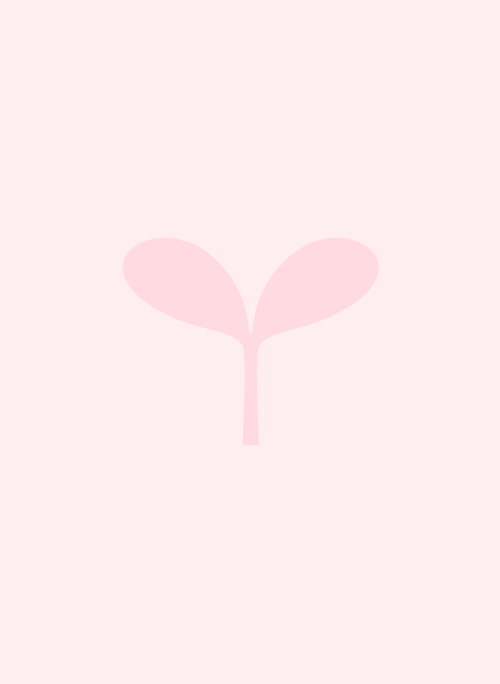あたしは思いっきり怪訝な声を出して、美鶴を見上げた。
…けど、その顔を今となっては覚えていない。
「あたしが美鶴を置いていく?」
「うん。
俺なんか、声かけられない。」
「何言ってるの。
美鶴があたしを遠ざけるんでしょう。」
「俺が、郁を?」
信じられないといった顔で、美鶴はあたしを見下ろした。
「なんでそんなこと言うの。」
「だって、美鶴はあたしにも素っ気ないんだもの。
比較的仲いいと思ってたのに、声かけてもあんまりしゃべらないもの。」
「それは、郁を待ってる人がいてあんまり引き留められなかったから。」
「そんなことないでしょ。」
はあっとあたしは大きなため息をついた。
あたしが一人のときに話しかけても、美鶴は「うん」か「そう」しか言わない。
あたしはこんなにも美鶴と一緒にいたいのに、美鶴はさり気なく突っぱねる。
「…今は話してる。」
「今、だけでしょ。
学校ではあたしはクラスメイト以下の女子に戻るのよ。」
黄色い声を上げて、美鶴に群がっている女子がうらやましくて仕方がない。
あたしよりも長い間、美鶴といるなんて、うらやましいったらない。
美鶴は困った顔であたしを引っ張った。
「そんなことない。」
「ある。」
「クラスメイト以下の女子って、俺が郁をそんな風に思ってるとでも?」
…けど、その顔を今となっては覚えていない。
「あたしが美鶴を置いていく?」
「うん。
俺なんか、声かけられない。」
「何言ってるの。
美鶴があたしを遠ざけるんでしょう。」
「俺が、郁を?」
信じられないといった顔で、美鶴はあたしを見下ろした。
「なんでそんなこと言うの。」
「だって、美鶴はあたしにも素っ気ないんだもの。
比較的仲いいと思ってたのに、声かけてもあんまりしゃべらないもの。」
「それは、郁を待ってる人がいてあんまり引き留められなかったから。」
「そんなことないでしょ。」
はあっとあたしは大きなため息をついた。
あたしが一人のときに話しかけても、美鶴は「うん」か「そう」しか言わない。
あたしはこんなにも美鶴と一緒にいたいのに、美鶴はさり気なく突っぱねる。
「…今は話してる。」
「今、だけでしょ。
学校ではあたしはクラスメイト以下の女子に戻るのよ。」
黄色い声を上げて、美鶴に群がっている女子がうらやましくて仕方がない。
あたしよりも長い間、美鶴といるなんて、うらやましいったらない。
美鶴は困った顔であたしを引っ張った。
「そんなことない。」
「ある。」
「クラスメイト以下の女子って、俺が郁をそんな風に思ってるとでも?」
あたしは勢いよく頷いた。
哀しそうな美鶴の頬に、雪が張り付いた。
それを拭おうともせず、美鶴はあたしを見つめていた。
「…それは、郁がそう思ってるからじゃないの?」
「あたしが?」
あたしは一瞬、美鶴が言ったことが信じられなかった。
あたしがそんなこと思ってるとでも?
「信じらんない。」
「かお…。」
「馬鹿じゃないの。
あたし、美鶴にそんなこと言われるなんて思ってもみなかった…!」
あたしが美鶴に対してこんなに怒ったのは、あれが初めてだったと思う。
もう何も話したくないと思ったのは、あれが初めてだったはず。
あたしは美鶴の顔を見もせずに、勢いよく立ち上がって背を向けた。
怒っているのに、胸が痛かった。
泣き出したいほど、つらかった。
あれは、怒りというより絶望だった気がする。
郁、と美鶴が立ち上がる音がした。
いつもなら、美鶴が発する「カオル」という音に立ち止らないなんてことはなかったのに。
あたしは速度を速めた。
帰って、気持ちを整理したかった。
哀しそうな美鶴の頬に、雪が張り付いた。
それを拭おうともせず、美鶴はあたしを見つめていた。
「…それは、郁がそう思ってるからじゃないの?」
「あたしが?」
あたしは一瞬、美鶴が言ったことが信じられなかった。
あたしがそんなこと思ってるとでも?
「信じらんない。」
「かお…。」
「馬鹿じゃないの。
あたし、美鶴にそんなこと言われるなんて思ってもみなかった…!」
あたしが美鶴に対してこんなに怒ったのは、あれが初めてだったと思う。
もう何も話したくないと思ったのは、あれが初めてだったはず。
あたしは美鶴の顔を見もせずに、勢いよく立ち上がって背を向けた。
怒っているのに、胸が痛かった。
泣き出したいほど、つらかった。
あれは、怒りというより絶望だった気がする。
郁、と美鶴が立ち上がる音がした。
いつもなら、美鶴が発する「カオル」という音に立ち止らないなんてことはなかったのに。
あたしは速度を速めた。
帰って、気持ちを整理したかった。
のに。
「郁…。」
いきなり耳元で美鶴が囁く声がした。
びくりと肩が竦み、足が止まった隙にがっちりと抱きとめられる。
自分の腰に回っている手が、肩に置かれている美鶴の頭が、信じられなかった。
「待ってよ…。」
掠れた声で、美鶴は囁いた。
「俺、郁に嫌われたの?」
なんでそんなこと訊くの。
「もう、顔も見たくない?」
あたしの脳は嵐を起こしていて、マトモに答えられなかった。
なのに、美鶴の声は今もはっきりと覚えている。
「郁…。」
ぎゅっと、背中にくっつく美鶴。
あたしは棒立ちしたままだった。
しばらくしてから、美鶴はゆっくりとあたしを放した。
そして正面に回り込み、あたしとしっかり目を合わせる。
「嫌い…。」
「…ホント?」
「うん。
…でも、好きのがおっきい。」
そう言うと、すごく傷ついた顔をした美鶴がほっと息をはいた。
「郁…。」
いきなり耳元で美鶴が囁く声がした。
びくりと肩が竦み、足が止まった隙にがっちりと抱きとめられる。
自分の腰に回っている手が、肩に置かれている美鶴の頭が、信じられなかった。
「待ってよ…。」
掠れた声で、美鶴は囁いた。
「俺、郁に嫌われたの?」
なんでそんなこと訊くの。
「もう、顔も見たくない?」
あたしの脳は嵐を起こしていて、マトモに答えられなかった。
なのに、美鶴の声は今もはっきりと覚えている。
「郁…。」
ぎゅっと、背中にくっつく美鶴。
あたしは棒立ちしたままだった。
しばらくしてから、美鶴はゆっくりとあたしを放した。
そして正面に回り込み、あたしとしっかり目を合わせる。
「嫌い…。」
「…ホント?」
「うん。
…でも、好きのがおっきい。」
そう言うと、すごく傷ついた顔をした美鶴がほっと息をはいた。
そして、あたしの頬を愛おしそうに撫で、そっと唇を重ねた。
抱きしめられたときは頭が真っ白になったのに、キスされたときは妙に冷静だった。
「嫌がんないんだ?」
悪戯に問う美鶴の声が、耳にこそばゆかった。
どこで覚えたのか、美鶴のキスは上手かった…と思う。
というのも、あたしのファーストキスは奴だったからだ。
後にも先にも、美鶴だけ。
だから上手か下手かなんてわからなかったけど、あたしの脳はショートして、何も考えられなくなった。
そしていつの間にか、あたしは美鶴の制服に掴まって、身体を預けていた。
今考えたらよくもまぁ、公園のど真ん中でそんな恥ずかしいことを堂々とやれたものだと思う。
でも、それくらい気持ちよかった。
一通りあたしは美鶴に口内を堪能された後、ようやく身体を解放された。
恐る恐る目を開けると、いつもは透き通るくらいに白い美鶴の頬がうっすらピンクに上気していた。
きっと、あたしもだっただろうけど。
そこから言葉は一言も交わさなかった。
美鶴はあたしの手を引いて歩き出し、それぞれの家へと続く道で別れた。
別れ際、美鶴が熱のこもった目であたしを見て微笑まなかったら、さっきの出来事は夢だったんじゃないかと疑うくらい、あたし達は愛の告白らしきものを交わさなかった。
抱きしめられたときは頭が真っ白になったのに、キスされたときは妙に冷静だった。
「嫌がんないんだ?」
悪戯に問う美鶴の声が、耳にこそばゆかった。
どこで覚えたのか、美鶴のキスは上手かった…と思う。
というのも、あたしのファーストキスは奴だったからだ。
後にも先にも、美鶴だけ。
だから上手か下手かなんてわからなかったけど、あたしの脳はショートして、何も考えられなくなった。
そしていつの間にか、あたしは美鶴の制服に掴まって、身体を預けていた。
今考えたらよくもまぁ、公園のど真ん中でそんな恥ずかしいことを堂々とやれたものだと思う。
でも、それくらい気持ちよかった。
一通りあたしは美鶴に口内を堪能された後、ようやく身体を解放された。
恐る恐る目を開けると、いつもは透き通るくらいに白い美鶴の頬がうっすらピンクに上気していた。
きっと、あたしもだっただろうけど。
そこから言葉は一言も交わさなかった。
美鶴はあたしの手を引いて歩き出し、それぞれの家へと続く道で別れた。
別れ際、美鶴が熱のこもった目であたしを見て微笑まなかったら、さっきの出来事は夢だったんじゃないかと疑うくらい、あたし達は愛の告白らしきものを交わさなかった。
そして、今。
あたし達は高校三年生になった。
夏休みも目前。
みんな暑い気候にだらけきっている。
それはあたしも例外ではなく、今も机に突っ伏している。
ひんやりとした天板が気持ちいい。
あたしは目を開けて、こっそりと美鶴を窺った。
白いシャツが、太陽に反射している。
相変わらずの長髪(とはいっても肩にはついていないが)のくせに、その横顔は涼しげだった。
あたしはというと、髪を結ってポニーテールにしているのに、暑くて汗だくだ。
あれから、一度も美鶴はあたしに触らない。
学校で顔を合わせたときもいつもと変わらなかった。
そしてその状態は今も続いていて、さりげなくあたしをイラつかせている。
破廉恥ながら、もう一回キスしてほしいなんて思ったり。
そんな自分が恥ずかしくて、きっと美鶴を睨んでみた。
…でもやっぱり好きだなぁ。
さらさらと風に揺れる髪を、梳いてみたい。
あの日、髪を指に絡ませてキスに没頭して以来、あの髪には触っていない。
と、美鶴がこっちを振り向いた。
目があって、首を傾げられる。
…あぁ、もう。
可愛いじゃないですか。
いーっ、と歯をむき出してやると、美鶴はこらえきれなかったようでぷっと吹き出した。
くっくっと口元を押さえて立ち上がり、あたしの机の横を通り過ぎ際、「可愛いよ。」と囁いていく。
あたしはかあっと赤くなった。
今、可愛いって言った?
…なんだか初めてな気がする。
あの日から一度もそういうことをしなかったくせに、今になってあたしをときめかせる。
ずるい、と思った。
美鶴は、ずるい。
いつもいつも、自分は優位な立場を崩さない。
焦らされているのは、あたしだけだ。
教科書を抱えて戻ってきた美鶴は、今度は何もしなかった。
…期待外れ。
あたしは悔しくなって、俯いた。
くっくっと口元を押さえて立ち上がり、あたしの机の横を通り過ぎ際、「可愛いよ。」と囁いていく。
あたしはかあっと赤くなった。
今、可愛いって言った?
…なんだか初めてな気がする。
あの日から一度もそういうことをしなかったくせに、今になってあたしをときめかせる。
ずるい、と思った。
美鶴は、ずるい。
いつもいつも、自分は優位な立場を崩さない。
焦らされているのは、あたしだけだ。
教科書を抱えて戻ってきた美鶴は、今度は何もしなかった。
…期待外れ。
あたしは悔しくなって、俯いた。
帰り道。
久々に一緒に帰った。
少し日が落ちて涼しくなった夕時、あたしと美鶴は並んで歩いた。
「まだ進路調査票、出してないんだって?」
嫌な顔をするだろうなとわかっていながら、あたしは敢えて切り出した。
するとやっぱり美鶴は苦い顔をして、「郁には関係ないよ。」と言った。
だから、あるんだってば。
これ以上美鶴がいじめられるのを見ていたくないのよ。
「美鶴はさ、どうしたいの?」
あたしは努めて明るい口調で言った。
美鶴は無表情で空を見上げる。
「さぁ。」
「さぁって…。
夢、あるの?」
しばらく、美鶴は黙った。
無視されたのかと思った頃、ようやく口を開く。
「俺は、普通の人生を歩みたい。」
「普通の、人生?」
「うん。
たとえば、サラリーマンにでもなって、結婚して。」
そうすればいいじゃない、と言うと、美鶴は他人事のように「そうだね」と言った。
「親は何て言ってるの?
進学か仕事、どっちにしろって?」
どうやらそれは触れてはいけなかったことらしい。
みるみる、美鶴の顔が強張った。
本人はそれに気付いていないようで、必死になにか答えを探している。
あたしは慌てて話題を変えた。
「ゴメン、そういえばさ…。」
焦ってペラペラと一人でしゃべっていると、美鶴の顔色がよくなってきた。
…美鶴、なんでさっきあんな顔したの?
あたしは頻繁に美鶴の顔色を窺った。
「郁。」
「ん?」
「なんでもない。」
「何よ。」
何度訊いても、美鶴はなんでもないと笑った。
変なの。
何か言いたいことがあるなら、言えばいいのに。
もう6年の付き合いになる。
中学の最初の方はあまりしゃべらなかったけど、最近は打ち解けてくれてると思ってるのに。
…冬に話したときのことが思い返されて、あたしは慌てて頭を振った。
そんなあたしを、美鶴は不思議そうな顔で見つめていた。
本人はそれに気付いていないようで、必死になにか答えを探している。
あたしは慌てて話題を変えた。
「ゴメン、そういえばさ…。」
焦ってペラペラと一人でしゃべっていると、美鶴の顔色がよくなってきた。
…美鶴、なんでさっきあんな顔したの?
あたしは頻繁に美鶴の顔色を窺った。
「郁。」
「ん?」
「なんでもない。」
「何よ。」
何度訊いても、美鶴はなんでもないと笑った。
変なの。
何か言いたいことがあるなら、言えばいいのに。
もう6年の付き合いになる。
中学の最初の方はあまりしゃべらなかったけど、最近は打ち解けてくれてると思ってるのに。
…冬に話したときのことが思い返されて、あたしは慌てて頭を振った。
そんなあたしを、美鶴は不思議そうな顔で見つめていた。
この作家の他の作品
表紙を見る
母方の祖父を知らずに育った紀歩。
母に聞いても、父の顔を知らないという。
祖母に聞いても、旦那のことを話そうとはしない。
しかし、ある日。
病に臥して死の淵をさまよっている祖母に呼ばれ、ついに紀歩は自らの祖父の秘密を知る。
「紀歩、貴方のおじいちゃんはねぇ…。」
2012.6.5
表紙を見る
~・~・~・~・~・~
とある小国に、美しいと評判の姫がいた。
彼女はすべてにおいて、秀でていて
それでもって神の御子であるという。
~・~・~・~・~・~
take a look,and then you can see...
国を揺るがす秘密を持った姫と、若い騎士との、
哀しい恋物語。
2011.7.8
-------------
ありさちゃんちゃん さんへ
レビュー、ありがとうございます!
久し振りにログインするとあらビックリな嬉しい★の表示が(笑)!
今、他のものを(激遅ですが)書いているので、それを終えたらリクエストにお応えしたいと思います<(_ _)>
これを見て頂けているかわかりませんが…
お礼をと思い、お返事書かせていただきました。
ありがとうございました(^^)
表紙を見る
もし、飼っている猫に、
人の魂が乗り移ったら?
どうしますか?
もし、それが、
初恋の相手の魂だとしたら…?
ごく普通のOL、嶌子が
かつて愛した人の魂が乗り移った愛猫と過ごした
切なく幸せな1週間
「…これ、ホントなわけ?」
「信じるしかないだろ、この状況。」
本当に、貴方なの?
吾が輩は……
2010.10.16
↓
2010.10.24
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…