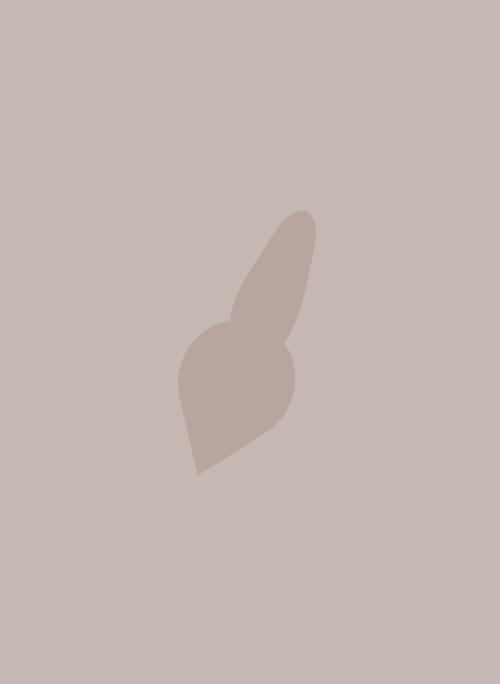「授業中メールするから、サイレント」
「うん、分かった」
教室へ入ると、案の定ユキが話しかけてきた。
一番後ろの席の私の前がユキだから、授業前はいつもこんな風に話している。
「拓と来てたでしょ」
「・・・なんで知ってるの」
「付き合ってるんだ?」
「・・・別にそんなんじゃないから。ほら、授業始まるよ」
先生が教室に入ってきても、それでもしつこく問いただしてくる。
「応援してるよ、あたしは」
応援されたって、まだ何も始まっていない。
ぼーっと時計の秒針を見ていると、机の中に隠してある携帯が光った。
周りを見渡すと、みんなノートに向かって黒板に書かれた文字を書いていた。
そっと携帯を開いて、メールを確認する。
『何してる?』
途端に、自分の笑い声が教室内に響く。
周りの視線が向けられて口を押さえ、俯き加減で返信を打つ。
『授業中です』
返信を送ってすぐに返事が送られてくる。
『そういえば、満月の画像どうした?』
『ちゃんと待受に設定したよ』
『いいことあるかも』
『でも満月は星が見たい』
『星?』
『流れ星を見てみたい』
「うん、分かった」
教室へ入ると、案の定ユキが話しかけてきた。
一番後ろの席の私の前がユキだから、授業前はいつもこんな風に話している。
「拓と来てたでしょ」
「・・・なんで知ってるの」
「付き合ってるんだ?」
「・・・別にそんなんじゃないから。ほら、授業始まるよ」
先生が教室に入ってきても、それでもしつこく問いただしてくる。
「応援してるよ、あたしは」
応援されたって、まだ何も始まっていない。
ぼーっと時計の秒針を見ていると、机の中に隠してある携帯が光った。
周りを見渡すと、みんなノートに向かって黒板に書かれた文字を書いていた。
そっと携帯を開いて、メールを確認する。
『何してる?』
途端に、自分の笑い声が教室内に響く。
周りの視線が向けられて口を押さえ、俯き加減で返信を打つ。
『授業中です』
返信を送ってすぐに返事が送られてくる。
『そういえば、満月の画像どうした?』
『ちゃんと待受に設定したよ』
『いいことあるかも』
『でも満月は星が見たい』
『星?』
『流れ星を見てみたい』
小さい頃、絵本かなんかで見たのを覚えてる。
流れ星に願い事を三回唱えると、願いを叶えてくれるとか。
でも私が住んでいるところには流れ星なんか流れなかった。
というか、星自体あまり見かけることがなくて。
絵で書くと星は黄色やオレンジ色っぽい色をしていた。
けど、私は星が何色かさえ分からない。
どんな形をしているか、どんな色なのか。
そんなの、人間が作ったものを真似してるだけ。
今だからこそ、願いは自分で叶えるものって分かってきたけれど。
朝とか昼は好きじゃないから。
明るい場所に居ると、自分の中の淀んだ気持ちが見透かされる気がした。
勿論そんなことはないんだけど、なんとなく明るい場所は好きじゃない。
光に何もかも見透かされそう。
流れ星に願い事を三回唱えると、願いを叶えてくれるとか。
でも私が住んでいるところには流れ星なんか流れなかった。
というか、星自体あまり見かけることがなくて。
絵で書くと星は黄色やオレンジ色っぽい色をしていた。
けど、私は星が何色かさえ分からない。
どんな形をしているか、どんな色なのか。
そんなの、人間が作ったものを真似してるだけ。
今だからこそ、願いは自分で叶えるものって分かってきたけれど。
朝とか昼は好きじゃないから。
明るい場所に居ると、自分の中の淀んだ気持ちが見透かされる気がした。
勿論そんなことはないんだけど、なんとなく明るい場所は好きじゃない。
光に何もかも見透かされそう。
だったら、暗い、何も見えないような世界が好き。
人が嫌いかと聞かれたら、頷く。
自分の心が暗いと言われればそうだと思う。
帰りに拓からこんなことを言われた。
「今日の夜、見に行こう」
その一言から私は眠くても寝られない状況にいる。
ユキからの誘いも断った。
十八時半。近くの公園で待ち合わせということになって、私はウキウキ気分で家へと帰った。
何処に行くのかも聞いていないけど、大きいバッグに荷物を詰めたり。
星を見られる。それだけで嬉しかった・・・
『2000.11.08
もしも願い事が叶えられるなら、
私は何をお願いするだろう?
世界平和?それとも、ちっぽけな事を願う?
願いってそんなチープなものなのかな』
人が嫌いかと聞かれたら、頷く。
自分の心が暗いと言われればそうだと思う。
帰りに拓からこんなことを言われた。
「今日の夜、見に行こう」
その一言から私は眠くても寝られない状況にいる。
ユキからの誘いも断った。
十八時半。近くの公園で待ち合わせということになって、私はウキウキ気分で家へと帰った。
何処に行くのかも聞いていないけど、大きいバッグに荷物を詰めたり。
星を見られる。それだけで嬉しかった・・・
『2000.11.08
もしも願い事が叶えられるなら、
私は何をお願いするだろう?
世界平和?それとも、ちっぽけな事を願う?
願いってそんなチープなものなのかな』
両親が仕事から帰ってくるのはいつも二十二時頃だった。
共働きで忙しい両親。慣れていること。
それに合わせて帰るという条件。
待ち合わせ時間より五分前に着いたけれど、公園にはもう拓の姿があった。
「ごめん、待った?」
「ううん」
と言っているけれど、街灯に照らされる拓の頬と鼻は真っ赤。
「じゃあ行こうか」
自転車に跨り、二人だけの旅が始まった。
11月とは思えないくらいの寒さで、風もとても冷たい。
マフラーを巻いているけれど隙間から入ってくる風のせいで感覚が麻痺する。
そして約40分かけて来たのは、大きな川原。
「ほら、星」
そう言われ、上を見てみると数え切れないくらい輝く星。
「すごい・・・」
寒さも忘れて駆け出すと、余計に星が近くにあるように見えた。
本当に小さくて、でも輝いているのは分かる。
初めて見る本当の星。
「すごいすごいすごい!」
あまりの感動に拓に飛びつくと、よろけて倒れてしまった。
その瞬間、私のバッグから出てきたのはマフラー。
「これ何?」
立ち上がりながら、拓が手に取る。
「あ、忘れてた・・・」
受け取りながら思い出す。
拓に渡そうとしていた、マフラーだということを。
星のことばかりに気をとられていて忘れていた。
共働きで忙しい両親。慣れていること。
それに合わせて帰るという条件。
待ち合わせ時間より五分前に着いたけれど、公園にはもう拓の姿があった。
「ごめん、待った?」
「ううん」
と言っているけれど、街灯に照らされる拓の頬と鼻は真っ赤。
「じゃあ行こうか」
自転車に跨り、二人だけの旅が始まった。
11月とは思えないくらいの寒さで、風もとても冷たい。
マフラーを巻いているけれど隙間から入ってくる風のせいで感覚が麻痺する。
そして約40分かけて来たのは、大きな川原。
「ほら、星」
そう言われ、上を見てみると数え切れないくらい輝く星。
「すごい・・・」
寒さも忘れて駆け出すと、余計に星が近くにあるように見えた。
本当に小さくて、でも輝いているのは分かる。
初めて見る本当の星。
「すごいすごいすごい!」
あまりの感動に拓に飛びつくと、よろけて倒れてしまった。
その瞬間、私のバッグから出てきたのはマフラー。
「これ何?」
立ち上がりながら、拓が手に取る。
「あ、忘れてた・・・」
受け取りながら思い出す。
拓に渡そうとしていた、マフラーだということを。
星のことばかりに気をとられていて忘れていた。
「これ、巻いてねー」
と言って、拓にマフラーを巻いていく。
私が巻いているのと色違い。
服を整理整頓していたら出てきた、ビニールに入った使っていないマフラー。
「おーあったかい」
嬉しそうに笑う拓。
それを見ているだけで、私も嬉しくなれた。
川原に並んで座りながら話をする。
「満月ねー昼より夜が好きだな」
手で丸を作って、その中に入る星を見つめる。
「どうして?」
不思議そうに私に聞く。
どうしてって言われると返答に少し困ってしまうけど。
「夜は泣いたって、誰も見ないでしょ?」
そう答えると、拓はふーんと言いながら空を指差した。
「でも、月が見てるよ」
星とは少し離れた場所にある月。
昨日よりも月の形が三日月っぽくなっている。
月の周りには青白い光。
川原の水に、月が反射してすごく綺麗。
「私は月より星が好き」
携帯を開き、写真を撮る。
その頃はデジカメ代わりとかに携帯の写真機能を使っていた。
可愛いものだったり、物珍しいものがあるとすぐ写真を撮った。
カシャ、という音がして、拓の携帯も少し遅れて一緒の音が鳴る。
と言って、拓にマフラーを巻いていく。
私が巻いているのと色違い。
服を整理整頓していたら出てきた、ビニールに入った使っていないマフラー。
「おーあったかい」
嬉しそうに笑う拓。
それを見ているだけで、私も嬉しくなれた。
川原に並んで座りながら話をする。
「満月ねー昼より夜が好きだな」
手で丸を作って、その中に入る星を見つめる。
「どうして?」
不思議そうに私に聞く。
どうしてって言われると返答に少し困ってしまうけど。
「夜は泣いたって、誰も見ないでしょ?」
そう答えると、拓はふーんと言いながら空を指差した。
「でも、月が見てるよ」
星とは少し離れた場所にある月。
昨日よりも月の形が三日月っぽくなっている。
月の周りには青白い光。
川原の水に、月が反射してすごく綺麗。
「私は月より星が好き」
携帯を開き、写真を撮る。
その頃はデジカメ代わりとかに携帯の写真機能を使っていた。
可愛いものだったり、物珍しいものがあるとすぐ写真を撮った。
カシャ、という音がして、拓の携帯も少し遅れて一緒の音が鳴る。
「流れ星、流れ星流れた!」
携帯に目を向けている私をよそに、拓が叫ぶ。
「え、うそ!?どこ!」
「もう流れちゃったか・・・」
しょげていると、拓が携帯を差し出した。
携帯の画面を見ると、撮った写真の端っこに、流れ星と思われる飛行物体がちゃんと写りこんでいた。
その写真を送ってもらった私は早速待ち受けの画面に設定して、それをずっと眺めていた。
「拓は待ち受けにしないの?」
拓の携帯を見てみると、満月の写真だった。
「俺は星より月が好きだから」
私と目を合わせて笑う。
その言葉を聞いた瞬間、自分はこの人が好きだと確信した。
自分のなかで他人とこんな風に笑ったり、同じ時間を過ごして嬉しいと思うことなんて一度もなかったから。
誰かといることは煩わしい、面倒くさい。
そんな気持ちがいつもあったから。
私には告白とも取れる言葉だったけれど、今となっては何もかも分からないね。
携帯に目を向けている私をよそに、拓が叫ぶ。
「え、うそ!?どこ!」
「もう流れちゃったか・・・」
しょげていると、拓が携帯を差し出した。
携帯の画面を見ると、撮った写真の端っこに、流れ星と思われる飛行物体がちゃんと写りこんでいた。
その写真を送ってもらった私は早速待ち受けの画面に設定して、それをずっと眺めていた。
「拓は待ち受けにしないの?」
拓の携帯を見てみると、満月の写真だった。
「俺は星より月が好きだから」
私と目を合わせて笑う。
その言葉を聞いた瞬間、自分はこの人が好きだと確信した。
自分のなかで他人とこんな風に笑ったり、同じ時間を過ごして嬉しいと思うことなんて一度もなかったから。
誰かといることは煩わしい、面倒くさい。
そんな気持ちがいつもあったから。
私には告白とも取れる言葉だったけれど、今となっては何もかも分からないね。
「じゃあ帰ろうか」
自然に手を繋いで、私は頷いた。
自転車に乗って、また他愛もない話をする。
明日は何時に学校に行こうか?学校サボっちゃう?
動物って好き?将来の夢ってある?
傍から見たら、本当に何気ないことだったんだけど。
二人から見たら、本当に精一杯の言葉。
お互いのことを知りたくて、もっと知りたくて。
けど、何を話せばいいのかなんて分からないから、何気ないことを話した。
「兄弟とかっている?」
「うん、お兄ちゃんが一人いる」
「何歳?」
「大学生で、一人暮らししてたんだけど・・・」
「してたんだけど?」
大学に入ると同時に一人暮らしを始めた兄。
けれど最近、家に入り浸っているということ。
バイトも大学もあるはずなのに・・・。
それについて親は何も触れようとしない。
「・・・へぇ」
「早く言っちゃえば、フリーターだと思う」
「そうなんだ」
少し考えて、言葉にする。
「悩みがあるんだよ」
「悩み?」
「悩みくらい誰にだってあるよ」
「満月の悩みは?」
そう聞かれるけれど、口を閉ざす。
「教えてくれないの?」
「教えない」
「なんで?」
それから何度も『教えて』、『教えない』と繰り返しているうちに私の家の前にまでたどり着いてしまった。
自然に手を繋いで、私は頷いた。
自転車に乗って、また他愛もない話をする。
明日は何時に学校に行こうか?学校サボっちゃう?
動物って好き?将来の夢ってある?
傍から見たら、本当に何気ないことだったんだけど。
二人から見たら、本当に精一杯の言葉。
お互いのことを知りたくて、もっと知りたくて。
けど、何を話せばいいのかなんて分からないから、何気ないことを話した。
「兄弟とかっている?」
「うん、お兄ちゃんが一人いる」
「何歳?」
「大学生で、一人暮らししてたんだけど・・・」
「してたんだけど?」
大学に入ると同時に一人暮らしを始めた兄。
けれど最近、家に入り浸っているということ。
バイトも大学もあるはずなのに・・・。
それについて親は何も触れようとしない。
「・・・へぇ」
「早く言っちゃえば、フリーターだと思う」
「そうなんだ」
少し考えて、言葉にする。
「悩みがあるんだよ」
「悩み?」
「悩みくらい誰にだってあるよ」
「満月の悩みは?」
そう聞かれるけれど、口を閉ざす。
「教えてくれないの?」
「教えない」
「なんで?」
それから何度も『教えて』、『教えない』と繰り返しているうちに私の家の前にまでたどり着いてしまった。
「満月?」
それは、他の誰でもなく私に向けられた声だった。
自転車を降りて、歩いていた足が止まる。
振り返るとそこには兄の姿と女性の姿。
「・・・お兄ちゃん」
そう言うと、拓はお辞儀をした。
次いで兄もお辞儀をする。
隣に居るのは、兄の彼女の真希だ。
背の高い兄と大きく背が離れている同い年の大学二年生。
いつ見ても、兄には勿体無いくらい素敵な人だと思う。
「こんな時間にお出かけ?」
「あ、はい」
それ以上話したきり、会話は途切れてしまう。
兄の視線が痛いくらいに私たちに向けられていた。
どんなことを兄が思っているか。
想像はついていた。許せないと思っているんだろう。
一秒でも早くこの場から立ち去りたい。
手を繋いでいたはずの左手は、いつの間にか一人ぼっちになった。
温もりがあったはずなのにどんどん冷えていく。
切なくなって目を伏せていると、携帯が鳴る。
「もしもしー?ごめん!うん、今から行くー!」
電話が鳴ったのは真希。
妙に語尾を伸ばす話し方が、変わらない真希の特徴。
電話を切ったあと「じゃあ私先に帰るね」と言って去ってしまった。
「じゃあ、満月帰ろうか」
一人になった兄が私に言う。
隣に居る拓を見ると、黙って頷いた。
「分かった・・・、じゃあ帰ったらメールするね」
「うん」
「また、明日」
その場で別れて、後姿をぼんやりと見ていた。
姿が見えなくなると同時に兄が言う。
「今のって、誰?」
家に上がってすぐに問いかけてくる。
靴を脱いでそのまま部屋へ上がろうとすると、腕を掴まれた。
それは、他の誰でもなく私に向けられた声だった。
自転車を降りて、歩いていた足が止まる。
振り返るとそこには兄の姿と女性の姿。
「・・・お兄ちゃん」
そう言うと、拓はお辞儀をした。
次いで兄もお辞儀をする。
隣に居るのは、兄の彼女の真希だ。
背の高い兄と大きく背が離れている同い年の大学二年生。
いつ見ても、兄には勿体無いくらい素敵な人だと思う。
「こんな時間にお出かけ?」
「あ、はい」
それ以上話したきり、会話は途切れてしまう。
兄の視線が痛いくらいに私たちに向けられていた。
どんなことを兄が思っているか。
想像はついていた。許せないと思っているんだろう。
一秒でも早くこの場から立ち去りたい。
手を繋いでいたはずの左手は、いつの間にか一人ぼっちになった。
温もりがあったはずなのにどんどん冷えていく。
切なくなって目を伏せていると、携帯が鳴る。
「もしもしー?ごめん!うん、今から行くー!」
電話が鳴ったのは真希。
妙に語尾を伸ばす話し方が、変わらない真希の特徴。
電話を切ったあと「じゃあ私先に帰るね」と言って去ってしまった。
「じゃあ、満月帰ろうか」
一人になった兄が私に言う。
隣に居る拓を見ると、黙って頷いた。
「分かった・・・、じゃあ帰ったらメールするね」
「うん」
「また、明日」
その場で別れて、後姿をぼんやりと見ていた。
姿が見えなくなると同時に兄が言う。
「今のって、誰?」
家に上がってすぐに問いかけてくる。
靴を脱いでそのまま部屋へ上がろうとすると、腕を掴まれた。
「今のやつとずっと居たの?」
「・・・関係ないでしょ」
そう言って部屋に入ると、勢いよく突き飛ばされた。
尻もちをつき体を強く打つ。
「ちょ・・・、何すんのよ!」
そう言うけれど、兄は何も言わない。
立ち上がれないままで居ると、腕を掴まれ体が起こされる。
すると右手を大きく振りかざし、私の頬に鈍い音と痛みが走った。
「何・・・?」
痛みよりも、驚きのほうが大きかった。
怒っているんだろう。
だけど、どうして手を上げたのか。
殴られるのは別に構わないけれど、理由も言わずに殴られるというのは自分の腑に落ちなかった。
「・・・お兄ちゃんもそういう人なんだ」
痛む体を無理やり起こして、溜め息を吐きながらベッドに腰掛ける。
「じゃあ私も聞くけど、どうして家に帰ってきたの?バイトは?学校は?」
聞けなかったそのことを聞くと、案の定兄は黙り込んだ。
「黙るんだね、都合が悪いと」
「どうせ学校嫌になっちゃったんでしょ?勉強ついていけなくなったんでしょ?」
「お兄ちゃん、昔から物事続いた試しがないもんね」
「昔からそう、私のそばべったりくっついて・・・正直気持ち悪かったっていうか」
全部を言い終わったとき、自分でもなんて冷たいことを言ったのかと思った。
独り言で終わらせたいけれど兄はその言葉を聞いていた。
罪悪感なんて生まれなかった。
だって全て正しいから。
「・・・関係ないでしょ」
そう言って部屋に入ると、勢いよく突き飛ばされた。
尻もちをつき体を強く打つ。
「ちょ・・・、何すんのよ!」
そう言うけれど、兄は何も言わない。
立ち上がれないままで居ると、腕を掴まれ体が起こされる。
すると右手を大きく振りかざし、私の頬に鈍い音と痛みが走った。
「何・・・?」
痛みよりも、驚きのほうが大きかった。
怒っているんだろう。
だけど、どうして手を上げたのか。
殴られるのは別に構わないけれど、理由も言わずに殴られるというのは自分の腑に落ちなかった。
「・・・お兄ちゃんもそういう人なんだ」
痛む体を無理やり起こして、溜め息を吐きながらベッドに腰掛ける。
「じゃあ私も聞くけど、どうして家に帰ってきたの?バイトは?学校は?」
聞けなかったそのことを聞くと、案の定兄は黙り込んだ。
「黙るんだね、都合が悪いと」
「どうせ学校嫌になっちゃったんでしょ?勉強ついていけなくなったんでしょ?」
「お兄ちゃん、昔から物事続いた試しがないもんね」
「昔からそう、私のそばべったりくっついて・・・正直気持ち悪かったっていうか」
全部を言い終わったとき、自分でもなんて冷たいことを言ったのかと思った。
独り言で終わらせたいけれど兄はその言葉を聞いていた。
罪悪感なんて生まれなかった。
だって全て正しいから。
この作家の他の作品
表紙を見る
「ネットから始まる恋ってどう思いますか?」
よくある恋の話。ネット編。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…