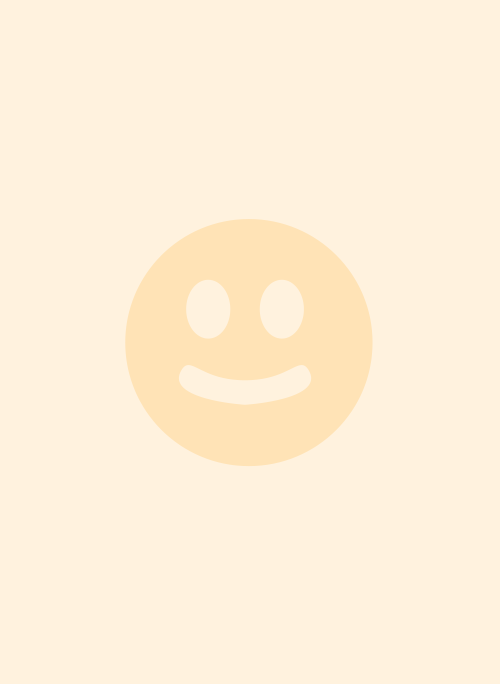それは娘が遅く帰った事を叱ったことから始まった。
「いったい何時だと思ってるの!!」
玄関の壁掛け時計は11時を指していた。
「うっさいなぁ!いいでしょ!他の家だと普通だよ」
「ちょっと待ちなさい!」
娘はこちらの顔すら見る事なく自分の部屋へと入っていく、わたしは追って部屋に入ろうとしたが、しっかりとロックされていた。
「ちょっと!話はまだ終わってないから開けなさい!」
「っせーんだよ!ババァ!」
その言葉と共にドアに何かを投げつける音がした。
「ちょっと!絵里奈!開けなさい!お母さんの話はまだ終わってないの!」
しばらくドアを叩いていると、突然扉が開いた。
「ちょっと!なにその荷物は!」
「っせーな!出てってやるよ!こんなウチ!」
「ちょっと待ちなさい!待ちなさい絵里奈!」
しかし娘はこちらの制止も聞かずに、わたしがつかんだ腕を乱暴に振りほどいて出て行ってしまった。
あとを追ってマンションの階段を降りていくと、絵里奈はマンション前に止まっている車の後部座席に乗り込んで、車は走り去って行ってしまった。
急いで自宅へ戻り娘に電話をかけてもつながる様子はなかった。何度か目には電話はつながる事なく切られるようになった。
仕方なく仕事で遅いお父さんへ電話をかけるけれど、つながる様子がなかったので留守電へと伝言を残した。
不安に時計を見ながら時間だけが過ぎていった。
しばらくすると電話がかかってきた。
「絵里奈!もう怒らないから早く帰ってきなさい!」
「おい、落ち着けよ」
その声はお父さん…つまり旦那の声だった。
「お父さん、どうしよう…あの娘いかにもガラの悪そうな車に乗って出て行ったの!」
「だから落ち着けって、大丈夫だろ、絵里奈ももう16になったんだから、そのうち帰って来るさ」
「でも、何かあったらって思うと…」
「そうやってお前が締め付けるから絵里奈も反発するんだろ」
「だからって!」
「ああ、今日はちょっと遅くなるけど帰るから、お前は先に寝てろ」
「…今日ぐらい早く帰って来てもいいじゃない」
「…じゃあ切るぞ」
そう言い電話はきれてしまった。静かな部屋には時計の秒針を刻む音だけが響いていた。
気がつけばいつの間にか眠っていた。キッチンの4人がけのテーブルに独りで座って眠っていた。
何時からわたしは独りで揃わない家族を待つようになったのだろう。時計の針は2時を過ぎようとしていた。
普通の家庭が夢だった。毎日晩ご飯を食卓で囲み普通にその日あったことを会話しながら、笑いあえる家庭…そんな些細な夢だった。
けれど現実は仕事と称して帰らない旦那…年を重ねるたびに反抗心が強くなる娘…学校でいじめにあって登校拒否からひきこもりになった息子。
どれもわたしが描いてものから遠くかけ離れていた。それでも希望はあると信じてすごしていた。
けれど現実にはそんな事はなかった。
2時半を過ぎた頃ようやく玄関の扉があいた。
「おい、今帰ったぞ」
わたしは黙って玄関へと向かう。
案の定、旦那は平然としていた。しかもかすかにどころかスーツからは女モノの香水がしている。
多少ならわたしも我慢して気づかないようにしていた。けれどこの日ばかりは我慢できなかった。
「娘が家出したのに、あなたは女のところですか?」
「何いってるんんだ、仕事だよ仕事」
「香水の匂い」
「え?ああ、帰りの電車でうつされたんだよ」
「もう少しマシなウソをつきなさいよ」
「…明日も忙しいんだ、今日は寝る」
そう言い旦那は寝室へと向かっていく。
どこからこんなに壊れてしまったんだろう…そんな事を思いながら、眠る事にした。
翌日、息子が食事を催促する物音が聞こえた。それはお腹が空くと壁を叩いてそれを知らせる。
息子がひきこもり始めた頃は、多少なりとも腕をふるい、美味しいものを作っていた。
けれど毎日毎日、お盆の上に乗ったカラの食器を見ている内に、言いようの無い虚しさが襲ってきた。
いつしか、いつからか作る食事は焼いたトーストだけになっていた。それも過去の話しで、今ではスーパーで安売りしている見切り品の菓子パンをそのまま扉の前に置いている。
本当に息子はこの扉の向こうにいるのだろうか、そんな疑問すら感じる。もう息子は死んでいて、実は見知らぬ者が住み着いているのでは無いか、そんなふうに感じるようになっていた。
そういえば昨日は娘と揉めたせいで菓子パンが切れていた。仕方ないので茶碗に昨日のご飯を盛っておいた。
息子の部屋からは何か怒声が聞こえるが、今のわたしには判別できるような気力はなかった。
昼がいつの間にか過ぎていた。そんな中電話がかかってきた。鳴り続ける呼出のベルが妙に響いて聞こえていた。
突然の電話…それは警察からの電話だった。
「事故がありまして、所有物からおたくの娘さんである可能性がありますので、確認までに病院まで確認に来ていただいてよろしいですか?」
それは娘の身元確認の警察から電話だった。
何を言っているのか判断できなかった。ただうわ言のように返事をしていた。しばらくして、息子がまた壁を叩き始めた頃ようやく気がついた。
わたしは無意識にメモをとっていたようだった。
わたしは冷凍庫から適当に何かを取り出して息子の部屋の前に置いた。
そして、メモに書かれた病院へと向かうことにした。