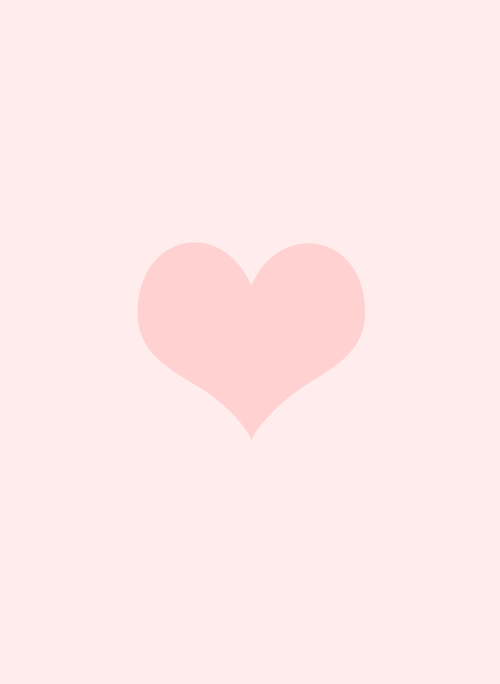激しい雨に叩きつけられながら、俺は歩いた。
頭から水を被ったように、濡れながら。
明るかったはずの空も、暗くなりかけている。
……また、雷鳴が響き渡った。
どこかに、山小屋とかねぇのかよ。
もう、この際、通りがかった車でも構わなかった。
けれど、俺の願いも虚しく、車は一台も通らない。
土砂降りの雨は冷たく、吹きつける風に木々が揺れる。
俺は、焦っていた。
このまま、夜にでもなったら………。
「朔ちゃん…。」
俺の背中から、梨子のか細い声。
「ん?」
少しでも不安にさせないように、俺は精一杯明るい声を出した。
「……ゴメンナサイ……あたし…足手纏いで………。」
「…………。」
梨子が、泣いているのは明らかだった。
「…朔ちゃんに…ついてきちゃって……ゴメンネ……。一緒に逃げたりしなければ……あたし…なんかが、いなければ……もっと……。」
「梨子。ついてきてくれて、ありがとう。」
「…………。」
「俺と、一緒に逃げてくれて…ありがとう。」
歩みを止める事なく、俺は言葉を続ける。
「梨子がいてくれたから、いつか捕まる事も怖くなかった。
……俺が一番怖いのは、梨子を失う事だよ。」
背中から聞こえる嗚咽と、ぎゅっと俺の肩を包む細い腕。
これが、
恋でも、愛でも、なかったとしても。
俺にとって彼女は紛れもなく、一番大切な女の子だ。
「…朔ちゃん……。」
「ん?」
「明かりが見えます……。」
「えっ?」
梨子が指し示す先、確かに滲んだ明かりが見える。
木々を掻き分けて近づくと、それは姿を現した。
山の中に不釣り合いとも思える派手なネオン。
ピンクと白、赤と白という奇抜な外壁の建物は、まるで…………。
「お城です!」
……絶対言うと思った。
「……梨子、違うよ。」
「え?」
「あれは………。」
………あれは、ラブホテルだ。
(失う事を恐れていた。
背中に感じる君の鼓動、
あぁ、こんなにも―…)
「朔ちゃん……。」
「…何だよ。」
「部屋がピンクです!」
「うるせぇーよ!!」
部屋の照明はピンク、円形のベッドのシーツは毒々しい程の赤。
いかにも、という感じの部屋を見て、梨子は目を丸くしている。
「朔ちゃん!見てください!猫足のバスタブです!」
「はい、はい。」
「朔ちゃん!ベッドが、お姫様ベッドですっ!」
「はい、はい。」
「朔ちゃ〜ん!さすが、お城ですねぇ!」
「…………。」
マジメに城だと思っているらしい梨子。
夢見る乙女に、ラブホだ、とは言えなかった。
「梨子、風邪ひくからシャワー浴びろよ。」
「朔ちゃんは?」
「……俺は、後でいい。」
そう答えて、俺はベッドに腰かける。
いくらラブホとはいえ、全く趣味の悪い部屋だと思った。
こんな緊急事態じゃなかったら、絶対に入らないだろう。
そして、俺自身、困惑していた。
ラブホに二人きり……。
自分の理性には自信があったものの、さすがに気まずい。
ここがラブホだと、梨子が気づいていないだけマシだったが…………。
やる事もないので、俺はテレビのリモコンに手を伸ばし、スイッチを入れた。
すると…………。
『ァン……ァ、ア…いやぁ〜。』
なっ!!?
テレビから聞こえてきたのは、女の喘ぎ声。
映し出されるのは、絡み合う男と女。
AVじゃねぇか!!?
半分パニックになって慌てる俺。
梨子は、全ての動作が完全に停止して画面をガン見。
何て気まずい状況だよっ!?
『ァッ、やぁ〜、ダメぇ〜…。』
うるせぇーよっ!!このバカテレビ!!!
つけたばかりのテレビを、焦りまくって消す。
テレビは消えて、ピンクな部屋は静寂に包まれる。
立ち尽くす梨子。
クソッ!余計に気まずい!!
「……朔ちゃん…。」
「な、何だよ……。」
「今のって……?」
「………あ〜っと、あー、え、映画じゃねぇ?
ほ、ほら!ラブストーリーとか…。」
「ラブストーリー!私、大好きなんです!!」
1トーン声が高くなって、ハシャぐ梨子。
「そ、そう……あっ、早くシャワー浴びちゃえよ。」
「あっ!そうですねっ!お待たせしてしまって、申し訳ございません。」
梨子は、トタトタとバスルームへ消えていく。
……よかった………。
梨子がド天然で……疑いもせずに、ラブストーリーだと信じてくれて………。
俺はテレビのリモコンを放り投げて、溜め息をついた。
梨子と交代で、俺はバスルームに入った。
熱いシャワーを浴びながら、俺はこれからの事を考えてみた。
いつまで続くか分からない逃亡生活。
いつかは……いずれは、捕まるだろう。
先の見えない逃亡にも、
捕まる事に対しても、
不安がないと言えば嘘になる。
この作家の他の作品
表紙を見る
学生時代は勉強に、
社会人になってからは仕事に―。
気づけば、
恋愛未経験のまま27歳。
恋の神様は意地悪で、
待てど暮らせど
私の王子様は現れず。
生真面目な駄菓子屋店長
岡田芳乃(27)
* オカダ・ヨシノ *
×
爽やか美形アルバイト
佐倉 蛍 (21)
* サクラ・ケイ *
「顔…真っ赤ですよ?」
人懐こい笑顔の好青年は、
ときどき不真面目になる。
*上司と部下の恋愛事情*
□ ■ □ ■
愛なんか、
恋なんか、
□ ■ □ ■
※この物語はフィクションです。
実在するものとは、一切関係ありません。
誹謗・中傷は、ご遠慮願います。
◇◆むぐさま◆◇
◇◆風美鈴さま◆◇
◇◆CoCoLoさま◆◇
◇◆英 暁さま◆◇
◇◆怱喜さま◆◇
素敵なレビュー
ありがとうございます!
◇2013.05.27〜◇
Berry's Cafe
「オトナ女子を惑わす年下男子特集」に掲載されました。
ありがとうございます!
2011年6月17日……完結
表紙を見る
“死ね”なんて
簡単に言うな。
“死にたい”なんて
簡単に言うなよ。
そう言って、
彼は悔しそうに泣いた。
泣きながら、怒っていた。
あたしも、
泣いていた。
生きていることを、
初めて愛しいと思った。
□ ■ □ ■
反抗期真っ只中の中学二年生・千鶴は、ある出来事が原因で不登校となり、そのまま夏休みを迎えていた。
「親も学校も人間関係もウザイ」
ある日、大好きな祖母が突然倒れてしまう。
そして千鶴は不思議な少年と出会うのだった――。
□ ■ □ ■
“命”
“生きること”
“明日があるという幸せ”
時をこえた約束を通して、千鶴が知っていく大切なこと――。
過去・現在・未来を繋ぐ
壮大な命の物語――。
※この物語は実際の出来事を題材としている部分が一部ございますが、実在する人物、場所等とは一切関係ありません。
誹謗・中傷は、ご遠慮願います。
◇―◆―◇―◆―◇―◆
第6回日本ケータイ小説大賞受賞、書籍化しました!
本当にありがとうございました!
◇―◆―◇―◆―◇―◆
2011年9月24日……完結
表紙を見る
「あたし、先生に欲情してる。」
一匹狼タイプの女子高生
雨音 泉(17)
― izumi amane ―
×
「ガキは、対象外。」
美形の校医
矢野夏海(28)
― natsumi yano ―
・……あの夏、永遠の夏……・
※この物語はフィクションです。
実在するものとは、一切関係ありません。
誹謗・中傷は、ご遠慮願います。
◇◆葵翼さま◆◇
◇◆櫻井千姫さま◆◇
◇◆佳歩さま◆◇
◇◆kei.hさま◆◇
◇◆。・★愛姫★・。さま◆◇
◇◆風美鈴さま◆◇
◇◆綺漓さま◆◇
◇◆彩音侑理さま◆◇
◇◆糸利 青さま◆◇
素敵なレビュー
ありがとうございます!
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…