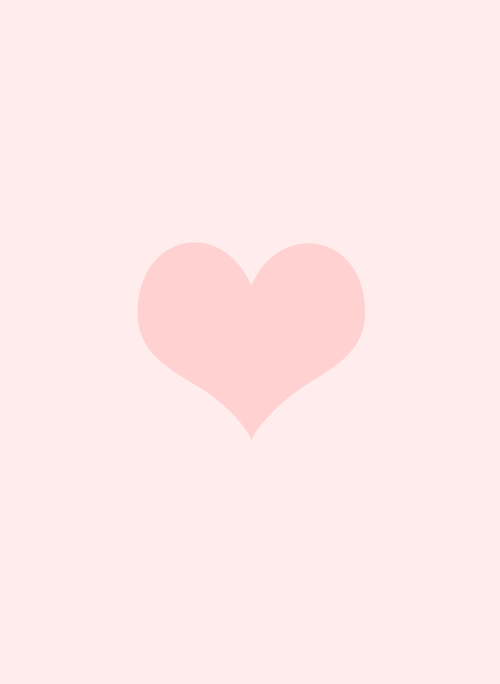俺は、いてもたってもいられなくなった。
得体の知れない不安がまとわりつく。
それが何なのか、自分でも分からなかった。
……きっと、俺が深く考えすぎているだけ。
昔から、そういうところがあるんだ。俺は。
重い足取りで部屋を出て、階段を下りた。
直接…梨子に尋ねよう。
きっと……いつものように、あっけらかんと言うだろう。
俺は、いつも、心配しすぎなんだよ………。
自分に言い聞かせながら、店へとつながる引き戸の前に立つ。
梨子と、リンダママと、蓮見組の若頭は、
まだ何やら話をしているらしい。
俺は、引き戸に手をかける。
その時、ある一言がはっきりと耳に届いた。
「本当に殺すつもりなのか?」
低く響いた声は、蓮見組の若頭。
俺は思わず、引き戸に触れていた手を引っ込めた。
殺す…って……。
穏やかな話でない事は、明らかだった。
「……もう少しなの。」
それは、梨子の声。
………何が、もう少しなんだよ?
俺は息を潜めて、わずかに開いている引き戸の隙間から中を覗いた。
……さっきと、何も変わらない。
カウンター席に並んで座ったままのリンダママと、蓮見組の若頭。
そして、厨房の中に立つ梨子。
「…今になってね、アタシも不安なのよ。」
リンダママが口を開いた。
それを最後に、沈黙する三人。
静寂を破ったのは、蓮見組の若頭だった。
「……まぁ、よく考えろよ。」
そう呟くと、若頭は梨子に何かを渡した。
グシャグシャになった茶の紙袋。
梨子は受け取ると、その中身を見ている。
「本当に、後悔しない?」
諭すように、リンダママは言った。
梨子は、ほんの一瞬だけ口元を緩めて微笑んだ。
それから、紙袋から何かを取り出しながら、ぽつりと呟いた。
「後悔なんてしないわ。」
その瞬間、俺は呼吸さえ忘れた。
瞬きさえだ。
梨子が紙袋から取り出した物、それは―――……、
それは、小型のピストルだった。
……―――梨子。
一体、何を考えてるんだ?
ピストルを見つめる梨子の眼差しは、酷く冷たかった。
まるで、氷のように―――……。
(俺は、奥田梨子を愛した。
けれど、俺は彼女の事を何も知らない。)
小さな部屋に敷かれた二組の布団。
隣で眠る梨子は、こちらに背を向けて穏やかな寝息をたてる。
風が吹くたびに、ガタガタと鳴る窓ガラス。
そんな些細な音が気になって、眠る事ができない。
……眠れない理由は、それだけじゃない。
……むしろ。
俺は梨子を起こさないように、注意深く起き上がる。
窓から差し込む月明かり。
今夜は満月のようで、いやに明るすぎる。
自分の枕の下から、問題の物を取り出した。
赤い表紙の薄いノート。
表紙に書かれた名前――………『 Shiori Mizusawa 』。
これが、この部屋にあった事を俺は梨子に言わなかった。
……さっき、引き戸の隙間から見た梨子は、俺が知っている梨子ではなかった。
酷く冷たい眼差し、無機質な話し方。
けれど、紛れもなく、奥田梨子なのだ。
俺が知らない梨子の顔。
― 「後悔なんてしないわ。」
ピストルを手にした梨子は、そう言った。
………梨子は、誰かを殺すつもりだ。
そして、リンダママと蓮見組の若頭は、それを知っている。
俺は、水沢の名前が書かれた赤いノートを見つめる。
分からない事が多すぎるんだ。
未だに、頭の中の整理だって出来やしない。
このノートに何かがあるかもしれない。
今は、このノート以外に縋る物がないのだ。
他人の物を勝手に見ていいのか。
だが、他に方法もない。
俺は躊躇いを捨てる。
息を呑み、赤いノートを開いた。
しかし、俺の想像を裏切る結果。
ノートには、何も書かれていなかったのだ。
……いや、正確に言えば書かれていたのかもしれない。
ノートの前半のページ半分程が、全て切り取られていたのだ。
一体、そこに何が記されていたのか?
切り取った人物は、誰なのか?
俺の疑問は、何一つ解決していない。
パラパラとノートを捲っていると、ひらりと何かが落ちた。
……写真?
それも、二枚。
畳の上に落ちた写真を拾う。
そして、
俺は驚愕するのだった。
一枚目の写真は、中学の卒業式。
ダッセぇ俺と、水沢詩織……。
俺の財布にも入っている、あの写真。
二枚目の写真は……。
中学の制服に身を包んだ水沢詩織と、面影が残る幼い奥田梨子。
二人は、笑顔で……。
その写真から伝わるのは、二人の親密さ。
何よりも、写真が撮られたと思われる場所は、この部屋だった。
水沢詩織と奥田梨子……。
どういう事なんだ…………。
俺は、頭を抱える。
何が、どうなっているのか。
その時、俺の中で一つの仮説が浮かび上がる。
もう一度、水沢と梨子が一緒に写っている写真を見つめた。
………まさか…。
俺は、隣で眠る梨子を見つめる。
無防備に、安心しきった表情で眠っている。
……まだ、可能性の段階だ。
俺は、自分に必死に言い聞かせていた。
翌日は、気持ちのいい秋晴れ。
移ろいゆく季節、風は少しずつ冷たくなっていた。
「梨子、デートしよう。」
「デート?」
「あぁ。」
俺は、そう言って笑った。
『スナック・リンダ』を出て、俺たちは手を繋いで海まで歩いた。
「海の匂いだぁ。」
真っ白な砂浜とブルーの海。
梨子は両手を広げて、深呼吸をした。
俺は、といえば、そんな梨子に背を向けて一人歩いた。
頭上の澄んだ空とは対照的な、濁った心を抱えたまま。
梨子が、俺の後を追う。
そうして、後ろから抱きついてきた。
……飛びついてきた、の方が正しいかもしれない。
「さぁくちゃんっ!」
「おっわっ!!」
「おんぶしてください!」
「…………。」
俺は返事の代わりに、梨子を背負う。
俺の肩に絡みつく、梨子の腕。
この作家の他の作品
表紙を見る
学生時代は勉強に、
社会人になってからは仕事に―。
気づけば、
恋愛未経験のまま27歳。
恋の神様は意地悪で、
待てど暮らせど
私の王子様は現れず。
生真面目な駄菓子屋店長
岡田芳乃(27)
* オカダ・ヨシノ *
×
爽やか美形アルバイト
佐倉 蛍 (21)
* サクラ・ケイ *
「顔…真っ赤ですよ?」
人懐こい笑顔の好青年は、
ときどき不真面目になる。
*上司と部下の恋愛事情*
□ ■ □ ■
愛なんか、
恋なんか、
□ ■ □ ■
※この物語はフィクションです。
実在するものとは、一切関係ありません。
誹謗・中傷は、ご遠慮願います。
◇◆むぐさま◆◇
◇◆風美鈴さま◆◇
◇◆CoCoLoさま◆◇
◇◆英 暁さま◆◇
◇◆怱喜さま◆◇
素敵なレビュー
ありがとうございます!
◇2013.05.27〜◇
Berry's Cafe
「オトナ女子を惑わす年下男子特集」に掲載されました。
ありがとうございます!
2011年6月17日……完結
表紙を見る
“死ね”なんて
簡単に言うな。
“死にたい”なんて
簡単に言うなよ。
そう言って、
彼は悔しそうに泣いた。
泣きながら、怒っていた。
あたしも、
泣いていた。
生きていることを、
初めて愛しいと思った。
□ ■ □ ■
反抗期真っ只中の中学二年生・千鶴は、ある出来事が原因で不登校となり、そのまま夏休みを迎えていた。
「親も学校も人間関係もウザイ」
ある日、大好きな祖母が突然倒れてしまう。
そして千鶴は不思議な少年と出会うのだった――。
□ ■ □ ■
“命”
“生きること”
“明日があるという幸せ”
時をこえた約束を通して、千鶴が知っていく大切なこと――。
過去・現在・未来を繋ぐ
壮大な命の物語――。
※この物語は実際の出来事を題材としている部分が一部ございますが、実在する人物、場所等とは一切関係ありません。
誹謗・中傷は、ご遠慮願います。
◇―◆―◇―◆―◇―◆
第6回日本ケータイ小説大賞受賞、書籍化しました!
本当にありがとうございました!
◇―◆―◇―◆―◇―◆
2011年9月24日……完結
表紙を見る
「あたし、先生に欲情してる。」
一匹狼タイプの女子高生
雨音 泉(17)
― izumi amane ―
×
「ガキは、対象外。」
美形の校医
矢野夏海(28)
― natsumi yano ―
・……あの夏、永遠の夏……・
※この物語はフィクションです。
実在するものとは、一切関係ありません。
誹謗・中傷は、ご遠慮願います。
◇◆葵翼さま◆◇
◇◆櫻井千姫さま◆◇
◇◆佳歩さま◆◇
◇◆kei.hさま◆◇
◇◆。・★愛姫★・。さま◆◇
◇◆風美鈴さま◆◇
◇◆綺漓さま◆◇
◇◆彩音侑理さま◆◇
◇◆糸利 青さま◆◇
素敵なレビュー
ありがとうございます!
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…