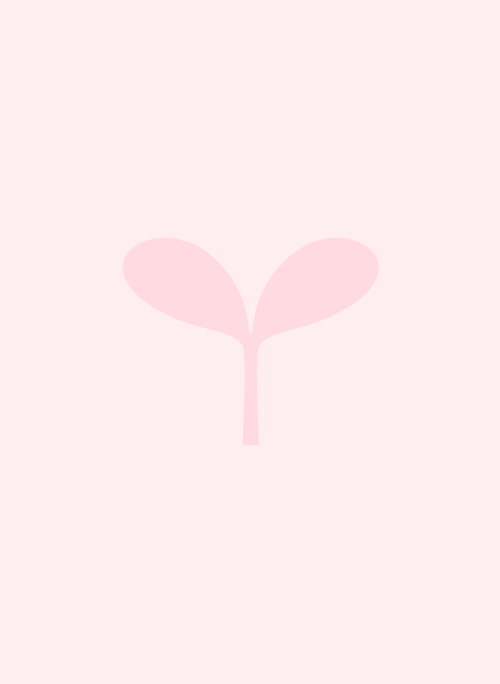「座って下さい」
俺はあなたに席を勧めた。
「君こそ大丈夫なんですか、時間」
七時半。もう大半の仲間は打ち上げの会場に向かっている。
「間に合わなかったら間に合わなかったでいいんです」
「そう」
「それで、今日の舞台どうでしたか?」
「良かったですよ。久しぶりにミュージカルを見たけれど、やっぱり舞台は良かった。君の歌も演技も、ジャックとレアの結婚式での君の歌は特に良かった」
俺は小さくお礼を言った。
「でもあなたは座っていた」
「観客だもの」
「エンディング、あなた以外のお客様は立ち上がって俺たちに拍手を送ってくれた。でもあなたは座ったまま、客席の隅の席で腕を組んで難しい顔をしていました」
「自惚れ?」
「違います。あなたがあんな難しい顔をしていた理由を教えて下さい。面白くないところがあったなら、プロとして許されないことだから…」
「私的なことだから。じゃあ私はこれで」
「そのシテキナコトは、舞台見ても忘れられなかったんですね」
「エンディングだったからだよ。もう終わりなんだな、と思ったら現実に引き戻された」
あなたは薄く笑う。
「舞台は本当に良かった。今日が最終公演なんて、もっと早くに見に来れば良かったよ」
「…有り難うございます」
「それじゃあ」
「あ、連絡先を教えてくれませんか」
どうして、という顔をする。
「次回作のチケット、用意します。都合のつく日とか解れば」
「悪いですよ」
「是非見に来て下さい。次はあなたの悩みなんか会場出るまで忘れるような舞台にしますから」
じゃあ何か書く物あるかな、と言われ、俺は裏返した台本とサインペンを出した。
「名字、何て読むんですか?」
「タスカワ」
「…十ってプラスの+なんですか?」
「嘘。ソゴウ、って読むんです」
「へえ…十河千尋さん。二回数字が出てくるんですね」
「見たままの感想を有り難う」
「いえ。じゃ、期待して下さいね」
そしてあなたは去って行った。
俺はあなたに席を勧めた。
「君こそ大丈夫なんですか、時間」
七時半。もう大半の仲間は打ち上げの会場に向かっている。
「間に合わなかったら間に合わなかったでいいんです」
「そう」
「それで、今日の舞台どうでしたか?」
「良かったですよ。久しぶりにミュージカルを見たけれど、やっぱり舞台は良かった。君の歌も演技も、ジャックとレアの結婚式での君の歌は特に良かった」
俺は小さくお礼を言った。
「でもあなたは座っていた」
「観客だもの」
「エンディング、あなた以外のお客様は立ち上がって俺たちに拍手を送ってくれた。でもあなたは座ったまま、客席の隅の席で腕を組んで難しい顔をしていました」
「自惚れ?」
「違います。あなたがあんな難しい顔をしていた理由を教えて下さい。面白くないところがあったなら、プロとして許されないことだから…」
「私的なことだから。じゃあ私はこれで」
「そのシテキナコトは、舞台見ても忘れられなかったんですね」
「エンディングだったからだよ。もう終わりなんだな、と思ったら現実に引き戻された」
あなたは薄く笑う。
「舞台は本当に良かった。今日が最終公演なんて、もっと早くに見に来れば良かったよ」
「…有り難うございます」
「それじゃあ」
「あ、連絡先を教えてくれませんか」
どうして、という顔をする。
「次回作のチケット、用意します。都合のつく日とか解れば」
「悪いですよ」
「是非見に来て下さい。次はあなたの悩みなんか会場出るまで忘れるような舞台にしますから」
じゃあ何か書く物あるかな、と言われ、俺は裏返した台本とサインペンを出した。
「名字、何て読むんですか?」
「タスカワ」
「…十ってプラスの+なんですか?」
「嘘。ソゴウ、って読むんです」
「へえ…十河千尋さん。二回数字が出てくるんですね」
「見たままの感想を有り難う」
「いえ。じゃ、期待して下さいね」
そしてあなたは去って行った。
ぎりぎり間に合った打ち上げ会場。その場で次回作の配役が発表された。俺はやっぱり脇役だったけれど、それも仕方がない。監督は全てを考えて配役を決めているんだから。
あなたに再び会ったのは、別れてから三時間後だった。
「なあ優、続きしようぜ?」
「まだ飲むつりなんですか?体に響きますよ、寺田さん。声も枯れるし」
「いいだろ一日くらい。一緒にタクシー乗れよ」
「結構です。俺、明日の早いバスで実家に帰るんですよ」
「乗れって言ってんだろ」
「みっともない。いい大人が」
そう言って俺を寺田さんから引き離してくれた。何だよお前、と寺田さんは凄んだが、あなたの睨みにすくんだのか、一人タクシーに乗って帰った。
「あ、有り難うございました」
「そんなに有難い事じゃないよ」
「あの、十河さん」
「何で私の名前…あ」
モーリス、とあなたと俺の声が重なった。
「暗いのと化粧してないので解らなかったよ。えっと…」
「天野優です」
「天野さん。打ち上げ終わったんだ」
「はい。今のは先輩役者で。ロバート役でした」
「ああ、あの爺さんね」
「十河さん、シテキナコトは解決したんですか?」
「…そう見える?」
「見えますね」
そうか…とあなたは夜空を仰いだ。頭に当てた左手薬指に光るもの。
あなたに再び会ったのは、別れてから三時間後だった。
「なあ優、続きしようぜ?」
「まだ飲むつりなんですか?体に響きますよ、寺田さん。声も枯れるし」
「いいだろ一日くらい。一緒にタクシー乗れよ」
「結構です。俺、明日の早いバスで実家に帰るんですよ」
「乗れって言ってんだろ」
「みっともない。いい大人が」
そう言って俺を寺田さんから引き離してくれた。何だよお前、と寺田さんは凄んだが、あなたの睨みにすくんだのか、一人タクシーに乗って帰った。
「あ、有り難うございました」
「そんなに有難い事じゃないよ」
「あの、十河さん」
「何で私の名前…あ」
モーリス、とあなたと俺の声が重なった。
「暗いのと化粧してないので解らなかったよ。えっと…」
「天野優です」
「天野さん。打ち上げ終わったんだ」
「はい。今のは先輩役者で。ロバート役でした」
「ああ、あの爺さんね」
「十河さん、シテキナコトは解決したんですか?」
「…そう見える?」
「見えますね」
そうか…とあなたは夜空を仰いだ。頭に当てた左手薬指に光るもの。
「指輪」
さっきはしていなかった。
「受けてきた。プロポーズ」
「え」
「何」
「されたんですか?十河さんからしそうなのに」
「ジェンダーフリーだよ」
あなたはやっぱり薄く笑う。
「返事をしなきゃいけないと思ってね。あの時、そんな事を考えてたんだ」
「そりゃ難しい顔もしますね」
さっきは失礼しました、と俺は謝った。
「何かお礼を」
「いいよ。チケット貰うし」
「あ、そうか」
「じゃあ、気を付けて帰りなよ。君は多分」
「何ですか?」
「多分、男に襲われやすい」
「…どういう意味ですか?それ」
「嘘だよ。でも用心するに越したことはない」
「ですね。有り難うございました」
さようなら、と言って別れたけれど、その時にはもう、またあなたに会う予感がしていた。何だろう、俺の中に不思議な気持ちがあった。
家路では何事もなく、帰って新しい台本と楽譜を見る。
今まで少年役しか貰えなかった俺だが、次の役は主人公の母親役になった。その役作りに、一度母のいる田舎へ戻るつもりだ。子守歌を歌う場面がある。お客様を全員眠らせるような心構えでいこう。
少年役ですっかり身に付いてしまった「俺」の一人称もやめなければいけないだろうか。
さっきはしていなかった。
「受けてきた。プロポーズ」
「え」
「何」
「されたんですか?十河さんからしそうなのに」
「ジェンダーフリーだよ」
あなたはやっぱり薄く笑う。
「返事をしなきゃいけないと思ってね。あの時、そんな事を考えてたんだ」
「そりゃ難しい顔もしますね」
さっきは失礼しました、と俺は謝った。
「何かお礼を」
「いいよ。チケット貰うし」
「あ、そうか」
「じゃあ、気を付けて帰りなよ。君は多分」
「何ですか?」
「多分、男に襲われやすい」
「…どういう意味ですか?それ」
「嘘だよ。でも用心するに越したことはない」
「ですね。有り難うございました」
さようなら、と言って別れたけれど、その時にはもう、またあなたに会う予感がしていた。何だろう、俺の中に不思議な気持ちがあった。
家路では何事もなく、帰って新しい台本と楽譜を見る。
今まで少年役しか貰えなかった俺だが、次の役は主人公の母親役になった。その役作りに、一度母のいる田舎へ戻るつもりだ。子守歌を歌う場面がある。お客様を全員眠らせるような心構えでいこう。
少年役ですっかり身に付いてしまった「俺」の一人称もやめなければいけないだろうか。
「それでいいと思うよ」
この前、君が「私」なんて自分の事を呼ぶから、少し笑ってしまった。
「そのままのほうが君らしい」
「そうですか?」
俺も俺に慣れちゃったんですけどね。君は続けた。
あの日から何度となく君に会い、私達は古い友達のような仲となった。私と君は一回り近く年が違う。それなのに、こんなにも早く友達のような関係を作れたのは君のお陰だろうか。
「母に言われたんですよ」
君は例のドーナツを口にする。ひょっとして、君の食べる物はこれだけなのか?
「ちゃんと飯を食べろ」
「あー、それも言われましたけど」
もぐもぐ。
「優も結婚していつか母親になるんだから、その呼び方やめなさい。今から心がけないと、もう直らないわよ」
って。
「俺、次の誕生日で二十二歳ですよ?まだ結婚とか早いですよね」
君は少しむっとした表情を作る。
「あ、元気ですか?奥さん」
急に話を振る。
「まだ結婚はしてないよ。うん、元気だ」
私はふと一つの案を思いついた。
「君、実際ちゃんと飯を食べているのか?」
「…」
「舞台役者って体力勝負じゃないのか?」
「そうなんですけどね」
「うちに食べに来ないか?オクサンは、これが料理上手なんだ」
「いいんですか?」
君の目がキラッと光った。食べるのが好きなのは本当のようだ。
この前、君が「私」なんて自分の事を呼ぶから、少し笑ってしまった。
「そのままのほうが君らしい」
「そうですか?」
俺も俺に慣れちゃったんですけどね。君は続けた。
あの日から何度となく君に会い、私達は古い友達のような仲となった。私と君は一回り近く年が違う。それなのに、こんなにも早く友達のような関係を作れたのは君のお陰だろうか。
「母に言われたんですよ」
君は例のドーナツを口にする。ひょっとして、君の食べる物はこれだけなのか?
「ちゃんと飯を食べろ」
「あー、それも言われましたけど」
もぐもぐ。
「優も結婚していつか母親になるんだから、その呼び方やめなさい。今から心がけないと、もう直らないわよ」
って。
「俺、次の誕生日で二十二歳ですよ?まだ結婚とか早いですよね」
君は少しむっとした表情を作る。
「あ、元気ですか?奥さん」
急に話を振る。
「まだ結婚はしてないよ。うん、元気だ」
私はふと一つの案を思いついた。
「君、実際ちゃんと飯を食べているのか?」
「…」
「舞台役者って体力勝負じゃないのか?」
「そうなんですけどね」
「うちに食べに来ないか?オクサンは、これが料理上手なんだ」
「いいんですか?」
君の目がキラッと光った。食べるのが好きなのは本当のようだ。
「奈緒の分もチケットを貰った、そのお礼もしたいし」
「あ、奈緒さんって言うんですね。オクサン」
「そう。今晩はどう?」
私は奈緒の携帯電話に電話を掛けた。君を家に招きたい旨を伝えると、彼女も喜んで承諾した。
「どう?」
「じゃ、お邪魔させて下さい」
嬉しそうに笑う。見ている方まで心が軽くなるような笑顔だ。
「稽古がこの後七時まであるんですよ」
仕舞いかけた携帯電話のサイドボタンを押す。背面の画面に時刻が表示された。四時五十二分。
「じゃあ、七時十分にまたここで」
「はい。わかりました」
君は立ち上がり、真っ直ぐゴミ箱へ向かった。そして稽古場へ戻って行く。私も立ち上がり、職場へ戻る。外回りの報告をして、残った仕事を片付けたら丁度良い時間になるだろう。
「あ、奈緒さんって言うんですね。オクサン」
「そう。今晩はどう?」
私は奈緒の携帯電話に電話を掛けた。君を家に招きたい旨を伝えると、彼女も喜んで承諾した。
「どう?」
「じゃ、お邪魔させて下さい」
嬉しそうに笑う。見ている方まで心が軽くなるような笑顔だ。
「稽古がこの後七時まであるんですよ」
仕舞いかけた携帯電話のサイドボタンを押す。背面の画面に時刻が表示された。四時五十二分。
「じゃあ、七時十分にまたここで」
「はい。わかりました」
君は立ち上がり、真っ直ぐゴミ箱へ向かった。そして稽古場へ戻って行く。私も立ち上がり、職場へ戻る。外回りの報告をして、残った仕事を片付けたら丁度良い時間になるだろう。
「ただいま」
「おかえり。いらっしゃい」
「こんばんは、初めまして」
あなたの伴侶となる奈緒さんは、柔らかい、という言葉がぴったりの女性だった。あなたのマンションを伺うのは初めてだけど、照明や調度など、あなたと奈緒さんの雰囲気に良く合っている。
あなたは俺を奈緒さんに、奈緒さんを俺に紹介した。
「千尋にも聞いたけど」
俺を見て奈緒さんは言う。
「本当に細いのね。折れそうよ」
「奈緒さんのご飯を楽しみにして来ました」
ありがとう、と柔らかく笑った。ご飯出来ているわよ。
食卓の上に広げられた料理の品々に、俺は思わず唾を飲んだ。彩りも鮮やかで、匂いも良い。見るからにおいしそうだ。
「どうぞ掛けて」
「あ、はい」
「おかえり。いらっしゃい」
「こんばんは、初めまして」
あなたの伴侶となる奈緒さんは、柔らかい、という言葉がぴったりの女性だった。あなたのマンションを伺うのは初めてだけど、照明や調度など、あなたと奈緒さんの雰囲気に良く合っている。
あなたは俺を奈緒さんに、奈緒さんを俺に紹介した。
「千尋にも聞いたけど」
俺を見て奈緒さんは言う。
「本当に細いのね。折れそうよ」
「奈緒さんのご飯を楽しみにして来ました」
ありがとう、と柔らかく笑った。ご飯出来ているわよ。
食卓の上に広げられた料理の品々に、俺は思わず唾を飲んだ。彩りも鮮やかで、匂いも良い。見るからにおいしそうだ。
「どうぞ掛けて」
「あ、はい」
決まった席なのか、あなたと奈緒さんは向かって座り、俺はその間の席に着いた。
「丁度出来上がったの。さ、食べて」
「頂きます」「いただきます」
見るからにおいしそうな物は、食べてもやはりおいしい。俺はみっともないとは解りながらも、どんどん箸を進めた。
「おいしい?」
はい、おいしいです。俺はそう言ったつもりだったが、はたしてそう聞こえただろうか。奈緒さんが笑み、あなたは喉で笑った。
「そんなにおいしそうに食べてもらえると、私も嬉しいわ」
「あの、」
今度はちゃんと飲み込んでから喋る。
「奈緒さんは、あまり食べないほうなんですか?」
「そう見える?」
見えない。と言ってしまえば失礼だが、奈緒さんはふっくらとした体型だ。
「私はね、私の作った料理をおいしそうに食べて貰うのが好きで」
奈緒さんはにっこりとあなたを見た。
「千尋は大学サークルの後輩なんだけど、」
「奈緒はマネージャーだろ?それは先輩と言うのか?」
「いいじゃない。でね、優ちゃん」
「はい」
「千尋がまたおいしそうに食べるのよ」
奈緒さんは頬を染めた。あなたの頬も赤い。
「奈緒。俺は君と暮らして体重が増えた」
「幸せ太りよ」
二人の左薬指には、同じデザインの指輪がそれぞれされている
「丁度出来上がったの。さ、食べて」
「頂きます」「いただきます」
見るからにおいしそうな物は、食べてもやはりおいしい。俺はみっともないとは解りながらも、どんどん箸を進めた。
「おいしい?」
はい、おいしいです。俺はそう言ったつもりだったが、はたしてそう聞こえただろうか。奈緒さんが笑み、あなたは喉で笑った。
「そんなにおいしそうに食べてもらえると、私も嬉しいわ」
「あの、」
今度はちゃんと飲み込んでから喋る。
「奈緒さんは、あまり食べないほうなんですか?」
「そう見える?」
見えない。と言ってしまえば失礼だが、奈緒さんはふっくらとした体型だ。
「私はね、私の作った料理をおいしそうに食べて貰うのが好きで」
奈緒さんはにっこりとあなたを見た。
「千尋は大学サークルの後輩なんだけど、」
「奈緒はマネージャーだろ?それは先輩と言うのか?」
「いいじゃない。でね、優ちゃん」
「はい」
「千尋がまたおいしそうに食べるのよ」
奈緒さんは頬を染めた。あなたの頬も赤い。
「奈緒。俺は君と暮らして体重が増えた」
「幸せ太りよ」
二人の左薬指には、同じデザインの指輪がそれぞれされている
「結婚式はいつなんですか?」
俺は唐突だとは思いながら聞いてみた。
「いつ?千尋」
「いつだろうな」
「決まってないんですか?」
「なかなか話を進めてくれないのよ」
「結婚したら、今の生活とどう変わるんだ?」
「私の苗字が変わって、千尋に扶養されるの」
「今とあまり変わらないじゃないか」
「保険とか税金とか」
「十河さん、結婚したくないんですか?」
ぽろっと口から出た言葉は、あまり望ましくない処に転がっていったようだ。一瞬、空気が止まった。
「何を言うのよ、優ちゃん。そしたら私、ここに居ないでしょう?」
奈緒さんは怒りも柔らかく伝える。
「そうですよね。失礼しました」
ただ笑うだけで、何も言わないあなたを怖いと思った。
俺は唐突だとは思いながら聞いてみた。
「いつ?千尋」
「いつだろうな」
「決まってないんですか?」
「なかなか話を進めてくれないのよ」
「結婚したら、今の生活とどう変わるんだ?」
「私の苗字が変わって、千尋に扶養されるの」
「今とあまり変わらないじゃないか」
「保険とか税金とか」
「十河さん、結婚したくないんですか?」
ぽろっと口から出た言葉は、あまり望ましくない処に転がっていったようだ。一瞬、空気が止まった。
「何を言うのよ、優ちゃん。そしたら私、ここに居ないでしょう?」
奈緒さんは怒りも柔らかく伝える。
「そうですよね。失礼しました」
ただ笑うだけで、何も言わないあなたを怖いと思った。
久しぶりの感覚だ。
「ちゃんと栄養にするんだろ?」
俺はあなたの車の助手席に乗って、心地よい満腹感に浸っていた。
「はい」
「普段は何を食べているんだ?」
「オールドファッション」
「だけ?」
「あとミルクティー」
「だけ?」
「嘘です。自炊はしないこともありません」
「嘘は良くない」
「十河さんだけには言われたくないですね。その先の信号を右です」
そうか、とあなたは笑ってハンドルを切った。
何となく、あなたを部屋に呼んでしまった。
「必要最低限、な部屋」
あなたは俺の部屋をそう例えた。基本的に物が少ない。
「どんどん色んなことをやるから、残したくないんです。過去の物とか」
「君は哲学家だな」
「そうですか?一番の理由は、節約ですけど。どうぞ」
俺はお茶を出す。緑茶の産地にある実家から送って貰ったものだ。
「今日の奈緒は随分嬉しそうだった。よかったら、これからもちょくちょく来ないか?」
「え、いいんですか?」
「奈緒には帰ってから話すけど、多分賛成してくれるだろう」
「やった」
「そんなに旨かったか?」
「はい。お店で食べたらかなりの値段がしてもおかしくないくらい」
「ちゃんと栄養にするんだろ?」
俺はあなたの車の助手席に乗って、心地よい満腹感に浸っていた。
「はい」
「普段は何を食べているんだ?」
「オールドファッション」
「だけ?」
「あとミルクティー」
「だけ?」
「嘘です。自炊はしないこともありません」
「嘘は良くない」
「十河さんだけには言われたくないですね。その先の信号を右です」
そうか、とあなたは笑ってハンドルを切った。
何となく、あなたを部屋に呼んでしまった。
「必要最低限、な部屋」
あなたは俺の部屋をそう例えた。基本的に物が少ない。
「どんどん色んなことをやるから、残したくないんです。過去の物とか」
「君は哲学家だな」
「そうですか?一番の理由は、節約ですけど。どうぞ」
俺はお茶を出す。緑茶の産地にある実家から送って貰ったものだ。
「今日の奈緒は随分嬉しそうだった。よかったら、これからもちょくちょく来ないか?」
「え、いいんですか?」
「奈緒には帰ってから話すけど、多分賛成してくれるだろう」
「やった」
「そんなに旨かったか?」
「はい。お店で食べたらかなりの値段がしてもおかしくないくらい」
この作家の他の作品
表紙を見る
「先生、わたしも弾きたい」
「俺たちが先生の運命を捻曲げたんだよ」
***
「先生」と、ピアノと、
ピアニスト達の愛情の物語。
│■■│■■■│
┴┴┴┴┴┴┴┴
表紙を見る
●
皎
皎
た
り
天
中
の
月
万策尽きた薬師が出会ったのは
美しい兎とひきがえる。
大切な人を救うために
今、何が出来るのだろう。
表紙を見る
むかし、むかし。
王様とお后様は
一人の女の子を授かりました。
その名は、『春夜姫』――
* * *
創作童話ですが、
メルヘンの王道をなぞっています。
全年齢対象
サイドストーリー
『鳥になった王子様』
併せてお楽しみ下さい。
※
完結編『春の夜と夏の空』を
執筆中です。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…