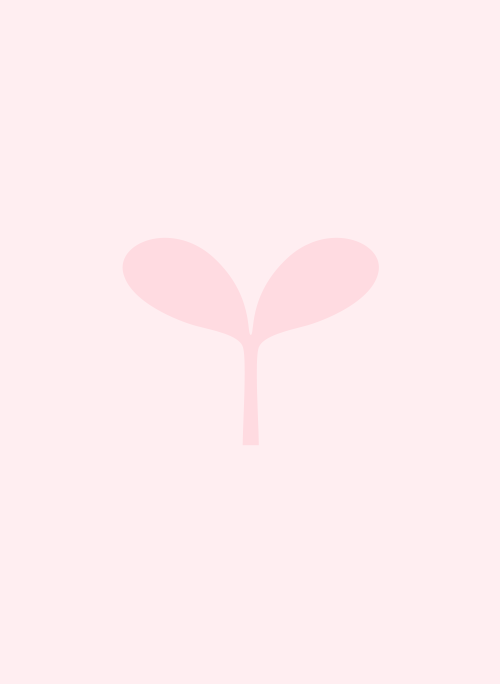君が主役を務めるという話を聞いた。と言うか、新聞の広告欄に宣伝が出ていたのを見たのだが。
奈緒がカレンダーと睨み合いをして、はや15分。膨らんだ腹を撫でながら、いつ劇場に行こうかと考えている。
奈緒、どこかで気付いているんだろうか。私と優の繋がりを。
確かに奈緒は愛している。彼女の中の、新しい命の誕生は私も楽しみだ。
でも、愛おしくてたまらないんだ。優。
「18日は?」
「え?」
「しっかりしてよ、パパ」
この日。
奈緒は赤いペンで来月の18日を指す。すでに赤く二重丸されてある。
「奈緒の誕生日だろ」
「そ。市役所行って、それから劇場。どう?」
市役所行って、つまり婚姻届を出して。
何を考えているんだか。
「大事な日だからダメ」
「どうして?」
「そんな大事な日のスケジュールを、奈緒には決めさせない」
嘘は習慣だ。
私は、煙草は嫌い、賭け事は興味がない、酒は下戸。でも嘘や冗談は滑らかに口から出る。
優、私は君との関係をどうしたらいいんだ。もう嘘ではごまかせない。答えを出さなければいけないんだ。
「千尋?」
奈緒が椅子に座る。
「劇場の方は、俺が考えておくよ。どの週の金曜日が病院かはわからないんだろ?」
「ねぇ、千尋」
私は奈緒の真面目な眼差しに驚いた。
「仕事大変なの?最近、上の空な時が多いじゃない?」
「そうか?」
奈緒は気付いているんだろうか。
「何かあったの?」
気付いているんだろうか。
「ねぇ」
気付いている、んだろうか。
「奈緒」
上手く出ろよ、嘘。
「奈緒の心配することじゃない。少しな、我が儘な先方がいるんだ。良い相手なんだけどさ。ここからは企業秘密。ごめん、家に持ち込まないようにはしていたんだけど」
どうだ。
「そっか」
奈緒は柔らかく笑った。私はその笑顔を見て、ふと気付いた。
「奈緒、化粧が濃くないか?」
ふふ、と奈緒は意味ありげな声を立てる。
「やっと気付いたのね。よっぽど大変な仕事なんだ」
「てっきり、浮気してるのかと思ったから」
限界、なんだろうか。
全部話してくれたあなた、私はどうすればいいんだろう。許す?認める?諦める?
そもそも、私があなたに声を掛けようとしたのは、あなたが結婚について悩んでいて浮かない顔をしていたから。私があなたに向かわなければ、あなたを知ることも、好きになることもなかった。
あなたと奈緒さんは、やっぱりお似合いだと思う。奈緒さんに赤ちゃんができたことにも、おめでとうと言いたい。
そうか。
私は嫌われるのが嫌いなんだ。嫌われたくないから、あなたが好きだし、奈緒さんを嫌いたくない、嫌いになれない。
「優」
「…寺田さん」
今度の演目で、寺田さんが私のパートナーとなる。
「元気ないんじゃないのか?せっかく、デカい役できるのに」
小さなレッスン室、私は鏡越しに寺田さんと話している。ペットボトルを握る。体が震えていた。
「優?」
私はペットボトルを投げ出して、ピアノに突っ伏した。ガン、と不協和音が鳴る。打ち付けられた腕が痛い。何故か涙が出た。あなたから話を聞いた後も、一人でいる時も涙なんか出なかったのに。
「優」
幅の広いピアノの椅子、隣に寺田さんが座った。私の肩に手を置く。
「どうした」
言うはずかない。泣き声が大きくなる。
そもそも、私があなたに声を掛けようとしたのは、あなたが結婚について悩んでいて浮かない顔をしていたから。私があなたに向かわなければ、あなたを知ることも、好きになることもなかった。
あなたと奈緒さんは、やっぱりお似合いだと思う。奈緒さんに赤ちゃんができたことにも、おめでとうと言いたい。
そうか。
私は嫌われるのが嫌いなんだ。嫌われたくないから、あなたが好きだし、奈緒さんを嫌いたくない、嫌いになれない。
「優」
「…寺田さん」
今度の演目で、寺田さんが私のパートナーとなる。
「元気ないんじゃないのか?せっかく、デカい役できるのに」
小さなレッスン室、私は鏡越しに寺田さんと話している。ペットボトルを握る。体が震えていた。
「優?」
私はペットボトルを投げ出して、ピアノに突っ伏した。ガン、と不協和音が鳴る。打ち付けられた腕が痛い。何故か涙が出た。あなたから話を聞いた後も、一人でいる時も涙なんか出なかったのに。
「優」
幅の広いピアノの椅子、隣に寺田さんが座った。私の肩に手を置く。
「どうした」
言うはずかない。泣き声が大きくなる。
寺田さんは私の肩を持って、ピアノから剥がした。私は椅子に横向に座り、泣き続ける。寺田さんはピアノを弾き出した。ファイの子守歌。
キラキラした右手、レガートで分散和音を奏でる左手。目を閉じて、眠りなさい。寺田さんの深いテノールが、部屋に響く。体をそっと包み込む、暖かい毛布のような歌声だ。やっぱり、子守歌はお父さんが歌うべきなんだ……。
気が付くと、私は休憩室のソファーにいた。寺田さんの声ではなく、本物の毛布も掛かっている。顔を上げて、時計を見た。大練習室で二部の通しが始まる。
「すみませんでした。何か、取り乱しちゃって」
「初めての主役だからな。疲れてんだろ」
「そうですね…」
「そんなに気負いするなよ。適当にやれ、適当に」
「寺田、天野に変なこと吹き込むな」
ういー。
私の居場所は、舞台の上。立って、芝居して、歌う。この場所が好きだ。
「優、今日の帰り」
どうだ?寺田さんは酒を飲む仕草をした。私はちょっと考えて、少しなら、と指で答える。
それから、とレッスン室で投げてしまったペットボトルを渡された。
「あー、ありがとうございます」
「…失恋でもしたのか?」
「へ!?」
「そうか。だから荒れてたんだな」
「ちょっと勝手に話を進めないで下さいよ」
「まあ飲め飲め」
「…寺田さんの奢りですよね」
寺田さんはまあまあ、と私のコップにビールを注ぐ。
「で、誰だ?相手は」
「失恋したならいいじゃないですか、関係ないでしょう」
「それはこっちの台詞だ。ちゃんとケリつけもらわないと、仕事に響くだろ」
私はビールを一口飲んだ。口の中に苦みだけが残る。
「寂しいなら、俺フリーだからな」
「…何言ってんですか?」
「俺、割とお前のこと好きだよ」
酔っ払いだ。
「今、俺のこと酔っ払いだと思ったろ」
「はい」
け、とか言いながら、寺田さんは肉じゃがを突いた。さすが売り物なだけに味はいいけど、奈緒さんの肉じゃがの方が優しい味だと思う。
「寺田さん」
「ん?」
「何で俺、主役貰ったんですかね」
「…人称、戻ってる」
「あ」
意識していたのに。
「ファイが当たったからじゃないか?モーリスも結構ハマってたけど、女もできる、って声かなり上がってた。あと、リエちゃんが寿退団したからな」
「だからって俺が主役…」
「何だよ、お前らしくねぇなぁ」
俺…私は席を立った。もう帰ろう。
「どうした」
「すみません、手洗いに」
ビールも肉じゃがも、全部流れていく。水洗トイレって有り難い。
「はぁ」
トイレを出て、そのまま店の外に行く。ペットボトルの水を一口。背中を通る夜の空気が頭をすっきりさせる。お腹もすっきり、頭もすっきり。これであなたとの関係もすっきりどうにかなれば良いのに。
「優ちゃん」
部屋の前に、奈緒さんがいた。びっくりした。
「…どうしたんですか?」
奈緒さんは私の前に箱を出す。中からシナモンが香る。
「アップルパイなんだけど、一緒に食べない?」
「あ…」
返事をする前に、お腹が鳴った。どうせ吐くんだろうけど。
鍵を開けて、部屋の明かりをつける。奈緒さんにスリッパを出して、ソファーに案内した。
「紅茶、ですね」
「そうね」
軽く手を洗い、やかんに水を入れてコンロにかける。その間に、包丁、取り皿二枚、フォークを二つ。カップとティーポットに、湯沸かし器の一番熱いお湯を入れた。
お湯が沸くのを待ちながら、念入りに手を洗う。うがいをして、一度奈緒さんのところへ。
「料理上手な人って、本当、憧れます」
返事がない。
「奈緒さん?」
「優ちゃん」
奈緒さんは部屋を物色していた。クローゼットやチェストが開けられている。
「何…」
「…可愛い下着ね。これで千尋を誘ったわけ」
「え?」
「解ってるのよ」
奈緒さんのギラギラした目が恐い。白雪姫は魔女にこうアドバイスされた。男の人が好きなのはアップルパイよ。
「あなたが千尋を奪った」
二の句が継げない。ふふ、と奈緒さんが笑う。
「否定しないのね」
「そんな、私は…」
「私。色気付いたつもり?」
「違います」
「じゃあ千尋は?」
「千尋さんは」
好きです。好き…だから。嫌わないで。奈緒さんも俺を嫌わないで。
やかんの高い音。沸いた。
コンロの火を消す。音は頼りなく萎み、湯気が上がった。お茶をいれる。
もう吐くモノなんてないのに、吐き気がしてトイレに駆け込む。肩で息をして、何とか落ち着こうとする。ポケットに入っていた携帯電話を開いて、リダイアル、通話。耳に当てて待つ。
「…優?」
「助けて…」
奈緒さんの足音。俺は電話を切った。
「優ちゃん」
声が、低い。恐い。
「…お客さんよ」
部屋の前に、奈緒さんがいた。びっくりした。
「…どうしたんですか?」
奈緒さんは私の前に箱を出す。中からシナモンが香る。
「アップルパイなんだけど、一緒に食べない?」
「あ…」
返事をする前に、お腹が鳴った。どうせ吐くんだろうけど。
鍵を開けて、部屋の明かりをつける。奈緒さんにスリッパを出して、ソファーに案内した。
「紅茶、ですね」
「そうね」
軽く手を洗い、やかんに水を入れてコンロにかける。その間に、包丁、取り皿二枚、フォークを二つ。カップとティーポットに、湯沸かし器の一番熱いお湯を入れた。
お湯が沸くのを待ちながら、念入りに手を洗う。うがいをして、一度奈緒さんのところへ。
「料理上手な人って、本当、憧れます」
返事がない。
「奈緒さん?」
「優ちゃん」
奈緒さんは部屋を物色していた。クローゼットやチェストが開けられている。
「何…」
「…可愛い下着ね。これで千尋を誘ったわけ」
「え?」
「解ってるのよ」
奈緒さんのギラギラした目が恐い。白雪姫は魔女にこうアドバイスされた。男の人が好きなのはアップルパイよ。
「あなたが千尋を奪った」
二の句が継げない。ふふ、と奈緒さんが笑う。
「否定しないのね」
「そんな、私は…」
「私。色気付いたつもり?」
「違います」
「じゃあ千尋は?」
「千尋さんは」
好きです。好き…だから。嫌わないで。奈緒さんも俺を嫌わないで。
やかんの高い音。沸いた。
コンロの火を消す。音は頼りなく萎み、湯気が上がった。お茶をいれる。
もう吐くモノなんてないのに、吐き気がしてトイレに駆け込む。肩で息をして、何とか落ち着こうとする。ポケットに入っていた携帯電話を開いて、リダイアル、通話。耳に当てて待つ。
「…優?」
「助けて…」
奈緒さんの足音。俺は電話を切った。
「優ちゃん」
声が、低い。恐い。
「…お客さんよ」
鍵が開いていた。
ドアを開けて中に入ると、見慣れた靴があった。反り返りが良くて、クッション性があって、とっても歩き易いの。確かそんなことを言っていた。
それと、いつものスニーカーと、履き込まれた男物の革靴。
「…」
無言のティーパーティー。紅茶とシナモンの匂いが漂っていた。
参加者は、君と奈緒と、確か寺田とかいう男。
「…誰だあんた」
私に一早く気付いたのは寺田だった。その声に君と奈緒が顔を上げる。
「「千尋」さん」
「…あんたが」
寺田は立ち上がった。私に掴みかかろうとする寺田を君が止める。
「優!」
「止めて下さい…悪いのは全部俺…」
ふん、と脇で聞いていた奈緒が鼻を鳴らす。
「どうして…奈緒はここにいるんだ?」
「どうして?自分こそどうしてよ。千尋」
そんなこと言ったって、もう全部を知っているんだろう?君は奈緒と寺田に洗いざらい話してしまったんだろう?
私はどうしたらいい。
「お茶を貰っていいかな」
紅茶を無言のまま飲み、冷めているが味のしっかりした奈緒のアップルパイを食べた。正直、美味しい。もとから君のところへ持ってくるつもりで作ったのだろうか。どんな気持ちで作ったのだろうか。
「…こうしましょう」
君は小さな声で提案した。
「俺はここを引っ越します。もう、千尋さんにも奈緒さんにも会いません」
声は震えている。その細い肩を、しっかりと抱き締めたい。
「でも優ちゃん、劇団は続けるんでしょう?千尋も私も、あなたがどこにいるか知ってるのよ?」
「あんた、優に辞めろって言うのか?」
奈緒と寺田が睨み合う。奈緒は不適に笑った。
「あなたのお嫁さんにでもすればいいじゃない」
私は奈緒の横顔を見て、それから寺田の顔を見た。満更でもなさそうな顔だ。
「優ちゃんはあなたに助けを求めた訳だし」
「……」
優を虐めて楽しいか、と奈緒に言いたくなる。けれども、理に適った感情かもしれない。
「…別れるか」
私は奈緒に向けて呟いた。
「嫌だろう、こんな男は」
「…あんた正気か?」
寺田に睨まれた。
「子供孕ませといて、そんな無責任なこと良く言えるな」
「もちろん金銭的な責任は…」
「…こうしましょう」
君は小さな声で提案した。
「俺はここを引っ越します。もう、千尋さんにも奈緒さんにも会いません」
声は震えている。その細い肩を、しっかりと抱き締めたい。
「でも優ちゃん、劇団は続けるんでしょう?千尋も私も、あなたがどこにいるか知ってるのよ?」
「あんた、優に辞めろって言うのか?」
奈緒と寺田が睨み合う。奈緒は不適に笑った。
「あなたのお嫁さんにでもすればいいじゃない」
私は奈緒の横顔を見て、それから寺田の顔を見た。満更でもなさそうな顔だ。
「優ちゃんはあなたに助けを求めた訳だし」
「……」
優を虐めて楽しいか、と奈緒に言いたくなる。けれども、理に適った感情かもしれない。
「…別れるか」
私は奈緒に向けて呟いた。
「嫌だろう、こんな男は」
「…あんた正気か?」
寺田に睨まれた。
「子供孕ませといて、そんな無責任なこと良く言えるな」
「もちろん金銭的な責任は…」
「馬鹿千尋」
声は、君のものだった。
「ゆ…」
「呼ぶな」
そう言い放って、君は奈緒の方を向いた。
「奈緒さん」
君は細い体を折る。
「ごめんなさい…パイ、とってもおいしかったです。有難うございました」
そのまま。
「だからもう、帰って下さい。千尋さんと帰って下さい」
そのまま。
「お願いします…千尋さんにおいしいご飯を作って下さい。元気な赤ちゃんを産んで、千尋さんと一緒に育てて下さい」
カーペットにポツポツと染みができた。君の涙だ。
奈緒は立ち上がった。
「私は千尋が好きなの。愛してるの。だから結婚するの。子供も産むの…優ちゃんに言われるまでもないわ」
奈緒は私の腕を掴んで引っ張り、立たせた。私は呆然としてしまって、されるが儘になっている。
「帰りましょう」
歩いてよ。奈緒が私の背中を押す。君は腰を曲げたまま動かない。寺田は私達を睨みつけ、早く出ていけと促す。この後、寺田は君をどうするんだろうか。君の足元の染みがどんどん大きくなっていく。
「優…」
もう呼ばないで。
口だけが動いてそう言った。
この作家の他の作品
表紙を見る
「先生、わたしも弾きたい」
「俺たちが先生の運命を捻曲げたんだよ」
***
「先生」と、ピアノと、
ピアニスト達の愛情の物語。
│■■│■■■│
┴┴┴┴┴┴┴┴
表紙を見る
●
皎
皎
た
り
天
中
の
月
万策尽きた薬師が出会ったのは
美しい兎とひきがえる。
大切な人を救うために
今、何が出来るのだろう。
表紙を見る
むかし、むかし。
王様とお后様は
一人の女の子を授かりました。
その名は、『春夜姫』――
* * *
創作童話ですが、
メルヘンの王道をなぞっています。
全年齢対象
サイドストーリー
『鳥になった王子様』
併せてお楽しみ下さい。
※
完結編『春の夜と夏の空』を
執筆中です。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…