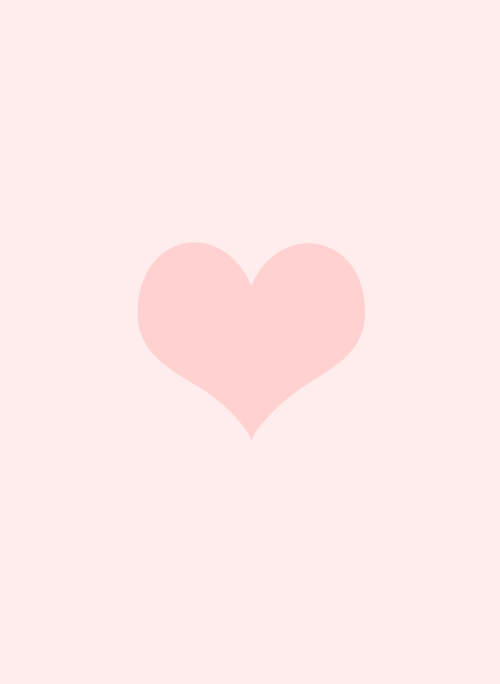目指すはただ一つ。
会場から出て行ってしまった
背中。
人気の無い裏庭にぽつんと
見えたその背中に、
私は思いきり抱きついた。
その背中の持ち主は
びくりとしたけれど、
こちらを向くことはしなかった。
だけど私は真っ赤なその耳に
答えを見つけて
言葉がついに口から飛び出した。
「好き。」
やっと言えた。
ずっとずっと君に言いたかった。
でも言えなかった。
言えない理由は月並みなものばかりで、口に出すのも恥ずかしいけれど、それでも言えないものは言えなかった。
でも、
あんなのかかれたら
追いかけずには居られない。
あんなのかかれたら、
好きだと告げない理由がない。
だって君がくれたのは。
「俺も。」
「“好き” 」
私と同じ、二文字の言葉。
私と同じ、意味の“好き”。
手をつないでベンチに座る。
私が書いた手紙を君に渡す。
すると君は目を開いて
驚いてから
満面の笑みを浮かべて
ささやいた。
同じ気持ちをありがとう。
君の走り書き、
私のラブレター。
どちらも同じ“好き”の形。
でも次に書くときは
“好き”じゃない。
“大好き”
にしよう。
私は君に内緒で微笑んだ。
声がした。
頭の中で優しく囁くように声がした。
ジリリリ......
「ほーぃ、と。」
誰にと言うわけでもなく
自分で設定したアラームを消す、
朝七時。
二日酔い、ガンガンの頭。
ダブルベットに、一人の私。
昨日も行きつけのバーで
一人で煽り酒。
飲んで、飲んで、飲んで。
一つの記憶、消したくて。
それなのに、頭に残る
私を咎める言葉。
「また飲んだの?」
お酒の飲めない彼。
お酒の好きな、私。
「電話、いつでもしていいのに。」
「おそいからー」
呂律の回らない私、
笑う彼。
「君からなら、いつでも嬉しいのに。」
酔ってるくせに、ときめいた。
結局幾度肌を重ねても、
数えきれないほど熱を分けあっても。
電話だけはできなかった。
残ったベットは広すぎて
こうして君の声が
遠くで鳴り響く。
あぁ、会いたい、なんて。
なんて私はバカなんだろう。
そんな、朝七時。
日曜日。
広すぎるベットに沈み
きつく目を閉じた。
この作家の他の作品
表紙を見る
失恋した、
失望した。
何も無い、空っぽのわたし。
そんなわたしの目の端に
「黒」。
一瞬で心を奪われた。
*幼なじみ攻略法シリーズの
登場人物も出演しております。
表紙を見る
ずっと、探してた。
ごめんなさいを、言いたくて。
ずっと、隠してた。
さよならを、言われたくなくて。
ずっと、嘘ついてた。
いつか消えるを、口癖にして。
ずっと、泣いていた。
大丈夫だと、言い聞かせて。
表紙を見る
「旅行行こう。」
黒い青年がすっと一枚の紙を差し出した。
「温泉でしょ!」
金の男の子はキラキラした目で私を見つめ、
「箱根が好きです。」
お日様のような女の子の笑顔は眩しい。
「車が良いとかは言わないんで!」
美人な女の子が顔の前で手を合わせれば、
「個室露天でぜひ。」
物凄いイケメンが物凄い決め顔で
そんなことを口走った。
さて、問題です。
.......何故こうなった。
幼馴染み攻略法番外編!
今回はあの六人で!旅行に!
行っちゃいます。
かなりシリーズネタになりますので
宜しければ幼馴染み攻略法シリーズを
後拝読なされるとより楽しめるかと
思います。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…