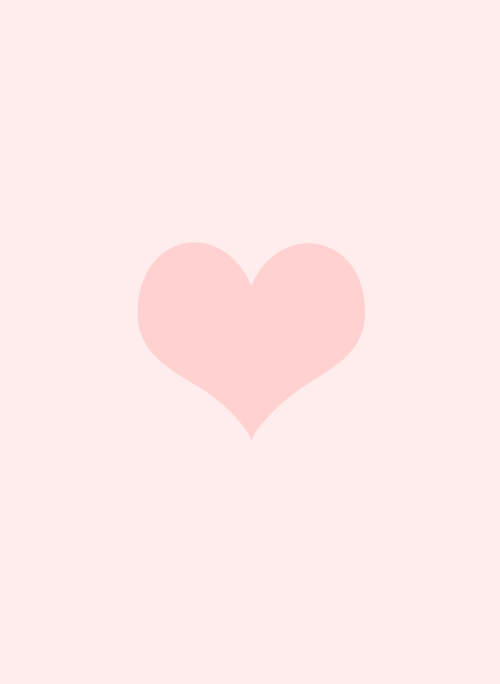【Side:千秋】
遥は、俺の彼女だった女だ。
一年前、俺に突然別れを告げ、消えた。
どこぞの御曹司と結婚するべくベルリンにいると風の噂で聞いていたが、結局俺と復縁したいとそいつと別れてきたらしい。
あのときはそのわがままもかわいかった。
でも、俺は今和葉に恋をしている。
二人で会いそう説明していたら、和葉たちも同じカフェに入ってきた。
面倒なことになる。
俺の予感は的中した。
.
―――週明け、遥は大学までやって来た。
「ねぇ、千秋。…私千秋のこと諦めるわ」
いきなりそう言う遥に警戒しつつも、俺は用事のためいったん部屋を離れた。
…携帯を部屋に置きっぱなしで。
その間に、あいつは俺になりすまして和葉にメールを送っていた。
罠をかけたんだ。
「ねぇ、千秋。最後にキスしてくれたら諦める。二度と近づかないわ」
戻ってきた俺に、遥はそう持ちかける。
俺は動かなかった。
そして暗黙の了解のように腕を回し、唇を重ねてきた。
以前だったらむしゃぶりついただろう。
でも今は、たった一瞬触れただけの和葉の唇がほしかった。
何も感じないキス。
遥のかけた罠は完成した。
.
―――ガタンッ!
ドアに何かがぶつかった音がした。
磨り硝子に一瞬映ったシルエットに、俺は血の気が引く思いだった。
遥をはねのけ、その人影を追いかける。
「―――和葉!」
しかし和葉は止まらなかった。
…俺の掌から滑り落ちるように行ってしまった。
「あーあ、行っちゃった」
この一言で、俺はすべてに気づいた。
つかつかと遥に近づき、その長い髪を掴む。
「ちょっ…痛いじゃない!」
騒ぐ遥にお構いなしで、俺は警告した。
「…次に顔を見せたら、ただじゃ済まさないからな」
.
「和葉、…落ち着いた?」
私は今、絵美のアパートにいる。
あのあと、授業が終わった頃を見計らって絵美に助けを求めた。
絵美に一通り話をすると、絵美は私の手を引き自分のアパートに連れてきたのだ。
そして、こう言いながら泣きはらした私に冷たいタオルを渡してくれた。
「ん。…なんとか」
本当は、あの光景がずっと頭から離れない。
――なにもしていないのに失恋しちゃうなんて。
やっぱり私にはもう恋なんてできないんだ。
特大のナイフが私の癒えかけた心臓にどっかりと刺さってしまった。
「絵美」
「ん?」
「私、やっぱりもう恋はしないよ」
絵美の表情が曇ったが、私はまた涙が溢れてきて見えなかった。
.
そのまま今夜は絵美のアパートに泊まることにした私は、絵美と一緒に夕食を作ったりお笑い芸人のバラエティー番組を見て過ごした。
絵美がいなかったら、こんなに穏やかにしていられなかっただろう。
そう感じていたときだった。
―――♪♪♪
私の携帯が鳴る。
私たちは顔を見合わせ、携帯を見つめた。
ディスプレイには“小早川千秋”の文字が表示されている。
「…絵美、出てよ」
私がそう言うと、絵美は無言で頷き電話に手を伸ばした。
「はい」
絵美が電話に出たのを確認して、私は思わずトイレに隠れた。
また、涙が溢れた。
.
何を話しているのだろうか。
聞きたいのに、聞きたくない。
私は耳を塞いでしゃがみ込んだ。
…でも、もう一人の私は必死に会話を聞こうとしている。
そして、何も聞こえないことに落胆しているのだ。
―――コンコン
「和葉、終わったよ」
絵美がドアの外から話しかけてきた。
私はそっとドアを開け、絵美のあとをついて部屋に戻る。
「小早川先生、今から迎えに来るって」
絵美は私に背中を向けながらそう言った。
.
「……何しに」
何しに来るの?
――イヤだ、会いたくない!
「和葉、ちゃんと向き合ってきな」
振り返り、絵美は涙ながらにそう言った。
「絵美――…」
「しっかり話つけて、それで振られちゃったんなら一緒に泣くから。私がついてるんだから大丈夫!ねっ?」
「……うん」
うん、そうだね。
どうせこれが最後になるんなら、ちゃんとぶつけてこよう。
「がんばる」
そう言って、私は心から笑った。
絵美も、つられて笑った。
.
それから数分後、絵美の家のチャイムが鳴った。
絵美が玄関に出ると、私はまた泣きたくなった。
悪い方にしか想像できなくて、壊れてしまいそうで、逃げ出したくてたまらなかった。
「…和葉!」
私の姿をとらえて、私の名前を口にする千秋さん。
あれだけ聞きたかったその声も、今は私の不安を増幅させてゆく。
私は、返事をすることもなく玄関へ向かった。
「行ってらっしゃい」
絵美が笑顔で見送ってくれた。
…うん、行ってくる。
私は千秋さんのあとを追い、車に乗り込んだ。
このまま千秋さんの家に行くらしい。
私は両手をぎゅっと握り、心を落ち着かせようとした。
.
私は、卑怯だから。
顔を見たら泣いてしまいそうだから。
だから運転している間に言ってしまおうと思います。
「私、言いたいことがあります」
しばらく信号が青になる気配がない。
…今が唯一のチャンスだろう。
「えっ?」
千秋さんはいきなりのことに疑問の声を出す。
私は、そんな彼にかまうことなく続けた。
「…好き、です」
私はまっすぐ前を向きながら告白した。
「ごめんなさい。でも、顔見たら…」
―――ぽたっ。
ぽた、ぽたっ。
泣かないで言いたかったのに、もう手遅れだった。
私は大粒の涙で頬を濡らしていた。
.
この作家の他の作品
表紙を見る
私の初めては
あなたにあげるから
あなたの初めても
…私にちょうだいね?
**********
里谷詩穂(22)
新入社員
×
高野 昴(27)
イケメン上司
**********
“初めて”の行方は
二人だけが知っている
表紙を見る
今日も明日も、君を。
ただひたすら、愛してる。
**********
七原 栞奈(ナナハラカンナ)
×
真山 恭平(マヤマキョウヘイ)
**********
.
表紙を見る
普通のOLである新城 早百合(しんじょうさゆり)24歳
あることがきっかけで、ちょっと変わった相手に好かれてしまう。
「――あなたの愛は、いずれ俺がもらいます」
妙に自意識過剰で俺様な、変わり者とも恋の行方は!?
*甘甘系を目指しています*
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…