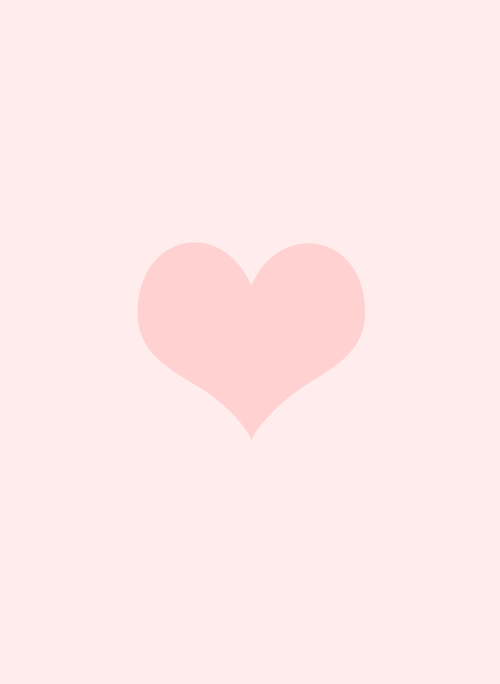「見えたよ」
「ふふっ」
ニヤニヤニマニマしてるふたり。
昇降口側は、あたし達の教室から丸見えなんだ。
この笑いからして、さっきの出来事は筒抜けなのだと見て取れる。
「んふっ! 恭一くん好き……」
“人のモン”=彼女。
んふふ……っ。
んふふふふふ……っ。
机の上に突っ伏して堪えきれない笑みをこぼし続けた。
王子のことを想っている女の子たちにも多少は見えてたハズ。
少しは嫌がらせに効果が出るかもなんて呑気に考えてた。
「で? 何があったの?」
――あ、そだ。
まだ話してないんだった。
解決には至らず、まだ未解決のままだけど。
どうやらイタズラではなく……、“本物の”挑戦状らしい。
あたし宛てに。
「こんなのもらったの」
スカートのポケットから、例のモノを取り出す。
「――あ、これ」
いち早く異変に気が付いたのは、オシャレ番長の比奈だ。
「……うっ、くさ」
香水が苦手なキナは、まだ強く残る香りに眉を寄せた。
「キナ、そんなしわ寄せてると、クールビューティーな顔が台無しだよ」
と、あたしから一言。
「何か知ってるの?」
「これ、期間限定で発売された香水」
――彼とデートした時、たまたまウィンドウに飾られてたの。
「コンセプトは“意中の彼を振り向かせる”香り」
――表には出なかったけど、これって裏テーマもあるの。
「え? 何?」
やたらと詳しい比奈に、その続きを催促した。
「略奪愛」
“あなたの大事なものを奪ってあげる”
瞬間――3人の視線が、この文字に注がれた。
「で? 何で昼、あんな場所に行ってたんだよ?」
ひとり仲間外れにされた王子は、昨日に引き続き不機嫌だ。
「じゃあどうして、あたしに気付かなかったの?」
――お昼休み、恭一くんの教室に行ったんだよ?
「女の子に囲まれててさ……」
ぶーっと、唇を尖らせた。
「何? ヤキモチ?」
“そうですよ”と目で訴えると、まるで勝ち誇ったように――スッと目を細めた。
「行こうとしたら、ちょうどいなくなってたんだよ」
なんちゅー、タイミングの悪さ。
そんな小さなすれ違いから始まって、気が付けばふたりの間には、大きな溝。
フッと過ぎった、恐ろしい考えをパパパと手を振って追いやる。
「……ん、」
拗ねた子供のように、無言のままポケットからソレを取り出す。
反応を見たくて、じいっと王子の瞳を見つめた。
「なんだよ、これ」
それを手に取った瞬間。
――多分、あの香りが鼻に届いた瞬間だと思う。
「……」
ショコラ色の瞳が、陰った。
「――…ねぇね、」
「……―――お……お…い!」
「んぁ……?」
「どうしたんだよ?」
今日もパパとママは帰りが遅いらしくて、兄弟だけでテーブルを囲っていた。
ココとハルに呼ばれて、ハッと気が付く。
あたし……どれくらいぼぉーっとしてたんだろ。
「さっきからブツブツいってっけど」
お皿に置かれたフォークがカランと乾いた音を鳴らした。
コップの麦茶を喉に流し込むハルは、あたしを見上げた。
「ちょっと、ね……」
そんなことを言いながら、帰りのあの場面を頭の中で何度も再生していた。
巻き戻しては、再生し、また巻き戻して――…。
――『……』
カードを見つめる彼の瞳は、付き合い始めた頃と同じ色。
……ううん、付き合う前の色だ。
――『知ってるの?』
そう聞いたあたしに、彼は何も答えてはくれなかった。
その後も会話をすることはなく、あたしのことも送ってくれなかった。
今は、
そんなことが問題なんじゃない。
あの香りと、王子の繋がり。
あの女の子……との、繋がり。
やっと噛み合った、ふたつの歯車なのに。
闇に隠れてて、見落としていたんだ。
“彼”の歯車には、もうひとつ歯車が噛み合っていたことを。
言いようのない不安に呑み込まれそうになりながら、布団の中でぎゅうっときつく目を閉じた。
あんまり気にしてなかった。
転校生が来るって話。
「今日らしいよ」
「その話で持ちきり」
クラスの皆は、なんだかソワソワ落ち着かない様子だった。
それこそ、可愛い子がいいとか、カッコいい男の子だとか。
今のあたしには、別にどうでもよかった。
そんなことよりも、微妙にぎくしゃくしてしまった彼との関係。
――その方が、大問題なのだ。
ふと、恭一くんに会いたくなって
転校生の話で盛り上がっている、キナと比奈に一言告げて。
あたしは彼の教室へと行ってみることにした。
……ああ、なんかダルい。
最近のあたしは、何かおかしい。
暴走し過ぎちゃって、疲れちゃったのかな。
燃料切れ――?
元気だけが、取り柄なのに。
あたしから妄想と暴走と、元気を取ったら何が残るんだろう。
重たい足取りのまま歩いていたら教室を通り過ぎ
気が付けば、校長室の前まで来ていた。
「無意識ってコワい」
独り言をこぼして、きびすを返した時だった。
「どーゆー事!?」
甲高い女の子の声と、机をバシン!と叩く音。
……え?
な、……何?
足が、そのまま床に張り付いたように動かない。
「あたし1組って希望出したんですけど」
「……ですから」
強気な声に、その後に続くか弱い校長先生の声。
「1クラス何名までって決まっているんです」
「じゃあせめて、隣のクラスがいいです」
「3組しか空いていなかったんですよ」
ハンカチで顔の汗を拭う校長の姿が想像出来た。
……え、?
この部屋にいるのが、転校生?
ということは――女の子?
今、学校中で盛り上がっている転校生。
それを1番乗りで知れたこと。
再びあたしは女探偵に成り変わりドアにピタリと耳を引っ付けた。
「クラスに案内しましょう」
ガタン、と椅子が音を鳴らす。
校長先生が立ち上がったんだ!
なぁんだ、もうちょっとお話聞きたかったのに。
ドアから耳を離すことを忘れたあたしは、そんなことをぼんやりと思ってたんだ。
「いいです! 自分で行けます」
気が付けば、いきなりドアが開いて――あたしは後ろへと飛ばされた。
「痛ったぁ……」
耳を押さえて、お尻に走る痛みに耐える。
「え? ――あ、」
目の前、あたしに気付いた噂の転校生は呆気にとられた声を出してる。
きっとドアのすぐそばに人がいるなんて……予想してなかったんだろう。
「大丈夫?」
あたしに怪我を負わせた張本人がしゃがみこんで手を差し出す。
あ、意外に優しい子――。
クラスは3組っていってたけど、何年生だろ?
顔を上げる前に上履きの色をチェック。
1年生の色だ。
差し出された手をしっかり握って立ち上がろうと引っ張られた瞬間だった。
その子とあたしがほんの少し近づいた時。
“あの香り”が鼻を掠めたんだ。
そのままグイッと力強く腕を引っ張られ、あたしは立ち上がれた。
「――…、あ……」
目を見開いて、目の前の女の子をマジマジと見つめる。
肩まである、指通りの良さそうな髪の毛。
黒くて吸い込まれそうな、強気な瞳。
ナチュラルなメイクに、白くて細長い足。
な、に……?
このカンジ――――。
この子、何かあたしに似てない?
「あたし、小宮胡桃っていうの」
――よろしくね!
男は度胸、女は愛嬌って昔から聞くけど。
目の前で微笑む、胡桃って子は、このふたつを併せ持っている気がした。
あたしと同じ強気なオーラ、負けず嫌いな性格。
外見に加え中身まで。
どことなくあたしに似ているって勝手に思ってしまう。
「彼は返してもらうね」
大きな目をくりくりさせて、似合わないセリフを吐いたんだ。
「本当はちぇりちゃんと同じクラスが良かったのになぁ」
なぜか、突き飛ばしたあたしにクラス案内を頼んできて。
さっき校長室から聞こえてきた1組って、あたしのクラスだったんだ。
「コレ、送って来たの……アナタでしょ?」
「あはっ、アタリ」
“あなたの大事なもの”
それは、……恭一くん以外ありえない。
でも、分からないのは胡桃ちゃんと王子の関係。
薄々気が付いてたけど――…
認めたく、ない。
けど、認めなくちゃいけない。
つまらない意地を捨てなきゃいけない時がきた。
「ちぇりちゃんって、勘、いいでしょ?」
全てを見透かすような瞳をあたしに向けて、淡いピンク色の唇の端をニイッと上げた。
この作家の他の作品
表紙を見る
本編では描かれなかった
もうひとつの蜜なお話★
◇ * ◆ * ◇
凜久 ― RIKU
×
瑠璃 ― RURI
×
Honey Love
◇ * ◆ * ◇
ちょっぴり
覗いてみませんか――…?
START 09.12.25
8.29.Sun
◇ラブ・ホリディ up*
表紙を見る
.・:*゚+・:・*:・゚・:*゚+゚*:・:・:*゚+゚・
・+・゚.・゚ ゚・.゚・+・
:*.゚ ゚.*:
:・ ・:
゚ ゚
ひとつの影から
走り出す LOVE
影に恋しちゃったオトコ
未来
×
冷たい瞳を持つ寒がりなネコ
美桜
――ねぇ 君は
一体何を隠しているの?
゜・*:.。. My girl .。.:*・゜
今夜キミを、奪いに行く――
start 09.12.24
end 10.5.2
* T h a n k s ! *
Misa☆ さま
日和♪+* さま
表紙を見る
私が好きになったのは
私よりちょっぴり背の低い
男の子
* ◆ * ◆ *
「ねぇ、瑠璃」
―ほらそうやって
「このままキスしちゃおっか」
――これ以上私を惑わせないで
身長差は変わらず3㎝
私だってドキドキさせたいの
やられっぱなしじゃいられない
3 2 1 …
0 ゼロ―――
加速し始めるカウントダウンは
はじける恋の予感を示す
蜜の味
* * * *
こちらは
「年上カノジョに蜜な罠」の続編となっております
そちらを先に読んで頂ければ
幸いです 壁|ω`*)゙
Start 09.8.31
End 09.12.20
。* Special Thanks *。
柚子こしょう★*゜さま
Misa☆ さま
りちゃこ さま
日和♪+* さま
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…