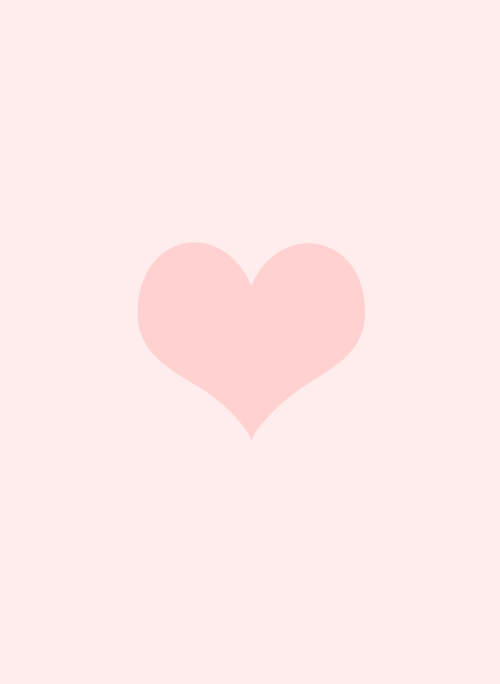一気にまくし立てられて、その言葉を理解するまでにかかる時間がオーバーしちゃう。
でも、あたしの頭は“恋愛関係”の話なら授業の勉強に比べて、フル回転してくれる。
――『あたし、諦めませんから』
――『みんなね、“最初”はそう言うんだよ』
――『でもね、“最後”は全員が泣き崩れる』
冷たい王子の仮面を取ろうとしないアイツの前でね。
ちぇりちゃんは知らないと思うけど、アイツは誰とも付き合っていないんだよ。
いや、付き合って来なかった。
今まで告白した女の子は数知れずみんな玉砕で終わってる。
また、この事実が“アタシならイケるかも!”“アタシこそ!”
……みたいな、夢見がちな女の子を増やしちゃってね。
前向きで諦めが悪い、ちぇりちゃんのようなね。
困ったもんだよ、本当。
やれやれ、と言った感じで肩をすくませる。
と、いうことだからよろしくね。
小さくなっていく先輩の後ろ姿を見送る事しかできなくて。
“そういえば、この人の名前……なんだっけ?”
なんて、いつものオチャらけた考えなんかも浮かばなかったんだ。
蕾のまま枯れていく花みたいに、
――これから始まるあたしの恋も始まる前に枯れてしまうんじゃないかって。
ガラにもない事が、頭の中を支配し始めて。
どん底まで落とされたテンションを抱えながら、あたしは教室へと戻った。
――もう、
今日最後の授業が何の科目だったかですらも、思い出せない。
「ダメ、かもしれない……」
始まった恋愛会談であたしは、先輩に警告されたことを話した。
「全員、玉砕だって」
――みんなみたいに、最初は意気込んでアタックしても最後は玉砕の道を辿ることになるのかな。
まだ2回しか会っていない相手。
でも、好きな気持ちは膨れていくばかり。
いつもは勝手に好きになることが多かったけど。
今回は違う。
やっぱり“助けてもらった”事実がこの気持ちに拍車をかけてしまったみたい。
あの人を想うだけで――いつもより、胸が苦しい。
切ないのに、嫌じゃない、この痛み。
「なに言ってんの」
目の前で盛大なため息をつくキナに、
「ちぇりらしくないよ」
心配そうに首を傾ける比奈。
「だ、だって……っ」
ただをこねる子供みたいに反論しようとしたあたしに、
「まだ何もしてないクセに何言ってんの?」
――ゾクリ。
そう発したキナの表情は、この世のものとは思えない程。
背筋が凍り付くような、恐怖。
親友のあたしでさえ、この顔を見たのは今までの人生の中で数回。
見下ろされる視線に、恐怖で何も言えなくなる。
「ほら、キナもこう言ってることだし……」
比奈でさえも、少し困惑しているのが伺える。
「ス、スミマセンデシタ」
片言の日本語でどうにか返事を返して。
この数分後。
2発のビンタを食らったあたしはあの人の教室を探して走ることになるのだ。
◇ * ◇
「キスしていい?」
あたしの暴走劇が始まろうとしていた。
少し高い位置であたしを見下ろすショコラ色の瞳。
茶色でも、焦げ茶色でもない、ミルクチョコみたいな色。
甘い予感に、溶けたチョコレートのように……あたしの心も溶け出すの。
何も言わない彼に、首に腕を回して顔を近付けようとした瞬間。
「――ダメ」
降ってきた言葉は、あまりにも残酷で……冷たくて。
溶け出したチョコは、ハートの型に流れ込む前に冷えて固まってしまう。
「……っ、」
するり、と彼から腕を解いて涙がこぼれないように俯いた。
1ヶ月の間、ギューもチューもしてくれなかったのは、あたしのことが嫌いだったから?
しつこくアタックして来たあたしに、嫌々付き合ってくれてたの?
溶けるように甘かったチョコの味が、みるみる苦味がかっていく。
「顔、上げて」
あたしの顎に降りてくるのは、細長い指。
その指にクイッと持ち上げられ、促されるままに広くなる視界。
「だって、男からするモノでしょ?」
……フツウ。
そう言ってゆっくりと重なったのは、紛れもなく恭一くんの唇だったんだ。
薄汚れたグレーで統一された廊下に、あたしの足音がリズムよく響く。
――キキ……ッ!
何かとてつもなく大切なことを忘れている気がして。
……あたしは急ブレーキをかけたんだ。
「あ、あれ……?」
“橘恭一くんの教室へと向かう”が、今のあたしの目的で。
そもそも、学年は分かったもののクラスまでは知らない……っ!
自分のアホさ加減に呆れつつ、その時のことを思い出す。
確か、体育の授業が終わって、会ったのは昇降口近くの1階。
うちの学校は変わっていて、毎年学年で階がバラバラに変わる。
1年生が、1階。
2年生が、2階。
3年生が、3階。
とか、順序よく並んでいないって先輩から聞いたことある。
現に、今は
1年生が、3階。
2年生が、1階。
3年生が、2階。
みたいな、ヘンテコな造りになっている。
おかげで1年生のあたしたちは、教室の窓から街を見下ろす形で景色を楽しめるけど。
正直、3階までの往復はキツい。
……って。
こんな事言ってるヒマないんだった。
確か、昇降口から西側に向かって歩いてきたとこをあたしが塞いじゃったんだよね。
記憶を辿りながら、廊下を歩く。
「ってことは、2-5より後ってことか」
何組だろ?端から見たら十分怪しい独り言をブツブツ呟きながら、廊下を進む。
そして、――ふと、視界の隅で影が揺れた。
「――あ、」
ショコラ色の丸い瞳が、キラリ。
2-7の教室から出て来ようとするそれはまさに……あたしの探していた人だったから。
――『確かめてみるといいよ?』
ショーの準備は、しといてあげるからさ。
ただし、教室は自分で探してね。
クラスを教えられることもなく。
意味深な笑みを浮かべた先輩は、最後にポツリ。
――『オンナノコが傷付く前に手を差し伸べる、ああ……俺って罪なオトコ』
とか、なんとか言ってたっけ。
「アキがとりあえず、待ってろっていうから」
冷たい瞳であたしを見下ろす姿は王子サマのよう。
もれなく“本当の愛を知らない”というオプション付きで。
表情が、瞳が、オーラが、どこか陰っていて、ひんやり冷たい。
……そうか、あの先輩、アキっていうんだ。
“ショーの準備はしておくから”ってこういう意味だったのか。
「あ、あの……っ」
あたしが意気込んで喋り出した時
「アキを使っといて何の用?」
冷たい言葉が、グサリ、と音を立てて突き刺さった。
確かに、お礼は言えたし、向こうからすれば“今さら”って思われても仕方ないかもしれない。
目の前に立ちはだかるのは、冷たいオーラで女の子を寄せ付けない強者王子。
い、一緒に帰りませんか。
一緒に帰りませんか、と。
呆れ顔のまま、ため息をこぼす王子にせかされるままに。
“今から”言おうとする言葉を、噛まないよう、復唱する。
「用ないなら、帰るけど?」
さぞかし告白に慣れていらっしゃるでしょう王子は、カバンを肩へとかけ直した。
「あの……っ、好きです!」
「……」
…………。
………………。
あたしの恋が、終わりを告げた瞬間だった。
「何やってんの?」
「まさかのミス、だね」
もう、救いようがない程。
反論のはの字も出てこないあたしは深いため息をもらした。
「一緒に帰ろうと、好きです。なんで誘いの言葉と愛の告白を間違えるかね」
「気持ちが先走っちゃったんだよね」
ヨシヨシ、と頭を撫でてくれる比奈の手。
――『分かってると思うけど、間違っても告白はNGね?』
もう、ウンザリする程されてるから。
……勘弁してやって。
「あ、あたし……っ」
アキ先輩の忠告をことごとく外し……今頃、あたしの暴走っぷりを笑っているハズだ。
「恭一くんのこと、あきらめないもん……っ」
それでこそ、ちぇりだよ?って言ってふたりは笑ってくれた。
一瞬で消えかかったあたしの恋の炎は、間一髪で消火を免れ、
今や甘い期待を夢見て、メラメラと燃え上がっている。
ここから、あたしの本領が発揮されることになる。
ストーカー並みの行動力に、暴走劇が追加され。
「おはよーこざいますっ!」
「……」
廊下ですれ違う時は、女子たちの視線に耐えながら笑顔で挨拶。
「あの……、一緒に帰りませんか?」
「帰んないから」
帰り、恭一くんの教室に寄ることは日課になった。
……冷たい言葉で一括されてしまうけど。
そしてあたしは……とある、体の変化を感じることになる。
「おはよーござ「ウザい」
毎日毎日、懲りずに挨拶をするあたしに、その日はついに、最後まで言わせてもらえなくて。
恭一くんに冷たい言葉を浴びせられる度に、体にゾクリと快感が走るような。
最初はやっぱり、さすがのあたしでも傷付いたよ?
でも、もう慣れたっていうか。
むしろ、もっと言って欲しいっていうか……。
Mへと目覚めてしまったのだ。
「……もっ、恭一くん大好き!」
大爆発を起こした気持ちに、あきらかに場違いな言葉。
「……手に追えねぇ」
深いため息でさえ、あたしにはすごく魅力的に映る。
「意外に根性見せてくれるじゃん?」
面白いモノを見るような目であたしを見るアキ先輩。
こんなあたしの奮闘記は、まだまだ始まったばかり。
◇ * ◇
「……んっ…」
やっとひとつに繋がれたふたつの唇は、すぐに離れてしまって。
待ち焦がれたキスがなんだか物足りなく感じてしまったあたしは。
「ちょ……っと、積極的過ぎ」
恭一くんの首に腕を巻きつけ、少し角度を変えた唇を押し当てた。
まるで――恋愛映画のヒロインになったような気分。
「ん…ふ……っ」
首の後ろへ回った手に引き寄せられて。
元々ゼロに等しかった距離がさらに狭まる。
今までの恭一くんからは、想像も出来ないような熱いキスで。
体中の体温がフツフツと沸騰するような熱さを感じながら、あたしはキスに酔いしれた。
「……ふへへ」
頬を机にべったりと貼り付け、抑えきれない笑みをこぼす。
「……も、すごく、好き」
唇を指でなぞるあたしを、好奇な視線がさ迷う。
「これは」
「完全に出来ちゃってるね」
「じゃ、いってらっしゃい」
「頑張ってね~」
いつもなら、みっつくっつける机が最近ではふたつに減っている。
こうして、恭一くんに会いにいける時間は限られてるから――お昼はとても貴重なモノなんだ。
こうして、毎日恭一くんに会いに行くのが日課になって、1週間と2日。
今のあたしの立ち位置は、友達でも……ましてや彼女でもない。
「恭一くん……っ」
「……」
――来た……と、ボソッと呟く様は、半分諦めモードだ。
ストーカーという、周りから見たら相当イタいであろう位置に君臨しているあたし。
でも、もう慣れちゃった。
最初は、頑張って早起きして作った手作りのお弁当を“いらない”の一言で瞬殺され。
毎日毎日、場所を変え教室から、体育館裏、非常階段、裏庭へと逃げ回る恭一くんを追っかけ回し
冷たい言葉を浴びせても、持ち前の超前向き思考で立ち上がるあたしに、
“もう何をしてもムダ”or
“ひたすら、シカト・もしくは、スルー”
ってことで、諦めちゃったみたいで。
お弁当を渡そうした回数、5回。
断られた回数、5回。
何の進展もないように見えがちだけど――。
「こんな場所、知らなかった」
恭一くんを追いかけて、初めて見つけた場所。
非常階段のおどり場、そこを少し下がった所に錆びた鉄製の階段がある。
立ち入り禁止の鎖を飛び越えると――ちょうどふたり分座れるスペースがあるんだ。
この作家の他の作品
表紙を見る
本編では描かれなかった
もうひとつの蜜なお話★
◇ * ◆ * ◇
凜久 ― RIKU
×
瑠璃 ― RURI
×
Honey Love
◇ * ◆ * ◇
ちょっぴり
覗いてみませんか――…?
START 09.12.25
8.29.Sun
◇ラブ・ホリディ up*
表紙を見る
.・:*゚+・:・*:・゚・:*゚+゚*:・:・:*゚+゚・
・+・゚.・゚ ゚・.゚・+・
:*.゚ ゚.*:
:・ ・:
゚ ゚
ひとつの影から
走り出す LOVE
影に恋しちゃったオトコ
未来
×
冷たい瞳を持つ寒がりなネコ
美桜
――ねぇ 君は
一体何を隠しているの?
゜・*:.。. My girl .。.:*・゜
今夜キミを、奪いに行く――
start 09.12.24
end 10.5.2
* T h a n k s ! *
Misa☆ さま
日和♪+* さま
表紙を見る
私が好きになったのは
私よりちょっぴり背の低い
男の子
* ◆ * ◆ *
「ねぇ、瑠璃」
―ほらそうやって
「このままキスしちゃおっか」
――これ以上私を惑わせないで
身長差は変わらず3㎝
私だってドキドキさせたいの
やられっぱなしじゃいられない
3 2 1 …
0 ゼロ―――
加速し始めるカウントダウンは
はじける恋の予感を示す
蜜の味
* * * *
こちらは
「年上カノジョに蜜な罠」の続編となっております
そちらを先に読んで頂ければ
幸いです 壁|ω`*)゙
Start 09.8.31
End 09.12.20
。* Special Thanks *。
柚子こしょう★*゜さま
Misa☆ さま
りちゃこ さま
日和♪+* さま
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…