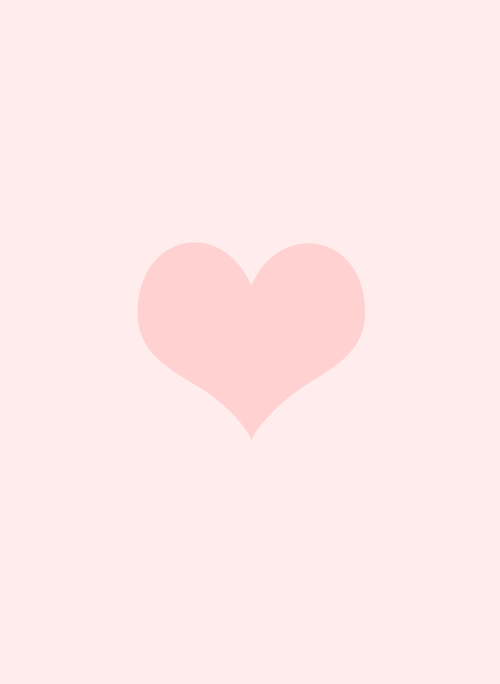「だってあたしのこと、本当に大切にしてくれたから」
――あんな風に熱く愛されたの、初めて。
そんなの、あたしは知らない。
中学時代の恭一くんなんて知らないし、
どれくらい好きだったとか、愛の深さとか。
あたしはどこまで自分を守る為に彼女の言葉に、聞こえないフリを続けるのだろう。
心はすでに、ボロボロのくせに。
「付き合って欲しい、って言ってくれた恭一くんの赤い顔」
――可愛かったぁ。
今すぐここを逃げ出したい。
でもそんなのあたしのプライドが許さない。
昔のノロケ話を続ける彼女に、黒い感情が剥き出しにされていく。
「ちぇりちゃんは、どうなの?」
「……、え?」
突然疑問系で返され、ハッと現実へと引き戻された。
「どうして付き合ったの?」
これ以上嫌な質問って、ない。
つまり、あれよ。
あれを聞きたいんでしょ。
告白“した”のか、“された”、のか。
「告白シマシタ」
音程のない、あたしの声。
ここで嘘を付いて何になるっていうの。
こんなに惨めな思いをしたのは、初めてだ。
「もういいでしょ」
赤くて、丸くて甘酸っぱかったさくらんぼは、
あたしの口の中で、黒くて歪んだ苦いものに姿を変えた。
カラになった白いお皿の上に、カランと音を慣らしながら、乱暴にフォークを置いた。
もう、返してよ……。
このままここにいたら、あたし、ダメになる。
「じゃ」
自分のお代をテーブルに叩き付けて、カバンを肩にかけた。
「もうエッチしたの?」
――1ヵ月以上経ってるんだよね?
楽しむような、声。
あたしはそれを無視して、お店を飛び出した。
悔しい
悔しい
悔しい……っ!
ここで涙を流したら、負けを認めたみたいで、必死にこらえた。
「ははっ、……ヒドい顔」
ショーウィンドウに映ったあたしの顔は、涙でぐちゃぐちゃになってた。
――彼と、永遠の愛を。
真っ赤なバラを散りばめた中に、純白のウエディングドレスを身にまとって走る女性。
飛び込んでくるその人を、抱き止める男性。
張り出されていたのは、ふたりが幸せそうに笑う大きなポスター。
「新しい香水、出たんだ……」
ふと、みずみずしいバラの香りが鼻の奥をくすぐって。
――あたしの涙を優しく止めてくれた。
その香りに誘われるままに、デパートの1階へと足を踏み入れる。
フラフラとおぼつかない足取りと虚ろな瞳をしたあたしは、どれだけ変な目でみられただろう。
気が付けば、その香水を手に取っていた。
「あら」
髪を綺麗にまとめ、バッチリとメイクを施したお姉さんがあたしの視界の隅に映った。
「気になる?」
顔を上げれば、黒を基調とした大人っぽくてオシャレなお店にハッとする。
「ふふ……っ、試してみる?」
あたしなんてどうみても場違いなのに、お姉さんは柔らかく微笑んでくれた。
「でも、アナタにはまだ少し早いかしら」
子供扱いをされてムッと視線を返すと、慌てた様子でお姉さんは続けた。
「違うのよ、そういう意味じゃないの」
――ブライド・フレグランスって言って、花嫁さんが結婚式の時に付ける香水なのよ。
「……え?」
「まだあんまり知られてないのよね」
――花嫁は、英語でbrideって言うでしょ?
そ、そうだった……すぐに理解出来なかった自分が恥ずかしい。
「6月に結婚した花嫁は、幸せになれるって聞いたことあるかしら?」
「知ってます、ジューン・ブライド」
「そうそう、それ」
――それをコンセプトに、この香水は作られたのよ。
そう話すお姉さんは、どこか寂しそうだ。
「6月限定で販売って当初から決まっているから」
――残念ね。
そうだ、……これは偶然なのか、運命なのか。
今日は6月最後の日。
「お姉さん、結婚したの?」
――この香水付けて。
パッと降ってきた疑問を、素直に口にする。
するとお姉さんは、
大きな目をさらに大きくさせて、マスカラがバッチリ塗られたまつげをシパシパさせた。
「そうよ」
その笑顔から、幸せがにじみ出てる。
いいなぁ、結婚かぁ。
女の子の永遠の憧れだよね。
――彼と、永遠の愛を。
今のあたしは、恭一くんとのそんな未来は描けない。
いくら想像してみても、それはあやふやなまま。
「今の人って、あんまりそういうの知らないのよね」
――6月の花嫁の伝説。
きっとあたしの考えが古いのね。
その言葉から、この香水があまり売れなかったことがなんとなく分かってしまった。
「あ、そうだ。ちょっと待っててね!」
そう言って奥の扉の向こうへと吸い込まれるように消えて行った。
改めてお店を見渡すと、本当にあたしなんて場違いなお店だと思い知らされる。
香水の専門のお店じゃなかったみたい。
メイク道具や化粧品、高そうな髪飾りが黒いテーブルの上にきちんと並べられている。
「お待たせ」
にっこりと微笑むお姉さんの手には、バラがプリントされた小さな手提げ袋。
「結婚に気付いたアナタに、あたしから幸せのおすそ分けよ」
――――――……
「ねぇね、おかえり~」
ココとナナのいつものお出迎え。
「ただいま! ハルは?」
「お風呂に入ってるよ」
髪を濡らしたココが答える。
元気がないことを感づかれたくないあたしは、
精一杯の笑顔を崩さないように、急いで部屋へと逃げ込む。
制服のまま、バフッとベッドへとダイブした。
「もらっちゃった……」
紙袋の中から黒い箱を取り出す。
七色に透けた小瓶の上には、バラに彫刻された赤いガラスが取り付けられている。
「……可愛い」
――香水って、こんなに小さいんだ。
手のひらでコロンと転がるそれがどこか愛らしい。
シュッとひと吹き出してみると、バラの香りがあたしをなぐさめるように優しく香った。
――『もうエッチしたの?』
皮肉めいた胡桃ちゃんの言葉が、何度も頭の中で響いた。
もう嫌ってくらい。
自分に魅力がないのか、あたしをそういう目で見れないのか。
……まだ胡桃ちゃんに、未練がある、とか。
だからあたしに手が出せない。
――『あんなに熱く愛されたの初めて』
白いほっぺを赤く染めてうっとりする彼女の表情が忘れられない。
どうして、どうして……?
どうしてあたし達はまだ“キス”止まりなの――?
考えれば考える程、自分がどんどん惨めになっていく。
「恭一くんのバカ……」
花柄のブランケットに潜り込んでポソッと呟く。
「姉ちゃん、ごはん出来たけど」
お風呂から上がったハルが、部屋へと入って来る。
「食欲ないから、今日はいいよ」
みんなの前で、“いつも通り”でいられる自信なんてなかった。
「なんかあった?」
あたしと同じで、勘のいいハルがそう聞いてきた。
お姉ちゃん想いで、妹たちの面倒もしっかり見てくれる弟。
あたしがこんなんだから、その分しっかり育ってしまったんだ。
「お姉ちゃん、ダメだね……」
いらない心配なんてかけたくないのに、きっともうハルは――気付いてる。
……あたしに元気がない原因を。
でも、部屋の外へ出て行く勇気もない。
ハルを追い掛ける気力さえも、今は湧いてこなかった。
バラの香りに包まれて、お風呂にも入らないままあたしはベッドの上で眠ってしまった――。
「……あ、? ほわ?」
ぼんやりと重たいまぶたを擦って手探りで時計を探せばもう11時を過ぎている。
「夜更かしはお肌の大敵……」
いけない、いけない。
早くお風呂でメイクを落として、くすんだ肌にパック、パック。
「もう皆、寝てるよね」
それを願って、音を出さないよう全神経を集中して部屋からそっと抜け出した。
カタ――…ッ
爪先に何か固いものが当たってあたしはビクッと肩を震わす。
この作家の他の作品
表紙を見る
本編では描かれなかった
もうひとつの蜜なお話★
◇ * ◆ * ◇
凜久 ― RIKU
×
瑠璃 ― RURI
×
Honey Love
◇ * ◆ * ◇
ちょっぴり
覗いてみませんか――…?
START 09.12.25
8.29.Sun
◇ラブ・ホリディ up*
表紙を見る
.・:*゚+・:・*:・゚・:*゚+゚*:・:・:*゚+゚・
・+・゚.・゚ ゚・.゚・+・
:*.゚ ゚.*:
:・ ・:
゚ ゚
ひとつの影から
走り出す LOVE
影に恋しちゃったオトコ
未来
×
冷たい瞳を持つ寒がりなネコ
美桜
――ねぇ 君は
一体何を隠しているの?
゜・*:.。. My girl .。.:*・゜
今夜キミを、奪いに行く――
start 09.12.24
end 10.5.2
* T h a n k s ! *
Misa☆ さま
日和♪+* さま
表紙を見る
私が好きになったのは
私よりちょっぴり背の低い
男の子
* ◆ * ◆ *
「ねぇ、瑠璃」
―ほらそうやって
「このままキスしちゃおっか」
――これ以上私を惑わせないで
身長差は変わらず3㎝
私だってドキドキさせたいの
やられっぱなしじゃいられない
3 2 1 …
0 ゼロ―――
加速し始めるカウントダウンは
はじける恋の予感を示す
蜜の味
* * * *
こちらは
「年上カノジョに蜜な罠」の続編となっております
そちらを先に読んで頂ければ
幸いです 壁|ω`*)゙
Start 09.8.31
End 09.12.20
。* Special Thanks *。
柚子こしょう★*゜さま
Misa☆ さま
りちゃこ さま
日和♪+* さま
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…