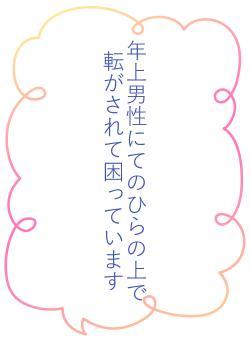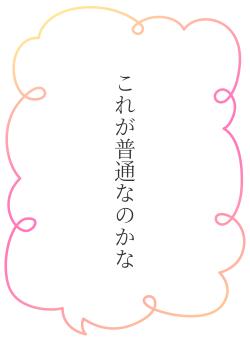自宅マンションの駐車場に愛車を止めて腕時計を見ると、九時半を過ぎたところだった。いそいそと車から降りて、雪の降る中今朝見た雪だるまが健在か確認しに行く。
いつから降り始めていたのか、結構積もった雪に隠され、雪だるまは小さな山のようになっていた。
『上の雪を落とせば、出てくるかな?』
雪山のてっぺんを撫でるようにして、中身を確認しようとしたのだが、何か違和感がある。履いていた皮手袋を脱いで、徐々に雪山を壊していくと、中には何も無かった。
真っ暗な中、マンションの壁に着いているライトに照らされたその場所は、そこだけ山の形に雪が積もっていたのだ。
誰かが雪山を造ろうとしても、必ず手や手袋の跡が残るし、固くなってしまう。この雪山は上から下まで綺麗にサラサラと崩れていったのだ。
『世の中不思議なこともあるもんだ…』
誰かが駆使して造ったのだとしたら…と思うと少し罪悪感を感じた。
自宅の鍵を開けて中に入る。いつもの場所に鞄を置き、いつものように布団の上に転がって一息つく。
おもむろに起き上がり、鞄の中を手探りでかき回し、白い小さな紙袋を取り出した。セロテープを剥がして中に入っている木製の雪だるまを手に取り、しばし眺める。
「朝の雪だるまは消えちゃったし、お前に『弥生』の名前をあげよう」
突き出た鼻をつつく。
『弥生はあたしの名前よ』
何処からか声がしたような気がした。
『何だ今のは?』
キョロキョロと当たりを見渡すが特に変わった所は無い。ましてや一人暮らしの身だ。誰かの声が聞こえてくるわけがない。
本棚の一角に木製の雪だるまを飾ろうと立ち上がると、また何か聞こえた。
『ちょっと、その子あたしにも見せてよ』
今度ばかりは空耳とは思えぬほどしっかりと聞こえてきた。若干の不信感と共に部屋の中を見渡すが、やはり変わった所は無い。
玄関に戻ってみたが、そこには自分の靴が一足あるだけ。きびすを返し、本棚に戻ろうとしたら右足が悲鳴をあげた。
「冷てぇっ」
何かこぼした記憶も無いのだが、数滴の水があったようで、靴下のかかと部分が濡れてしまった。
『靴を脱ぐときに雪でも飛ばしたか?』
そう思ったが、勢いよく脱いだとしてもここまで飛んでくるような場所でもない。靴下を脱いで洗濯機に放り込んだ。木製の雪だるまを持ったまま、布団の上にあぐらを掻く。
「何だったんだろうなぁ、今の声は」
雪だるまに話しかけるように独り言を言うと返事が返ってきた。
『何ってあたしよ、あたし。弥生って名前くれたじゃない』
ギョットして当たりを見渡す。探す、探す、探す。
「誰か居るのか?」
馬鹿馬鹿しいと思ったが聞いてみた。
『ここに居るじゃない』
怪訝な顔をしてるのが自分でも解る。一体誰と、いや、何と会話をしているんだ?混乱する思考の中何度も何度も部屋を見渡す。
『もぅ、ここよ、ここ。テーブルの足元に居るじゃない』
この部屋にあるテーブルとは、テレビ台にしている小さなものだけだ。
その足元を見ると確かに何か居る。床に木製の雪だるまを置き、恐る恐る近付いてみると、そこにはなんとも小さな女の子が居た。
十五センチくらいの大きさだろうか。体育座りをしているため余計に小さく見える。
「…弥生…?」
聞くとコクコクと頭を縦に振った。手のひらに乗せようと思い、その体に触れると非常に冷えていた。
よく見るとガタガタと振るえている。
「お前、冷たいな…寒いのか?」
『寒いわけ無いじゃない。暑いのよ。氷ちょうだい、氷』
訳が分からない。
「は?氷?こんなに体冷たいのに?」
『冷たいのは当たり前よ。あたし雪だるまだもの。それより早く氷ちょうだいよ』
必死な口調の彼女に、深皿に数個の氷を入れて近くに置くと、勢いよく氷の中に潜り込んだ。
「うわ、見てると寒いよ、何してんの?」
『あー、寒い。気持ちいい』
安堵の表情を浮かべて氷の中から顔を出した。
『あなた、朝雪だるまに『弥生』って名前付けたでしょ?』
「え、何で知ってるんだ?」
『あたしがその『弥生』だもの。名前を付けてもらって嬉しかったんだー』
そう言って満面の笑みを浮かべる。
つまりは、朝見た雪だるまが、名前を付けてもらった事に嬉しくて、擬人化して彼の部屋に訪れた…という事らしいが、
「これって現実か?」
氷風呂に浸かって微笑んでいる彼女を見ていると、寒くなってきて、付けてなかったストーブを点火した。
『現実よ。って、ストーブ付けないでよ、暑いじゃない』
そう言って少し溶け始めた氷の中に顔を埋める。
夢か現実か解らないが、今自分が貴重な体験をしていることに間違いはない。
そう思うとすんなりと受け入れることが出来た。確かに雪だるまは雪で出来てる。暖かいところは苦手だろう。
「氷、増やそうか?」
そう言う武志に、『まだいいわ』と軽く返事を返すと、先ほどの木製の雪だるまを見せろとせがんできた。
『なかなかいい物を持ってるわね』
近くに置いてあげると自分とあまり変わらない背丈の雪だるまをまじまじと眺め始めた。
『手が無いと可哀想ね』
弥生がふっと息を吹きかけると、枝のような腕が生えてきた。
「うぉ、すげ」
思わず感嘆の声を上げた武志に、自慢げな表情を見せる弥生。
『これをずっと大事にしてると、何か良いことあるわよ、きっと』
あたしもこの子に出会えて良かった。そう付け加えた。
腕が生えて、一層木らしさが見えてきた雪だるまだったが、温かみは何も変わらない。
『あたし、そろそろ外に帰らなきゃ。仕様がないから、この子と出逢わせてくれたお礼に、あたしに出来ることなら何でも叶えてあげるわ。かき氷とか作れるし、牛乳を少しくれればアイスクリームも作れるわよ』
胸を張って鼻高々に話す弥生だったが、この寒い冬にそれは遠慮したいと思っていた所、ふと今日職場にきた年配の女性を思い出した。
「じゃあ、来年のクリスマスイブにまた会いに来てくれよ」
一瞬きょとんとした表情を見せた弥生だったが、相当嬉しかったのか、
『仕様がないわねぇ』
と、照れ隠しもせずにこれ以上無いほどの笑顔を見せて『約束よ』と武志の顔を指差した。
「あぁ、約束だ」
『忘れたら承知しないから』
「そっちこそ」
自然と笑みが零れる。
『忘れないように、この子にあたしが名前を付けてあげる』
そう言ってしばらく悩んだ後で、
『『氷河』ね』
と、人差し指を立てた。
『ホントに忘れないでよ?』
「あぁ、忘れないよ」
氷風呂から這い出した弥生はちょっと顔を近づけて頂戴とせがんだ。
うつ伏せになり、近くによると、とても冷たい唇で頬にキスをした。
『約束のキス。それじゃああたしは帰るわね』
一方的に言い放ち、大きく手を振った後、そこには雪山しか残っていなかった。