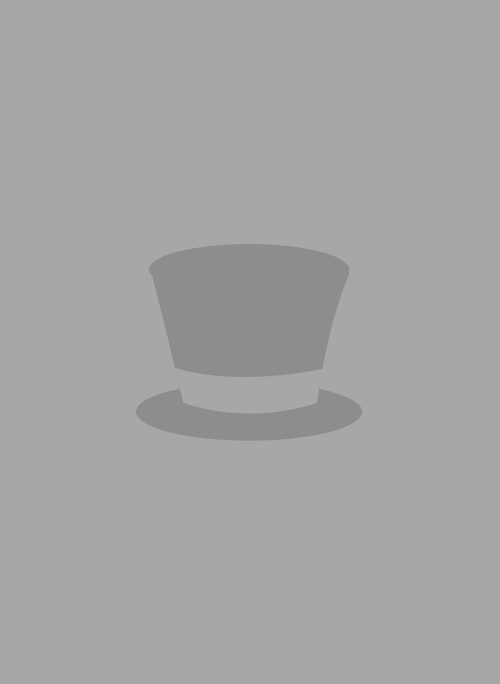そんな道に、いつもならばいない不良らしき少年たちの集団がいた。
狭い道にたむろしてぶつかったり邪魔だという視線を向ける人々を気にも留めないで座り込んでいる。
彼らの年代はこの時間帯では帰宅する人間のが多いというのに、そこにたむろし始めた者たちは一向に帰る気配を見せない。
それどころか、時刻が遅くなるに連れて人数が増えていく。
他の人間たち同様、早苗も彼らに迷惑とばかりに視線を投げかけて通り過ぎようとした。
その時、早苗は正面から来た男とぶつかった。
たむろしていた連中ばかり見ていたから前に対する注意が薄れたのだろう。
すみません、と一言謝ってその場を去ろうとした。
「あっれ、君さぁ?人にぶつかっておいてそれだけで済ますの?」
「は?」
突如として、たむろしていたチンピラに声をかけられた。
近い距離であるにも関わらずボリュームの大きな声が人々に響き渡り、数人がこちらに目を向けた。
見ず知らずの人にぶつかってしまったこと、チンピラに声をかけられたこと、街行く人の目が集まってきた恥ずかしさと怒りで早苗の顔に赤みが走る。
「ダメでしょぉ、ねぇ?人に迷惑かけたらちゃあんと慰謝料払わなきゃ」
「僕はそんなもの──」
「オッサンは黙ってな!」
まだ30代前半であろうその男性は、チンピラの異様な迫力に黙らされてしまった。
チンピラは立ち上がり早苗を嫌な目つきでじろじろと舐めまわし、視線と同じようなねちっこく話しかけてくる。
──こいつに技かけてねじ伏せてやりたい・・
早苗は苛々とそんなことを考え、チンピラの顔めがけて飛んで行きそうになる拳を押さえた。
狭い道にたむろしてぶつかったり邪魔だという視線を向ける人々を気にも留めないで座り込んでいる。
彼らの年代はこの時間帯では帰宅する人間のが多いというのに、そこにたむろし始めた者たちは一向に帰る気配を見せない。
それどころか、時刻が遅くなるに連れて人数が増えていく。
他の人間たち同様、早苗も彼らに迷惑とばかりに視線を投げかけて通り過ぎようとした。
その時、早苗は正面から来た男とぶつかった。
たむろしていた連中ばかり見ていたから前に対する注意が薄れたのだろう。
すみません、と一言謝ってその場を去ろうとした。
「あっれ、君さぁ?人にぶつかっておいてそれだけで済ますの?」
「は?」
突如として、たむろしていたチンピラに声をかけられた。
近い距離であるにも関わらずボリュームの大きな声が人々に響き渡り、数人がこちらに目を向けた。
見ず知らずの人にぶつかってしまったこと、チンピラに声をかけられたこと、街行く人の目が集まってきた恥ずかしさと怒りで早苗の顔に赤みが走る。
「ダメでしょぉ、ねぇ?人に迷惑かけたらちゃあんと慰謝料払わなきゃ」
「僕はそんなもの──」
「オッサンは黙ってな!」
まだ30代前半であろうその男性は、チンピラの異様な迫力に黙らされてしまった。
チンピラは立ち上がり早苗を嫌な目つきでじろじろと舐めまわし、視線と同じようなねちっこく話しかけてくる。
──こいつに技かけてねじ伏せてやりたい・・
早苗は苛々とそんなことを考え、チンピラの顔めがけて飛んで行きそうになる拳を押さえた。
その仕草が逆の意味にとられたようだ。
チンピラのニヤニヤ笑いが更に大きくなり、男性は少し挙動不審な動きを見せていた。
はじめの慰謝料の話はどこへやら。
もうネタが無いのか普通にカツアゲをしてくるチンピラに早苗は心を決めた。
──もう、ここまできたら此れが原因で道場追い出されることも無いよね
出来るだけ予備動作を小さくし、右腕を振るった。
「「え?」」
早苗とチンピラが同時に声をあげた。
早苗の拳はチンピラに届くことなく自分の頭より少し高いところでぶつかった男性に止められ、男性はそのまま早苗の腕を強く引き、走り出した。
「え、わっちょ、ちょっと!!」
突然のことに転びそうになりながら早苗は男性にされるがまま駅前の人ごみの中に消えていった。
路地に取り残されたチンピラはその場にかがんだ。
「あーあ、王子様に取られてやんの。」
後ろに待機していたうちの一人が冷やかしたのを合図に他のメンバーからもからかいの野次が飛ぶ。
立ち上がったチンピラの手には、あるものが握られていた。
「いいや、まだまだこれからさ」
それは、中学校の生徒手帳。
無論、里山早苗という少女の。
* * * * *
その後、男性は人通りの多い通りに出たところでようやく早苗の手を離した。
─こんな強引に連れてこなくてもいいじゃないのさ
と思いながらも、一応は助けてくれたので相手にお礼を言って頭を下げた。
「い、いやそんなほどのことでもないですよ。・・本当は言い寄られる前にちゃんと断れればいいんですけどね。
では、僕は此れで失礼します。君も、充分気をつけてください。」
そういって男性は人ごみの中に消えていった。
家路にたってから、何だかどっと疲れが押し寄せてくる。
何かロマンチックな物語の始まりになりそうだと期待する者もいるかも知れない。
けれど早苗はこんなゴタゴタもううんざりだと思った。
しかし、その願望は粉々に打ち砕かれることとなる。
駅前でのことがあってから数日後、変化は起きた。
早苗が下校していると、学校から少しはなれた公園の入り口でたむろしている学生がいた。
見慣れない制服──この辺りの中高校生ではないことは確か。
物珍しい視線を送って通り過ぎる。そのはずだった。
だが、そのうちの一人に腕を掴まれた。
「ちょっと待てよ。」
「何、私に用でもあるの?」
「大アリ、だなぁおい。」
「そうそう」「ヘヘッ」
─こっちはあんたらのことなんか知らないってのに。何なんだよもう・・
公園の奥、通りからは見えにくいところに連れて行かれる。
逃げ道の無いように早苗を囲む。
─此れじゃまるでリンチじゃない。・・・いや、『まるで』じゃなくて『本当の』かな
背中を冷や汗が伝う。
そして、彼らは早苗の予想通りの言葉を吐き出した。
「おい、有り金全部だせよ。」
早苗はツン、と横を向いた。
「嫌」
「おお?いいのか、んなこと言って」
「カバン取り上げてあさっちゃうよ?」
早苗のカバンに近い子が手をかける。
とっさにカバンを引いてその子の頭に振り下ろす。
「いってぇ!中身何入ってんだよコイツ!」
頭を抑える子を周りは面白がって笑った。
「私、急いでるんだけど。そもそもバスとか使って学校来てる訳じゃないし、寄りたい場所もなくて金なんて持ってくる訳ないだろ」
彼らはさっと目配せを交わす。ニヤニヤとした笑みはさらに口端を吊り上げた。早苗もこんなことで彼らが引く訳はないと思っていたが、以前よりも増した嫌な予感が、背中を通り抜けた。
「そうなったらやっぱ、なぁ」
「おうよ」
「そうそう、体で払ってもらおうか」
早苗は即座に何が言いたいか察した。
―この糞野郎共…!!
「こいつを捕まえろッ!」
彼らが一斉に動き出した。
「嫌」
「おお?いいのか、んなこと言って」
「カバン取り上げてあさっちゃうよ?」
早苗のカバンに近い子が手をかける。
とっさにカバンを引いてその子の頭に振り下ろす。
「いってぇ!中身何入ってんだよコイツ!」
頭を抑える子を周りは面白がって笑った。
「私、急いでるんだけど。そもそもバスとか使って学校来てる訳じゃないし、寄りたい場所もなくて金なんて持ってくる訳ないだろ」
彼らはさっと目配せを交わす。ニヤニヤとした笑みはさらに口端を吊り上げた。早苗もこんなことで彼らが引く訳はないと思っていたが、以前よりも増した嫌な予感が、背中を通り抜けた。
「そうなったらやっぱ、なぁ」
「おうよ」
「そうそう、体で払ってもらおうか」
早苗は即座に何が言いたいか察した。
―この糞野郎共…!!
「こいつを捕まえろッ!」
彼らが一斉に動き出した。
早苗は身構えた。恐怖はない。
─相手は5人。試合じゃ1対1しかやないからなぁ、大丈夫かな?
そんなことを考えながら重いバック振り回した。
一番手前まで近づいていた相手にバックが当たる。振り回した遠心力を利用してそいつのこめかみに蹴りを叩きこんだ。そいつはそのままバランスを崩して隣にいた者を巻き込んで転んだ。
「ぐっ!」「うわ、おい!」
─体育のまんま短パンはいておいてよかった!
倒れた者の逆の隣の攻撃を身を低くしてかわし、鳩尾に鋭い突きを入れる。
「うぁっ!」
─あと、2人!
そう思って振り向いた時、後ろからの蹴りをまともに受け前から攻撃を仕掛けてきた者と正面からぶつかった。
「キャッ」
「へぇ、案外可愛い声だすじゃねーの!」
そいつに捕まる前にあごにしたから手のひらを叩き込み、腹に思いっきり膝蹴りを入れた。
「うっ!」
振り向く前に下に向けていたバックを思いっきり上に振り回す。
当たりはしなかったが、後ろから来ていた者がバックをよけて止まる。
その隙にすばやく間合いを詰め顔めがけて右ストレートを叩きこんだ。
「がっ、てめ」
くるり、と背を向けて走った。ちょっと様子見に振り返ったら、砂場に足を取られて転びそうになった。その時、あるものが目に入った。
─お、いいものはっけーん!
─相手は5人。試合じゃ1対1しかやないからなぁ、大丈夫かな?
そんなことを考えながら重いバック振り回した。
一番手前まで近づいていた相手にバックが当たる。振り回した遠心力を利用してそいつのこめかみに蹴りを叩きこんだ。そいつはそのままバランスを崩して隣にいた者を巻き込んで転んだ。
「ぐっ!」「うわ、おい!」
─体育のまんま短パンはいておいてよかった!
倒れた者の逆の隣の攻撃を身を低くしてかわし、鳩尾に鋭い突きを入れる。
「うぁっ!」
─あと、2人!
そう思って振り向いた時、後ろからの蹴りをまともに受け前から攻撃を仕掛けてきた者と正面からぶつかった。
「キャッ」
「へぇ、案外可愛い声だすじゃねーの!」
そいつに捕まる前にあごにしたから手のひらを叩き込み、腹に思いっきり膝蹴りを入れた。
「うっ!」
振り向く前に下に向けていたバックを思いっきり上に振り回す。
当たりはしなかったが、後ろから来ていた者がバックをよけて止まる。
その隙にすばやく間合いを詰め顔めがけて右ストレートを叩きこんだ。
「がっ、てめ」
くるり、と背を向けて走った。ちょっと様子見に振り返ったら、砂場に足を取られて転びそうになった。その時、あるものが目に入った。
─お、いいものはっけーん!
早苗の目に留まったのは、子供の砂場用の遊具──バケツ
早苗は小さなバケツを手にとると、砂場の砂の─特に乾いててさらさらしている部分をバケツいっぱいに取り少年たちに投げた。
砂は彼らのところまで届かず、少し手前に着地し盛大に砂埃を上げた。
「「ゲホッ、ゲホゲホッ!」」
砂埃は彼らの目や口にまで侵入し、少しの間だけ、彼らの視界を妨げた。
「あいつ、逃げ足スゲー速ぇー」「感心してんなバカ!」
彼らの視界が回復したとき、彼らの前に早苗の姿は無かった。
*******
少年たちの目の届かなくなった所までくると、早苗は足を緩めた。
「あーもう、制服が埃だらけになっちゃったじゃん!」
砂がまとわりついている部分に関しては自業自得なのだが、そんなことは気にしない。
「それにしてもあたし足速いなぁ、陸上部入れるんじゃないの?」
あははーと笑いながら軽い足取りで家に帰った。
しかし、それから数日後。
またもや彼らが現れた。
その日だけではない。
倒しても、倒しても、何回でも彼らはやってきた。
帰り道のどこかで待ち伏せをしているのだ。
おかげで、早苗の友人たちは早苗を帰りに誘わなくなった。
そんなことの繰り返しで早苗の機嫌が良くなるはずもなく、いつもしかめ面をしているといつしか早苗は、恐ろしいヤンキーである、だとか、放課後に後輩いびりをしてカツアゲをしている、だとか、ストレス解消に他校の者と殴り合いの喧嘩をしているなどのうわさが広まった。
最後のに関しては多少間違っているものの、否定はできず、その態度が勝手に全てのうわさを認めたと誤解された。
こうして早苗は周りに勝手にヤンキーに仕立て上げられたのだった。
早苗に好意をもって近づいてくるものはいなくなり、喧嘩のうわさを聞きつけて腕試しにと敵意を持って近づいてくる者はどんどん増えていき──
───今に至る。
──つまらない・・
それが早苗の今の生活の本音だった。
学校に行けば怯えられるか、冷やかしを受けるか、蔑(さげす)んだ目で見つめられるかのどれか。
教師も同じようなもので、世話焼きな先生には「どうしたんだお前」といわれる始末。
──私が悪いんじゃない。何も悪くない・・なのにどうしてなんだろう・・?
ある日、またも襲撃があったときに早苗は聞いた。
「あんたらさ、何でアタシをしつこく狙ってくんの?」
彼らはニヤニヤと笑うだけで、答えない。
その中のリーダー格らしき髪に軽く赤いメッシュを入れた人が1歩前に進みでた。
──あいつ!駅前にいた奴!
そう、駅前の路地で早苗に絡んで来た男だった。
学ランであることを見れば、恐らく高校生であろうと思われる。
そいつがポケットから取り出したのは、早苗の生徒手帳。
「出かけるときまで持ち歩いてるなんて、優等生だなぁ」
からかい混じりの言葉を吐き出すと周りにいた者たちも下卑(げび)た笑いをこぼす。
「わざわざ返しに来てくれたって訳?ご苦労様」
「どうぞ来てくださいって言わんばかりに丁度よく落としてくれたもんだから?俺たちの親切心がもうウズウズしちゃって、さ。
でパシらせてみれば案外強いってんじゃねーか。それじゃぁ拾った俺みずからが行くべきじゃない?」
この作家の他の作品
表紙を見る
霊感持ちの無声少女
-屋代言乃-
ヤシロ コトノ
言乃の声が聞こえる人
-日奈山炯斗-
ヒナヤマ ケイト
歓楽街の裏で相次ぐ殺人事件
浮かび上がる蠢く組織
一人の“幽霊”が
事件を大きく動かす
バラバラになる二人
――このままじゃアイツ
消えるぜ?――
孤独な逃走劇が
今、幕を開く
§
言炯-コトケイ-シリーズ
第二弾
start 2012/06/05
§
前作
空耳此方-ソラミミコナタ-
番外編
RAIN RAINBOW
こちらも宜しくお願いします!
表紙を見る
英国喜劇リトレイス
外伝
本編では描くことの出来なかった
キャラクターの過去・背景
そして後日談
SSを書いて行きたいと思います
†
本編
ストーリー原案
日田 恵
執筆
白川 紘哉
表紙を見る
人は誰もが自由に生きて行ける訳ではない
身分
立場
運
時代
それらのしがらみが人間を大きく左右する
しかし――
人を動かすのは
それだけではないかも知れない
人では決して届かない
人より高みに位置する存在の手が――
今、彼らを突き動かす
─英国喜劇リトレイス─
四男坊の復讐
「俺は必ず…兄貴をブッ殺す!!」
どうなるイギリス!
どうなる四兄弟!
*
ストーリー原案
日田 恵
*
外伝
英国喜劇リコレクション
こちらもどうぞ《*≧∀≦》
*
start 2012.3
finish 2012.7.13
*
イギリスを舞台としていますが
実際の史実とは関係ありません
お楽しみください♪ヽ(´▽`)/
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…