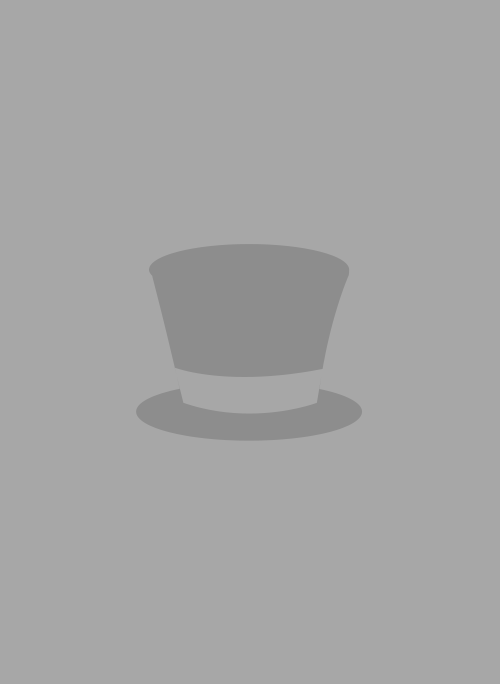「何の憧れだか知らないけど…
大人だっていじめはあるしそれで自殺なんてざらにあるよ」
早苗は碧をじっと見つめて息を飲む。
碧は空を見つめたまま続ける。
「ケンカなんか大人な分、罪に問われちゃうからおおっぴらに出来ないし
ぶっちゃけ学校とそんなに変わらないさ」
碧はタバコを靴で消してゴミ箱に落とした。
「こうやって吸って見たって何にも変わらない」
碧は座る早苗の前に立って早苗をしっかり見つめる。
そしておもむろに箱を差し出した。
「それでもまだ、コレ欲しい?」
大人だっていじめはあるしそれで自殺なんてざらにあるよ」
早苗は碧をじっと見つめて息を飲む。
碧は空を見つめたまま続ける。
「ケンカなんか大人な分、罪に問われちゃうからおおっぴらに出来ないし
ぶっちゃけ学校とそんなに変わらないさ」
碧はタバコを靴で消してゴミ箱に落とした。
「こうやって吸って見たって何にも変わらない」
碧は座る早苗の前に立って早苗をしっかり見つめる。
そしておもむろに箱を差し出した。
「それでもまだ、コレ欲しい?」
しばらくの沈黙の後、ゆっくりと、早苗は首を横に振った。
すると碧はにっこり笑って早苗の方を向いたまま背後のゴミ箱にタバコの残りを投げた。
「あっ!」
もったいない、と早苗が言う間もなくタバコはゴミ箱に吸い込まれてた。
碧は笑顔のまま早苗の顎をクイッと上げる。
「もったいなくないでしょ?諦めたものはスッパリ諦める!
助言ついでに私も禁煙したげるからさ」
ついでにの意味がよくわからない。
が、笑っていない笑顔の碧に圧されひきつった顔しか出来ない早苗。
――…この寒気どっかでも経験したぞ?
一瞬、誰かの顔が脳裏を過るがわからない。
そんなことを考えてる間に圧力に耐えられなくなり、早苗は頷いていた。
「よし!」
碧は早苗の頭をポンとたたく。
早苗は碧を見上げる。
「若者よ、今を思いっきり楽しみな。深く考えずに、ね」
碧の見事なウィンクを受け、早苗の頬はほんのり染まる。
そして、久々の笑顔で―
「はい!!」
それを満足そうに見て、碧は早苗に背を向けて歩き出した。
「あの、ありがとうございました!」
碧は手をヒラヒラ振って答えた。
早苗はバッグを持ち上げ早めの帰路についた。
家に帰って、部屋の机にカバンをおいた。
――何か…凄くカッコよかったな、碧さん
ベッドに寝転び時計を見た。
当然だが、時間まで随分ある。
ふと、制服から放り出した携帯を見る。
やはり一言入れておくべきだろうか?
いや、と早苗は否定する。
あれから一度もちゃんと話していないし、学校でのことだ。
襲撃なんかじゃない。
ただのいじめだ見せしめだ
――ダメダメ!そんなこと考えちゃ!
早苗は体を起こし首をふる。
やられたら、やりかえせばいい。
何も考えず突っ込めばいい。
きっと碧さんが言いたかったのはそういうこと。
だから、堂々と正面きって立ち向かえば何かは変わる。
現状は変えられる。
早苗は大きく息を吸い込み、目を閉じた。
どんなに心を決めても浮かぶ二人の顔。
そしてすぐあとに以前ノートにでかでかと書かれた「二股女」の文字。
彼氏にするならユウジ。
そう言ってこの関係は始まった。
私もまんざらではなかった。
でも――
葵さんのバイト先を覗いたとき、遠回りしてまで送ってくれたのは
そのままでいいと言ってくれたのは
いじめで落ち込んだ私に気づき相談に乗ってくれたのは――
――全部ヒスイだ…
そう、ヒスイも決して悪い人ではないんだ。
早苗はもう一度携帯を見る。
――私が好きなのは、どっち…?
きっと今夜、そのことにも決着をつけないといけないだろう。
どちらなのか。
早苗は揺れる思いを押し潰すようにきつく目を閉じ、ベッド横たわっていた。
夜・廃工場前
約束どおり、早苗は一人でその場に降り立った。
「さて、どうしますかね・・」
月明かりもないこの宵。
人のいない廃工場は不気味な佇まいで存在していた。
結局、ベッドの上で考えようとしたら眠りに落ちて結論は出ずじまい。
行かないことも考えたが、早苗は家を出た。
──ここで終わらせられるかも知れない。答えは出なくとも、それはそれでチャンス。
『楽しみな』
碧の言葉がよみがえる。
──考えなくても何とかなるっ!よし!
早苗は顔をパシンと叩き、裏手へ向かった。
砂利を踏みしめ、角を曲がる。
「おー、来た来た」
そう言ったのは、いつぞやの高校生。
西高の赤メッシュ男が工場の閉ざされた扉に背をもたれている。
そして同じ制服の男子が数人その周りをうろうろ。
さらに隣の土地との境界の柵の前には手を縛られて座らされる友人の姿が。
「由香ッ!?」
早苗は困惑して声を上げた。
──約束が違う!私が来なかったら『仲間が痛い目にあう』って!
早苗がキッと赤髪男をにらむと、そいつはまた嫌味なにやにや笑いを浮かべていた。
「この子は友達で、仲間じゃないだろ?」
「なんだと?」
「痛い目にあわすのは仲間。友達については言ってない」
「だから何してもいいって?」
「そ。」
「ふざけんじゃねぇよ!んの卑怯者!」
「いじめに卑怯も何もないっしょ?」
男は早苗の前に立ち、にこやかに言う。
「それに俺たちはさ。ぶっちゃけ君はもうどうでもいいわけ」
「じゃ、放っておいてくれない?」
「残念。そうは行かないんでさ」
男は早苗のあごに手をかけ、クイと上げる。
そして早苗の耳元で声を低くして囁いた。
「俺たち今は雇われ者なんだよ。ご褒美くれる代わりにあんたを襲えってさ」
早苗は驚愕して男を見た。
男は肩を震わせて嘲笑う。
「よっぽど嫌われてんだな、俺たちが勝手にあんたを襲ったのは最初の一回だけ」
そして、さらに声のトーンを落とし、至近距離にいる早苗でさえ聞き取りにくい声で言った。
「ご苦労なこったな。
俺らにやらせるだけじゃなくて学校でもお前を─みたいだから」
この作家の他の作品
表紙を見る
霊感持ちの無声少女
-屋代言乃-
ヤシロ コトノ
言乃の声が聞こえる人
-日奈山炯斗-
ヒナヤマ ケイト
歓楽街の裏で相次ぐ殺人事件
浮かび上がる蠢く組織
一人の“幽霊”が
事件を大きく動かす
バラバラになる二人
――このままじゃアイツ
消えるぜ?――
孤独な逃走劇が
今、幕を開く
§
言炯-コトケイ-シリーズ
第二弾
start 2012/06/05
§
前作
空耳此方-ソラミミコナタ-
番外編
RAIN RAINBOW
こちらも宜しくお願いします!
表紙を見る
英国喜劇リトレイス
外伝
本編では描くことの出来なかった
キャラクターの過去・背景
そして後日談
SSを書いて行きたいと思います
†
本編
ストーリー原案
日田 恵
執筆
白川 紘哉
表紙を見る
人は誰もが自由に生きて行ける訳ではない
身分
立場
運
時代
それらのしがらみが人間を大きく左右する
しかし――
人を動かすのは
それだけではないかも知れない
人では決して届かない
人より高みに位置する存在の手が――
今、彼らを突き動かす
─英国喜劇リトレイス─
四男坊の復讐
「俺は必ず…兄貴をブッ殺す!!」
どうなるイギリス!
どうなる四兄弟!
*
ストーリー原案
日田 恵
*
外伝
英国喜劇リコレクション
こちらもどうぞ《*≧∀≦》
*
start 2012.3
finish 2012.7.13
*
イギリスを舞台としていますが
実際の史実とは関係ありません
お楽しみください♪ヽ(´▽`)/
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…