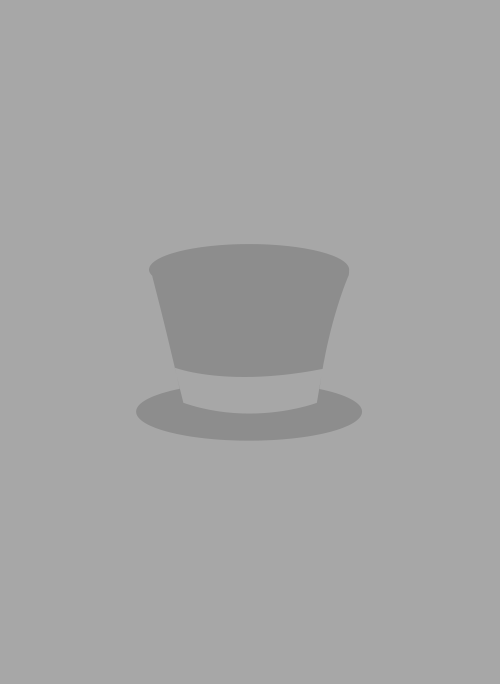早苗はツン、と横を向いた。
「嫌」
「おお?いいのか、んなこと言って」
「カバン取り上げてあさっちゃうよ?」
早苗のカバンに近い子が手をかける。
とっさにカバンを引いてその子の頭に振り下ろす。
「いってぇ!中身何入ってんだよコイツ!」
頭を抑える子を周りは面白がって笑った。
「私、急いでるんだけど。そもそもバスとか使って学校来てる訳じゃないし、寄りたい場所もなくて金なんて持ってくる訳ないだろ」
彼らはさっと目配せを交わす。ニヤニヤとした笑みはさらに口端を吊り上げた。早苗もこんなことで彼らが引く訳はないと思っていたが、以前よりも増した嫌な予感が、背中を通り抜けた。
「そうなったらやっぱ、なぁ」
「おうよ」
「そうそう、体で払ってもらおうか」
早苗は即座に何が言いたいか察した。
―この糞野郎共…!!
「こいつを捕まえろッ!」
彼らが一斉に動き出した。
「嫌」
「おお?いいのか、んなこと言って」
「カバン取り上げてあさっちゃうよ?」
早苗のカバンに近い子が手をかける。
とっさにカバンを引いてその子の頭に振り下ろす。
「いってぇ!中身何入ってんだよコイツ!」
頭を抑える子を周りは面白がって笑った。
「私、急いでるんだけど。そもそもバスとか使って学校来てる訳じゃないし、寄りたい場所もなくて金なんて持ってくる訳ないだろ」
彼らはさっと目配せを交わす。ニヤニヤとした笑みはさらに口端を吊り上げた。早苗もこんなことで彼らが引く訳はないと思っていたが、以前よりも増した嫌な予感が、背中を通り抜けた。
「そうなったらやっぱ、なぁ」
「おうよ」
「そうそう、体で払ってもらおうか」
早苗は即座に何が言いたいか察した。
―この糞野郎共…!!
「こいつを捕まえろッ!」
彼らが一斉に動き出した。
早苗は身構えた。恐怖はない。
─相手は5人。試合じゃ1対1しかやないからなぁ、大丈夫かな?
そんなことを考えながら重いバック振り回した。
一番手前まで近づいていた相手にバックが当たる。振り回した遠心力を利用してそいつのこめかみに蹴りを叩きこんだ。そいつはそのままバランスを崩して隣にいた者を巻き込んで転んだ。
「ぐっ!」「うわ、おい!」
─体育のまんま短パンはいておいてよかった!
倒れた者の逆の隣の攻撃を身を低くしてかわし、鳩尾に鋭い突きを入れる。
「うぁっ!」
─あと、2人!
そう思って振り向いた時、後ろからの蹴りをまともに受け前から攻撃を仕掛けてきた者と正面からぶつかった。
「キャッ」
「へぇ、案外可愛い声だすじゃねーの!」
そいつに捕まる前にあごにしたから手のひらを叩き込み、腹に思いっきり膝蹴りを入れた。
「うっ!」
振り向く前に下に向けていたバックを思いっきり上に振り回す。
当たりはしなかったが、後ろから来ていた者がバックをよけて止まる。
その隙にすばやく間合いを詰め顔めがけて右ストレートを叩きこんだ。
「がっ、てめ」
くるり、と背を向けて走った。ちょっと様子見に振り返ったら、砂場に足を取られて転びそうになった。その時、あるものが目に入った。
─お、いいものはっけーん!
─相手は5人。試合じゃ1対1しかやないからなぁ、大丈夫かな?
そんなことを考えながら重いバック振り回した。
一番手前まで近づいていた相手にバックが当たる。振り回した遠心力を利用してそいつのこめかみに蹴りを叩きこんだ。そいつはそのままバランスを崩して隣にいた者を巻き込んで転んだ。
「ぐっ!」「うわ、おい!」
─体育のまんま短パンはいておいてよかった!
倒れた者の逆の隣の攻撃を身を低くしてかわし、鳩尾に鋭い突きを入れる。
「うぁっ!」
─あと、2人!
そう思って振り向いた時、後ろからの蹴りをまともに受け前から攻撃を仕掛けてきた者と正面からぶつかった。
「キャッ」
「へぇ、案外可愛い声だすじゃねーの!」
そいつに捕まる前にあごにしたから手のひらを叩き込み、腹に思いっきり膝蹴りを入れた。
「うっ!」
振り向く前に下に向けていたバックを思いっきり上に振り回す。
当たりはしなかったが、後ろから来ていた者がバックをよけて止まる。
その隙にすばやく間合いを詰め顔めがけて右ストレートを叩きこんだ。
「がっ、てめ」
くるり、と背を向けて走った。ちょっと様子見に振り返ったら、砂場に足を取られて転びそうになった。その時、あるものが目に入った。
─お、いいものはっけーん!
早苗の目に留まったのは、子供の砂場用の遊具──バケツ
早苗は小さなバケツを手にとると、砂場の砂の─特に乾いててさらさらしている部分をバケツいっぱいに取り少年たちに投げた。
砂は彼らのところまで届かず、少し手前に着地し盛大に砂埃を上げた。
「「ゲホッ、ゲホゲホッ!」」
砂埃は彼らの目や口にまで侵入し、少しの間だけ、彼らの視界を妨げた。
「あいつ、逃げ足スゲー速ぇー」「感心してんなバカ!」
彼らの視界が回復したとき、彼らの前に早苗の姿は無かった。
*******
少年たちの目の届かなくなった所までくると、早苗は足を緩めた。
「あーもう、制服が埃だらけになっちゃったじゃん!」
砂がまとわりついている部分に関しては自業自得なのだが、そんなことは気にしない。
「それにしてもあたし足速いなぁ、陸上部入れるんじゃないの?」
あははーと笑いながら軽い足取りで家に帰った。
しかし、それから数日後。
またもや彼らが現れた。
その日だけではない。
倒しても、倒しても、何回でも彼らはやってきた。
帰り道のどこかで待ち伏せをしているのだ。
おかげで、早苗の友人たちは早苗を帰りに誘わなくなった。
そんなことの繰り返しで早苗の機嫌が良くなるはずもなく、いつもしかめ面をしているといつしか早苗は、恐ろしいヤンキーである、だとか、放課後に後輩いびりをしてカツアゲをしている、だとか、ストレス解消に他校の者と殴り合いの喧嘩をしているなどのうわさが広まった。
最後のに関しては多少間違っているものの、否定はできず、その態度が勝手に全てのうわさを認めたと誤解された。
こうして早苗は周りに勝手にヤンキーに仕立て上げられたのだった。
早苗に好意をもって近づいてくるものはいなくなり、喧嘩のうわさを聞きつけて腕試しにと敵意を持って近づいてくる者はどんどん増えていき──
───今に至る。
──つまらない・・
それが早苗の今の生活の本音だった。
学校に行けば怯えられるか、冷やかしを受けるか、蔑(さげす)んだ目で見つめられるかのどれか。
教師も同じようなもので、世話焼きな先生には「どうしたんだお前」といわれる始末。
──私が悪いんじゃない。何も悪くない・・なのにどうしてなんだろう・・?
ある日、またも襲撃があったときに早苗は聞いた。
「あんたらさ、何でアタシをしつこく狙ってくんの?」
彼らはニヤニヤと笑うだけで、答えない。
その中のリーダー格らしき髪に軽く赤いメッシュを入れた人が1歩前に進みでた。
──あいつ!駅前にいた奴!
そう、駅前の路地で早苗に絡んで来た男だった。
学ランであることを見れば、恐らく高校生であろうと思われる。
そいつがポケットから取り出したのは、早苗の生徒手帳。
「出かけるときまで持ち歩いてるなんて、優等生だなぁ」
からかい混じりの言葉を吐き出すと周りにいた者たちも下卑(げび)た笑いをこぼす。
「わざわざ返しに来てくれたって訳?ご苦労様」
「どうぞ来てくださいって言わんばかりに丁度よく落としてくれたもんだから?俺たちの親切心がもうウズウズしちゃって、さ。
でパシらせてみれば案外強いってんじゃねーか。それじゃぁ拾った俺みずからが行くべきじゃない?」
早苗はそいつを思いっきり睨みつけた。
「じゃあさっさと返してくんない?」
「そんな怖い顔すんなよ。こいつらには無償で遊んでくれたってのにこれ返して俺には何もナシじゃつまんないだろ?」
「アタシはもっとつまんない」
「つれないなぁー」
──アンタのことなんかどうだっていいっての!
男は余裕のニヤニヤ笑みを貼り付けて早苗を見ている。
目線を早苗から話さないままに、ポケットから携帯を取り出しどこかに電話をかけ、相手が出たのを確認すると会話もせずに切った。
「さてと、じゃ始めましょか」
一人の少女と数人の男は一斉に動き出した。
早苗達が戦いを始めた頃、少し離れた道に二人の男子生徒が下校していた。
二人が他愛の無い話題を話しながら歩いていると、前方からただならぬ雰囲気をまとったどこぞの学校の学ラン姿の男十人近くがあわただしく走って二人を通り過ぎて行った。
彼らの後姿を見て、一人が少し興奮気味にささやいた。
「なんだあれ?」
「さあな、最近うわさの喧嘩じゃないのか?」
一人とは反してもう一人は面倒そうに答えた。
そんなことは微塵も気にせず、少年は問いを続ける。
「隣のクラスの里山の?」
「そう、あの制服はガラの悪さで有名な西高だろうな。あの女も随分面倒なとこに目つけられたな。」
最初の少年は「ふーん」と言って彼らが去ったほうを見つめた。
そして、唐突に言った。
「なぁ、ちょっと見に行こうぜ?」
「あ?」
もう一人の少年は連れの一言に眉を吊り上げた。
「嫌に決まってんだろ。何でわざわざ面倒に首を突っ込むような真似すんだよ」
最初の少年は「お願い!」という風に手を合わせた。
「ちょっとした興味だって。な?頼むよ、ヒスイ」
ヒスイと呼ばれた少年は黙って、少年をにらみつけた。
少年は子供のようにヒスイの制服の端っこを引っ張って訴える。
「なー、行こうぜー?」
「ったく、仕方ねーな!ちょっと覗いたら帰るぞ!」
「やりぃっ!」
そう言って少年は先ほどの彼らを追って走り出した。
「おい、待てよユウジ!」
ヒスイもユウジの後を追いかけていった。
──何か、嫌な予感がする
近づく敵を片っ端からなぎ倒しながら、早苗は思った。
それは、あのリーダー格の男の未だしっかりと張り付いている嫌な笑みの所為だろうか。
それとも、今回になっていつものよりも格上の人間が登場したことで話が段々と大きくなっている不安感からか。
とにかく、何がと明確にはいえない何かが早苗の集中力の邪魔をしていた。
その時、早苗は別の違和感に気がついた。
いつもならそろそろ相手もへばってくる頃だ。
なのに、一向に勢いは収まらない。
それどころか向こうの士気は先ほどよりも増していた。
──一体何が────?
その答えはすぐに出た。
早苗の目の前に今まで見たことの無い男が躍り出た。
その男の攻撃をかわすと早苗は一旦間合いを取った。
明らかに、最初よりも人数が増えている。
見ればまだ何人かこちらに向かってきている。
早苗は歯をギリ、と軋らせ、思いっきりリーダーを睨んだ。
──あんの・・卑怯者ぉ!!
その一瞬の隙を突かれた。
横から走ってきた男のタックルを受けそのまま吹っ飛ばされる。
「うぁっ」
その先にいた男が蹴りを入れる。
立ち上がる間も無いままにさまざまな方向からの攻撃を受ける。
少しすると、続いていた攻撃がピタ、と止んだ。
頭を庇っていた手の隙間から恐る恐る周りを見ると、手下たちは少し離れて早苗を囲みあのリーダーの男が近づいてきた。
近づく敵を片っ端からなぎ倒しながら、早苗は思った。
それは、あのリーダー格の男の未だしっかりと張り付いている嫌な笑みの所為だろうか。
それとも、今回になっていつものよりも格上の人間が登場したことで話が段々と大きくなっている不安感からか。
とにかく、何がと明確にはいえない何かが早苗の集中力の邪魔をしていた。
その時、早苗は別の違和感に気がついた。
いつもならそろそろ相手もへばってくる頃だ。
なのに、一向に勢いは収まらない。
それどころか向こうの士気は先ほどよりも増していた。
──一体何が────?
その答えはすぐに出た。
早苗の目の前に今まで見たことの無い男が躍り出た。
その男の攻撃をかわすと早苗は一旦間合いを取った。
明らかに、最初よりも人数が増えている。
見ればまだ何人かこちらに向かってきている。
早苗は歯をギリ、と軋らせ、思いっきりリーダーを睨んだ。
──あんの・・卑怯者ぉ!!
その一瞬の隙を突かれた。
横から走ってきた男のタックルを受けそのまま吹っ飛ばされる。
「うぁっ」
その先にいた男が蹴りを入れる。
立ち上がる間も無いままにさまざまな方向からの攻撃を受ける。
少しすると、続いていた攻撃がピタ、と止んだ。
頭を庇っていた手の隙間から恐る恐る周りを見ると、手下たちは少し離れて早苗を囲みあのリーダーの男が近づいてきた。
「流石に、どんだけ強いっても一人でこの人数相手にはプロじゃない限り無理だよな」
早苗の顔のそばでしゃがみ、早苗の顔を覗き込む。
無論、あの笑みを携えて。
「あんたまだまだ遊べそうだからさ、ちょっと一緒に来てよ。」
「ッ・・」
「よく聞こえないんだけど?」
男は耳に手を当てる仕草をして、早苗の顔に近づけた。
早苗はその耳めがけて、思いっきり叫んでやった。
「誰が行くかっつってんだこのゲス!」
その声は耳に響き、数秒男の動きを止めた。
そして、立ち上がると言った。
「女の子がそういう言葉遣いはダメだよ──ねっ!」
男は早苗の腹に足を叩きこんだ。
「うっ・・ゲッホゲホ、ゲホ」
「もうちょいお仕置きが必要かねぇ・・お前ら、自由にしていいぞ」
男は輪の中からでてから言った。
「「「イエーイ!」」」
周りの者たちが沸き立ったその時だった。
「ちょっと待ったぁ!!」
早苗にとって、希望の光となる声が、降ってきた。
この作家の他の作品
表紙を見る
霊感持ちの無声少女
-屋代言乃-
ヤシロ コトノ
言乃の声が聞こえる人
-日奈山炯斗-
ヒナヤマ ケイト
歓楽街の裏で相次ぐ殺人事件
浮かび上がる蠢く組織
一人の“幽霊”が
事件を大きく動かす
バラバラになる二人
――このままじゃアイツ
消えるぜ?――
孤独な逃走劇が
今、幕を開く
§
言炯-コトケイ-シリーズ
第二弾
start 2012/06/05
§
前作
空耳此方-ソラミミコナタ-
番外編
RAIN RAINBOW
こちらも宜しくお願いします!
表紙を見る
英国喜劇リトレイス
外伝
本編では描くことの出来なかった
キャラクターの過去・背景
そして後日談
SSを書いて行きたいと思います
†
本編
ストーリー原案
日田 恵
執筆
白川 紘哉
表紙を見る
人は誰もが自由に生きて行ける訳ではない
身分
立場
運
時代
それらのしがらみが人間を大きく左右する
しかし――
人を動かすのは
それだけではないかも知れない
人では決して届かない
人より高みに位置する存在の手が――
今、彼らを突き動かす
─英国喜劇リトレイス─
四男坊の復讐
「俺は必ず…兄貴をブッ殺す!!」
どうなるイギリス!
どうなる四兄弟!
*
ストーリー原案
日田 恵
*
外伝
英国喜劇リコレクション
こちらもどうぞ《*≧∀≦》
*
start 2012.3
finish 2012.7.13
*
イギリスを舞台としていますが
実際の史実とは関係ありません
お楽しみください♪ヽ(´▽`)/
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…