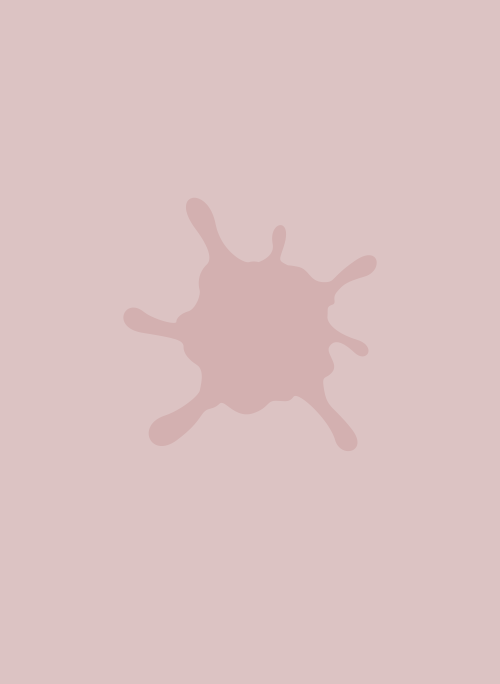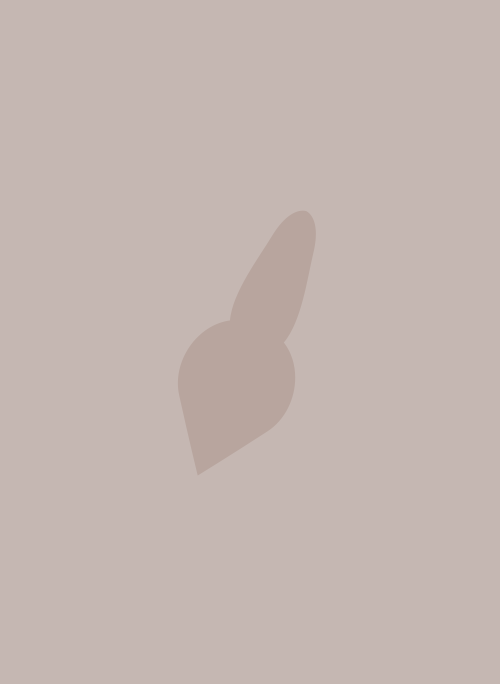「ハムおじさん……それって」
僕はテーブルの上に置かれた肉の塊を指差した。
ハムおじさんは言う。
「んっ? なんだい。ハムパンマンも食べたいのかい。まったく食いしん坊だなぁ」
「そうじゃなくて」
「そういえば……チーターさん達は、僕が届けたハムサンドウィッチ、ちゃんと食べてくれたかなぁ」
チーターさん家のチー太くんがいなくなったのは一昨日。
その日ハムおじさんは新しいハムを燻製していた。
そのハムを・・・ハムおじさんは僕の頭に。
そして、そのハムで作ったサンドウィッチを、今日チー太くんの両親に。
気がつくと僕は間合いをつめて、ハムおじさんの首を絞めていた。
僕はテーブルの上に置かれた肉の塊を指差した。
ハムおじさんは言う。
「んっ? なんだい。ハムパンマンも食べたいのかい。まったく食いしん坊だなぁ」
「そうじゃなくて」
「そういえば……チーターさん達は、僕が届けたハムサンドウィッチ、ちゃんと食べてくれたかなぁ」
チーターさん家のチー太くんがいなくなったのは一昨日。
その日ハムおじさんは新しいハムを燻製していた。
そのハムを・・・ハムおじさんは僕の頭に。
そして、そのハムで作ったサンドウィッチを、今日チー太くんの両親に。
気がつくと僕は間合いをつめて、ハムおじさんの首を絞めていた。
ギギギと口の端から泡を吹いて、ハムおじさんは溺れるように、もがいていた。
ばたばたとさせていた右手が何かをつかんだ。
厨房に置いてあった血だらけの包丁を掴んだハムおじさんは僕の腕に向かって切りつけた。
すんでのところで手を離した僕は数歩後ろに下がる。
左手で喉元をおさえながら、ハムおじさんは鬼の形相で包丁を振りかぶる。
僕は横に置いてあった業務用の4キロもある小麦粉の袋を破き、振り回した。
ばたばたとさせていた右手が何かをつかんだ。
厨房に置いてあった血だらけの包丁を掴んだハムおじさんは僕の腕に向かって切りつけた。
すんでのところで手を離した僕は数歩後ろに下がる。
左手で喉元をおさえながら、ハムおじさんは鬼の形相で包丁を振りかぶる。
僕は横に置いてあった業務用の4キロもある小麦粉の袋を破き、振り回した。
空間内は瞬時に粉末で満たされ、ハムおじさんは顔に多量の小麦粉を浴びて、顔を僕から背けた。
怯んだ隙を見計らって後ろに回り込み、チョークスリーパーで再び首を絞める。
フッと右手の力が抜けた。
見ると僕の右腕は切断され、傷口からはフレッシュな鮮血が蛇口のごとく噴出していた。
形勢は逆転し、僕はテーブルに押し倒され、ハムおじさんは僕の上に馬乗りになった。
ハムおじさんは目を血走らせながら、握りしめた包丁を僕の心臓に振り下ろす。
そんな時だった。
そんな絶望的な状況の中で、僕はまったく別のことを考えていた。
怯んだ隙を見計らって後ろに回り込み、チョークスリーパーで再び首を絞める。
フッと右手の力が抜けた。
見ると僕の右腕は切断され、傷口からはフレッシュな鮮血が蛇口のごとく噴出していた。
形勢は逆転し、僕はテーブルに押し倒され、ハムおじさんは僕の上に馬乗りになった。
ハムおじさんは目を血走らせながら、握りしめた包丁を僕の心臓に振り下ろす。
そんな時だった。
そんな絶望的な状況の中で、僕はまったく別のことを考えていた。
この町のみんなは本当に優しい。
僕は人でもなく動物でもない。
そんな得体のしれない僕を、みんなと同じように学校に通わせてくれた。
共に歩む仲間として扱ってくれた。
だからみんなの愛に応えたい。
僕はみんなを守りたい。
だって僕はハムパンマン。
みんなに頼りにされるのが嬉しくて、みんなの為に働くことが生きがいだ。
みんなの為になるのなら・・・・自分の命は惜しくない。
僕は人でもなく動物でもない。
そんな得体のしれない僕を、みんなと同じように学校に通わせてくれた。
共に歩む仲間として扱ってくれた。
だからみんなの愛に応えたい。
僕はみんなを守りたい。
だって僕はハムパンマン。
みんなに頼りにされるのが嬉しくて、みんなの為に働くことが生きがいだ。
みんなの為になるのなら・・・・自分の命は惜しくない。
ハムおじさんが僕の胸に包丁を突き立てた頃。
テーブルに置いてあるライターに手を伸ばす。
そして小麦粉の粉塵が高密度に飛び交うこの密室で。
僕はライターに火をつけた。
END
テーブルに置いてあるライターに手を伸ばす。
そして小麦粉の粉塵が高密度に飛び交うこの密室で。
僕はライターに火をつけた。
END
最後までお読みいただきありがとうございます。
最後どうなったの!?と思われた方は、ネットで『粉塵爆発』と調べてください。
決してやったら駄目ですよ。
死にます。
ハムおじさんの犯行の動機は、大きく分けて二つ。
一つは人類を滅ぼされた復讐。
もう一つは純粋な食欲ですね。
ちなみに作者がこの作品で一番気に入っているのは、スキンちゃんというネーミングです。
スキンとはコンドームのことです。今はあんまり言わないけど。
この作品を通じて、作者がいかにイカレてるかがわかっていただけたら幸いです。
感想お待ちしてます。
ありがとうございました。
最後どうなったの!?と思われた方は、ネットで『粉塵爆発』と調べてください。
決してやったら駄目ですよ。
死にます。
ハムおじさんの犯行の動機は、大きく分けて二つ。
一つは人類を滅ぼされた復讐。
もう一つは純粋な食欲ですね。
ちなみに作者がこの作品で一番気に入っているのは、スキンちゃんというネーミングです。
スキンとはコンドームのことです。今はあんまり言わないけど。
この作品を通じて、作者がいかにイカレてるかがわかっていただけたら幸いです。
感想お待ちしてます。
ありがとうございました。
この作家の他の作品
表紙を見る
9月22日 早朝7時15分
起床
天気は快晴。昨日の雨が嘘のようだ。
日差しは強いが、暑過ぎることなく程よい。
小鳥のさえずりも耳をすませば聞こえてくる。素敵な朝。
朝食は軽く食パンとコーヒー。
食べ終わるとパジャマを脱いでスーツを羽織る。右手にはカバンをたずさえて。
時計の針は8時15分。玄関で靴をはいて扉を開ける。
すると目の前には一人の少女。
少女は顔はズタズタに引き裂かれ、両の腕の骨はありえない方向に曲がっている。
その顔はニヤニヤと薄ら笑いを浮かべて、僕の家の玄関先で立っていた。
何事もなかったかのように扉を閉めて、鍵をしめた。
そして首をかしげる。
おかしいな。
何でだろう。
今の女の子は昨日確かに。
僕が殺してやったはずなのに。
※この作品にはグロテスクな描写だけでなく、胸糞悪い展開もふんだんに含まれております。
表紙を見る
何か良いことがあったとしても
悪いことがあったとしても
何か嬉しいことがあったとしても
悲しいことがあったとしても
おもむくままの君が
うつむきたいと願うなら
誰に何といわれようと
君のために
下を向いて歩いていこう
表紙を見る
─────昨日、遠い外国でたくさんの人が亡くなったらしいよ
ふーん
・・・どうでもいいから
─────難民の人達は今も食べ物すら無くて困ってるんだって
あっそ
・・・どうでもいいから
─────明日、この近くで募金活動するんだけど、よかったら一緒にいかない?
あのさ
そんなことどうでもいいから
とにかく私のことはほっといて
─────ねぇ、さっきからなんなのその態度。ひどくない?
たくさん困ってる人がいるんだよ?
・・・もう本当に
そんなことどうでもいいから
世界平和とかどうでもいいから
・・・おねがい
誰か私の気持ちを受け止めて
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…