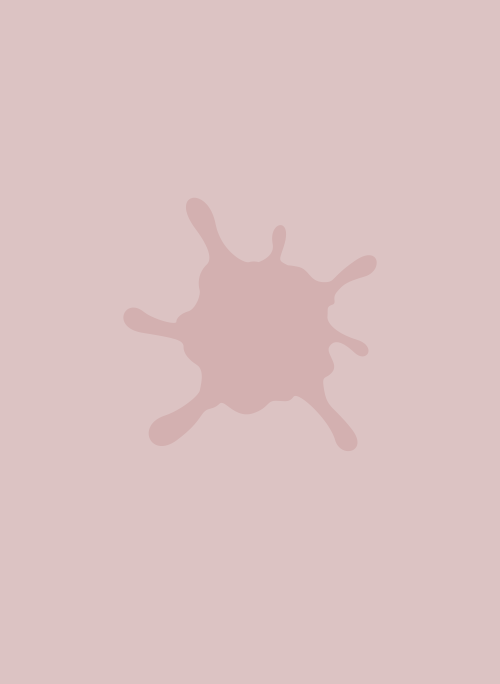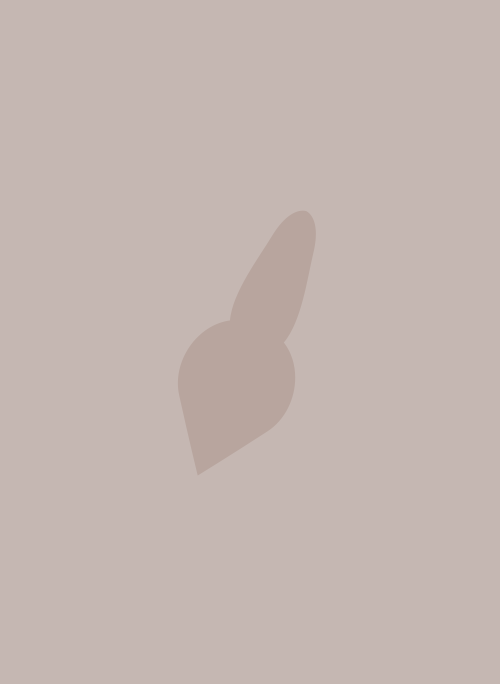「じゃあ行ってくるよ、ハムおじさん」
「ああ、気をつけて行っておいで」
僕はハムおじさんに手を振って、いつものように空のパトロールに出た。
ハムおじさん。
この地球でただ一人の人間。
そして僕を作ってくれた人。
昔は人間が大勢いたらしいのだけれど、自分達で戦争を繰り返して、数は激減してしまった。
動物たちはその間、人間達に隠れて独自の進化を遂げて、知能をつけた。
今ではすべての動物が二足歩行で移動し、コミュニケーションツールとして言語を用いて仲良く暮らしている。
知恵をつけた動物たちは人間達をせん滅しようとした。
今まで好き勝手に生きてきた人間たちに堪忍袋の緒が切れたらしい。
その唯一の生き残りがハムおじさんだ。
ハムオジさんは当時はまだ赤子で、子供に罪はないだろうということで生かされた。
そんな生い立ちのハムおじさんだけど、動物たちに可愛がられて育てられて、すっかり動物たちとの暮らしになじんでいる。
今日はチーターさんの家に、美味しいサンドウィッチを届けるって言っていた。
僕もみんなの為にがんばらなきゃ。
僕は空を飛びながら、町に異常がないか目を光らせた。
すると。
「あ~ん。お腹がすいたよ」
町はずれの森の方から子供の泣き声が聞こえてきた。
この声は……カバさん家のカバ吉くんだ!
僕は急いで森に向かった。
森の中を声を頼りに低空飛行で飛んでいると、切り株に腰をかけてめそめそと泣いているカバ吉を発見した。
「お~い。カバ吉く~ん」
僕の声に気づき、カバ吉君は僕の方に顔を向けた。そして嬉しそうに僕に駆け寄った。
「ハムパンマン。怖かったよぉ~!」
「こんな森の奥に一人で来ちゃだめじゃないか。ここに何しに来たんだい」
「えへへ。実はお腹が空いちゃって……。森にキノコを採りにきたんだ」
「お腹がすいたのならハムおじさんのところに行けば良かったのに。ほら、僕の頭をお食べ」
「わ~い。ありがとう」
カバ吉くんはお礼を言うなり、夢中で僕の頭にかじりついた。
むしゃむしゃと音を立てて、みるみる内に僕の頭は半分になってしまった。
「カバ吉くん。たべすぎだよ」
「……僕ね、ハムパンマンは、ハムとパンがなくても十分いけると思うんだ」
「全部食べるつもりだね。それじゃあ僕は何者でもないただの『マン』になってしまうじゃないか。そんな哲学的なヒーロー、僕はごめんだ」
「えへへ。バレたか」
「こんどハムおじさんの所においで。美味しいサンドウィッチを御馳走してくれるよ」
「わ~い!」
僕はカバ吉くんを背中に乗せて、宙にふわりと舞い上がった。
そこで一つ問題起きた。
僕が高度を上げようとマントをコントロールしているのに、一向に上にあがらない。
「カバ吉くん。また太ったね」
「えへへ。実は太ったせいでお母さんにおやつ禁止にされちゃって、それで森に……」
「ハムおじさんの所にはダイエットしてから行きなさい」
「え~。今日にでも行こうと思ったのに」
「我慢しなさい」
「できるかなぁ」
「これから大人になったら、我慢しなきゃいけないことがいっぱい……って空とんでるときに頭かじっちゃだめぇぇぇぇ!」
僕はなんとか低空飛行を保ち、森を出た。
森を出ると、公園で子供たちがブランコや砂遊びをして遊んでいて、それを見守るようにウサミ先生がベンチを座っていた。
「ウサミ先生こんにちわ」
「あらハムパンマンとカバ吉くんじゃない。こんにちわ。ハムパンマン大丈夫?」
「ええ。カバ吉くんくらいの重さなら背中に乗せても大丈夫ですから」
「そうじゃなくて、もう頭が握りこぶし一つ分しか残ってないわよ」
「カバ吉くん。もう降りてくれるかな」
「はぁ~い」
カバ吉くんは残りわずかな僕の頭を、名残惜しそうに見ながら砂場に向かっていった。
僕はウサミ先生が座るベンチに腰を下ろすと、ウサミ先生が笑いながら僕に声を掛けた。
「うふふ。ハムパンマンだいぶ食べられちゃったね」
「胴体のほうを食べられなかっただけマシです。さすがに体を食べられたら死にます。
しかしウサミ先生もいつも子供の相手大変ですね」
「子供が好きだからね。そんなに大変って感じでもないかな」
ウサミ先生。
この町の学校の先生で、子供たちに勉強を教えている。
今日みたいな学校のない休みの日でも子供たちの遊び相手をして、街のみんなからの信頼も厚い。