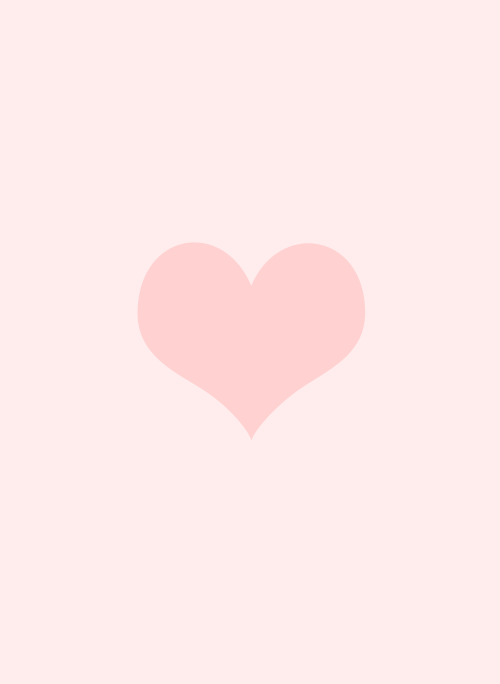カキーン・・・
「・・・っしゃ!!」
「いいぞ、悠!!走れ~!」
あたしは、君に向かって出来る限りの声を出した。
あたしと悠は付き合っている。
「菜緒~!!」
ホームランをして、気分のいい悠があたしに手を振った。
「悠~~!!」
どう見ても、ラブラブなカップル。
「おい。そこのバカップル。」
「皆ちゃん!!」
皆ちゃんこと、あたしの友達はあたし達の恋を応援してくれている。
「皆ちゃん、今日も見に来てたんだ。」
「うん。あんたたちの、いちゃつき具合を。」
キラーンと目を輝かせた、皆ちゃんの前に悠が横に入る。
「ちょっと、俺の彼女とらないでくんない??」
「はぁ??」
皆ちゃんが、首をかしげた。
その後に、ぷぷっと笑った。
「なんだよ、皆。」
「ははは、ウケる~~!!」
あっはははと、大きな口で笑った。
「ちょ、からかわないで。皆ちゃん。」
あたしは慌てて、皆ちゃんの口を押さえた。
そう、そんな日を越えて
明日は入学式。
明日から、あたしたちは高校生になる。
「悠、何組になるかな~。」
「菜緒と同じがいいなぁ。」
なんて
あま~い話をしていた。
明日は入学式。
高校生。
それは、夢の舞台となる甲子園への道。
甲子園は、俺の全部が詰まってる。
「菜緒~!!」
俺は、菜緒にいつも駆け寄る。
「悠!!」
菜緒も、それにのって駆け寄る。
「菜緒、緊張するな~。」
「え、何が。」
「何が・・・って、入学式だよ!!入・学・式!!」
俺は、高校の大切さを大きくアピール。
「あ、そう。そっか~、そうだった。」
「そうだった・・・って、なんで忘れてんの!?」
俺は、菜緒に目線を送った。
「あ、ごめーん!!あたし、今日お母さんに頼まれてることあったんだった。」
菜緒は、それを無視するかのように、後ろを向いた。
「おい!!菜緒!!」
スタスタ・・・
「待てよ。」
俺は、菜緒があの約束を忘れてしまっているんじゃないかと、心配になった。
「なんて、無責任な奴・・・。」
俺は、頬を赤くさせながら言った。
明日、正直楽しみだなぁ。
俺は、子どもみたいにはしゃいだ。
はぁ。
危なかった。
悠ったら、デリカシーってもんはないの??
あんな人の多い場所で言えるはずがないじゃない。
あたしは、
入学式
=甲子園
=行く
=結婚
になるんですけど!!
そんなこと、考えてるのは
あたしだけかもしれないし・・・。
言えるはずないって。
「に・・・逃げてきちゃった。」
あたしは、気づいたら家の前に居た。
逃げて来るのは、まずいよね・・・。
あたしは、今自分がした行動に後悔した。
「ばかぁ。あたしのバカ!!なんで逃げて来てんのよ!?」
あたしは、自分で自分の頭を叩いた。
「おい。叩いてもっとバカになったら、どうすんだよ。」
「は????」
あたしは、驚いて後ろを振り返った。
「菜~緒。」
「悠・・・。」
あたしは、呆然とした。
なんで、悠が??
「菜緒、驚いた?」
にっと笑った。
「なっ、なんでここにいるのよ??」
「へへ。嬉しい?」
いつもに増して可愛い顔をした。
「ばっ、ばか!!そんなはず、ないでしょう?」
あたしは、顔を真っ赤にした。
あり得ない!
悠なんて、あり得ない!!
絶対ないって!!!
「俺、ばかって言われるの、正直傷つくんですけど。」
「え。えっと、ごめん・・・。」
あたしは、落ち込んだような顔をしていたみたいで、
「あっれ?菜緒、落ち込んだ??」
は?
んなわけないでしょ??
「違うしッ!!」
あたしは、本当は甲子園のことで頭がいっぱいだった。
そんなこと、悠にはいえないけど。
「あっれ。あれって、跡部菜緒と、悠?
なんであの2人が一緒に。」
木陰から、優しく見つめるジャージの少年。
「おい。不二、ぼさっとすんな。」
「あ、すみません。」
その少年は、またランニングをはじめた。
あたしは、まだ知らなかった。
ブンッ
俺は、思い切りバットを振った。
ふぅ。
俺はゆっくりため息をついた。
・・・?
ん?
なんか、視線を感じる。
俺は、勢いよく後ろを振り向いた。
「・・・」
なんだ。
陸上部のランニングか。
俺は、まだ“陸上部”にはピンときていなくて、また素振りの練習をした。
『ホームラン』
俺は、菜緒を甲子園に連れて行く。
俺の、ホームランで。
「悠!!」
「はい!」
俺は、誰かに呼ばれて振り向いた。
・・・。
部長だ。
「悠!」
「はい!なんスか?」
俺は決めて、返事をした。
部長の後に、監督とコーチが来た。
俺が、呼ばれて連れてこられた場所。
“部室”
そこには、
越前、大石、桃城。
俺より先輩な3人がいた。
俺は、その中のメンバーに入ったような気がして嬉しかった。
そして、部長がなにやら話し始めた。
「今日、君らをここに呼んだのは・・・。」
まだ、ほんの少ししか、話していないのに鼓動が高鳴る。
部室に部長の声が響く。
そして、また話し続ける。
「君らを、スタメンにしようと思っているからだ。」
え??
スタメン!?
本当に?
俺は、嬉しくてたまらなかった。
早く、菜緒に伝えないと。
そればかり考えていた。
「あれ~、悠がいない。どこ行っちゃったのよ。」
はあ、とため息をつくあたしに誰かが近づいて来るのが、自分でも分かった。
「跡部・・・菜緒。」
あたしは、振り向くのをやめた。
声からして、それが男だということは理解できた。
しかし、その男はあたしのことを知っていた。
あたしは、振り向くのが急に怖くなった。
「・・・・」
あたしは、無言のままだった。
「跡部 菜緒。俺に見覚えがあるか。」
・・・え?
見覚え?
なんで。どうして。
もしかして、あたしはこの人に会ったことがあるの。
初対面じゃないの?
知り合い?
いとこ?はとこ?親戚?
あたしは、どんなに考えてもその男の声には聞き覚えがなかった。
でも、なぜか懐かしくて
でも、なにか壊してしまいそうで。
あたしは、途中で曖昧であるが、この人には前に会ったことがあるのだと確信した。
放課後の廊下。
誰もいない長い道。
そこに、一人の男の声だけが響きわたる。
「・・・ぁ・・・なた。もしかして、あたしのこと・・・。」
少し震えていた
あたしの声。
あたしは、怯え構えで後ろに振り向いた。
そこにいたのは、
「え・・・」
あたしは、思いもよれぬ出来事に声を失った。
そこにいたのは、
不二。
悠の中学時代、初試合で戦った相手。
不二。
茶色のサラサラヘアー。
吸い込まれそうなブルーの瞳。
忘れることのできない桃色の唇。
「跡部 菜緒・・・ちゃん。驚いた?」
あたしは、声変わりした不二の顔に引き寄せられた。
「不二・・・。」
あたしは、思わず口に出してしまった。
「菜緒。」
いきなり呼び捨てで、あたしは胸がなった。
ダメ。
駄目。
だめだよ。
あたし。
『菜緒』
は、悠しか呼んじゃだめなんだから。
「・・・め。だめ。」
あたしは、小さい声で言った。
「何?菜緒ちゃん。」
よかった。
呼び捨てじゃない。
「い、いえ。何も。」
あたしは、俯きながら言った。
「『菜緒』は悠だけだ って思ったんだろう?」
え!?
どうして、それを。
なんで。
「別に、そういう意味じゃない。」
あたしは、そっぽを向いた。
「菜緒ちゃんは悠にいつもべったりだったもんなぁ。」
「違います。そんなんじゃない。」
あたしは、ほっぺを赤くして言った。
「まぁまぁ、そうお気になさらずに。」
不二はいつも、笑顔だった。
「不二ってば、訳わかんない。」
あたしは、少し懐かしい気持ちでドキンとした。
「・・・晴(ハル)って呼んでよ。」
不二はにこっとした。
「・・・は、晴。」
あたしは、顔が真っ赤だった。
「菜緒~!どこだ~?」
俺は、廊下を走り回った。
「くそっ。後は、三階西側の廊下だけだ。」
三階西側の廊下は、特別人気のない所。
俺は、嫌なことばかり思い浮かんできた。
「...まさか。」
俺は、勢いよく走り出した。
二階東側から、階段を駆け上った。
「はぁはぁ!」
間に合ってくれ!!
菜緒!!
~三階西側
「くそっ。開かねぇ!!」
俺は、外から錆び付いた鍵を強引にこじ開けようと思った。
ーガシャンッ
「はっ、開いた。」
・・・・・・!!
「・・・え」
俺は、息をのんだ。
この状況が理解できなかった。