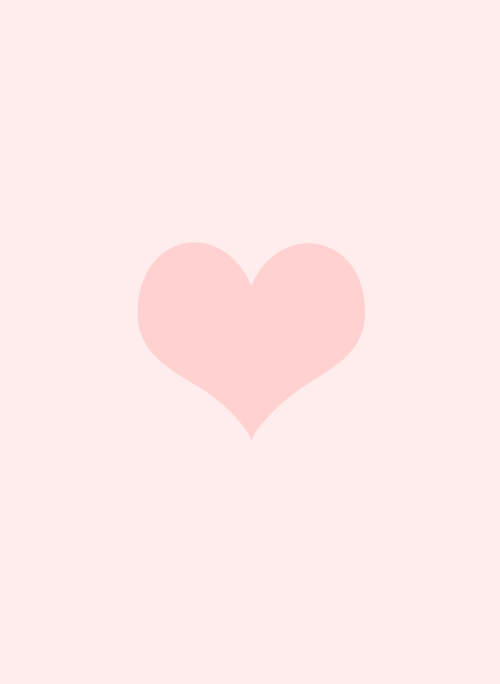「いいんじゃねぇ?好きで。」
はっきりそう言い切った蓮
「いや…でも……」
「ほら、よく言うだろ?好きなのは自由だって」
「……は?」
そういう問題か?
「まぁ、それと、棗は今でも花音が忘れられないんだろ?」
「あっ…あぁ―…」
「花音もなんかツラそうだったぞ。」
それは俺もわかってる
でも、それは俺に別れを告げた罪悪感からきてるのかもしれない……
そう思ってしまう…
「じゃあ聞くけど、お前は花音が好きなわけ?」
「は…?何、当たり前のことを……」
「ぶはっ」
「なっ、何だよ?!」
なんで今笑われてんだ?
「悩むことねぇじゃん。当たり前だって言えるぐらい好きなんだから」
「あっ……」
「お前はずっと、花音を好きでいたんだろ?それが当たり前なんだろ?」
そうだ………
花音が俺を好きだと知らなかった時だって…
それでも俺は花音を好きだった
そっか……
好き意外、俺の中には存在しないんだ…
「ふっ。で、お前は今どうしたい?」
「俺は……花音に好きだって伝えたい」
関係ないんだ…。
花音が俺を好きじゃなかったとしても…
好きだってことを伝えたい。
「じゃあ行ってこいよ」
「蓮……」
ニカッと笑って俺の背中を軽く叩いた
「俺、行ってくるわ」
「おうっ!行ってこい」
俺はカバンを持ち、教室を出ようとした
あっ……
「蓮ッ!」
「あ?」
「サンキューな」
「おっ、おうよ//」
ふっ。
ちょっと照れた蓮に笑みがこぼれながら、俺は走り出した
花音悪いな。
俺、諦め悪いみたいだ。
……少しぐらい、悪あがき許せよ。
「はぁ―…はぁ―…」
あの後、学校からずっと走って帰ってきた
何も考えず、ただがむしゃらに走った
乱れた息をゆっくり調えながら部屋に入る
未だに火照っているあたしの身体
そんな身体をギュッと抱きしめて座り込んだ
力強く抱きしめられた時に思い出された、懐かしい体温
たった1週間しか経っていないのに、愛しく感じてしまう温かさ
ダメ……
ダメ…………。
もっと深く、この気持ちは封印しないと―……。
――ピンポ―ン
どのくらいの時間が経ったのだろう…
聞こえたチャイムの音にハッとした
あっ…そっか。
お母さん出かけてて居ないんだった…。
最初は出ないでもいいや、と思っていたけど、何度も鳴らされるチャイム
もぉ―…なんなのよ……
ノロノロと階段を下り、玄関のドアノブに手をかけ開けた
「はい…。どちらさま……ッ」
な、なんで?
なんで棗がいるの!?
――バッ
反射的にドアを閉めようとした。
しかし
「待って。花音!」
そう言ってドアを閉めるのを阻止する棗
「ちょっとでいいから、話しさせて」
「っっ……」
必死そうな棗に、何も言えなくなった
「入って」
ここじゃ棗の両親に見られるかもしれない……
あたしは棗を部屋に招き入れた
リビングじゃ、もしかしてお母さんが帰ってきたら大変だからね…
「で、話しってなに?」
小さいテーブルに向かい合って座る棗に、冷たくそう言った
冷たく言うしかないあたしは胸の中で謝った…。
「俺…さ、今さら幼なじみに戻ろうとか思わない…」
っ……何それ……
「花音も最近しゃべってこないっていうのは同じ理由だろ?」
「そ!それは……」
しゃべりかけられなかったの…。
一方的に別れを告げたあたしを、棗は軽蔑したんじゃないかって…
そう思われるのが怖かった……
でも本当は、幼なじみに戻ってしまったら、あたしは棗をきっとずっと好きでいてしまう……
そう無意識のうちに思ってしまっていたんだ…
だったらこのまま幼なじみに戻らず終わった方がいい。
そう心ではわかっているのに……
なんで涙が出そうになるの…
なんで離れていってほしくないって思ってるの……
棗の顔が見れず手を握りしめ、うつ向いてしまう…
「だから、今日はっきり言っとく…」
っっ………
胸がギュ―と締め付けられる……
「俺は……」
「………」
怖い…聞きたくない……
「俺………花音が好きだ」
「…………え」
「幼なじみに戻るつもりはない。俺が望むのは“幼なじみ”じゃなくて花音が認める“彼氏”なんだ」
「………棗…」
「今までずっと好きでいたんだ。そう考えればあの時に戻ったって思えばいい。」
「だから、誰に何て言われようと、俺は花音を諦めるつもりはない」
泣きそうな顔をあげられないあたし…
だから棗がどんな顔をしてるか見ることが出来ない
「好きでいるのは勝手だろ♪」
やっと涙を押し殺して見た棗の顔は、以前と変わらず優しくあたしを見ていた
「……っっ」
なんで…?あたしあんな酷い別れ方したんだよ…
最低な女なんだよ……
棗にならもっといい彼女が出来るのに……
なのに………
「俺、意外に執念深いから覚悟しろよ」
ニッコリ微笑みかける棗
でも…でもあたしは………
「帰って…」
「え……」
「帰ってよっ!!」
無理やり部屋から押し出した
「花音っ!」
「帰って!」
棗を追い出し、ドアを閉めた
開けられないように、ドアを必死に押した
「花音っ!」
聞こえる棗の声を遮るように、手で耳を塞いだ……
一時して、聞こえていたあたしを呼ぶ棗の声も聞こえなくなり、シーンとした空気が流れていた
………もう帰った?
そう思ったとたん、我慢していた涙が頬を伝った……
本当は嬉しかったの…
こんなあたしをまだ好きだって言ってくれたこと…
嬉しくて仕方なかった……
でもそれじゃダメなんだ…
この作家の他の作品
表紙を見る
「なぁ―。シよっか?」
「なっ……何を………?」
「決まってんじゃん。夫婦
がする事っていえば……」
「っッ!///あたしは結婚なんて
認めてなぁ―い!!」
*-------------------------*
宮澤財閥の御曹司
宮澤 彗 [Miyazawa Sui]
×
相崎財閥の令嬢
相崎 沙羅 [Aizaki Sara]
*-------------------------*
突然親に紹介された婚約者
しかも結婚するのは決定っ!!
2人のSweet☆Planが
今スタートする!
☆甘々です。ご了承
ください(__)★
連載開始☆2月26日☆
連載終了☆4月30日☆
〜〜*〜〜*〜〜*〜〜*〜〜
表紙を見る
「ご主人様って呼んでみ?」
「……は?」
「ほら。ちゃんと言えたら
ご褒美あげるから」
「っ…///呼ばなぁ―いっ!!」
*----------------------*
桜川学園の王子様生徒会長
井之上 輝 [Inoue Hikaru]
×
宮澤財閥の令嬢で生徒会副会長
宮澤 花梨 [Miyazawa Karin]
*-----------------------*
誰にでも優しい完璧な人だと
思っていた。
それがまさか……
あんな俺様で意地悪
だったなんてっ!!
【クラスメイトは婚約者!?
〜Sweet☆Plan〜】
彗と沙羅の子供の話です。
※こちらだけ読んでも大丈夫です
甘々です。ご了承ください。
**表紙公開-2011.1.22-**
**更新開始-2011.1.23-**
**完結-2011.6.17-**
\クラスメイトシリーズ第二段/
表紙公開中っ!!
表紙を見る
――将来の夢なんてない
――将来への希望も特にない
というより持つだけ無駄だ
普通のあたしにとっての人生って
そんなモノだと思っていた……
「夢をもたないなんて、つまらないね」
そう言って悲しそうに笑うキミに
――恋に落ちるまで……
「ねぇ、キミの夢はなに?」
――あたしの夢は……
夢を諦めた少年
×
夢を持たない少女
*甘く切ない物語*
~*キミが望むのなら…
あたしはいつでも笑う*~
テーマ 夢×切甘×恋
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…