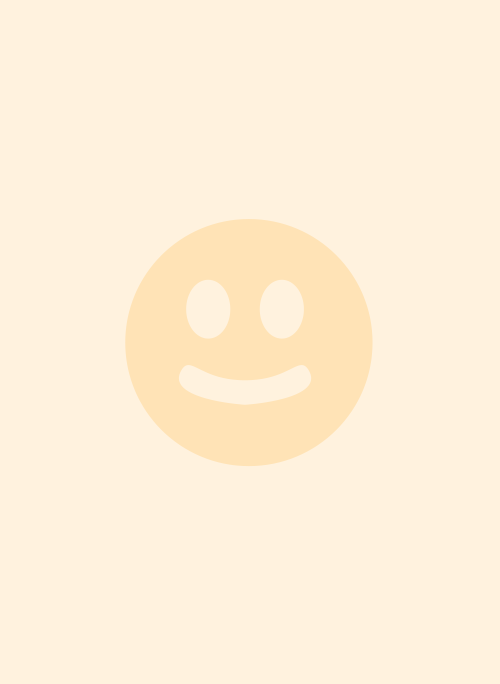「君が歌っていたのか」
ある日、私の立つ断崖に、一人の男性が現れます。
スーツ姿、サングラスをかけた、私よりもずっと年上の男性。
魔力も悪意も感じられません。
どうやら人間のようでした。
「筋はいいんだが、如何せん歌が良くない」
その人はサングラスを外し、優しく笑顔を浮かべました。
「今度はもっと幸せな歌を歌ってみないかい?」
ある日、私の立つ断崖に、一人の男性が現れます。
スーツ姿、サングラスをかけた、私よりもずっと年上の男性。
魔力も悪意も感じられません。
どうやら人間のようでした。
「筋はいいんだが、如何せん歌が良くない」
その人はサングラスを外し、優しく笑顔を浮かべました。
「今度はもっと幸せな歌を歌ってみないかい?」
あれから一年が過ぎました。
…ここは天空宮という不思議な街。
当たり前のように車がメインストリートを行き交い、雲を突き抜け宇宙まで届く軌道エレベーターが市街中心部に聳え立つ一方で、港の沖合いには『リヴァイアサン』と呼ばれる海竜が、山岳部には『天空険道』という魔物がひしめく8000メートル級の岩山が存在するという、ファンタジーとSFがごった煮になったような都市です。
歩道を歩く人々も、今時の流行のファッションに身を包んだ人間の青年もいれば、中世の騎士のような甲冑を装備した虎の獣人、耳の尖った金髪のエルフ美女、肩や肘の接合部に継ぎ目のある自動人形(オート・マタ)『メイドール』など様々。
初めてここを訪れる人達にとっては、この街は本当に空想世界の産物のようでしょう。
…ここは天空宮という不思議な街。
当たり前のように車がメインストリートを行き交い、雲を突き抜け宇宙まで届く軌道エレベーターが市街中心部に聳え立つ一方で、港の沖合いには『リヴァイアサン』と呼ばれる海竜が、山岳部には『天空険道』という魔物がひしめく8000メートル級の岩山が存在するという、ファンタジーとSFがごった煮になったような都市です。
歩道を歩く人々も、今時の流行のファッションに身を包んだ人間の青年もいれば、中世の騎士のような甲冑を装備した虎の獣人、耳の尖った金髪のエルフ美女、肩や肘の接合部に継ぎ目のある自動人形(オート・マタ)『メイドール』など様々。
初めてここを訪れる人達にとっては、この街は本当に空想世界の産物のようでしょう。
夢物語の舞台のような天空宮市。
そのスクランブルの真ん中を走る、魔法機関搭載の高級車のリアシートに、私は座っていました。
フルスモークのリアガラスから、幻想風景を眺めます。
中からは見えても、道行く人達に車内の私の姿は見えません。
移動の時、私はいつもこの車に乗せてもらいます。
私が普通に街中を歩くには、ちょっと有名人になりすぎてしまったもので…。
「あの…下平さん…」
私は高級車の運転をする、運転席の男性に声をかけました。
「んー?何だい?」
サングラスをかけた、気のよさそうな三十歳くらいの男性が、ルームミラー越しに私を見ました。
下平アルベルトさん。
一年前、私が一人歌を奏でていた崖…今では『断崖歌劇場』と呼ばれる場所ですが…そこにいた私に声をかけてきた、初めての男性。
この天空宮市にある、大手芸能プロダクションの若き社長さんです。
一年前のあの日…。
友達も身寄りもなく、孤立して、歌だけが心の支えだった私に、下平さんは声をかけてくれました。
そのスクランブルの真ん中を走る、魔法機関搭載の高級車のリアシートに、私は座っていました。
フルスモークのリアガラスから、幻想風景を眺めます。
中からは見えても、道行く人達に車内の私の姿は見えません。
移動の時、私はいつもこの車に乗せてもらいます。
私が普通に街中を歩くには、ちょっと有名人になりすぎてしまったもので…。
「あの…下平さん…」
私は高級車の運転をする、運転席の男性に声をかけました。
「んー?何だい?」
サングラスをかけた、気のよさそうな三十歳くらいの男性が、ルームミラー越しに私を見ました。
下平アルベルトさん。
一年前、私が一人歌を奏でていた崖…今では『断崖歌劇場』と呼ばれる場所ですが…そこにいた私に声をかけてきた、初めての男性。
この天空宮市にある、大手芸能プロダクションの若き社長さんです。
一年前のあの日…。
友達も身寄りもなく、孤立して、歌だけが心の支えだった私に、下平さんは声をかけてくれました。
―――
――――――
―――――――――
――――――――――――
「せっかく他人の心を動かせる歌が歌えるのに、どうしてそんなしみったれた歌ばかり歌うんだい?もっと癒されるような…笑顔になれるような歌を歌えば、みんなもっと喜んでくれるのに」
「……」
泣きべそをかいたまま、私はそのサングラスをかけた男性、下平さんを見つめます。
「…心を動かせる歌なんて…そんな…」
「ははぁん?」
下平さんがニッと笑いました。
「才能のある者にありがちな事だ。君は自分の歌にどれだけ他人を魅了する力があるのか、わかっていないんだな。その気になれば、この世界の全ての人間を虜にするほどの力があるっていうのに」
あまりに大袈裟な下平さんの物言いに、思わず顔を赤らめてしまいます。
それに。
「『みんな喜んでくれる』って…誰も私の歌なんて聴いてくれていません…」
俯き加減に、小さく溜息混じりに私は言います。
「んー?」
――――――
―――――――――
――――――――――――
「せっかく他人の心を動かせる歌が歌えるのに、どうしてそんなしみったれた歌ばかり歌うんだい?もっと癒されるような…笑顔になれるような歌を歌えば、みんなもっと喜んでくれるのに」
「……」
泣きべそをかいたまま、私はそのサングラスをかけた男性、下平さんを見つめます。
「…心を動かせる歌なんて…そんな…」
「ははぁん?」
下平さんがニッと笑いました。
「才能のある者にありがちな事だ。君は自分の歌にどれだけ他人を魅了する力があるのか、わかっていないんだな。その気になれば、この世界の全ての人間を虜にするほどの力があるっていうのに」
あまりに大袈裟な下平さんの物言いに、思わず顔を赤らめてしまいます。
それに。
「『みんな喜んでくれる』って…誰も私の歌なんて聴いてくれていません…」
俯き加減に、小さく溜息混じりに私は言います。
「んー?」
孤独で、孤立していて、本当に寂しい、悲しい。
そんな気持ちを吐露したつもりなのに、下平さんは笑みすら浮かべて、私の言葉を聞いていました。
その表情が、少し癪に障ります。
「何が可笑しいんですか?」
「いや…だってさ」
彼は崖の下…そこに広がる森の中を指差しました。
「よく見てご覧。あの木の陰…あそこの木の枝の上、それにあの岩陰にも…」
「…?」
言われるままに、私は目を凝らし。
「…!」
ハッと息を飲みます。
「君は孤立しているって言うけれども…だったら何であんな場所に隠れて、『彼ら』は崖の上の君を見つめているんだろうね?」
「……」
知らなかった…。
今まで、あんな場所に人がいるなんて気づきませんでした。
「彼らも僕と同じく、君の歌に魅了されたんじゃないのかな?」
――――――――――――
―――――――――
――――――
―――
そんな気持ちを吐露したつもりなのに、下平さんは笑みすら浮かべて、私の言葉を聞いていました。
その表情が、少し癪に障ります。
「何が可笑しいんですか?」
「いや…だってさ」
彼は崖の下…そこに広がる森の中を指差しました。
「よく見てご覧。あの木の陰…あそこの木の枝の上、それにあの岩陰にも…」
「…?」
言われるままに、私は目を凝らし。
「…!」
ハッと息を飲みます。
「君は孤立しているって言うけれども…だったら何であんな場所に隠れて、『彼ら』は崖の上の君を見つめているんだろうね?」
「……」
知らなかった…。
今まで、あんな場所に人がいるなんて気づきませんでした。
「彼らも僕と同じく、君の歌に魅了されたんじゃないのかな?」
――――――――――――
―――――――――
――――――
―――
そんな風にして私は下平さんに見い出され、今ここにいるのですが…。
「やっぱりいいですよ、下平さん…私、学校なんて…」
「まぁた…」
サングラスを指先でキュッと押し上げ、下平さんは溜息をつきました。
「いいかい?CDこそ販売していないものの、今や君はマジカルネットでのダウンロード件数450万、ヒットチャート軒並み1位獲得の歌姫なんだ。メディアへの露出は、今はほんの数枚の画像のみに過ぎないけれど、君の顔を知らない者なんてこの世の中に幾らもいないだろう。今にテレビ出演も引っ切り無しにオファーが来るようになる」
そう。
たった一年で私は知らぬ者のいないほどの存在となりました。
私は崖の上で歌っていた頃と同様に、ただ歌を奏でていただけ。
そりゃあ歌う曲は少し明るいものになって、下平さんのお陰で素敵な衣装も着させてもらえるようになったりはしましたが…それでも、やっている事は一年前と全く変わりません。
急激な周囲の変化に、私自身戸惑いを隠せないのです。
なのに、この上テレビ出演だなんて…。
私は嫌われ者で、黒い翼を持つ悪魔なのに…。
「やっぱりいいですよ、下平さん…私、学校なんて…」
「まぁた…」
サングラスを指先でキュッと押し上げ、下平さんは溜息をつきました。
「いいかい?CDこそ販売していないものの、今や君はマジカルネットでのダウンロード件数450万、ヒットチャート軒並み1位獲得の歌姫なんだ。メディアへの露出は、今はほんの数枚の画像のみに過ぎないけれど、君の顔を知らない者なんてこの世の中に幾らもいないだろう。今にテレビ出演も引っ切り無しにオファーが来るようになる」
そう。
たった一年で私は知らぬ者のいないほどの存在となりました。
私は崖の上で歌っていた頃と同様に、ただ歌を奏でていただけ。
そりゃあ歌う曲は少し明るいものになって、下平さんのお陰で素敵な衣装も着させてもらえるようになったりはしましたが…それでも、やっている事は一年前と全く変わりません。
急激な周囲の変化に、私自身戸惑いを隠せないのです。
なのに、この上テレビ出演だなんて…。
私は嫌われ者で、黒い翼を持つ悪魔なのに…。
「こらっ」
下平さんの少し強めの口調。
私はビクッとなって顔を上げます。
「俯かない、下向かない。デビューする時に約束しただろう?」
「は、はい…」
内向的ですぐネガティブな事を考えてしまう私への、下平さんとの約束事。
『俯かない、下向かない』
私が顔を上げたのを確認して、彼は運転しながら話を続けます。
「たとえばトーク番組への出演依頼が来たとしよう。色々司会の人が質問してきたとして…君は上手く受け答えできなかったらどうする?テレビを見ている視聴者はこう思うんだ…『あー…歌は上手くても、我らが歌姫は教養のない、的外れな受け答えしか出来ない子なんだな』って…」
「っ…!」
そんな…想像するだけで涙目になってしまいます。
「脅すつもりはないけどね」
クスッと笑う下平さん。
「歌姫だって、一般教養くらいは身につけておかないと。それに同年代の子達との共同生活というのも、それはそれで色々と得られる物があるもんさ」
下平さんの少し強めの口調。
私はビクッとなって顔を上げます。
「俯かない、下向かない。デビューする時に約束しただろう?」
「は、はい…」
内向的ですぐネガティブな事を考えてしまう私への、下平さんとの約束事。
『俯かない、下向かない』
私が顔を上げたのを確認して、彼は運転しながら話を続けます。
「たとえばトーク番組への出演依頼が来たとしよう。色々司会の人が質問してきたとして…君は上手く受け答えできなかったらどうする?テレビを見ている視聴者はこう思うんだ…『あー…歌は上手くても、我らが歌姫は教養のない、的外れな受け答えしか出来ない子なんだな』って…」
「っ…!」
そんな…想像するだけで涙目になってしまいます。
「脅すつもりはないけどね」
クスッと笑う下平さん。
「歌姫だって、一般教養くらいは身につけておかないと。それに同年代の子達との共同生活というのも、それはそれで色々と得られる物があるもんさ」
車はゆっくりと、市街を抜けて坂道を登っていく。
天空宮市郊外。
少し小高くなった丘の上に、目的の建物はあります。
欧風建築の大きな建物。
まるでファンタジーに出てくる、お姫様の住んでいる王宮のようです。
その王宮めいた建物に隣接するように連なる、数多くの建造物。
丘そのものが、一つの街として形成されているように見えました。
天空宮市の郊外に、もう一つ小規模な街があるような、そんな印象。
あの街丸々一つが、学園都市だと言ったら信じてもらえるでしょうか。
下手な田舎町よりも、ずっと大きな建築群だというのに。
「ほら、見えてきたよ」
運転しながら下平さんが言います。
「あれが君が今日から通う、天空宮学園だ」
天空宮市郊外。
少し小高くなった丘の上に、目的の建物はあります。
欧風建築の大きな建物。
まるでファンタジーに出てくる、お姫様の住んでいる王宮のようです。
その王宮めいた建物に隣接するように連なる、数多くの建造物。
丘そのものが、一つの街として形成されているように見えました。
天空宮市の郊外に、もう一つ小規模な街があるような、そんな印象。
あの街丸々一つが、学園都市だと言ったら信じてもらえるでしょうか。
下手な田舎町よりも、ずっと大きな建築群だというのに。
「ほら、見えてきたよ」
運転しながら下平さんが言います。
「あれが君が今日から通う、天空宮学園だ」
初等部から大学まである、エスカレーター方式でもある学園。
とてつもなく広い全ての校舎は、広大な学園都市内の路面電車で行き来が可能。
魔法学、一般教養、体術、剣術、射撃、戦略、調理、法学、演劇、工学、医学など、およそ学問と呼べるものは全てここで学ぶ事ができ、科目は選択式なのだそうです。
在籍しているのは人間、エルフ、ドワーフ、獣人など様々で、国籍、種族問わず。
卒業者は各方面のエリートとして職業に携わっているらしいです。
自由な校風に似合わず、レベルの高い学校みたいです。
生まれてこの方、教育らしい教育なんて受けた事のない私に、こんな学園での生活が務まるのかどうか…。
そんな私の不安を知ってか知らずか。
「さ、ついたよ」
下平さんは天空宮学園事務局の前に、車を横付けしました。
「話はもう理事長につけてあるから。君はこの書類を持って行くだけでいい」
「……」
とても、不安です。
緊張で頬が硬くなり、心臓は早鐘のように鳴り続けています。
とてつもなく広い全ての校舎は、広大な学園都市内の路面電車で行き来が可能。
魔法学、一般教養、体術、剣術、射撃、戦略、調理、法学、演劇、工学、医学など、およそ学問と呼べるものは全てここで学ぶ事ができ、科目は選択式なのだそうです。
在籍しているのは人間、エルフ、ドワーフ、獣人など様々で、国籍、種族問わず。
卒業者は各方面のエリートとして職業に携わっているらしいです。
自由な校風に似合わず、レベルの高い学校みたいです。
生まれてこの方、教育らしい教育なんて受けた事のない私に、こんな学園での生活が務まるのかどうか…。
そんな私の不安を知ってか知らずか。
「さ、ついたよ」
下平さんは天空宮学園事務局の前に、車を横付けしました。
「話はもう理事長につけてあるから。君はこの書類を持って行くだけでいい」
「……」
とても、不安です。
緊張で頬が硬くなり、心臓は早鐘のように鳴り続けています。
この作家の他の作品
表紙を見る
この宇宙のどこかにいるかもしれない
某宇宙人の
ちょっと真面目な
そっくりさんコメディ
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…