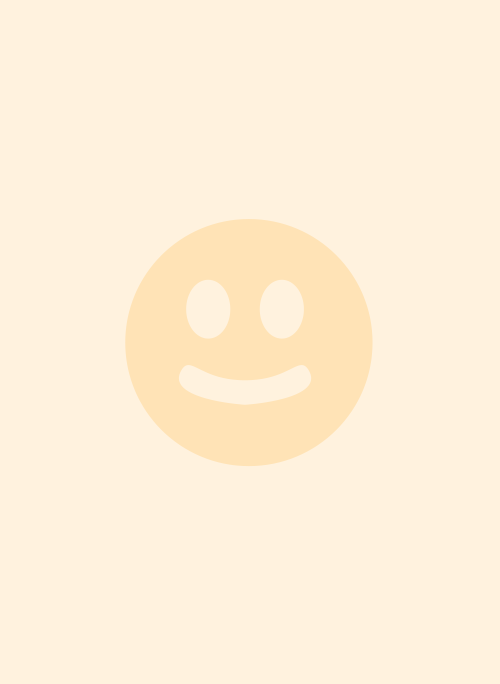姿形が違う存在というのは、どこか不安を煽るものです。
この存在は自分達にとって本当に友好的なのか。
害意を持っているのではないか。
自分に危害を及ぼすのではないか。
勝手に想像し、決め付け、自分から遠ざけるものです。
だって、みんな傷つきたくないから。
痛い思いをするのは嫌だから。
そんな理由で、私は幼い頃から虐げられ、疎まれ、孤立してきました。
仕方ありません。
私の背中には、どんな異種族にもない黒い翼があったから。
私は『悪魔』だから。
容姿こそ、人間と大差はありません。
だけどこの翼があるばかりに、私は仲間に入れてもらえず、随分寂しい思いをしたものです。
行くアテもなくて、留まる場所もなくて、巡り巡って辿り着いた、街を見渡せる高い崖。
孤立してしまった不安を何とか抑えたくて、一人歌なんて歌ってました。
寂しさを紛らわせたくて、小さな声で口ずさんでみる。
「Obwohl obwohl ein Flügel, den ich den Himmel leite, und zu treten, ein Flügel zu Freiheit steigt auf in diesen Hochhimmel, weder der Schwarze noch das Weiß hat Verbindungen(空翔ける翼、自由への翼 あの高い空へ舞い上がるのに 黒も白も関係なんてないのに)」
それは、私のかつていた世界に伝わる異世界語。
独学で覚えた、見様見真似のその言葉を使って奏でる、魔力を帯びた歌でした。
魔力を帯びた…といっても、周囲に影響を及ぼすほどのものではありません。
感情を込めて歌ううちに、知らずこもってしまった魔力。
寂しい、怖い、悲しい、一人は嫌…。
そんな気持ちが内から外へと向けられるうちに、言の葉に乗って流れ出てしまった魔力。
そんな歌を、毎日毎日、断崖の上から奏でました。
自分は孤立している。
自分は一人だ。
誰にも愛されていない。
そう思い込み、嘆きの歌を奏で、どれくらいの時間が過ぎたのでしょう。
「君が歌っていたのか」
ある日、私の立つ断崖に、一人の男性が現れます。
スーツ姿、サングラスをかけた、私よりもずっと年上の男性。
魔力も悪意も感じられません。
どうやら人間のようでした。
「筋はいいんだが、如何せん歌が良くない」
その人はサングラスを外し、優しく笑顔を浮かべました。
「今度はもっと幸せな歌を歌ってみないかい?」
あれから一年が過ぎました。
…ここは天空宮という不思議な街。
当たり前のように車がメインストリートを行き交い、雲を突き抜け宇宙まで届く軌道エレベーターが市街中心部に聳え立つ一方で、港の沖合いには『リヴァイアサン』と呼ばれる海竜が、山岳部には『天空険道』という魔物がひしめく8000メートル級の岩山が存在するという、ファンタジーとSFがごった煮になったような都市です。
歩道を歩く人々も、今時の流行のファッションに身を包んだ人間の青年もいれば、中世の騎士のような甲冑を装備した虎の獣人、耳の尖った金髪のエルフ美女、肩や肘の接合部に継ぎ目のある自動人形(オート・マタ)『メイドール』など様々。
初めてここを訪れる人達にとっては、この街は本当に空想世界の産物のようでしょう。
夢物語の舞台のような天空宮市。
そのスクランブルの真ん中を走る、魔法機関搭載の高級車のリアシートに、私は座っていました。
フルスモークのリアガラスから、幻想風景を眺めます。
中からは見えても、道行く人達に車内の私の姿は見えません。
移動の時、私はいつもこの車に乗せてもらいます。
私が普通に街中を歩くには、ちょっと有名人になりすぎてしまったもので…。
「あの…下平さん…」
私は高級車の運転をする、運転席の男性に声をかけました。
「んー?何だい?」
サングラスをかけた、気のよさそうな三十歳くらいの男性が、ルームミラー越しに私を見ました。
下平アルベルトさん。
一年前、私が一人歌を奏でていた崖…今では『断崖歌劇場』と呼ばれる場所ですが…そこにいた私に声をかけてきた、初めての男性。
この天空宮市にある、大手芸能プロダクションの若き社長さんです。
一年前のあの日…。
友達も身寄りもなく、孤立して、歌だけが心の支えだった私に、下平さんは声をかけてくれました。
―――
――――――
―――――――――
――――――――――――
「せっかく他人の心を動かせる歌が歌えるのに、どうしてそんなしみったれた歌ばかり歌うんだい?もっと癒されるような…笑顔になれるような歌を歌えば、みんなもっと喜んでくれるのに」
「……」
泣きべそをかいたまま、私はそのサングラスをかけた男性、下平さんを見つめます。
「…心を動かせる歌なんて…そんな…」
「ははぁん?」
下平さんがニッと笑いました。
「才能のある者にありがちな事だ。君は自分の歌にどれだけ他人を魅了する力があるのか、わかっていないんだな。その気になれば、この世界の全ての人間を虜にするほどの力があるっていうのに」
あまりに大袈裟な下平さんの物言いに、思わず顔を赤らめてしまいます。
それに。
「『みんな喜んでくれる』って…誰も私の歌なんて聴いてくれていません…」
俯き加減に、小さく溜息混じりに私は言います。
「んー?」
孤独で、孤立していて、本当に寂しい、悲しい。
そんな気持ちを吐露したつもりなのに、下平さんは笑みすら浮かべて、私の言葉を聞いていました。
その表情が、少し癪に障ります。
「何が可笑しいんですか?」
「いや…だってさ」
彼は崖の下…そこに広がる森の中を指差しました。
「よく見てご覧。あの木の陰…あそこの木の枝の上、それにあの岩陰にも…」
「…?」
言われるままに、私は目を凝らし。
「…!」
ハッと息を飲みます。
「君は孤立しているって言うけれども…だったら何であんな場所に隠れて、『彼ら』は崖の上の君を見つめているんだろうね?」
「……」
知らなかった…。
今まで、あんな場所に人がいるなんて気づきませんでした。
「彼らも僕と同じく、君の歌に魅了されたんじゃないのかな?」
――――――――――――
―――――――――
――――――
―――
そんな風にして私は下平さんに見い出され、今ここにいるのですが…。
「やっぱりいいですよ、下平さん…私、学校なんて…」
「まぁた…」
サングラスを指先でキュッと押し上げ、下平さんは溜息をつきました。
「いいかい?CDこそ販売していないものの、今や君はマジカルネットでのダウンロード件数450万、ヒットチャート軒並み1位獲得の歌姫なんだ。メディアへの露出は、今はほんの数枚の画像のみに過ぎないけれど、君の顔を知らない者なんてこの世の中に幾らもいないだろう。今にテレビ出演も引っ切り無しにオファーが来るようになる」
そう。
たった一年で私は知らぬ者のいないほどの存在となりました。
私は崖の上で歌っていた頃と同様に、ただ歌を奏でていただけ。
そりゃあ歌う曲は少し明るいものになって、下平さんのお陰で素敵な衣装も着させてもらえるようになったりはしましたが…それでも、やっている事は一年前と全く変わりません。
急激な周囲の変化に、私自身戸惑いを隠せないのです。
なのに、この上テレビ出演だなんて…。
私は嫌われ者で、黒い翼を持つ悪魔なのに…。