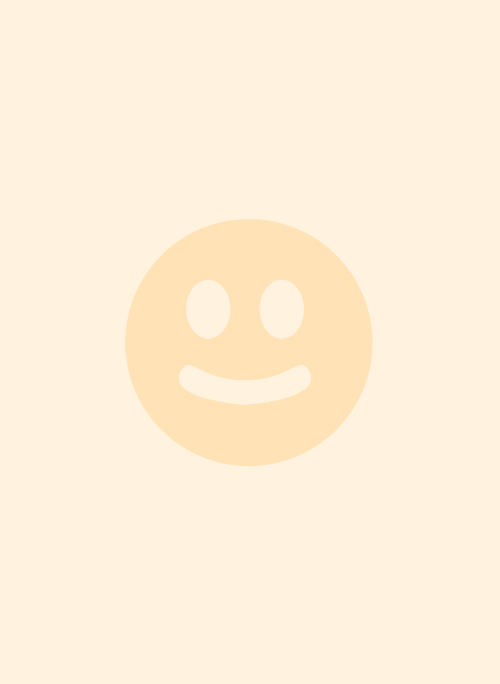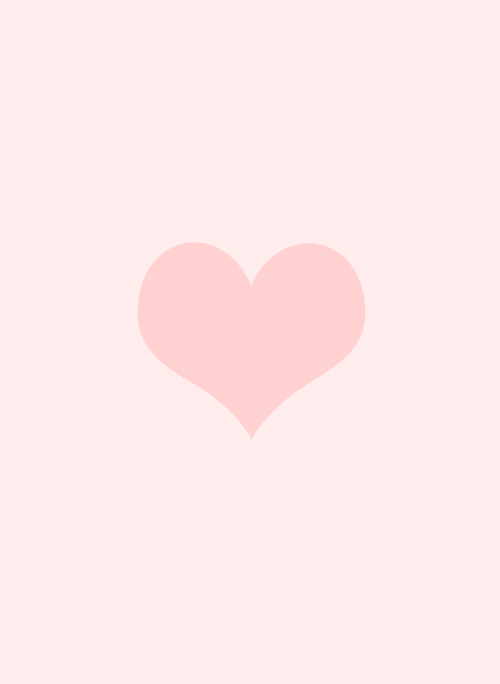「何かを聞いて欲しかったんじゃないの?」
「………は?」
「何かいいたいことあるんなら、相手と連絡つくうちにいっとかないと、後悔するから!」
あたしの、疾風へあてたこの言葉。
まぁ自分への言葉でもあった。
自分自身に言い聞かせることで、颯と話す勇気がでるはずだと思ったから。
「李衣…お前…」
「勘違いしないでね?心から疾風を許したわけじゃないから」
「はっ…李衣らしいな」
何か吹っ切れたような笑顔の疾風に、なんだか少し、心が和やかになった。
「俺…二股かけてたこと、美代に言ったんだ」
え……?
「李衣からフラレたことばっか考えてて、美代にこのまま俺が中途半端な気持ちで接したら、また李衣みたいにしちまうかもって…」
「……馬鹿だね…」
フッと笑うあたしに、疾風は困ったように眉を下げた。
「だから…李衣の気持ちも、美代の気持ちも、踏みにじってたことに気付けなかった」
不意に、疾風は天井を向いた。
「ははっ…馬鹿だよなぁ…ほんと。…成長してない。立派な大人だっていうのに、心は子供のまま…」
「美代さんは…疾風に対してなんていったの?」
「美代は…俺に何も言わなかった。ただ“彼女に謝りたい"それしか言わなかった」
何それ。
つらすぎるポジションじゃん…美代さん…
「ありえない…なんでそのとき“美代は悪くない"っていわなかったの?」
「…いえなかったんだよ…俺がいえる立場じゃないって…思ったんだ。だから…俺は何もいわずに美代の部屋からでた」
はぁ?!
「ちょっと待って。同居してたわけ??」
「あぁ…」
「疾風…どんだけ悪い男なの?美代さんの気持ち…踏みにじってまた踏んでんじゃん」
「え……」
「ったく…だから男は…」
「す…すいません」
「あたしに謝るくらいなら、はやく美代さんのとこ帰りなよ」
「え…李「はーやーくー…」
「わっわかったよ」
腰掛けていた、保健室のベットから立ち上がった疾風は、あたしに背中を向けた。
「李衣…」
「もう…なんなの?はやくいきなって」
「李衣…ごめん。あと、ありがとう。…俺は李衣を愛してたよ」
「あたしも、愛してた」
過去形になった愛の言葉に、寂しさはなかった。
「いってくる」
「いってらっしゃい」
ガラガラッピシャッ
シーンと静まり返った保健室は、何故だか寒気がした。
じわっと暖かいものが、目にたまる。
「ははっ…全く…なんだっていうの…?」
1人になったとたん、颯のぬくもりを求めちゃうなんて…
「い…いかなきゃ…ダメなの…に…ヒクッ」
こんな泣き顔じゃ、颯にあいにすらいけないよ…
「颯…」
フワッ
「え…」
久しぶりに、あの香水の香りが鼻をかすめた。
「李衣…」
「はっ颯…?」
背中から抱きしめられてて、顔もみえないし、背中から伝わる体温と、心拍数しかわからないけど…香水と、声が…颯がいると示してくれてる。
「なんで泣いてんだ?」
「そっれは…はっ颯が…」
「俺が…?」
涙はさっきよりも酷くなって、ますます喋りにくい。
「お…なの人と…」
「おな?なんのことだよ」
「しらばっ…くれないで…よぉ」
「はぁ?」
こんなときも冷たいんだなぁ…颯は。
「お前、さっき田中といたろ?」
「え…」
「俺、聞いてたんだよね。お前らの会話…アイツ、李衣の元カレだよな」
「う…ん…」
「アイツとなんかあったのか?」
「ちが…うから…」
「じゃぁなんだよ」
「だから…颯が…」
「俺?それともアイツ?」
「颯だってば!」
あたしは、思わず颯のほうを向いた。
「李衣…なんか不安なのか?」
「颯…?」
あたしがみた颯は、いつもの颯より弱々しく見えた。
「話し合おう。2人で…ゆっくりな」
……颯?やっぱり別れちゃうの?
………あたし達…
少し止んだ涙も、また溢れだす。
嫌だよ。あたし、思ってたよりも、颯のこと…
『愛してる』
結構バイトは順調。
古着屋って案外楽だし、楽しいな。
「いらっしゃいませ」
俺は、なるべく愛想よく挨拶をする。
「中谷くんっ?!もうちょっと笑顔振り撒きなさいよ。イケメンな顔を売りなさいよ!」
この横暴な態度の、黒髪ロングはここのオーナー。
名前は、マリアンヌ・アレクサンドリア。
すっげぇ名前だけど、一応日本語喋れるハーフ。
通称:マリアさま
「す…すいません…マリアさん…」
「もうっ!マリアさまでしょーがっ!!」
……………めんどくせ…
「マリアさま…笑顔、これでどうですか?」
にっこりと王子スマイルを、オーナーにぶつけた。
「いやんっ♪中谷くんったら///」
頬を染める姿がなんともいえねぇよ…(汗)
「ねぇえ?外の服、ちょっとたたんできてくれない?今すっごい荒れてるから」
「はーい」
俺は外に出て、洋服をたたみはじめた。
「中谷くーん?コレ、ここに置くから設置手伝って〜」
小走りの足音が聞こえたと思ったら、オーナー(マリアさま)が来た。
「あっはい」
俺は物を受け取り、外のどの位置に置くとか、指示を受けながら設置していった。
「流石ねぇ〜筋がいいわ」
にこりと笑顔を向けたオーナーに、
「ありがとうございます」
俺も笑顔を向けた。
……そんなとこを、李衣に見られてたなんて、俺はこれっぽっちも考えてなかった。
李衣にだんだんと、不安を抱かせていたなんて…
《ピンポーン》
その日夜、俺の家のチャイムが鳴った。
「はい、どちら様って…」
「こんにちわーっ」
「よーっす、は・や・て様♪」
「小宮間に、琥桃かよ」
「なんですかーその残念がりかたー!!」
「そうだぞー?颯、俺が折角来てやったのに」
どんだけ自分中心なんだよ。
まず最初言ってたように、今、夜だから。
夜中だから。
「ちょっとー…話しいいです?」
少し顔付きの変わった小宮間に、俺は無言で頷いた。
この作家の他の作品
表紙を見る
゚*゙:¨*;.・゚*゙:¨*;.゚*゙:¨*
昔、心に傷を負った少女
桜木 昴が中心となり巻き起こす
壮絶なラブコメディー♪
彼女のハートを射止めるのは…?
次々にでてくる男達から
昴は誰を選ぶのか…?
゚*゙:¨*;.・*゙:¨*;.・゚*゙:¨*
2010年4月12日‐START‐
2011年2月14日‐END‐
(HPで2009年12月31日から書きはじめていたものです)
2100000pv突破!!
本当に有り難いです!!
これからも自分の作品を
よろしくお願いします<(__)>
ジャンル別ランキング最高17位でした!(2011年)
再びジャンル別に入りました!
最高20位(2012年12月13日〜23日現在)
2月25日に再びランクインしました。
3月26日に再びランクインしました。
現在2015年2月15日コメディジャンル
ランクイン中です。
ありがとうございます!!
皆様の励ましや
応援のおかげです…(泣)
※《現在episode:12修正予定》
2015年2月16日更新 P.342まで終了。
あとがきP.460内容変更
-感想THANKS-
姫蜜柑様、LilaSnow様、ぴよぴよマーチ様、桃也様
ーレビューTHANKSー
桃也様、綾瑠愛様
本当に本当にありがとうございました♪
『天男2nd』もよろしくお願いします(只今更新停止中)
では、どうぞ
いってらっしゃいませ↓
表紙を見る
魔界は…存在している――…
そこにはspellが使える魔人が住んでいる
『spell』…魔法、魔力――…
しかし、地球上で自然と身につく
人間達が居るという
そんな人間達は強制的に
『SPELLSCHOOL』に連れていかれる
そこで魔法を磨き、魔力を付け
世のため人のため…犬となり働く
そんなSPELLSCHOOLに連れていかれた
平凡現、路地裏暮らしの男が
成長していく物語
出てくる地名は
存在しないものにしています!
地球ではありますが(笑)
流血あります…
結構なバトルものかと…
シリアスな場面もありますが
笑えるような作品にします!!
意見や質問等待ってます!!
20000pv突破!!
ありがたやありがたや<(__)>
2011.2.26非公開スタート
2011.3.9公開
暇なとき読んでみて下さい♪
英語とか化学(科学)的な
難しい言葉が多いですが
なるべく解説とか入れてます!!
↓read?
表紙を見る
【短編】
『てめシリ』夕暮編Part2!!
***
『なぁ、炬哲。めっちゃ好っきゃで?』
…可愛い炬哲に、溺れてもーてます。
***
Start/2012.8月9日
End/2012.8月10日
第一弾→夕暮編1→第二弾→夕暮編2
の順でどうぞ!!
夕暮編1と第二弾は飛ばしても大丈夫です!!
ただ、第一弾を読んだほうがわかりやすいです。
いつか単品で読めるよう修正します(泣)
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…