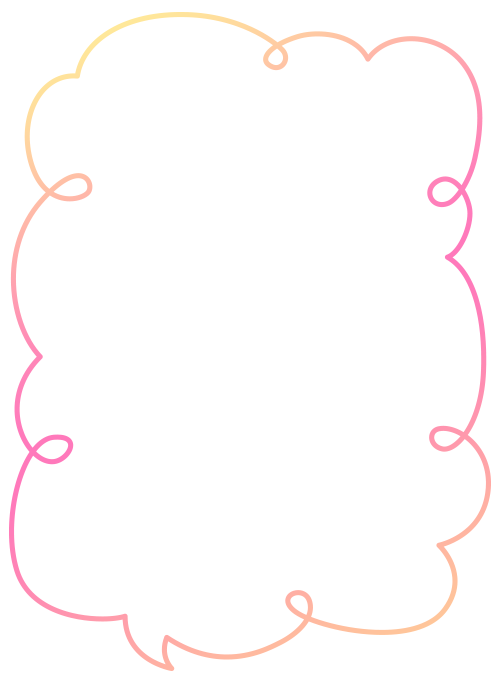どうしてそこにいるの?
どうして傘をささないの?
どうして…?
聞きたいことはたくさんあった。
だけど…
聞くだけ聞いて、その後どうするんだろう、と躊躇われる。
…何も出来なかったら?
余計に涙の傷を増やすだけにも思える。
そう考えるから身動きが取れなくなるのだ。
それでも俺はゆっくりと歩みを進めた。
1年前に出来なかったことを果たすために。
『何も出来ないかもしれない。』
でも
『何か出来るかもしれない』
今踏み出せば、もしかしたら…。
俺と彼女の距離はあと7メートル。
彼女は俺には気付かない。
どうして傘をささないの?
どうして…?
聞きたいことはたくさんあった。
だけど…
聞くだけ聞いて、その後どうするんだろう、と躊躇われる。
…何も出来なかったら?
余計に涙の傷を増やすだけにも思える。
そう考えるから身動きが取れなくなるのだ。
それでも俺はゆっくりと歩みを進めた。
1年前に出来なかったことを果たすために。
『何も出来ないかもしれない。』
でも
『何か出来るかもしれない』
今踏み出せば、もしかしたら…。
俺と彼女の距離はあと7メートル。
彼女は俺には気付かない。
「ここに…おいでよ。」
「え…?」
俺は彼女に傘を差し出した。
…ようやく絞り出せた言葉だった。
俺の目の前には目を丸くした彼女がいた。
「濡れる…だろ?ってもう濡れてるけど。」
我ながら…もう少し考えてから喋れよ、と思う。
つーかここに来いって…相合傘?
しかも相手はあの『雨音紗衣』
緊張よりも何よりも、自分の計画性のなさに死にたくなる。
「…もう少し…濡れていたいの。」
彼女の視線はまた遠くへと移る。
一度だけ右手で涙を拭って、俺に背を向けた。
「じゃっ…じゃあ…。」
「…?」
彼女はゆっくりと振り返る。
「傘、置いておくから。
帰りはそれ使って。」
「え…?」
「あんま意味ないかもしれねぇけど…。
それでもこの雨の中傘をささずに帰るのは辛いと思うからさ。」
「でもっ…。」
俺は彼女の言葉を遮って傘を木に立て掛け、その場を後にした。
…制服に雨が浸みる。
俺は下駄箱の上に投げたカバンを無理矢理掴んで、そのまま走った。
じわじわと靴下が濡れる、あの嫌な感覚が広がっていくのを感じながら。
我ながら…もう少し考えてから喋れよ、と思う。
つーかここに来いって…相合傘?
しかも相手はあの『雨音紗衣』
緊張よりも何よりも、自分の計画性のなさに死にたくなる。
「…もう少し…濡れていたいの。」
彼女の視線はまた遠くへと移る。
一度だけ右手で涙を拭って、俺に背を向けた。
「じゃっ…じゃあ…。」
「…?」
彼女はゆっくりと振り返る。
「傘、置いておくから。
帰りはそれ使って。」
「え…?」
「あんま意味ないかもしれねぇけど…。
それでもこの雨の中傘をささずに帰るのは辛いと思うからさ。」
「でもっ…。」
俺は彼女の言葉を遮って傘を木に立て掛け、その場を後にした。
…制服に雨が浸みる。
俺は下駄箱の上に投げたカバンを無理矢理掴んで、そのまま走った。
じわじわと靴下が濡れる、あの嫌な感覚が広がっていくのを感じながら。
* * *
…案の定と言うべきか。
とにかく俺は風邪をひいた。
熱はない…と信じたい。
でも、傘を貸した次の日に俺が休めば、それはそれで気に病むんじゃないかとか、無駄なことをいちいち考えてた。
だから学校に来たとも言える。
「…なんか顔赤い。」
「マジ?そんなに分かる?」
「熱あんの?」
「ないと信じてる。」
「信じるな。今すぐ保健室行け。」
「…行きたくな…。」
「いいから行け。」
…こういう時のユウは少し怖い。
でもその迫力に気圧されて、俺は渋々席を離れた。
朝から保健室行くとか、俺…何しに来たのか分かんねぇ…。
…つーか頭痛ぇ。
そう思って頭を抱えた。
「…っと…やべ。フラフラするんだけど…。」
廊下の壁に手をつく。
この冷たさが心地いいなんて、相当身体が熱い証拠だ。
「霧夕くん。」
不意に後ろから声を掛けられた。
…声で分かる。
彼女から声を掛けてきたのは、生まれて初めてだ。
…案の定と言うべきか。
とにかく俺は風邪をひいた。
熱はない…と信じたい。
でも、傘を貸した次の日に俺が休めば、それはそれで気に病むんじゃないかとか、無駄なことをいちいち考えてた。
だから学校に来たとも言える。
「…なんか顔赤い。」
「マジ?そんなに分かる?」
「熱あんの?」
「ないと信じてる。」
「信じるな。今すぐ保健室行け。」
「…行きたくな…。」
「いいから行け。」
…こういう時のユウは少し怖い。
でもその迫力に気圧されて、俺は渋々席を離れた。
朝から保健室行くとか、俺…何しに来たのか分かんねぇ…。
…つーか頭痛ぇ。
そう思って頭を抱えた。
「…っと…やべ。フラフラするんだけど…。」
廊下の壁に手をつく。
この冷たさが心地いいなんて、相当身体が熱い証拠だ。
「霧夕くん。」
不意に後ろから声を掛けられた。
…声で分かる。
彼女から声を掛けてきたのは、生まれて初めてだ。
「あ…雨音…。」
「体調…悪いの?」
「んなことない。だいじょーぶだいじょーぶ。」
「…顔赤いし…フラフラしてる。
保健室行くの?」
「少し休みに行くだけだから。」
「…私も行く。」
「え?」
…今のは幻聴?
だっておかしいだろ?
あの雨音が…保健室の付き添い?
「昨日傘を貸してくれたお礼に。」
そう言った彼女の表情は確かに無表情だった。
だけどその奥には…
あ、もちろん俺の思い違いの可能性大だけれど、少しだけ心配してくれているような気持があるようにも感じた。
…彼女は決して『冷たく』なんかない。
ただ…見せていないだけ。その優しさを、想いを。
もしかしたら、見ようとしていないだけなのかもしれない。
フラフラする俺の右腕が不意に掴まれる。
「え…?」
「危ないから。」
保健室まで、俺たちにそれ以上の会話はなかった。
「体調…悪いの?」
「んなことない。だいじょーぶだいじょーぶ。」
「…顔赤いし…フラフラしてる。
保健室行くの?」
「少し休みに行くだけだから。」
「…私も行く。」
「え?」
…今のは幻聴?
だっておかしいだろ?
あの雨音が…保健室の付き添い?
「昨日傘を貸してくれたお礼に。」
そう言った彼女の表情は確かに無表情だった。
だけどその奥には…
あ、もちろん俺の思い違いの可能性大だけれど、少しだけ心配してくれているような気持があるようにも感じた。
…彼女は決して『冷たく』なんかない。
ただ…見せていないだけ。その優しさを、想いを。
もしかしたら、見ようとしていないだけなのかもしれない。
フラフラする俺の右腕が不意に掴まれる。
「え…?」
「危ないから。」
保健室まで、俺たちにそれ以上の会話はなかった。
* * *
「…センセーいな…。」
「私、探してくるよ。」
「あーいいよ。そんなことまでしてくれなくて。雨音は授業に戻んないと。」
「でも…私のせいだから…。」
淡々と紡がれる言葉。
でもその端々に、彼女の想いが見え隠れしている。
…彼女の瞳の奥には…優しさが溢れている。
「違うよ。雨音のせいじゃない。」
「だって昨日…。」
「俺が勝手に気になって、俺が勝手に雨音に傘を押しつけただけだから。
で勝手に風邪ひいた。そんだけ。」
一気に言い過ぎた。
…雨音が少しきょとんとした顔で俺を見つめている。
「そんなに『勝手』なの?霧夕くんって。」
「え?」
反応するのはそこか?とか色々思ったけど、そんなことよりも少し上目遣い(本人は絶対に無自覚)で見られたことに、異常なくらい心臓がドキドキいってる。
…鎮まれよ、心臓。頼むから。
「霧夕くん?」
「あ…ホント、大丈夫だから。雨音は授業行って。」
「私はっ……霧夕くんっ!!」
ぐらっと視界が歪んだのを最後に、俺の意識は途切れた。
「…センセーいな…。」
「私、探してくるよ。」
「あーいいよ。そんなことまでしてくれなくて。雨音は授業に戻んないと。」
「でも…私のせいだから…。」
淡々と紡がれる言葉。
でもその端々に、彼女の想いが見え隠れしている。
…彼女の瞳の奥には…優しさが溢れている。
「違うよ。雨音のせいじゃない。」
「だって昨日…。」
「俺が勝手に気になって、俺が勝手に雨音に傘を押しつけただけだから。
で勝手に風邪ひいた。そんだけ。」
一気に言い過ぎた。
…雨音が少しきょとんとした顔で俺を見つめている。
「そんなに『勝手』なの?霧夕くんって。」
「え?」
反応するのはそこか?とか色々思ったけど、そんなことよりも少し上目遣い(本人は絶対に無自覚)で見られたことに、異常なくらい心臓がドキドキいってる。
…鎮まれよ、心臓。頼むから。
「霧夕くん?」
「あ…ホント、大丈夫だから。雨音は授業行って。」
「私はっ……霧夕くんっ!!」
ぐらっと視界が歪んだのを最後に、俺の意識は途切れた。
* * *
雨の…音…?
「んっ…。」
ぼーっとする頭。
もやもやとした視界。
頭を押さえながら、目に飛び込んでくる光が眩しくて、右目だけを閉じた。
「頭…痛いの?」
「あ…っ…雨音…?」
その声に反応して、俺は両目を開けた。今度はしっかりと。
目の前にいたのは紛れもなく…
「雨音…なんで…。」
「目の前で倒れたから。放っておけなくて。」
「だってもう…って今何時?」
「9時半。丁度1時間くらい寝てたよ。」
「1時間も?」
「顔、やっぱり赤いみたい。
もう少ししたら保健の先生、戻ってくるみたいだから。
もうちょっと休んでた方がいいと思う。
…私、そろそろ戻るね?」
「あ…うん…。」
…なんだか…目が潤んでる?
そう思う間もなく、彼女は俺に背を向け、保健室を後にした。
そして俺はゆっくりと身体を横たえた。
…まさか…1時間ずっとそばにいてくれた…なんてことはないよ…な。
見に来ただけ、だろ。多分。
それに気になるのは…
もしかして…泣いていたんだろうかってことだった。
雨の…音…?
「んっ…。」
ぼーっとする頭。
もやもやとした視界。
頭を押さえながら、目に飛び込んでくる光が眩しくて、右目だけを閉じた。
「頭…痛いの?」
「あ…っ…雨音…?」
その声に反応して、俺は両目を開けた。今度はしっかりと。
目の前にいたのは紛れもなく…
「雨音…なんで…。」
「目の前で倒れたから。放っておけなくて。」
「だってもう…って今何時?」
「9時半。丁度1時間くらい寝てたよ。」
「1時間も?」
「顔、やっぱり赤いみたい。
もう少ししたら保健の先生、戻ってくるみたいだから。
もうちょっと休んでた方がいいと思う。
…私、そろそろ戻るね?」
「あ…うん…。」
…なんだか…目が潤んでる?
そう思う間もなく、彼女は俺に背を向け、保健室を後にした。
そして俺はゆっくりと身体を横たえた。
…まさか…1時間ずっとそばにいてくれた…なんてことはないよ…な。
見に来ただけ、だろ。多分。
それに気になるのは…
もしかして…泣いていたんだろうかってことだった。
無理矢理、目を逸らされた。
そんな気がした。
昨日の涙の理由を、俺は知らない。
今の涙の理由を、俺は想像すら出来ない。
「熱出してる場合じゃねぇって…俺…。」
呟きは虚しく消える。
俺は確実に調子に乗っているんだ。
雨音と話せた、たったそれだけのことで。
もっと手を伸ばしてみたくなる。
もっと知りたい。
涙の理由も、笑わない理由も。
たとえ聞くことしか出来なくても、それでも。
瞳の奥の哀しさに、優しさに気付いたのは
今は俺だけだと思うから。
「…『単純』ってユウに笑われそ…。」
そんな気がした。
昨日の涙の理由を、俺は知らない。
今の涙の理由を、俺は想像すら出来ない。
「熱出してる場合じゃねぇって…俺…。」
呟きは虚しく消える。
俺は確実に調子に乗っているんだ。
雨音と話せた、たったそれだけのことで。
もっと手を伸ばしてみたくなる。
もっと知りたい。
涙の理由も、笑わない理由も。
たとえ聞くことしか出来なくても、それでも。
瞳の奥の哀しさに、優しさに気付いたのは
今は俺だけだと思うから。
「…『単純』ってユウに笑われそ…。」
*紗衣side*
…不審に思われっぱなしなんだと思う。
だって私…泣いてばかりだ。
「…あんな避け方…っ…。」
霧夕くんは傷付いたかもしれない。
そして気付いていたはずだ。
昨日の涙にも、今日の涙にも。
その理由を聞かないのは、きっと優しいからなんだろう。
その優しさも、あの寝起きの仕草も
似てる。苦しいくらいに。
彼を思い出させる。鮮明に。
忘れたことなんてないけれど
記憶を余計に呼び覚ます。
赤の他人のはずなのに、似ているってだけでこんなに…
「涙…止まんない…なんて…。」
どれだけ泣けば済むんだろう。
他の日なら平気なのに。
どうしてもダメだ。
雨の日だけは、どうしても。
…不審に思われっぱなしなんだと思う。
だって私…泣いてばかりだ。
「…あんな避け方…っ…。」
霧夕くんは傷付いたかもしれない。
そして気付いていたはずだ。
昨日の涙にも、今日の涙にも。
その理由を聞かないのは、きっと優しいからなんだろう。
その優しさも、あの寝起きの仕草も
似てる。苦しいくらいに。
彼を思い出させる。鮮明に。
忘れたことなんてないけれど
記憶を余計に呼び覚ます。
赤の他人のはずなのに、似ているってだけでこんなに…
「涙…止まんない…なんて…。」
どれだけ泣けば済むんだろう。
他の日なら平気なのに。
どうしてもダメだ。
雨の日だけは、どうしても。
この作家の他の作品
表紙を見る
「ほ…本物…!?」
「あ、はい。声優、やってます。」
ハマっているアプリのアイドル声優が集うライブを見て、【推し】ではないユニットのリーダーに目を奪われてしまった里依(りい)
そんなことは生まれて初めてで、ライブの余韻が抜けないままぼんやりといつも通り、こっそりとしたオタクとして生活していたはずなのに…
「似てる人だな…とは、その…確かに思いました…けど。」
「さすがに本人だとは思わないですよね。」
本物に出会い、イベントでもないのに会話をしてしまうことがあるなんて…!
声優さんの邪魔をしてはいけない。
キャラクターと声優さんを同一視してもいけない。
ましてや、個人的な感情としての『好き』なんて、抱いてはいけない。
それは、ファンとしてあるまじき思いで、行動。
【ファンは恋をしないのです】
奥手アラサーオタク×二次元アイドルの中の人
「でも声優は、恋をしますよ?」
表紙を見る
シャッターを切る音が
俺を見る眼差しが
ひとつひとつの仕草が
私に向けられた笑顔が
そのどれもが大切だと思えたとき
それはきっと、特別な想いなのだと
気付くことになる
想いは混ざって溶けて
消えはしないけれど
成就するだけでもなくて
変わっていくもの
止めていくもの
変えていくもの
リナリア
そういえばあの日も、
ゆらゆら揺れる小さな花が
逞しく咲いていたっけ。
執筆開始
2018.5.21
表紙を見る
落ち着いた雰囲気
(何も考えていないだけ)
清楚系かつ綺麗系
(並みの社会人になりたくて気を遣っただけ)
捌けない仕事はない
(スキルアップできるように努力してるだけ)
似合わないのを知っているけど
ビターチョコは苦手なの。
「だから、お前は男の趣味が悪いんだよ。」
苦々しいくらい正論ばかりぶつけてくる同期、相島
「…私だって、ほんとのことが言えたらなって思ってるもん。」
働く女性たちの代表、紗弥
見かけばっかり大人っぽくても
ビターを少しも好きになれないの。
ビターチョコをかじったら
少しは大人になれるのかな?
ビターチョコをかじったら
素敵な恋でも落ちてくるの?
執筆開始
2017.3.1
2017.4.1
完結しました!
(ていうかこの日だけで仕上げました)
2018.2.13
オススメ作品に掲載されました。
ありがとうございます!
2018.2.18
どんなチョコが好き?
少し遅めのバレンタインエピソード
追加しました!
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…