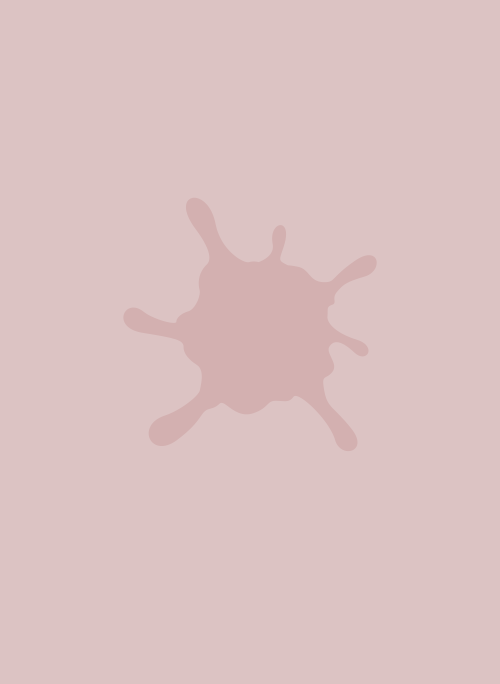入ってすぐに、異常に気付いた。
…廃墟、だった。街の入り口なのに。
ボロボロの建物が立ち並び、人気が全く無い。
「えっ…えっ?」
辺りをキョロキョロ見回しても、誰もいない。
何故っ!?
もしかして場所を間違えた?
けれどここには父に案内されたし、看板にも街の名前があった。
…と言うことは、間違いは無い。
父はここで、オレの手続きを済ませたと言っていたし…。
…とりあえず、歩いてみよう。
…廃墟、だった。街の入り口なのに。
ボロボロの建物が立ち並び、人気が全く無い。
「えっ…えっ?」
辺りをキョロキョロ見回しても、誰もいない。
何故っ!?
もしかして場所を間違えた?
けれどここには父に案内されたし、看板にも街の名前があった。
…と言うことは、間違いは無い。
父はここで、オレの手続きを済ませたと言っていたし…。
…とりあえず、歩いてみよう。
真っ直ぐに歩くと、ふと違和感を感じた。
…何だろう? 肌にイヤものを感じる…。
けれど誰かには会わないと…。
オレは早足になった。
そして廃墟を抜け、森の中へ…ってココ、街中だよな?
不思議に思いながらも歩き続ける。
だって今のオレにはそうするしかないから。
―人の声が聞こえてきた。
あれ? 奥の方から人の声?
ちょっとおかしく思いながらも歩いて行くと、洞窟の前に来た。
耳をすませると、ここから人の声が聞こえてくる。
オレは中に入った。
…何だろう? 肌にイヤものを感じる…。
けれど誰かには会わないと…。
オレは早足になった。
そして廃墟を抜け、森の中へ…ってココ、街中だよな?
不思議に思いながらも歩き続ける。
だって今のオレにはそうするしかないから。
―人の声が聞こえてきた。
あれ? 奥の方から人の声?
ちょっとおかしく思いながらも歩いて行くと、洞窟の前に来た。
耳をすませると、ここから人の声が聞こえてくる。
オレは中に入った。
中は豆電球が光を放っていて、何とか歩ける。
けれど人一人通るギリギリの幅だ。
それでも何とか歩き続ける。
途中、坂を上ったり下ったりしたけれど、一本道なのはありがたい。
汗をかき始めた頃、鉄の扉の前に来た。
そこには『ココが魔破街』と、扉に彫られていた。
…やっと到着、か?
オレはため息をつき、取っ手に手をかけ、押した。
ぎぎぎっ…!
嫌な音をさせながら、扉は何とか開いた。
光に眼を細めながら、オレはやっと魔破町に来た。
だけど…。
けれど人一人通るギリギリの幅だ。
それでも何とか歩き続ける。
途中、坂を上ったり下ったりしたけれど、一本道なのはありがたい。
汗をかき始めた頃、鉄の扉の前に来た。
そこには『ココが魔破街』と、扉に彫られていた。
…やっと到着、か?
オレはため息をつき、取っ手に手をかけ、押した。
ぎぎぎっ…!
嫌な音をさせながら、扉は何とか開いた。
光に眼を細めながら、オレはやっと魔破町に来た。
だけど…。
ごとっ…
足元に何か落ちてきた。
「? …~~~っ!」
声にならない絶叫が、ノドから溢れ出た。
バンッ!
思いっきり鉄の扉に背を付ける。
何故なら…落ちてきたのは、男のクビ。歳は50はいっているような男のクビだった。
だらしなく舌をだし、クビと眼から血を溢れ出している男は、死んで間もないだろう。
…まだ目玉が動いていたから。
「ったく…」
その時向こうから、女の子が来た。
「チカンなんてサイテーね」
足元に何か落ちてきた。
「? …~~~っ!」
声にならない絶叫が、ノドから溢れ出た。
バンッ!
思いっきり鉄の扉に背を付ける。
何故なら…落ちてきたのは、男のクビ。歳は50はいっているような男のクビだった。
だらしなく舌をだし、クビと眼から血を溢れ出している男は、死んで間もないだろう。
…まだ目玉が動いていたから。
「ったく…」
その時向こうから、女の子が来た。
「チカンなんてサイテーね」
片手に血塗れの斧を持ち、自身も血に塗れたセーラー服を着た女の子は、オレを見て、ポカンとした。
「…アラ? 珍しいわね。お客様?」
「いっいえ、今日からここに住むことになったサマナと言います。ムメイさんって方はご存知ですか? 学校に行けば会えるって聞いたんですけど…」
「ムメイ…先生のこと? アラ、それじゃあアナタが転入生?」
彼女は明るく笑って、斧を投げ捨てた。
そしてオレに駆け寄ってきた。
「ようこそ! 魔破街へ。あたしはサラ。アナタとは明日からクラスメイトよ」
「そっそう」
「ムメイ先生から事情は聞いているわ。アナタ…」
彼女は花の様な笑みを浮かべながら、とんでもない一言を言った。
「お父様に売られたのね」
「…アラ? 珍しいわね。お客様?」
「いっいえ、今日からここに住むことになったサマナと言います。ムメイさんって方はご存知ですか? 学校に行けば会えるって聞いたんですけど…」
「ムメイ…先生のこと? アラ、それじゃあアナタが転入生?」
彼女は明るく笑って、斧を投げ捨てた。
そしてオレに駆け寄ってきた。
「ようこそ! 魔破街へ。あたしはサラ。アナタとは明日からクラスメイトよ」
「そっそう」
「ムメイ先生から事情は聞いているわ。アナタ…」
彼女は花の様な笑みを浮かべながら、とんでもない一言を言った。
「お父様に売られたのね」
「………は?」
オレが、父に、売られた?
「まあそんなこと、どーでも良いか。来て、学校へ案内するわ」
そう言ってオレの手を握って歩き出す。
柔らかくあたたかい手だけど…血まみれだ。
「あっあの…」
「なぁに?」
「この人のこと…警察に言った方が…」
先に進むと、男の体がバラバラになって道に転がっていた。
「ああ、後で処理班の人が処理してくれるから大丈夫よ」
「いっいや、そうじゃなくて…キミのことなんだけど」
オレが、父に、売られた?
「まあそんなこと、どーでも良いか。来て、学校へ案内するわ」
そう言ってオレの手を握って歩き出す。
柔らかくあたたかい手だけど…血まみれだ。
「あっあの…」
「なぁに?」
「この人のこと…警察に言った方が…」
先に進むと、男の体がバラバラになって道に転がっていた。
「ああ、後で処理班の人が処理してくれるから大丈夫よ」
「いっいや、そうじゃなくて…キミのことなんだけど」
「あたし?」
サラはきょとんとした。
…こんなに可愛いのに。
可愛いと言うよりは、美人だ。整った顔立ちに、リンとした声がとても合っている。
「アラ、いけない!」
彼女はハッと気付いたようだった。
「あたしったら、あなたを案内するのにこんな血まみれで!」
って、何か違う!
しかしサラは自分の体を見下ろし、しゅん…と落ち込む。
「初対面からこんな汚い格好をさらしてしまうなんて…」
サラはきょとんとした。
…こんなに可愛いのに。
可愛いと言うよりは、美人だ。整った顔立ちに、リンとした声がとても合っている。
「アラ、いけない!」
彼女はハッと気付いたようだった。
「あたしったら、あなたを案内するのにこんな血まみれで!」
って、何か違う!
しかしサラは自分の体を見下ろし、しゅん…と落ち込む。
「初対面からこんな汚い格好をさらしてしまうなんて…」
「いっいや、その格好は別にいいんだけど…」
ホントはよくないけど!
「あの男の人のこと…警察に言わなくて良いのかなって」
「ケーサツ? ケーサツってなぁに?」
「えっ?」
…彼女はとぼけて言っているワケじゃない。
本当に警察という言葉も意味も知らない。
純粋な困惑の表情が、それを物語っている。
「警察って、ホラ。悪いことや人を傷付けた時に、その罪と罰を取り締まる職業のことで…」
「罪? 罰? …ああ、本で読んだことがあるわ」
それは『罪と罰』!
しかしサラは首を傾げる。
ホントはよくないけど!
「あの男の人のこと…警察に言わなくて良いのかなって」
「ケーサツ? ケーサツってなぁに?」
「えっ?」
…彼女はとぼけて言っているワケじゃない。
本当に警察という言葉も意味も知らない。
純粋な困惑の表情が、それを物語っている。
「警察って、ホラ。悪いことや人を傷付けた時に、その罪と罰を取り締まる職業のことで…」
「罪? 罰? …ああ、本で読んだことがあるわ」
それは『罪と罰』!
しかしサラは首を傾げる。
「表の世では、そういう職業の人がいるのね」
「『表の世』?」
「そうよ。ここにはケーサツという職業の人はいないわ。代わりにいるのは処理班」
「処理班?」
その言葉はあまり聞かない。
「そう。さっきの死体を処理してくれる人達のことを言うの。まあ職業ね。死体を処理した後、死亡届けのこととかもしてくれるから」
「キミは…」
オレは勇気と声を振り絞った。
「裁かれないの?」
「裁く? …何を?」
…そこでオレはようやく、この街の異常さに気付いた。
そう、ここはオレが住んでいた世の中の常識が通用しない。
恐るべき、罪と罰が無い世界だったのだ。
「『表の世』?」
「そうよ。ここにはケーサツという職業の人はいないわ。代わりにいるのは処理班」
「処理班?」
その言葉はあまり聞かない。
「そう。さっきの死体を処理してくれる人達のことを言うの。まあ職業ね。死体を処理した後、死亡届けのこととかもしてくれるから」
「キミは…」
オレは勇気と声を振り絞った。
「裁かれないの?」
「裁く? …何を?」
…そこでオレはようやく、この街の異常さに気付いた。
そう、ここはオレが住んでいた世の中の常識が通用しない。
恐るべき、罪と罰が無い世界だったのだ。
この作家の他の作品
表紙を見る
【マカシリーズ】をはじめて、大分経ちます。
作品数も多く、登場人物も多くなりました。
なのでこの辺りで一度、キャラクター紹介をしたいと思います。
裏話もチラホラ書いています。
表紙を見る
わたしの通う高校には、一人の『魔女』がいる。
『魔女』は助けを求められると、必ず助けてくれる。
けれどその反面、『魔女』を否定する者には厳しいらしい。
でも彼女は何故、『魔女』になったのだろう?
表紙を見る
ある日、マカが教室へ入ると、そこには見知らぬ男子生徒が1人いた。
ところが周囲の生徒達はみんな、彼のことを知っている。
だがマカ自身は、彼のことなど何一つ知らない。
この違和感を確かめるべく、同じ学校に通う魔女・リリスと共に彼のことを探り始めるのだが…。
【マカシリーズ】になります。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…