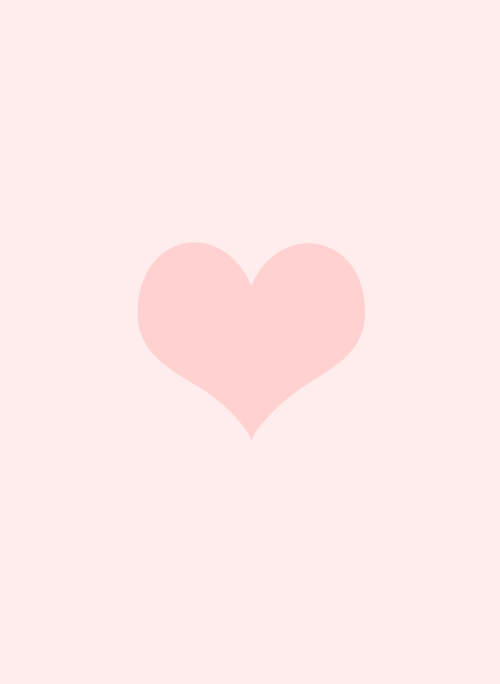山の端(は)まで茜色に染まり、風は冷たく吹き下ろす。
庭をてんてんと舞う鵯に餌を撒く柚木崎 継虎(ゆきざき つぐとら)の髪が揺れた。
まざまざと感じる秋の色、それは肌にも心にも染み渡る。
既に水を与えられた桔梗は、その顔に雫をたっぷりと乗せていた。
籠の中の餌がなくなり、それに気付いた鵯もやがて一羽二羽と空へと旅立つ。
近くの枝に、遠くの空に、思い思いに飛び回る自由を見て、継虎の口元が微かに笑う。
あれから日が随分と経ってしまった、そうは思うものの時は止まらない。
それでもまだこの手に残るぬくもりと、耳を誘うあの声と、瞼の裏に焼きついた姿が、いつも心を握っていた。
「ここにいたか」
空で踊る鵯を眺め過ぎたか、その声が聞こえるまで人が来る気配に継虎は全く気付かなかった。
ゆっくりと振り返れば屋敷の中に兄、夢継(ゆめつぐ)が立っている。
「兄上、来るならば……」
「突然弟の顔を見たくなる時もあるさ。土産も持って来た、隣に来い」
悠然とした佇まいに、その色の白い手がゆっくりと継虎を呼ぶ。
柔らかに微笑む兄を見て、継虎も素直に応じて戻ろうとした。
「あ、継虎様! 探したんですよ、こんなところに……」
「すず、少し静かに話せ。兄上の前だ」
そのとき丁度頬をほんのり赤く染めた少女が屋敷内から現れた。
息を切らして言う彼女を継虎は眉を寄せ窘めるものの、夢継が朗らかに笑う。
「よい、よい。すずは元気なのが良いだろう」
「わわ……夢継様申し訳ありません。今円座をお持ちしますね!」
しかし継虎の言葉は何処へか消え、すずは勢いよく頭を下げ、廊下を戻ろうと素早く反転する。
その様(さま)にまた笑う兄を横目に、継虎の眉間は更に寄った。
「ここではなく席を設けろ、酒と一緒にだ」
ため息交じりで口にした言葉に、すずの肩がびくりと揺れる。
そろり、と振り返った顔はまるで子どもを窘める母親のよう。
「朝から酒はないだろう、弟よ。すず、ここで良いよ、庭が綺麗だ。それにお茶に変えておくれ。あと私が持って来た菓子を」
すずの内心を汲んだのか、苦笑いを浮かべながら夢継は言う。
それに対し口を開きかけた継虎より先にすずは「かしこまりました!」と向きを変えてから一礼し、足早にその場から消えてゆく。
言いかけた言葉は溜め息に代わり、澄んだ空に溶けていった。
それを見てまた笑う兄の顔が、朝日に照らされる。
屋敷へ上がろうと履物を脱いだところで、別の者が円座を持って来た。
庭を向いて座ると、先程の鵯に加え雀が数羽、枝で遊んでいるのが見えた。
「遠い目をするようになったな」
囀る小鳥を眺める継虎に、兄がぽつり零す。
首を動かせば兄も樹の上の小鳥を見ているようだった。
「すずが気にかけておったぞ。最近お前の様子が変だと」
ゆっくりと話すその姿をまた横目に、継虎は庭先へと顔を向ける。
「何かあったか」
窘めるわけでも怒るわけでも、ましてや愉しむ様子もない淡々とした兄の問いに、ふと夏が蘇る。
何もかも知らない国、そこで手にしたものはかけがえのない大きなぬくもり。
「言えぬなら、恋煩いかもしれぬな」
今度はくくくと喉を鳴らした兄に、どう言うべきかとも迷う。
「いや……煩ってなど」
ただあながち間違いでもなく、真実でもない。
「その様なこと……必要ないと」
あれを恋と言うには幼過ぎる。
あれを思い出と言うには近過ぎる。
空を流れる雲を見て、継虎は小さく息をつく。
「必要ないとはまた……すずは報われぬな」
独り言のように口にした兄には応えず、ただゆっくりと瞼を閉じた。
どれほど想えど、二度と手にすることはないそのぬくもり。
それは代わりのものなど通用せず、ひたすらに身を焦がすのみ。
何度も願ったその想いを、幾度も噛み締め、押し殺してきた。
「竹」
呼ばれた名に、瞼を押し上げる。
再び目にした空に鳶が一羽泳いでいた。
「言えぬなら、言わずとも良い。だが忘れないでおくれ。私はいつもお前を頼りにしているのだ。お前がいなければ、私はただの弱虫だ」
さよさよと流れる小川のような声に、継虎が「そんなことは」と返すも言葉の続きは手で遮られる。
「私もそうだが、いずれお前も家の為に為すべきときが来ようぞ」
ふっと力の抜けた笑顔で言う僅かな言葉に、継虎は倍以上の意味を知る。
だがそれは家の為などではなく、国の為なのだとわかっていた。
そしてその流れは抗うものではないということも。
暫し訪れた沈黙に、小鳥と鳶の歌声だけが響く。
陽に照らされても冷たい風は二人を通り抜け、秋を知らせる。
「今はまだ」
その便りを受け取りながらも、ずっとまだ無理だと思ってきた。
「何れそのときがきたら、兄上にも語れるかと」
そして今もまだ、秋を知らないまま過ごしていたいと思う。
否、きっと一生秋を知らずに生きてゆくのだと。
小さく零した言葉に、兄が「そうか」と頷くのを見届けて、継虎は再び庭へと目を移した。
鮮やかに咲き誇る桔梗、風に揺れる枝葉。
二人の間に訪れたのは心地よい沈黙、だがそれもやがて小さな足音で消されてしまう。
いつの間にか枝にいた小鳥は、雀一羽になっていた。
【了】
たった五頁、その上本当に一場面だけの短篇を手にとって下さり、ありがとうございます。
ずっと書きたいな、と思っていたのに公開できたのは本編が完結してから半年も後。
秋なんて終わり、冬まっただ中。
本編では多分きっと継虎のこういう感情はほとんど出てないんじゃないかなぁと思っています。
だからこそ、どうだったのか書きたいなと。
その割に淡々とし過ぎてしまったなぁとも。
何故『秋』なのか、気づいて頂けたら幸いです。
桔梗を選んだのはその花言葉から(ちなみに背景色は「桔梗色」だったり)
鵯は昔から愛され、人に慣れる鳥で秋の季語だったからという理由ですので、話とはあまり関係なかったりします。
あと「竹」と呼ばれるのは継虎の幼名が「竹吉」だからです。
本編で言ったかしら…どうだっただろう。
大変短く拙いものを失礼致しました。
最後までお読み頂き、本当にありがとうございます。
2010.1.31 タチバナユノ