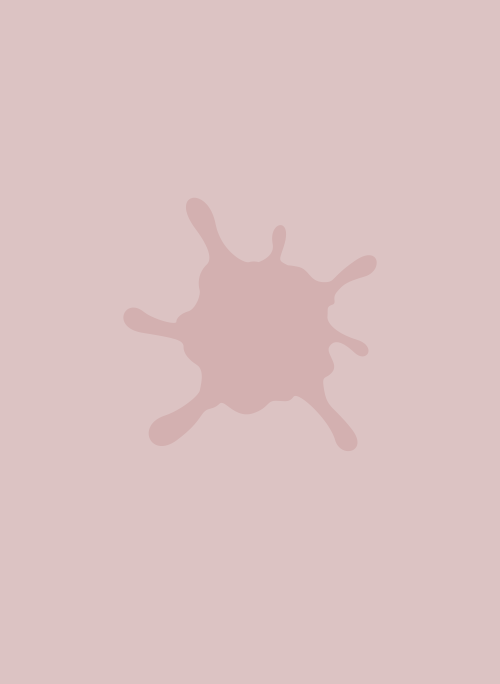高速で回っていく世界が
次に止まった時には、
眼の前に、
『●●北男子高等学校』
と書かれた校門があった。
「もう着いたの?」
「見ればわかるでしょ。
ほら。ヘルメ。」
そう言って手を出す姉ちゃんに
被っていたヘルメットを脱いで渡す。
「ほら、さっさと降りた降りた。」
バイクの後頭部座席から降りて、
さっきとは違う態度に違和感を覚える。
「ねえ、何怒ってるの?」
恐る恐る聞いてみる。
「は?あんた、
彼氏に会いに来たんでしょう?
傷心のあたしに
見せつけてくれやがってこの野郎っ」
キーッなんていいそうな勢いで
姉ちゃんは怒鳴った。
あ、そーいやここって男子高か。
校門のところに書いてある。
って!
そんな呑気にしてる場合じゃなくて、
早くフォロー入れなきゃ殺される!
慌てて脳内がパニック状態になった私は
次の言葉を口走った。
「か、借りがあるのっ!」
「借り?」
「うん。」
何言ってるんだと思いながらも
次の言葉を考える。
「こっ、この前、
助けてもらって、
お礼を言ってなかったから、
言いに行こうと思ったら、
何か連れてかれたって聞いて、、」
次の言葉が見つからなくて
しどろもどろになってる私に
姉ちゃんはわかったとでもいう口ぶりで、
「ふーん。
つまりお礼代わりに助けたいと。」
コクコクとうなずく。
「わかった。
じゃ、頑張れ。」
何とか機嫌を直した姉ちゃんに
私は安堵した。
「負けたら承知しない。」
ヘルメットの
ガラスのようなものから
透けて見える中の姉ちゃんの表情は
どこか意味ありげに笑っていて、
怖かった。
「し、死んでも負けないし!」
精いっぱいの虚勢を張って言い返した。
「ふうん。
今日は威勢がいいじゃん。」
姉ちゃんはそういうと
バイクのエンジンをかけなおした。
「健闘ってやつを祈ってるよ。」
左手をひらひらと振って、
姉ちゃんはバイクを発進させた。
バイクはすぐに見えなくなった。
バイクが見えなくなって、
私は校舎のほうに体を向ける。
落書きがところどころある校舎は、
一目見ただけで
不良だらけなんだと思った。
すでに短いスカートを見下ろす。
「…。
女がいたら不自然だよねぇ」
たった今気がついた問題に
途方にくれる。
「…。
まあ、学校抜け出してる時点で、
もうあれだね。問題児。」
開き直る。
そして、早く行こう。
あの馬鹿の所へ。
校舎のほうへ歩きながら
邪魔臭いブレザーの上着を脱いで、
腰に巻き、
ワイシャツの袖を肘までまくって、
胸元のリボンをとってポケットにしまう。
もう春の肌寒い風はなくて、
心地いい風が優しく吹いていた。
これから、
おそらく殴り合いの喧嘩をするであろう
私には不似合いすぎるくらいに。
下駄箱のところで、
私は悩んでいた。
「うぅーん…。」
なんで悩んでいるのか?
それはね…
「土足で行くべきか否か…。」
である。
上靴を持ってくれば
よかったかなと後悔する。
いや、でも、
別に土足でもよくないか?
なんでって?
床には外靴で歩いたであろう足跡が
点々とあるからだ。
でも、いくらなんでも
土足というのは抵抗がある。
でも早く行かないと、
織が酷い目に遭うのは
わかっていたので、
余計に焦って、
思考がうまく働かない。
靴下で行くべき?
でも、そうしたら、
靴下が真っ黒ならぬ、
真っ茶色になるだろう。
「うぅーー…。」
思考停止状態近いなかで
物を考えるのは辛い。
「うぅぅーーー。」
なので、
少し頭痛がする。
あぁ、もう面倒くさい。
「いいや、土足で。」
靴脱いだり履いたりって
面倒臭いし。
廊下をずんずんと当てもなく進む。
今は授業中のようで、
廊下は人もいなく閑散としていた。
ふとひとつの教室を通り過ぎる。
中からは雑談をする男子の声と、
無視して授業をする先生の声。
きっと、
中は休み時間同様に
遊んでいる奴らを無視して
先生は勝手に授業を
進めていっているのだろう。
義務教育が何ちゃらってやつ。
現実には、
ドラマや漫画に出てくるような
熱血教師はいない。
だとしたら、
誰かがやってくれるのを
ただひたすら待つんじゃなくて、
自分がやるべきだと思う。
ま、そのことに気づくのは
まだまだ先のことだと思うけれど。
ドアのガラスから見えないように
四つん這いになって行く。
くっ。
腰が…。
腰を襲う苦痛に耐えながら
私は四つん這いのままで進んでいった。
辛い。
い
…というか、
たった今気がついたことがまたひとつ。
私、織がどこにいるか知らない。
んでもって、
私、方向音痴。
「……………。」
現実に打ちひしがれる。
「………。」
仕方なく、
耳を澄まして集中する。
織の声か何かが聞こえますように。
……。
うるさいはずなのに、
周りはとても静かだった。
……。
【聞こえて、聴こえて。】
……。
【キコエテ、織ノ声。】
胸の奥で無意識に呟く声。
…「ぁ…。」
不意に、
擦れた、聞きなれた声が小さく聞こえた。
こっち?
一瞬だけ、
小さく聞こえた声を頼りに
四つん這いの状態から立ち上がって、
走っていく。
駆けていく。
…というか、
たった今気がついたことがまたひとつ。
私、織がどこにいるか知らない。
んでもって、
私、方向音痴。
「……………。」
現実に打ちひしがれる。
「………。」
仕方なく、
耳を澄まして集中する。
織の声か何かが聞こえますように。
……。
うるさいはずなのに、
周りはとても静かだった。
……。
【聞こえて、聴こえて。】
……。
【キコエテ、織ノ声。】
胸の奥で無意識に呟く声。
…「ぁ…。」
不意に、
擦れた、聞きなれた声が小さく聞こえた。
こっち?
一瞬だけ、
小さく聞こえた声を頼りに
四つん這いの状態から立ち上がって、
走っていく。
駆けていく。
織。
織っ。
織っ!!
胸の奥の声は大きくなっていく。
やがて一つの
空き教室らしきところに辿り着く。
声はここからした。ハズ。
ドアを開ける前に、
武器となるものを持っていないことに
気付いた。
でも、
いまさら取りに行く気にもなれないし、
それに、
戻ってこれないというのもある。
「…。」
約5秒の試行錯誤の結果。
私は素手で闘ることにした。
体中の力を抜いて、
目の前のドアをスライドさせる。
ドアを開けた先には、
殴られ、蹴られて
顔が青タンだらけになっている
織が倒れていた。
「織。」
今まで焦っていたのは嘘の様に、
私はとても落ち着いていた。
ゆっくり、ゆっくり、
織に歩み寄っていく。
そして、
織のすぐ側まできて、
しゃがみ込んで、織の顔を見る。
遠くから見ても
青タンだらけだとわかるその顔は、
近くからみるともっと酷かった。
「痛くないの…?」
愚問を織に問いかけた。
織の反応は、無い。
気を失っているらしかった。
「ねぇ?」
小さく問いかける自分の声は、
驚くほどに弱々しく、頼りなく聞こえた。
「お。迷子の子猫ちゃんはっけーん。」
背後から聞こえる、
低く、おちゃらけた声。
振り向くと、
一人の男子生徒を筆頭に、
十数人の男子が出入り口に立っていた。
おちゃらけた声を発したと思われる
筆頭の男子生徒以外、
私を見て驚いていた。
「あ、土足。
いけないんだー?」
「そーゆうあんた等も土足だけど?」
ツッコむ。
男子生徒はあちゃーって顔をして、
「ま、いんじゃない?」
と、流した。
「で、君は、
そこのライオンもどきのお迎えかな?」
何故か不意に場の空気が冷たくなる。
「そーですけど、何か?」
威勢よく言い返す。
「困るんだよねぇ?
勝手に連れて帰ってもらっちゃぁ。」
おちゃらけた声とは裏腹に、
冷たい表情と、視線。
一瞬で、
【強い。】と判断した。
この作家の他の作品
表紙を見る
目覚めたら、
そこは異世界の真っ只中だった。
変色した少女の瞳と髪の色。
その色は
その世界を創造した女神の色と
まったく同じだった。
少女をめぐる戦争。
少女は一体何を思う?
そして騎士の想いは?
1人の少女と1人の騎士が織りなす
異世界ファンタジー。
・゜.・○。●゜.◌.・.゜.●。゜・.
感想ありがとうございます
*MaHaRo*さま
LilaSnowさま
ひびき瑛理さま
●。.・゜.。○゜・.゜○.・゜●..゜
表紙を見る
ひきこもり。
略してひっきー。
彼女は
外をあまり知らなくて、
知らないうちに苦しんで
気づいたら外の人に恋をしていました。
ひっきーの恋は叶う?
それとも叶わない?
貴方は物語の展開 どっちがいいですか?
*★☆*★☆*★☆*★☆*★☆*★
感想ありがとうございます
心夏さま
悠華さま
アベル.さま
相良逢依さま
*★☆*★☆*★*★☆*★☆*★☆
表紙を見る
人を呪う事ができるという、
人気のテディベア
【呪いのテディベアセット】
手に入れる方法は、
人を、
恨んで
怨んで
ウラミツヅケルコト。
そして、
今日もまた一人、
狂気に、
堕ちてゆく。
作者の下らない連載に
どうぞお付き合いください。。。
…☆・・・*……★・・・☆…・・・*…★・・・
感想ありがとうございます
ブラックマリアさま
悠華さま
樽崎知景さま
睦輝紗斗さま
★・・・☆・・・*…★・・・☆・・・*…★・・・
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…