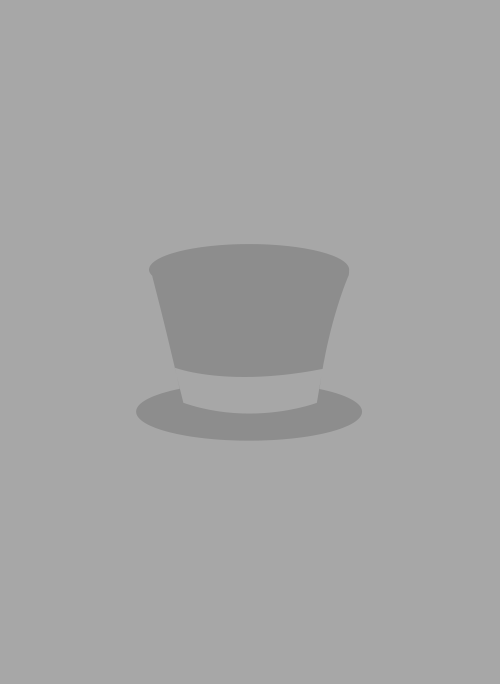「…」
完全に見えなくなった瞳。
しかし、そんなに不便に感じなかったのは、アスカのこれまでの生活のせいであろう。
王が出掛け、不在となった玉座の間。
静かな空間で、アスカの鼓動と吐息だけが、そこにある生きる証明だった。
そんなことに気付いただけで、アスカは幸せだった。
まだ何かを感じられる。
目から流れる血が、固まりかけていた。
アスカは拭うことをせずに、ただ耳をすましていた。
自分の音以外に、何かが聞こえてきたからだ。
それは、小鳥の囀り。
城の外を自由に過ごす小鳥達の声。
アスカは、その囀りに初めて、楽しさを感じた。
今まで、アスカの周りに楽しさを与える存在はいなかった。
王宮の地下でも。
嘲り、偽り…愛想笑いと謀略。
アスカは道具であり、人として扱われてはいなかった。
そして、王宮を出た後は…人を超えて、神と呼ばれた。
(ああ…)
アスカは、囀りが聞こえてくる方に手を伸ばした。
その時、後ろから声がした。
「王がやったのか?」
その声に振り返っても、アスカには誰なのか確認する目がなかった。
「治癒は不得意だが…血くらいは、拭ってやろう」
「あ…」
後ろに立つ人物が、膝を折ったことは、空気の流れでアスカにはわかった。
地下室の暗闇にいた時から、耳と皮膚の感覚は研ぎ澄まされ、敏感になっていた。
「あなたは…」
アスカは、声で人物を確定した。
先程、この部屋に来た…赤毛の女の人。
顔を上げたアスカの両目に走る一筋の傷を見て、サラはため息をついた。
(ライ様は…何を苛立っていらっしゃるのか)
サラにはわからなかった。
しかし、普段はそういうことをしない人だともわかっていた。
(王になられてから…少し御変わりになられたかもしれない)
アスカの血を右手で一度拭うと、サラは手のひらで両目を覆った。
「温かい…」
思わずアスカの口から、声がこぼれた。
(しかし…それでも)
サラはゆっくりと立ち上がると、傷口が塞がったアスカの顔を見下ろした。
完全に見えなくなった瞳。
しかし、そんなに不便に感じなかったのは、アスカのこれまでの生活のせいであろう。
王が出掛け、不在となった玉座の間。
静かな空間で、アスカの鼓動と吐息だけが、そこにある生きる証明だった。
そんなことに気付いただけで、アスカは幸せだった。
まだ何かを感じられる。
目から流れる血が、固まりかけていた。
アスカは拭うことをせずに、ただ耳をすましていた。
自分の音以外に、何かが聞こえてきたからだ。
それは、小鳥の囀り。
城の外を自由に過ごす小鳥達の声。
アスカは、その囀りに初めて、楽しさを感じた。
今まで、アスカの周りに楽しさを与える存在はいなかった。
王宮の地下でも。
嘲り、偽り…愛想笑いと謀略。
アスカは道具であり、人として扱われてはいなかった。
そして、王宮を出た後は…人を超えて、神と呼ばれた。
(ああ…)
アスカは、囀りが聞こえてくる方に手を伸ばした。
その時、後ろから声がした。
「王がやったのか?」
その声に振り返っても、アスカには誰なのか確認する目がなかった。
「治癒は不得意だが…血くらいは、拭ってやろう」
「あ…」
後ろに立つ人物が、膝を折ったことは、空気の流れでアスカにはわかった。
地下室の暗闇にいた時から、耳と皮膚の感覚は研ぎ澄まされ、敏感になっていた。
「あなたは…」
アスカは、声で人物を確定した。
先程、この部屋に来た…赤毛の女の人。
顔を上げたアスカの両目に走る一筋の傷を見て、サラはため息をついた。
(ライ様は…何を苛立っていらっしゃるのか)
サラにはわからなかった。
しかし、普段はそういうことをしない人だともわかっていた。
(王になられてから…少し御変わりになられたかもしれない)
アスカの血を右手で一度拭うと、サラは手のひらで両目を覆った。
「温かい…」
思わずアスカの口から、声がこぼれた。
(しかし…それでも)
サラはゆっくりと立ち上がると、傷口が塞がったアスカの顔を見下ろした。