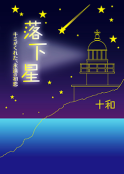那智……。
どうしようもなくドロドロで
醜くて、汚いあたしの気持ち。
世界でただひとり
那智だけが笑ってくれるね。
「……今日は、帰り早かったんだね」
ひとしきり爆笑したあと、乱れた髪を手櫛で整えながら言った。
「あー」
那智はあたしから離れ、机の上からスケッチブックを持ってきた。
「久しぶりに描きたくなってん」
「えっ」
そこには、鉛筆で描かれた無数のデッサン。
そして、そのどれもが。
「……あたし?」
思わず顔が赤くなるほど、あたしであふれかえっていた。
「本物より美人に描けたやろ?」
「うっさい、バカ」
「ははっ」
憎まれ口を叩きつつも、あたしは素直に感動していて。
スケッチブックを持ったまま、夢中で見入っていると、
「なんでやろなぁ」
那智はあたしの髪をもてあそぶように、くるりと指先に巻きつけた。
「お前見てると、無性に描きたくなるねん」
「……」
神経が通っていないはずの髪の毛でさえ
那智が触れた場所は熱くなる。
あたしはスケッチブックから目をそらし、ゆっくり彼を見上げた。
あ……また、この瞳。
見つめられたら世界が止まる。
身体の奥までしびれるような感覚に、抗えなくなる。
もっと。
もっと、って……。
「じゃあ…また描いてくれる?」
その瞳に、もっとあたしを映してほしい……。
「今度は、あたしのこと見ながら描いて」
「あぁ、ええよ」
耳元でささやかれた声は、まるで特別な契約のようで。
あたしは幸福と同時に、ふいに悲しくなった。
リビングの棚に隠された、婚姻届。
あんな紙切れ一枚の方が
あたしと那智を結ぶものより
ずっとずっと強いんだ。
どんなに強くあたしたちが想い合っても、かなわないんだ。
「藍? どないした」
「……ううん」
――このまま
那智が描く世界の中だけで
生きていられたら。
うかつだった。
あたしは少し、神木のおばさんを見くびっていた。
『ねぇ、藍ちゃん。もしかして昨日、那智の部屋にいた?』
今朝、洗面所で顔を洗っていたあたしの背後に立って、おばさんはそう言った。
『え……? いた、けど』
濡れた顔のまま、鏡の中で目が合う。
昨夜あれだけ爆笑していたあたしたちの声は、おばさんにも聞こえていただろう。
だから指摘されても、最初はたいして驚かなかった。
『それが何? すぐに自分の部屋に戻ったんだからいいでしょ』
『……でも、那智の部屋から2時間くらい、ふたりの声が聞こえてた気がするんやけど……』
ギクリとした。
同時に、ゾッとした。
たしかにあたしはあの後、2時間ほど那智の部屋にいたんだ。
でも本当に小さな声で話していたから、普通は聞こえるはずがないのに。
そう、たとえばドアの前に立って、じっくり耳をすましたりしない限りは。
『藍ちゃん。変なこと聞くけど、あんたたち――』
おばさんの話の途中で、あたしは顔もふかずに洗面所を出た。
「……あのババァ」
教室の机に突っ伏して、つぶれた声で吐き捨てる。
あのせいで1・2時間目の授業は、全然集中できなかった。
「桃崎さん。次、体育だよ~」
ハイテンションで声をかけてきたのは、同じクラスの亜美。
以前、那智のことで話しかけてきた女子だ。
あれ以来、亜美はやたらあたしに絡んでくる。
「体育、だるいな……休みたい」
「ダメだよー。今日はグラウンドでハードル走だよぉ? 全校の男子が、桃崎さんの走る姿を楽しみにしてるのにー」
……何だ、そりゃ。
結局、渋々あたしは体育を受けることにしたのだけど
遅刻気味にグラウンドに出た時点で、後悔することになった。
那智のクラスの教室は、1階。
しかもこの時間は、気が弱い先生の授業中らしく。
那智たちのグループは授業そっちのけで、窓際にたまって談笑している。
「あ、弟くんだぁ」
亜美の声を無視して、あたしはハードルを並べる手伝いを始めた。
「おっ。那智の姉ちゃんだ。
ジャージでもキレイだよな~」
教室の方からも声が聞こえてくる。
聞こえないふり。
気にしないふり。
雑音をシャットアウトして、黙々とハードルを並べるあたし。
「ねぇねぇ。弟くん、こっち見てるよ」
亜美があたしの肩をとんとん叩く。
「あっそ」
「手、振らなくていいの?」
「は? なんで」
「姉弟なんだし、別に変じゃないでしょ」
いやいや、変でしょ。と心の中でつっこんでいると。
「何、照れてんの? 付き合いたてのカップルみた~い」
無邪気な口調で、そんなことを言われてしまった。
「……そんなわけないじゃん!」
考えるより先に、あたしは怒鳴っていた。
ハッと気づいて口をつぐむあたしの前には、困惑した表情の亜美。
「……ごめん」
しゅんとしてあやまったのは、亜美の方だった。
最低だ、あたし。
今朝のことでイライラした挙句、亜美に八つ当たり。
周囲の視線も、那智の教室からの視線も、こっちに集中しているのがわかる。
いたたまれなくて、黙って亜美のそばから離れた。
「よし、順番にタイム計るぞー」
先生の号令に合わせ、2列に並んだ生徒たちが次々にハードルを飛び越えて行く。
自分の番が回ってきたあたしは、靴ひもを結び直してスタート地点に立った。
「ん? 桃崎、顔色悪くないか?」
ホイッスルを口から離した先生が、心配そうにあたしを見下ろした。
……言われてみれば、少し目まいがするかもしれない。
さっきのことで頭に血が上っているせいか、それとも、昨夜から何も食べてないせいか。
「休むか?」
「……いえ」
あたしは気にしないことにして、ゴール地点に目をやった。
ホイッスルが響き、地面を強く蹴る。
頭の中でうずまく雑音を振り切るように、あたしは加速をつけてハードルを飛び越えていく。
――『藍ちゃん。変なこと聞くけど、あんたたち』
――『付き合いたてのカップルみた~い』
黙れ……。
みんな、うるさい。
黙れ、黙れ、黙れ――。
「桃崎さんっ!?」
横を走っていた生徒が、あたしの名前を叫んだ。
我に返ったあたしは、目の前に迫っていたハードルにやっと気づく。
とっさに飛び越えようとしたけれど間に合わず
ハードルと一緒にバランスを崩し、地面に体を打ち付けた。
「痛……っ」
舞い上がった砂ぼこりが口に入って、ジャリ、と嫌な音を立てた。
この作家の他の作品
表紙を見る
~書籍化決定しました~
高2の <真緒>が友達になったのは
完璧なイケメン転校生 <蒼>
だけど彼には秘密があった。
「約束しろ。僕のことは
誰にも話さないって」
ある日、見た目は蒼と同じなのに
中身は正反対の少年
<ホタル>が現れて――…
2019.8.18~2020.2.29
表紙を見る
『ねぇ。オニ高のプリンス
って 知ってる?』
――知ってるも何も。
その人
隣に住んでますから!
・・*☆*・・・・・・・・・・・・・・・・
息をのむほどキレイな顔
無愛想で 超マイペース
時々 ワケわかんないけど
時々…すごく優しい
そんなお隣サマに
あたしは恋をしました
・・・・・・・・・・・・・・・・*☆*・・
2011.2.11~6.11
表紙を見る
校内一の人気者
ワルかっこいい健吾に
★体当たりLOVE★
.:+・゚ ゜゚・*:.。..。.:+・゚
『お前は俺が見つけた
最高の女なんだ』
――Kengo
『健吾にはあたしが
いるからね』
――Riko
.:+・゚ ゜゚・*:.。..。.:+・゚
サイテー最悪な
失恋をしたあたしに
突然訪れた……
サイコー?の出逢い
――――――――――
Love and Days
2008.11.8~2009.3.13
2009.9.18 書籍化
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…