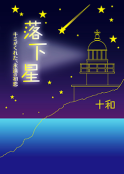捕らわれた視線。
瞬間、すべての音が消えた。
セミの鳴き声も。
木々のざわめきも。
海からの汽笛も。
何もかもが音をなくし、自分たち以外の世界が止まった。
『……お前、この辺で見ぃひん顔やな』
見下ろしてくる眼光に、ぞくりと戦慄が走る。
獣の眼だ、と思った。
深い森の奥でひっそりと生きる孤高の聖獣。
獲物を見つければ一瞬で
痛みすら感じさせず命を奪いそうな――
思わず上体を退くと、石畳のひんやりした感触が腕に伝わった。
詰まる距離。
ドクッ、ドクッ、と心臓が暴れだす。
しだいに目が慣れると、彼の輪郭がはっきりと見えてきた。
漆黒に光る長いまつげ。
完璧な曲線を描く唇。
そして、
あたしの方に伸びてくる左手。
『お前――』
彼の指先が髪に触れる寸前。
あたしは思わず、ギュっと目をつむった。
『――もしかして“藍”か?』
『え?』
そっとまぶたを上げるとそこには、黄色い花ビラをつまんだ彼の指。
あ……、髪についていた花ビラを取ってくれたんだ。
やっと思考が回転し始めたあたしは、改めて彼の顔を見上げた。
整った目鼻立ち。
今まで出会ったこともないくらい、キレイな。
『あ、あんた……なんで、あたしの名前知ってんの?』
答えはもう想像がついていたけれど、たずねてみた。
そのとたん、彼はプッと吹き出して。
『声、震えすぎ』
急に11歳の悪ガキの顔になって
笑ったんだ。
それから那智は誇らしげに、採ったばかりのカブト虫を見せてくれた。
あたしは生まれて初めて触る、昆虫の感触に悲鳴を上げ、それを見た那智がまた笑った。
灼熱の夏。
12歳と11歳だった、あたしたち。
自分たちの運命をまだ知らなかった、幼いふたり。
一目惚れとか、恋心とか、そんなんじゃなかった。
あの日、生まれた感情は
言葉や理屈じゃ説明できない。
だけど今もハッキリと
あたしの心に、焼きついたままなのだ。
『勝手に触んなや』
あの一瞬。
まぶしくて
まぶしくて。
太陽が落ちてきたのかと思った。
――那智が、下級生に告白されたらしい。
転校してきて1ヶ月。
あたしが知っているだけでも、すでにもう4人目。
友達がいないあたしの耳にさえ、那智の噂は毎日のように飛び込んでくる。
「……だれも、かれも、
惹かれちゃうんだよなぁ」
夕方の薄暗いリビングでぽつり、ひとり言をつぶやくあたし。
学校から帰ってきたら、家には誰もいなかった。
静寂のリビング。
窓はピカピカに磨かれ、
花瓶には花が生けられ、
手作りのヌイグルミなんてものもある。
神木のおばさんが住み始めてから、日に日に、他人の家みたいになっていく我が家。
「誰が誰に惹かれるって?」
ふいうちで後ろから声をかけられ、あたしは飛び上がった。
「あぁ……那智。ビックリした」
「電気くらい点けろや」
パチン、と音がして、部屋の中が明るくなる。
蛍光灯の下、濡れたように艶めく那智の黒髪。
「うちのオカンは?」
「留守。買い物じゃないかな」
「ふーん」
台所に飲み物を取りに行く那智が、あたしのすぐ横を通った。
ふたりきりになるのは久しぶりだな。
そう思ったら、脈が少し速くなった。
「那智」
「んぁ?」
「今日、また告白されたんだって?」
那智は冷蔵庫に手をついたまま、ふり返らずに笑う。
「情報早っ。井上公造か、お前」
「聞く気がなくても、勝手に噂が流れてくるんだよ。
……今日の女の子、泣いてたらしいじゃん」
「んー? あぁ、そうやな」
まったく悪びれる様子のない那智。
あたしが怒ることじゃないけれど。
全然、怒る必要ないんだけど。
なんとなくモヤモヤして、学ランの背中をにらんだ。
「泣かすような、ひどい断り方したの?」
「全然。あっちがお前の話を出してきたから、ハッキリ言うただけや」
「え?」
あたしの話?
冷蔵庫をパタンと閉めて、那智がふり返った。
「“藍さんみたいな美人と住んでたら、あたしなんてブスに見えるだろうけど”ってよ。
“分かってんなら告白してくんな”って答えたら、泣きよった」
「……」
鬼だ、こいつ。
「……サイテー」
そうつぶやきながら、
だけどニヤけそうになる頬を、ぐっとこらえた。
サイテーなのは、あたしもだね。
那智のあんな発言に、ちゃっかり優越感を抱いたりして。
「そういうお前の方こそ、しょっちゅう告白されてるらしいやん」
ペットボトルのコーラを片手に、那智がリビングに戻ってくる。
コーラを飲む動作に合わせ、小さく上下する那智の喉ぼとけ。
ボタンを開けた学ランからチラリとのぞく、鎖骨のラインに見とれていると、
「けっこう、俺の同級にも多いんやぞ」
あたしの正面に立ち、那智が言った。
「お前を狙ってる男」
「……は? まさかぁ。
最近あたし、下級生から告白なんて全然――」
「あぁ、俺がおるからやろ」
サラッとつぶやき、那智はペットボトルのふたをゴミ箱に投げた。
そして、かすかに濡れた唇で
ムカつくくらい、キレイな弧を描いて。
「俺の許可なしに、お前に近づくヤツはおらん」
……どういう意味よ、それ。
ただの冗談なのか。
それとも、そうじゃないのか。
期待と困惑が胸の中でもつれ、あたしは那智の瞳を凝視する。
けれど彼は意地悪に微笑むだけで、ちっとも真意が読み取れない。
「那――」
「あ」とつぶやいた那智が、窓の方を向いた。
つられてあたしも、外に意識を集中させる。
駐車場に入ってきた、車の音。
お父さんの車だ。
「帰ってこんでも、えぇのに」
しらけた表情で那智がぼやいた言葉は、あたしの心の声と、ぴったり同じだった。
そう、同じなのに。
「うん」とうなずくことが、できない。
気ままな猫が人間の腕をすり抜けるように、那智はするりと踵を返し、リビングを出て行った。
「ただいまぁ」
ほどなくして、外側からドアが開いた。
そこにはお父さんと一緒に、神木のおばさんの姿も。
「さっき偶然、外で会ったんよ。荷物が多いから乗せてもらってん」
尋ねてもいないのに、いちいち説明してくるおばさん。
ホント、“帰ってこんでも、えぇのに”。
この作家の他の作品
表紙を見る
~書籍化決定しました~
高2の <真緒>が友達になったのは
完璧なイケメン転校生 <蒼>
だけど彼には秘密があった。
「約束しろ。僕のことは
誰にも話さないって」
ある日、見た目は蒼と同じなのに
中身は正反対の少年
<ホタル>が現れて――…
2019.8.18~2020.2.29
表紙を見る
『ねぇ。オニ高のプリンス
って 知ってる?』
――知ってるも何も。
その人
隣に住んでますから!
・・*☆*・・・・・・・・・・・・・・・・
息をのむほどキレイな顔
無愛想で 超マイペース
時々 ワケわかんないけど
時々…すごく優しい
そんなお隣サマに
あたしは恋をしました
・・・・・・・・・・・・・・・・*☆*・・
2011.2.11~6.11
表紙を見る
校内一の人気者
ワルかっこいい健吾に
★体当たりLOVE★
.:+・゚ ゜゚・*:.。..。.:+・゚
『お前は俺が見つけた
最高の女なんだ』
――Kengo
『健吾にはあたしが
いるからね』
――Riko
.:+・゚ ゜゚・*:.。..。.:+・゚
サイテー最悪な
失恋をしたあたしに
突然訪れた……
サイコー?の出逢い
――――――――――
Love and Days
2008.11.8~2009.3.13
2009.9.18 書籍化
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…