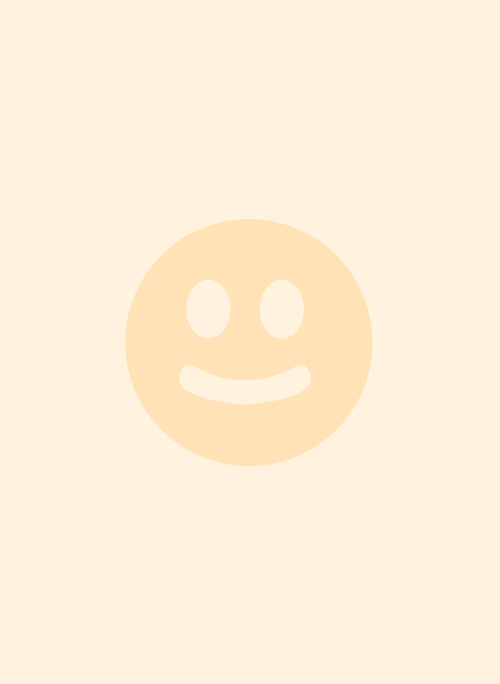「神様はお考えを変えるということはできません。どうか、この話しを理解していただき、頑張っていただきたく、この旨をお伝えしに参った次第でございます」
水谷さんは私に何度も頭を下げた。
「やりますよ。やらなきゃ死ぬんでしょ」
「桜理さま。ありがとうございます。私も出来ることは協力させていただきます」
「相手はどこにいるの。探すだけで、一年かかることをさせるつもりはないんでしょ」
「お相手の方にお会いになったからあの夢を見たのです。神様はあなたの魂にそのようなしかけを施しました。思い出してください、昨日あなたが初めて出会った方の中にいたはずです」
初めて会った人。
私は、人の顔を覚えるのが苦手で、一度だけ会った人は、次の日は初めましてになってしまう。
水谷さんは私に何度も頭を下げた。
「やりますよ。やらなきゃ死ぬんでしょ」
「桜理さま。ありがとうございます。私も出来ることは協力させていただきます」
「相手はどこにいるの。探すだけで、一年かかることをさせるつもりはないんでしょ」
「お相手の方にお会いになったからあの夢を見たのです。神様はあなたの魂にそのようなしかけを施しました。思い出してください、昨日あなたが初めて出会った方の中にいたはずです」
初めて会った人。
私は、人の顔を覚えるのが苦手で、一度だけ会った人は、次の日は初めましてになってしまう。
「顔を覚えるのが苦手なんですか」
水谷さんは困ったなぁと首を傾げた。
困ったのはこっちも同じで、相手が分からなきゃこのゲームを進められない。
ただ死を待つだけになってしまう。
それは嫌。
「もう今月は学校も終わりで、冬休みにはいるので、1月から頑張ろうと思うので、ヒントみたいなものを考えて来て下さい」
「分かりました。神様に相談してきます」
水谷さんは困ったなぁと首を傾げた。
困ったのはこっちも同じで、相手が分からなきゃこのゲームを進められない。
ただ死を待つだけになってしまう。
それは嫌。
「もう今月は学校も終わりで、冬休みにはいるので、1月から頑張ろうと思うので、ヒントみたいなものを考えて来て下さい」
「分かりました。神様に相談してきます」
「お願いしますね。このことは、誰かに話しても良いんですか?」
「えぇ。ただ、彼にこのことを話して、言葉だけの愛を告げられただけではあなたは助かりません。心からの愛の言葉があなたを輪廻の呪縛から解き放つのです。どうするかはあなた次第です」
「分かりました」
心からの愛なんて分かるの?
神様のさじ加減じゃないの?
聞きたかったけど、今は止めた。
色々、整理して考えて見たかった。
それに、彰と猛流が来るタイミングだ。
水谷がいた時には、その空間事態が時を止まっているように感じられたけど、今は時が流れているのを感じた。
「えぇ。ただ、彼にこのことを話して、言葉だけの愛を告げられただけではあなたは助かりません。心からの愛の言葉があなたを輪廻の呪縛から解き放つのです。どうするかはあなた次第です」
「分かりました」
心からの愛なんて分かるの?
神様のさじ加減じゃないの?
聞きたかったけど、今は止めた。
色々、整理して考えて見たかった。
それに、彰と猛流が来るタイミングだ。
水谷がいた時には、その空間事態が時を止まっているように感じられたけど、今は時が流れているのを感じた。
「お前は、知らない人間を家にあげるなと何度言わせるんだ」
家に来た彰と猛流に水谷の話しをしたら即お説教をもらった。
「だって、今日見た夢の内容をばっちり当てるんだもん。名前だけ知ってるならすぐ追い返すけど、妙に生々しく話すし」
「それで、一年後のお前の誕生日にお前が死ぬっていうのか」
猛流はケータイのスケジュールの来年の12月を見ている。
「解せん。そんな人の死を口にするような奴の言うことを聞いていいわけがない。見知らぬ男に愛されろなど非常識だ」
彰はずっと怒ったままだ。
「来月、また来るんだろ。その時はオレらも呼べよ」
「うん」
「じゃあ、大晦日に向けて新曲作ろうぜ」
「猛流!もう少し考えたらどうだ。桜理が新手の詐欺に引っ掛かってるかも知れないんだぞ」
家に来た彰と猛流に水谷の話しをしたら即お説教をもらった。
「だって、今日見た夢の内容をばっちり当てるんだもん。名前だけ知ってるならすぐ追い返すけど、妙に生々しく話すし」
「それで、一年後のお前の誕生日にお前が死ぬっていうのか」
猛流はケータイのスケジュールの来年の12月を見ている。
「解せん。そんな人の死を口にするような奴の言うことを聞いていいわけがない。見知らぬ男に愛されろなど非常識だ」
彰はずっと怒ったままだ。
「来月、また来るんだろ。その時はオレらも呼べよ」
「うん」
「じゃあ、大晦日に向けて新曲作ろうぜ」
「猛流!もう少し考えたらどうだ。桜理が新手の詐欺に引っ掛かってるかも知れないんだぞ」
「そいつがいないなら話してたって意味がない。来月、オレらも一緒に会ってそれで決めれば良いだろ?それよりも大晦日まで時間ねぇぞ」
「仕方ないな。桜理、歌詞は出来てるだろうな」
「少しはね。昨日、邪魔が入って少ししかかけなかった」
「邪魔?」
「そ、久保田くんが」
「お前にしては珍しいな人を覚えてるなんて」
彰は感心したような顔をしてるけど
「顔はもう覚えてないの。久保田くんって呼んだのだけは覚えてる。久保田くんって名前も勝手につけたし」
そう返したら、ため息をついて呆れた顔をされた。
「仕方ないな。桜理、歌詞は出来てるだろうな」
「少しはね。昨日、邪魔が入って少ししかかけなかった」
「邪魔?」
「そ、久保田くんが」
「お前にしては珍しいな人を覚えてるなんて」
彰は感心したような顔をしてるけど
「顔はもう覚えてないの。久保田くんって呼んだのだけは覚えてる。久保田くんって名前も勝手につけたし」
そう返したら、ため息をついて呆れた顔をされた。
「桜理らしいな。よし、音楽部屋いこうぜ」
猛流は笑ってリビングを出て行った。
この家の地下には防音室があってそこには、ピアノが置いてある。
私達はそこで練習をするのが決まりだった。
「今年最後のライブだ。絶対成功させてやろうぜ」
その大晦日の路上ライブから私の命をかけたゲームが始まることを。
後に私はこんな始まりなんて望んでいなかったと嘆くことを誰も気づくことはなかった。
猛流は笑ってリビングを出て行った。
この家の地下には防音室があってそこには、ピアノが置いてある。
私達はそこで練習をするのが決まりだった。
「今年最後のライブだ。絶対成功させてやろうぜ」
その大晦日の路上ライブから私の命をかけたゲームが始まることを。
後に私はこんな始まりなんて望んでいなかったと嘆くことを誰も気づくことはなかった。
大晦日のライブが終わったその夜。
大成功で終ったライブの祝賀会のような形ではしゃいで、リビングでそのまま眠ってしまった。
私は夢を見た。
すぐに分かった。
この夢は私の前世のオウリの記憶を移している夢だと。
オウリは昼は眠って夜は、家の傍の酒場のような所で歌を歌ってお金を稼いでいた。
その歌声はとても伸びやかで、素晴らしい声をしていた。
歌うオウリの金色のふわりとウェーブのかかった髪と、神秘的なスモーキークオーツの様な瞳は彼女美しさをさらに引き立てていた。
酒場にいる誰もがオウリが歌い出すと彼女に目を向けた。
大成功で終ったライブの祝賀会のような形ではしゃいで、リビングでそのまま眠ってしまった。
私は夢を見た。
すぐに分かった。
この夢は私の前世のオウリの記憶を移している夢だと。
オウリは昼は眠って夜は、家の傍の酒場のような所で歌を歌ってお金を稼いでいた。
その歌声はとても伸びやかで、素晴らしい声をしていた。
歌うオウリの金色のふわりとウェーブのかかった髪と、神秘的なスモーキークオーツの様な瞳は彼女美しさをさらに引き立てていた。
酒場にいる誰もがオウリが歌い出すと彼女に目を向けた。
彼女の歌には人を引き付けるものがあった。
同じボーカリストとして嫉妬を覚えた。
自分の前世なのに。
彼女の生まれ変わりだという私は、あんなに音域は広くないし、歌唱力も彼女の半分にも満たない気がする。
「なんだい、もう終わりかい」
一曲歌うと、彼女はステージから下りて、カウンターの端に腰をかけた。
足を組むと、真っ赤なベルベットのドレスのスリットから真っ白な足が見えた。
店主らしき初老の女性がオウリの前にグラスを置いた。
「興が乗らない。ねぇ、今日はやけに人がいるね。こんな寂れた酒場に」
オウリは店を見回して呟いた。
中央の席には、身なりの良い男達がキレイに着飾った女の人達を侍らせて酒を煽っていた。
「寂れたは余計だよ。政府の高官さ」
同じボーカリストとして嫉妬を覚えた。
自分の前世なのに。
彼女の生まれ変わりだという私は、あんなに音域は広くないし、歌唱力も彼女の半分にも満たない気がする。
「なんだい、もう終わりかい」
一曲歌うと、彼女はステージから下りて、カウンターの端に腰をかけた。
足を組むと、真っ赤なベルベットのドレスのスリットから真っ白な足が見えた。
店主らしき初老の女性がオウリの前にグラスを置いた。
「興が乗らない。ねぇ、今日はやけに人がいるね。こんな寂れた酒場に」
オウリは店を見回して呟いた。
中央の席には、身なりの良い男達がキレイに着飾った女の人達を侍らせて酒を煽っていた。
「寂れたは余計だよ。政府の高官さ」
「政府?何でそんなお偉いさんがそれこそおかしいでしょ」
「さあね。私には関係ないことだよ。たっぷりと金を払ってくれれば誰だろうと文句はないよ」
「そりゃそうだね。でも、モップは用意した方が良いかもね。きな臭いよ」
その後、声を潜めた。
「向こうの席で、一人で飲んでる男見たことないよ。ヤバい感じがする」
「明日にでも準備をして置くよ。それを飲んだら、向こうで酌をするか、歌を歌うかどっちかしといで、働かない奴に金は払わないよ」
「わかりましたよ」
オウリは怒られた子供のような顔をすると、グラスの中身を一気に飲み干すとまたステージに立った。
「さあね。私には関係ないことだよ。たっぷりと金を払ってくれれば誰だろうと文句はないよ」
「そりゃそうだね。でも、モップは用意した方が良いかもね。きな臭いよ」
その後、声を潜めた。
「向こうの席で、一人で飲んでる男見たことないよ。ヤバい感じがする」
「明日にでも準備をして置くよ。それを飲んだら、向こうで酌をするか、歌を歌うかどっちかしといで、働かない奴に金は払わないよ」
「わかりましたよ」
オウリは怒られた子供のような顔をすると、グラスの中身を一気に飲み干すとまたステージに立った。
この作家の他の作品
表紙を見る
乙女ゲームってなんのこと?
悪役令嬢ってなんのこと?
婚約者の姉の奇行に毎日のように振り回させるようになってしまったマリーベル、彼女は平穏な日常を取り戻せるのか?
表紙を見る
誰かを好きになって、その人に自分を好きになってもらう、たったそれだけのことなのに
それが一番難しい。ってことを私達は思いしる。
表紙を見る
オレの妹は小さい頃から破天荒だった。
彼女の通った道には数々の伝説が出来上がっていった。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…