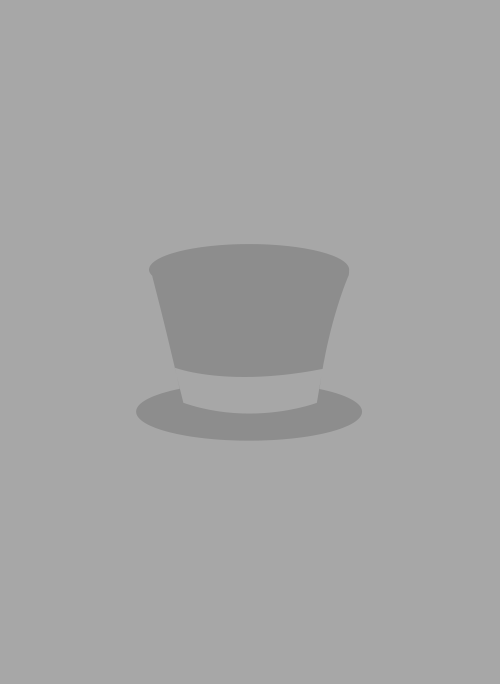その断末魔の叫びにも似た唸りを発しながら大きく開かれた口からは鮮血が滴り落ち、鋭い牙は脂にまみれ、空気がピリピリと震える程の衝撃波が碧を包み込んだ。
(碧…碧…逃げなさい…早く)
(誰?…お母さん?…何処?)
何処からともなく風のように聞こえてくる呼びかけに碧は必死で問い掛けた。
(助けてお母さん・・・助けて!)
「碧!しっかりするんだ!」
いつの間にか自分が大量の汗をかいてベッドにいる事に気付いた碧は不思議そうに回りを見渡した。
「碧、大丈夫よ・・・私がついているから」
母親の夏美が涙を流しながら抱きしめる。しばらく意識が朦朧として状況が把握出来なかった碧は此処が病院のベッドの上だと言う事に初めて気がついた。
「私・・・どうしちゃったの?」
「心配したぞ碧、紺野さんから連絡貰った時は心臓が止まりそうだったよ」
余裕を取り戻した肇がほっとした笑みを浮かべる。
(お母さんが付いていてくれたから、あんな声聞いたのかなあ・・・)
両手で碧を抱きしめ頭を撫で続ける夏美を見てそう考えたが一瞬後にはその考えを否定していた。
(違う・・・あの声は夏美お母さんじゃない・・・私を生んでくれたお母さんの声だ)
何故だかは分からないが、その考えが正しい事を碧は確信していた。
「碧、何か欲しい物ないか?何なら食べたいものでも飲み物でも買ってくるぞ」
「ありがとうお兄ちゃん、じゃあジュース飲みたいな。喉が痛くって」
「じゃあ俺が買ってくるよ」
さっきまで黙って後ろのほうに立っていた雅彦が慌てて割ってはいる。即座に雅彦を振り返った和哉は左手で雅彦を制しながら厳しい口調で言った。
「駄目だよ、碧が何飲みたいのか金沢じゃ分らないだろ?俺が行くからここで待ってろ」
(碧…碧…逃げなさい…早く)
(誰?…お母さん?…何処?)
何処からともなく風のように聞こえてくる呼びかけに碧は必死で問い掛けた。
(助けてお母さん・・・助けて!)
「碧!しっかりするんだ!」
いつの間にか自分が大量の汗をかいてベッドにいる事に気付いた碧は不思議そうに回りを見渡した。
「碧、大丈夫よ・・・私がついているから」
母親の夏美が涙を流しながら抱きしめる。しばらく意識が朦朧として状況が把握出来なかった碧は此処が病院のベッドの上だと言う事に初めて気がついた。
「私・・・どうしちゃったの?」
「心配したぞ碧、紺野さんから連絡貰った時は心臓が止まりそうだったよ」
余裕を取り戻した肇がほっとした笑みを浮かべる。
(お母さんが付いていてくれたから、あんな声聞いたのかなあ・・・)
両手で碧を抱きしめ頭を撫で続ける夏美を見てそう考えたが一瞬後にはその考えを否定していた。
(違う・・・あの声は夏美お母さんじゃない・・・私を生んでくれたお母さんの声だ)
何故だかは分からないが、その考えが正しい事を碧は確信していた。
「碧、何か欲しい物ないか?何なら食べたいものでも飲み物でも買ってくるぞ」
「ありがとうお兄ちゃん、じゃあジュース飲みたいな。喉が痛くって」
「じゃあ俺が買ってくるよ」
さっきまで黙って後ろのほうに立っていた雅彦が慌てて割ってはいる。即座に雅彦を振り返った和哉は左手で雅彦を制しながら厳しい口調で言った。
「駄目だよ、碧が何飲みたいのか金沢じゃ分らないだろ?俺が行くからここで待ってろ」