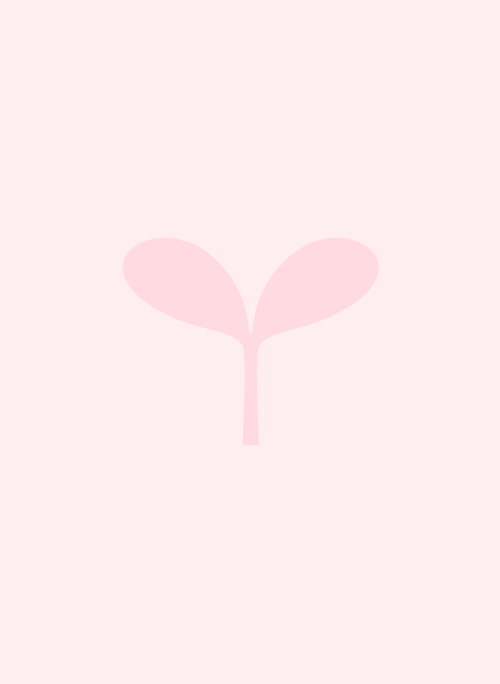あたしの笑った意味がわかったみたいで、
苦笑いしながらあたしを地面に降ろした。
「笑わないで」
恥ずかしそうに苦笑いしながらちょっと俯く。
「重かったなら降ろせばよかったのに」
「それはやっぱり男だしね。カッコつけたいじゃん」
「あはは」
気まずそうに笑う目の前のこの人をますます愛しいと思った。
「もう真っ暗だね」
「あー」
言われるまで気づかなかった。
もう周りは真っ暗でいつもの公園だった。
「帰ろっか」
ぎゅっと手を握って歩き出す。
「ふふふ」
いきなり笑い出した(ちょっと不気味)
あいつを怪訝に見つめるとあたしの視線に気づいたようでこっちを向いた。
「なんか気持ち悪いよ」
「うわっ。ズバッと言うね」
その行動があまりにも可笑しくて吹き出してしまった。
そんなあたしを見てパアッと表情を明るくさせた。
「ん?」
「笑ったー」
可愛いーなんて言いながらぶんぶん手握った手を振った。
「さっきから笑ってなかった?」
自然過ぎて気にしてなかった。
「今の笑顔はよかったのー。キュンてきた」
キュンて普通言わなくない?
でもこいつの笑顔を見たらなんかどうでもよくて、
とにかく笑ってた気がする。
「あっ!!」
びくってなったのがわかった。
あいつの握った手にぎゅっと力が入った気がした。
いきなり大きな声出さないでほしい。
「どうしたの?」
「ケータイ」
そう言ってポケットをごそごそとあさる。
「番号教えて」
ケータイをあたしに向けて準備バッチリなんて言いながら笑ってる。
あたしもポケットからケータイを取り出して赤外線で送る。
「繋がったねー、俺たち」
あははなんて笑って嬉しそうに顔を崩したから、
あたしも一緒になって笑った。
「ん?」
急になったケータイの画面を開くと知らない番号。
「俺の番号。登録しといて」
「うん」
家まであとちょっとというところで気づいた。
家の前に誰かいることに。
暗くてそれが誰なのかはわからない。
自然と手に力が入る。
だんだんと近づいて行ってうっすらと顔が見えてきた。
「‥‥お母さん」
「響!!」
あたしの小さな呟きに気づいたみたいで、
駆け寄ってくる。
「どこ行ってたの?家に帰ったら誰もいないし、心配したんだから」
「ごめんなさい」
お母さんがこんなに早く帰ってくるなんて思わなかった。
異常なまでに心配する。
それが重い。
あたしだってもう高校生だ。
その心配は重いんだよ、お母さん。
「手だってこんなに冷たくして、風邪ひいたらどうするの。響は昔から体が弱いんだから」
違う
「この間だって肺炎おこしたじゃない」
違うよ
「また入院するのは嫌でしょ?」
違うよお母さん
「あたしはお姉ちゃんじゃないよ」
「何言ってるの?」
「あたしは体なんか弱くないし、今まで肺炎だって入院だってしたことない!!」
あぁ言ってしまった。
言わないよう言わないように我慢してたのに。
俯いていた顔を上げたら、困惑したお母さんの顔。
こんな顔させたいわけじゃないのに。
いつも笑っててほしかっただけ。
耐え切れなくなったあたしは今来た道に走り出していた。
「響ちゃんっ!!」
後ろからあいつの声が聞こえたけど、
振り返れない。
立ち止まれない。
今振り返ったら、立ち止まったら、泣いてしまいそうで、
とにかくただ走っていた。
昔から体が弱くて、11歳でこの世を去ったお姉ちゃん。
大好きだったお姉ちゃん。
「きぃ、おいで」
そう言ってあたしの頭を撫でてくれた。
体が弱かったお姉ちゃんばかりを気にしていたお母さんは、
あたしがどんなにテストで100点をとっても、
かけっこで一位になっても
「お姉ちゃんは学校にも行けないのに、走ることも出来ないのに、よくそんなものが見せられるわね」
そう言ってあたしを叱って叩いた。
「頑張ったね」
そう言って頭を撫でてほしかっただけなの。
いつもはお姉ちゃんのことばかりでも、
そのときだけは、わずかな時間だけあたしを見ていてくれたら、
それで十分だったんだ。
そんななかでお姉ちゃんだけはあたしを褒めてくれた。
「偉いねきぃ。凄いねきぃ」
そう言って頭を撫でながら、
太陽みたいな笑顔をあたしに向けてくれた。
「きぃがおっきくなるのお星様になって見てるからね」
お姉ちゃんが死ぬちょっと前に言ってたこと。
そのときにはもう体中に管なんかが繋がれていて、
その声は弱々しかった。
その数日後お姉ちゃんは死んだ。
あたしには死ぬってことがいまいち悲しく思えなくて、
ただ、もうお姉ちゃんには会えないのかってそう思った。
そのときのことはあんまり覚えてなくて、
お母さんがあたしの隣で狂ったように泣き崩れていたことだけはうっすらと覚えている。
この作品のキーワード
設定されていません
この作家の他の作品
表紙を見る
高校3年の春、桜の木の下で君と出会った
名前も知らない君は
何故か私のことを知っていて。
君は誰?
「今日も君が笑顔でいられますように」
のほうもよろしくお願いします。
表紙を見る
君の笑顔が好きでした
だから笑っていて下さい
私の小さな願いです
初めての作品です。
駄文ですが、ぜひ呼んでみて下さい。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…