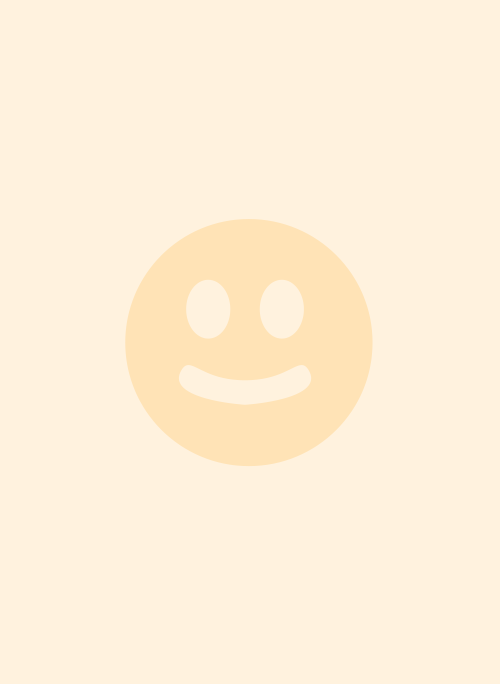時刻は深夜2時過ぎだっただろうか。
俺はピンクの包みを手に、そっと姉貴の部屋に忍び込んだ。
息を潜めて、姉貴の眠るベッドに近づくと。
……スー…
規則正しい寝息を立てて眠る姉貴の顔が白く浮かびあがり、思わず息を飲んだ。
そっと包みを枕に置く。
……それだけで終わらせるはずだった。
なのに。
「…ん、」
小さく寝返りを打つ姉貴の姿に、心臓が大きく揺れて。
僅かにはだけたパジャマから覗く胸元に、ゴクンと唾を飲んだ。
……触れたい。
そう思うより先に、俺の手は勝手に動いていた。
そっと、姉貴の髪に触れてみた。
細くて艶やかな髪の毛に指を通し、サラサラと流す。
そして、震える手で、その白い頬に触れた。
一瞬だけ、ピクリと瞼を動かした姉貴。
だけど気づくことなく、再び寝息を立て始める。
続いて、唇。
一瞬触れるのを躊躇った。
だけど、好奇心がそれを促した。
暗闇の中で薄い桜色に浮かびあがった唇。
それを、人差し指でそっとなぞってみる。
もどかしいのか口が微かに開いた瞬間、俺は慌てて指を離した。
……制御できなくなりそうで。
キスしてしまいそうだったんだ。
それが、初めて姉貴に触れた瞬間だった。
一夜の過ちとでも言おうか。
イケないことだと知りつつも、俺の中の欲望は日を増すごとに大きくなる。
姉貴の笑顔が見たい。
姉貴に触れたい。
…キスがしたい。
自分が異常であることは、とうの昔に気づいてた。
それでも、駄目だと言い聞かせれば言い聞かせるほど、逆に想いが強くなる一方で……
苦しかった。
辛かった。
だから──…
好きでもないヤツを抱いた。
俺たちには幼なじみがいた。
……俺の運命を変えた女。
名前は梓。
ガキの頃からわりと仲が良くて、年のわりに大人っぽい、というかませていたのかもしれない。
中1の冬休みに入る前、つまりクリスマスの直後。
俺は梓に告白された。
どうやら、ガキの頃からずっと思いを寄せてくれていたらしい。
単純に嬉しかった。
梓は当時ショートカットで、さわやかな雰囲気が姉貴に似ていたんだ。
顔だって申し分ないくらいに可愛い。
料理も上手いし、何よりよく気が効く子だった。
返事はもちろんOK。
即答だった。
彼女は嬉しそうに涙を流して喜んでいた。
そして、俺は、
そんな彼女の涙に罪の意識を感じていた。
──身代わり。
なんて酷い言葉だろう。
それでも、結果的に事実なんだから仕方ない。
俺は──…姉貴への気持ちを振り切る為に、梓とつきあうことを選んだ。
つきあっていれば、そのうち好きになれると思っていた。
何より普通の恋愛がしたかった。
─……けど。
その考えはあまりにも浅はかで。
それが後々犠牲を生むことになるなんて、全く想像の余地が無かった───。
彼女と会うときは、専ら公園か梓の家だった。
梓は俺の家に来たがったけど、頑として拒否し続けた。
──会わせたくなかったんだ。
姉貴に知られたくなかった。
何より、姉貴を前に梓にどう接すれば良いかが分からなかった。
つきあい始めて2ヶ月経った日。
俺は初めて梓を抱いた。
そして、俺にとってのファーストキスもした。
それは、想像していた苺味なんてちっともしなくて、味気無くて。
この行為に意味があるのかすら疑問に思えて。
それでも梓は、毎日積極的に唇と体を重ねてきた。
下唇に噛みつかれながら、──あぁ、女の唇は柔らかいな、なんてぼんやりと考えていて。
ふと、
姉貴だったら?
姉貴だったらどんなキスをするんだろう?
姉貴だったらどんなふうに抱かれるんだろう?
そんな疑問が頭をよぎった瞬間、俺は梓の肩を掴んで体を離していたんだ。
「…りっくん?」
当然梓は、不安そうな表情で俺を見上げた。
……ごめん。
「…今日は、無理」
そう言うのが精一杯で、俺の言葉が梓の心をどんなに傷つけているか、なんて考えもしなかった。
そして。
やがてそれは疑問を生み、不信を生んだ。
少しずつ、俺の気持ちが自分に無いことを察し始めていたのだろう。
キスをねだらなくなった変わりに、俺を束縛をするようになったんだ。
それには焦りすら感じられて、必死な姿を見るたびに胸がチクリと痛んだ。
「やだっ…真弥、すごい熱じゃないの!」
それは突然の出来事だった。
珍しく朝食に起きてこない姉貴を心配して、母親が部屋を覗きに行くと、姉貴はものすごい高熱でうなされていたらしい。
……大丈夫か?
姉貴はガキの頃から健康体で、俺と違って滅多に風邪を引いたことが無かった。
そんな姉貴が、この時期に高熱…
今月高校受験を控えているというのに。
心配でたまらなかった。
飯どころじゃなくなって、すぐにでも部屋に駆けつけてやりたかった。
「……おい、大丈夫か」
出かける直前。
グッタリとした表情でリビングに現れた姉貴に声をかけた。
「…へ?あぁ、平気平気!それより陸、今日は梓ちゃんと楽しんできなよ?」
デートなんでしょ、と弱々しそうな声で微笑む姉貴に、胸がズキンと痛んだ。
それでも俺はただ、頷くことしか出来なかった。
なにが、楽しんできなよ?だよ。
こんな状態のお前を放っておいて楽しめるわけがねぇだろ。
本当は梓との約束より、俺は姉貴の側に居たかったんだ。
この作品のキーワード
設定されていません
この作家の他の作品
表紙を見る
初めて本気で恋をした
涙が枯れるくらい
愛しい、と思えた
たとえば それが
血を分けた弟だとしても──。
*---*---*---*---*
2008/12/10 Start
2009/2/9 End
※閲覧について※
この話は近親相姦を扱う内容で、一部性的表現含みます。
閲覧にはご注意下さい><
*---*---*---*---*
表紙を見る
「使えねぇガキだな、おい」
鬼畜サド王子
(桜沢 志季)
VS
自称ツッコミ女王
(相澤 美希)
熱いバトルが今始まる!?
++++++++++++
☆ケータイ小説大賞エントリー第一号☆
初挑戦させて頂いてます!
2009.5.2
☆完結しました☆
++++++++++++
2009.2.12 Start
2009.5.2 End
表紙を見る
思わず胸がキュンとなる
甘い甘い恋のおはなしを
あなたに贈ります +゚
世界の片隅で
今日もまた
誰かと誰かが
恋に落ちる…
※平均10P完結の短編集です
Special ThanX!
*nonokaさん*
*Ruysさん*
とっても素敵なレビュー
ありがとうございます!
★New★
『Best Friend』
5/12 (完結住み)
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…