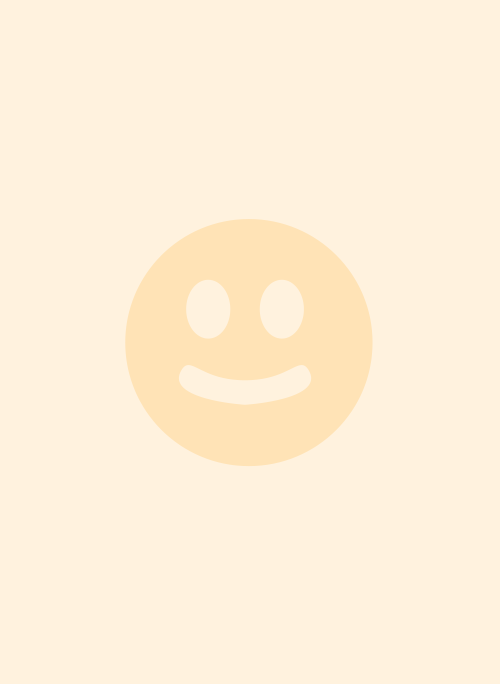その夜。
俺は親の目を盗んで、こっそりエロ本を部屋に持ち込んだ。
いつでもごまかせるように漫画本の間に挟んで、ベッドの上でこっそり開いて。
ページをめくれば、そこに広がるのは俺の知らない大人の世界。
エロとかスケベとか、そんな単語で片付けられない程の衝撃があったのを覚えてる。
時間を忘れて食い入るように読みふけって、気づけば夜になっていた。
夢中で。
夢中になりすぎていて、気づかなかった。
「…ねー、陸」
心臓が止まるかと思った。
ハッとして顔を上げると、仁王立ちのまま俺を見下ろす姉貴がいたから。
「ま、まや…」
「今隠したの、何」
「え…」
「それだよ、それ!」
ビシッと姉貴が指を差したのは、今まさに慌てて閉じたエロ本の裏表紙だった。
逃げられないと観念して、おとなしくそれを渡すと。
「な、な、な、なにこれー!!」
姉貴は俺以上に衝撃を受けたらしい。
すぐに白目を剥き、顔はゆでダコみたいに真っ赤になっていた。
「…すごーい。おっぱい大きい!ボンボンだよ!」
ヤダヤダと騒ぎつつも、興味があるのか姉貴はなかなか本を離さない。
「大人になったら私も巨乳になれるかな?」
「さ、さぁ」
……突然何を言い出すんだ、と思った。
それでも、その言葉で姉貴を意識してしまったのは事実で。
思えば、この日。
俺は初めて欲情した気がする。
ハダカの姉貴を想像したら、自然と身体が疼いた。
その時はただの生理現象だと思ってた。
だから、気づかなかった。
それが“異常”であること。
そして、抱いてはならない感情であることを──────。
──キョウダイは結婚できない?
そんなの、当たり前だろ。
血が繋がってるんだから。
「じゃあ……
どうして姉貴に欲情したんだ?」
……!
大人になった俺が、冷静に問いかけてくる。
「…それ、は、」
たまたま想像したのか、姉貴のハダカだっただけで。
「いや、お前は普段から、実の姉に対してもってはいけない感情を抱いてる」
───嘘だ。
違う。ありえない。
だって、血が繋がっているのに。
俺は──…
俺は──…
中学に入学した頃から、少しずつ自分の想いに疑問を持つようになった。
実の姉貴が気になる─…
恋とか愛とか、よく分からない感情。
それでも意識すればドキドキするし、身体が熱くなる感覚さえ覚える。
一番のキッカケは、学年1美人と言われる同じクラスの女に告白されたときだった。
確かにそいつは一般的に見たら美人だし、皆が騒ぐのは分からなくない。
でも─…どうしても、アイツ、姉貴と比べてしまう。
一つ一つの行動を見ても、姉貴だったら、姉貴なら、といちいち結びつけてしまう自分がいて、ようやくそれが普通の感情ではないことに気づいた。
それを認めてしまった瞬間、事の重大さにしばらく愕然とした。
抱いてはいけない感情。
血の繋がった近親者への恋心。
だけどその頃には、自分の気持ちに歯止めが効かなくなっていたんだ。
忘れもしない、中学1年のクリスマス。
俺は初めて姉貴に触れた。
「今日は早寝しないと」
夕食を済ませるなり、姉貴は何やら嬉しそうに階段をかけ上がっていった。
母親に訪ねると、「真弥はまだサンタを信じてるのよ。バカよねぇ」と笑った。
……マジでバカだ。
んなもん、いるわけねぇだろ。
そう呆れながらも、気づけば勝手に頬が緩む。
不覚にも、可愛いなぁなんて思ってしまって。
姉貴は高校生になっても、とにかく純粋な女の子だった。
汚れを知らない、純粋無垢な女の子。
中学に上がっていろんな汚れや悪さを知った俺にとって、姉貴の存在は綺麗すぎた。
眩しかったんだ。
同じ血が通っているとは思えない、俺とは正反対の性格。
心が真っ白で、綺麗で、暖かくて──……。
今思えば、最初は憧れだったのかもしれない。
それがいつしか、恋に変わっていったんだと思う。
サンタの存在を未だに信じ続ける姉貴に、母親は毎年プレゼントを用意していた。
「純粋すぎるのも困っちゃうわ」
なんて苦笑いしながらも、結局姉貴の欲しがっている物を用意している。
そして、これはついでだけど、と
必ず俺にもくれるのだ。
そんなとか、あぁ、俺たちは愛されてるんだなと実感した。
「でもあいにく、お母さん今夜夜勤なの。陸、真弥の部屋に置いといてくれる?」
お願い!と手を合わせる母親に、俺は渋々包みを受け取った。
…今夜は俺がサンタクロースか。
面倒なはずなのに、なぜか浮き足立つ自分がいた。
早く姉貴の笑顔が見たい。
夜になるのが待ち遠しくて仕方なかった。
時刻は深夜2時過ぎだっただろうか。
俺はピンクの包みを手に、そっと姉貴の部屋に忍び込んだ。
息を潜めて、姉貴の眠るベッドに近づくと。
……スー…
規則正しい寝息を立てて眠る姉貴の顔が白く浮かびあがり、思わず息を飲んだ。
そっと包みを枕に置く。
……それだけで終わらせるはずだった。
なのに。
「…ん、」
小さく寝返りを打つ姉貴の姿に、心臓が大きく揺れて。
僅かにはだけたパジャマから覗く胸元に、ゴクンと唾を飲んだ。
……触れたい。
そう思うより先に、俺の手は勝手に動いていた。
そっと、姉貴の髪に触れてみた。
細くて艶やかな髪の毛に指を通し、サラサラと流す。
そして、震える手で、その白い頬に触れた。
一瞬だけ、ピクリと瞼を動かした姉貴。
だけど気づくことなく、再び寝息を立て始める。
続いて、唇。
一瞬触れるのを躊躇った。
だけど、好奇心がそれを促した。
暗闇の中で薄い桜色に浮かびあがった唇。
それを、人差し指でそっとなぞってみる。
もどかしいのか口が微かに開いた瞬間、俺は慌てて指を離した。
……制御できなくなりそうで。
キスしてしまいそうだったんだ。
この作品のキーワード
設定されていません
この作家の他の作品
表紙を見る
初めて本気で恋をした
涙が枯れるくらい
愛しい、と思えた
たとえば それが
血を分けた弟だとしても──。
*---*---*---*---*
2008/12/10 Start
2009/2/9 End
※閲覧について※
この話は近親相姦を扱う内容で、一部性的表現含みます。
閲覧にはご注意下さい><
*---*---*---*---*
表紙を見る
「使えねぇガキだな、おい」
鬼畜サド王子
(桜沢 志季)
VS
自称ツッコミ女王
(相澤 美希)
熱いバトルが今始まる!?
++++++++++++
☆ケータイ小説大賞エントリー第一号☆
初挑戦させて頂いてます!
2009.5.2
☆完結しました☆
++++++++++++
2009.2.12 Start
2009.5.2 End
表紙を見る
思わず胸がキュンとなる
甘い甘い恋のおはなしを
あなたに贈ります +゚
世界の片隅で
今日もまた
誰かと誰かが
恋に落ちる…
※平均10P完結の短編集です
Special ThanX!
*nonokaさん*
*Ruysさん*
とっても素敵なレビュー
ありがとうございます!
★New★
『Best Friend』
5/12 (完結住み)
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…