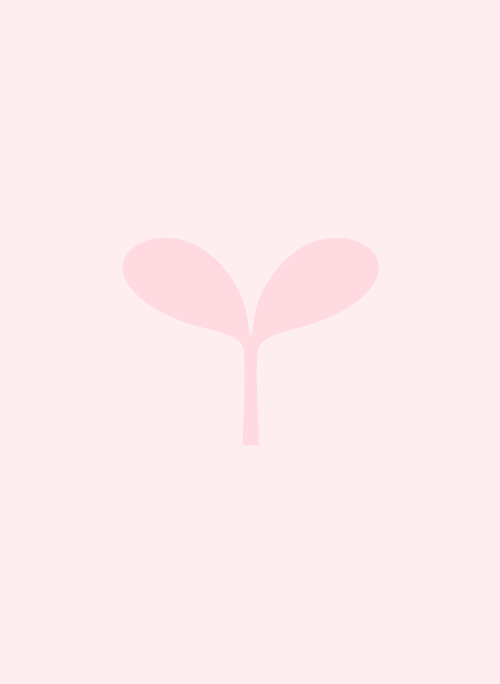「なんだか、傍にいると落ち着くっていうか、そりゃドキドキもするけど、それよりも安心するの。傍にいたいなぁ、って思うの」
「そういうのを好きって言っちゃだめかなぁ?」
やっぱりわかって貰えないかなぁ。
なんだか二人にはわかってほしい気もした。
不安げに二人を見つめると、二人は急に笑いだした。
それに更に不安になる。
そんなに変なこと言ったんだろうか。
「潤ちゃん、杏ちゃん?」
「いやー、真琴らしいなぁって思って」
潤ちゃんはよほど可笑しかったのか、目の端に溜まった涙を拭いながら言った。
私らしい?
「今度はいい恋出来るんじゃない?」
杏がぽんぽんと頭を撫でてくれた。
「いい恋?」
「そ。だって真琴、今まで付き合ってきた人たちは、安心出来ないとか、落ち着かないとか、一緒にいると疲れるとか言ってたじゃん」
「だけど、桜の人は安心するんでしょ?一緒にいたいって思うんでしょ?だったらいい恋出来るよ」
潤ちゃんも頭を撫でてくれる。
わかってくれたんだ。
彼女たちと友達になってよかった。
心からそう思った。
「で、いつ告白するの?」
杏ちゃんがちょっといたずらっぽい笑顔でこっちを見ている。
「うーん。とりあえず、名前くらい分かってからしようかと」
「告白するんだ」
潤ちゃんはちょっと意外そうな顔。
「うん。なんだかこの気持ちは伝えたいなぁって思って」
「そっか。まぁ頑張って。あたしらはいつでも応援してるから」
「うん」
また伸びをする。
なんだか、今日の校庭の桜はいつもより綺麗に見えた。
次の日は土曜日。
あの人はいつ来るか解らないから今日は会えないかもしれない。
本当は一日中あそこにいようかとも思ったけど、いくらなんでもそれはやり過ぎかと思って午後から行くことにした。
しっかし、暇だなぁ。
特に何もすることがない私は縁側に座ってぼーっとしていた。
それにしても、今日はいい天気だなぁ。
散歩ついでに、あの人が来ていないか見てこようかな。
そう思って立ち上がると母親がこっちに歩いてきた。
「あぁ真琴、ちょうどいいところにいた」
「明日の廃品回収で昔の教科書とか雑誌とか出したいから、物置に積んであるダンボール玄関に出しておいて」
「なんで私が」
「あんたどうせ暇なんでしょ」
まぁそうですけど。
仕方ない、午後から行くことにしよう。
「ちゃんと見えるとこに置いておくのよ」
「はーい」
スニーカーを履いて物置に向かう。
重い戸を開けると、薄暗い物置に光が差し込む。
最近では誰も中に入っていないからちょっとだけ埃っぽい。
うわ、マスクとか必要かなぁ。
でも、取ってくるのもめんどうだし、早く終わらせちゃお。
さっそく作業に取り掛かる。
そして、ダンボールの山を見て愕然とした。
ぱっと見ただけでも10はある。
絶対にもっとあるはずだ。
こんなのを女にやらせるのか。
ぐちぐちやってても終わらない。
さっさと終わらせよう。
ダンボールは思っていたよりもずっと重くて、一つ運ぶのも一苦労だった。
これをあと10個以上運ぶのか。
すでにやりたくない気持ちでいっぱいだった。
しかも、その中には使わなくなったおもちゃなんかも混ざっていたりして、いちいち確認しなければいけない。
これ、午前中に終わるんだろうか。
そんな不安さえ感じた。
もう、午前中に終わらなかったらお母さんに任せよう。
そう思って、また作業に取り掛かる。
またダンボールを開いて中身を確認する。
あーあ、またおもちゃ入ってるよ。
いい加減うんざりしてきながら空いているダンボールにおもちゃを移していく。
そこで、ふと視界に入ったものに目を奪われた。
小さい頃大事にしていたオルゴール。
中には小物を入れられるようになっている、ちょっと大きめのオルゴールだ。
なくしたと思ったらこんなところにあったのか。
なんだか凄く懐かしい。
確か死んだおじいちゃんがくれたものだ。
どうやら傷はそんなについていないようだ。
汚れは大分凄いけど。
ふたを開けてみると何か入っていた。
なんだろう。
中身を取り出してみる。
中に入っていたのは桜の押し花だった。
押し花が貼ってある画用紙を裏返すとそこには幼い字で「ゆうた」と書かれていた。
これはゆうたって人のものなんだろうか。
よくわかんないや。
押し花を戻そうと、オルゴールの中を覗きこんだとき、もう一枚紙が入っていることに気付いた。
どうやら写真のようだ。
そこに写っていたのは、溢れそうな笑顔をカメラに向けている私と、同じ位の年の男の子だった。
気付いたら走り出していた。
押し花と写真を握りしめて。
あの写真の男の子は絶対あの人だ。
多分あの押し花を私にくれたのもあの人だろう。
そう思ったら急に無性にあの人に逢いたくなった。
だから走り出していた。
あの桜の木がある場所に向かって。
いるかはわからない。
いないかもしれない。
でも、いるかもしれない。
だから、その小さな可能性に賭けてひたすら走った。
ただ、あの人に逢いたくて。
桜の木のところに行くと、あの人がいた。
私のほうには背を向けて、桜を見上げている。
息を整えながらゆっくりあの人に近づく。
あともう少しのところであの人がふりむいた。
「走ってきたの?」
ちょっと驚いているみたいだ。
私はただ頷いた。
「何かあったの?」
「これ、あなた?」
握っていて、ちょっとくしゃくしゃになった写真を差し出す。
思ったよりも声が掠れていた。
相当喉にきたんだろう。
あの人はちょっと驚いた顔をして写真を受け取った。
そして、小さく頷く。
「よく、この写真で俺だってわかったね」
「笑顔が」
「笑顔?」
喉がひりひりして、そこで言葉を切ると、答えに詰まったと思ったのかあの人が続きを促してきた。
「笑顔があなたと同じだったから」
この作品のキーワード
設定されていません
この作家の他の作品
表紙を見る
ボロボロだった
あたしの心を
誰も聞いてくれない
あたしの歌を
愛されないと思っていた
あたしの全てを
受け止めて
抱きしめてくれたのは
どうしようもなく
馬鹿でマヌケで
でも温かいあなたでした
表紙を見る
君の笑顔が好きでした
だから笑っていて下さい
私の小さな願いです
初めての作品です。
駄文ですが、ぜひ呼んでみて下さい。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…