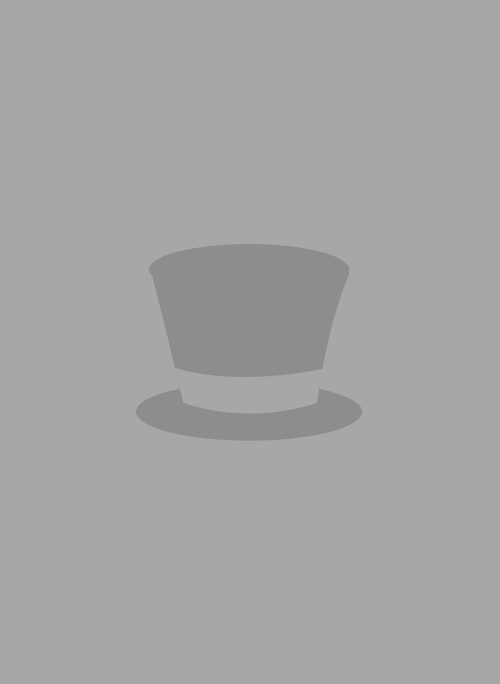壊されたのは、12年前。
切り始めたのは、8年前。
毎日のように、旭 美枝は剃刀を手首に当てた。
最早儀式でしかなく、其処にあった意味は忘却の彼方へ。
軽く引くと、紅い切傷が生まれる。
彼女の手首には同じ様な傷跡が無数に走り、治りかけている傷跡はかさぶたが小さくなっている。
その上に、交差するように紅い線を引いた。
また手首に当てた。
また手首を切った。
何時から、彼女は此れに安心を覚えたのだろうか。
しばらく自傷行為は行われた。
.
ようやく美枝が剃刀を床に投げ出した頃には、時計の針は上に上り、窓の外は暗闇となっていた。
無数に重ねられた小さな切傷から垂れた血液は、ゆっくりと指先を伝い、やがてポタポタと重力に従い床へ落ちる。
美枝は看護婦姿だった。
つまり、仕事を終え、着替えもせずにそのままコートを着て帰って来たのだ。
そして帰って来て呆然と立ち尽す暇もなく、洗面所の剃刀へと手が伸びた。
「……………ふふ」
なぜか出てくる笑み。
私がこんなことしてるって知ったら、きっと皆びっくりするわね。
一週間我慢したからか、傷跡は消えかかっていた。
それを眺めていたら、何だか腹が立った。
数十分前の光景が浮かんだ。
そして剃刀を押し付けた。
――――――――
――――――
―――
夜中になり、我に返った美枝は、とりあえずハンドタオルで傷口を押さえた。
玄関に戻り、放り投げていたバックを手に、リビングへ戻った。
バックから空の弁当を取り出し、流しに置いて
「うそ、切りすぎた……」
ハンドタオルが真っ赤に染まり、シンクに紅い液体が数滴落ちた。
.
無数に重ねられた小さな切傷から垂れた血液は、ゆっくりと指先を伝い、やがてポタポタと重力に従い床へ落ちる。
美枝は看護婦姿だった。
つまり、仕事を終え、着替えもせずにそのままコートを着て帰って来たのだ。
そして帰って来て呆然と立ち尽す暇もなく、洗面所の剃刀へと手が伸びた。
「……………ふふ」
なぜか出てくる笑み。
私がこんなことしてるって知ったら、きっと皆びっくりするわね。
一週間我慢したからか、傷跡は消えかかっていた。
それを眺めていたら、何だか腹が立った。
数十分前の光景が浮かんだ。
そして剃刀を押し付けた。
――――――――
――――――
―――
夜中になり、我に返った美枝は、とりあえずハンドタオルで傷口を押さえた。
玄関に戻り、放り投げていたバックを手に、リビングへ戻った。
バックから空の弁当を取り出し、流しに置いて
「うそ、切りすぎた……」
ハンドタオルが真っ赤に染まり、シンクに紅い液体が数滴落ちた。
.
ハンドタオルを洗濯物に出し、バスタオルを左手首に巻いて弁当箱を水に浸けた。
水に流れていく自分の血液を眺めながら、美枝は服の下から右手を突っ込んだ。
太股辺りに、ざらついた感触があった。
アイツは死んだのよ……
もう、私を苦しめる事は無いの…
そう、私はもう自由だ。
ニヤリと笑った美枝は、視線を冷蔵庫に掛けた小さなコルクボードへ向けた。
其処には写真がびっしりと貼ってあり、全て同じ人間が写りこんでいた。
写真はハートに切り抜かれていたり、その人間と一緒に写っていた女性の顔が破かれ、その上から美枝の顔写真が貼られてるものもある。
笑顔で写るその人間を見た美枝は、華やいだ笑みを浮かべた。
そうよ、私はあなたを手に入れる事ができるわ。
だって、自由になれたのよ。
.
「おはようございます!」
気持ちの良い朝の光に目を細め、美枝は今日も天気である事に幸福を覚えた。
「おはよう、美枝ちゃん」
「おはようございます、狭山さん!」
「旭さん、おはようございます」
「おはよう、香織ちゃん」
廊下ですれちがった患者と挨拶しながら、美枝はある姿を探していた。
今日は朝からのシフトだった。
あの人も同じ。
そう思うだけで、至福だった。
「杏花さんおはよう」
「……今日はユカリよ」
美枝が勤める病院は精神病院だ。
普通の病院と違って、何時患者が暴れるか解らない、自殺しようとするか解らない、逃げ出すか解らない、そんな所だった。
看護婦達にとって精神病院とは「外れくじ」的なもので、大体が一年以内でギブアップしてしまう、大変な場所だ。
そんな「外れくじ」でも、美枝はめげずに働き、今年で4年目になる。
それは自分自身が精神的な問題を抱えていて、患者に感情移入できるからだろうか。
少しずつ、ゆっくりでも前に進もうともがく患者を見ていたら、自分も頑張りたい、なんて考えるようになったのかも知れない。
美枝は、この病院が好きだった。
.
更衣室に入り、左肩に掛けたバックを下ろそうとした。
「…………っ」
持ち手が、手首に瞬間的に圧力をかけた。
力を加えたのは一瞬でも、痛みは後を引く。
袖を捲ったら、血が止まったばかりの傷口が現れた。
不意に、看護婦という、病を治すサポートをする身分でありながら、自傷行為を止められない自分が悲しくなった。
患者さん達だって、「治らなくてもいいんですか?」と厳しく叱っている看護婦が手首を切っていると知ったら、
「じゃあ自分はどうなんだよ」
そう思うに違いない。
泣きそうな顔で立っていた美枝の背後のドアが開き、
「あら? 誰かドアの前に立ってる? ――――――ごめーん、退いて!」
背中にぶつかった更衣室のドアから飛び退き、美枝は背を向けて自分のロッカーに行った。
「あ、旭さん。おはよ」
「うん、おはよう」
同僚の奈津子が、丸っこい顔を笑顔に変えて挨拶した。
「旭さん、今日ひま? 駅前にあるケーキ屋さんの食べ放題クーポン入手したの!」
「ごめん、今日は無理」
「えー? じゃあ明日は?」
「大丈夫だよ」
「じゃ明日行こう明日! 食べまくろう!?」
「了解! 全種類食べまくろう!」
「やたー!―――――あ、そういえば旭さん、河野先生が探してた」
その言葉を聞いた途端、美枝の顔から溶ける様に笑顔が消え、表情が変化した。
奈津子はそんな美枝には気付かずに、
「かっこいいよねー、河野先生! いいなぁ、旭さん河野先生のお気に入りなんだから……」
「でも看護婦としては、だよ。 それに人遣い荒いんだから」
それでもうらやましー! という奈津子の声を背中に受け、美枝は更衣室を出た。
.
「河野先生」
「ああ、旭さん、丁度良かった。―――特別隔離室にこの前入れた仲木戸さんをこちらに戻すの今日だから、カテーテル外すの気を付ける様に。まだ暴れるならそのままね」
「はい」
「あと、杏花ちゃんの催眠療法、午後にやってみようと思う。念のためガンバトロールと鎮静剤用意して」
「はい」
河野圭司は美枝より三歳年上の三十歳だ。
若いが腕は確かで、一時アメリカの病院に居たという。
顔立ちも美しく、看護婦達の憧れの的だ。
「朝から忙しいぞ、ちょっとコーヒーでも一緒にどうだい」
「―――はい」
―――――――――
――――――
―――
コーヒーの自販機を通り過ぎ、角を曲がって監視カメラの死角に入った。
階段の下に扉がひとつあり、その中は何もない、使われていない部屋だった。
その部屋のただひとつだけの鍵をポケットから出した河野は、素早く鍵を開けて美枝と中に入った。
部屋は二畳半程で、四方はコンクリートの壁が囲み、唯一、光を入れる窓は三メートル程高い所にあった。
「美枝……」
かすれた声で呟き、河野は美枝を後ろから抱き締めた。
美枝は、耳元で聞こえる河野の荒い呼吸に少し引いたが、目を閉じてその呼吸だけに神経を尖らせたら、だんだん身体の中心が潤うのが嫌でも解った。
美枝は河野の腕の中で身体を回転させて、河野と向き合うと、どちらからともなく唇を重ね合わせた。
.
さすがにそういう経験位はある。
美枝は、自分の中で果てた河野の首筋を撫でた。
男の割には細い首。
何とも形容し難い気持ちになり、美枝はむさぼる様に首筋に唇を押し当てた。
―――――――――
――――――
―――
「よし、じゃあ今から仲木戸さんの様子を見に行って―――」
「河野先生!」
「はい。―――ああ、有藤先生」
「探してたんですよ!203の小中さんが今日の検査受けないってゴネて……。良ければちょっと手伝って下さらない?」
「あ、良いですよ。―――ごめん、仲木戸さん頼む」
「はい」
事を終え、河野と美枝は他の看護婦達と共に特別隔離室へ向かうところだった。
そこを女医の有藤が呼び止め、河野を連れて行ってしまった。
「バレバレ」
特別隔離室への廊下を歩きながら、美枝の耳元で奈津子が言った。
「有藤、絶対河野先生を狙ってる。どうせ、手伝ってくれたお礼〜なんて口実で食事とかに誘うつもりだよ。昨日も何か帰りに一緒にどっか行ってたじゃん?―――アレで何かあったのかな」
なかなかどうして、奈津子と自分の考えが同じだったなんて思いもよらなかった美枝は、
「――――っ」
嫌な予感に目を細めた。
.
昨日、河野が有藤の車に一緒に乗ったのを、美枝は目撃した。
試しに河野と有藤の家前を通って確認したが、二軒とも、人が帰ってきた気配は無かった。
車のハンドルを握る左手の薬指で、指輪が光っていた。
河野が美枝にプレゼントした指輪だった。
その指輪が放つ鈍い光を見ていると、指先からだんだんと体が冷えていくのが解った。
そして家に帰って、我慢していた自傷行為をした。
今日も、二人で出かけるのだろうか?
何処に?
ホテル?
レストラン?
「急患が入った」と電話して嫌がらせてやろうか。
いや、そんなことしなくていい。
後で、殺っちゃえばいいんだ。
.
午後22時。
美枝は自宅のリビングのソファに座り、じっと目の前のテーブルに乗せてある携帯を睨んでいた。
「……………」
根拠は無い。
だが、必ず河野が電話してくる、という確信があった。
美枝の頭の中で河野と有藤が愛し合っている光景が作り出され、美枝の神経を刺激した。
いらついた美枝は立ち上がると、昨日床に投げたままの剃刀を拾い上げた。
そして服の左腕を捲ると、傷だらけの手首に――――
《プルルルルッ》
いきなり鳴りだした携帯の電子音に反応して、美枝は剃刀を落とした。
電子音は美枝の眠りかけていた記憶を呼びさました。
―――――――――
――――――
―――
「美枝、一緒にお風呂に入ろうか」
父親がそういって当時10歳だった少女に微笑んだ。
少女は、何時もと変わらぬ父親の笑みに、嬉しそうに笑いながら頷いた。
.
この作品のキーワード
設定されていません
この作家の他の作品
表紙を見る
モバスペBOOKより。
作者の妄想炸裂ですごめんなさい。
コピペしてくだけなのですぐ完結するかと。
話が進むにつれ、若干濡れ場がありますのでご注意を。
なるたけぼかしてはいますが。
表紙を見る
何時から
殺したのかな
何時から
狂ったのかな
(伏緒ワールド全開、ギャグとミステリがドッキング)
(本元はモバスペBOOKにあります。HTMLタグ等に手間取ってこちらへの更新は亀)
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…