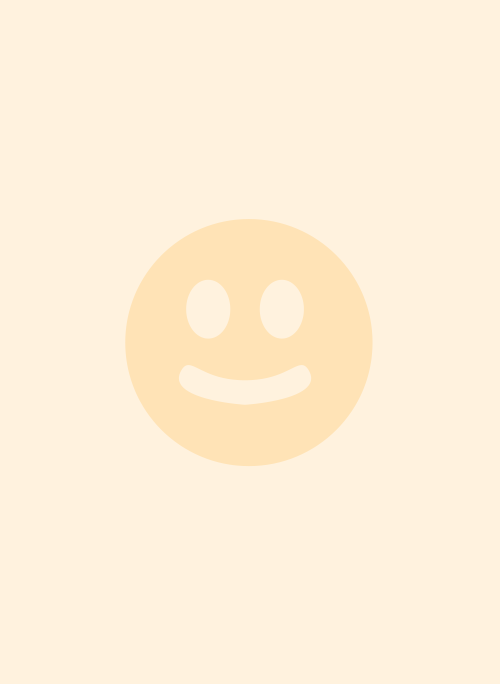「花蓮好きだ」
「うん」
好きな人に好きだと言われることはとても嬉しいことのはずなのに。
「花蓮、何作ってるんだ」
「秘密」
「マフラーとかにしかみえないんだけど」
「もうすぐクリスマスだからね。この青と黒は晋太郎兄ちゃんので、オレンジと黄色はタツの。毛糸沢山もらったから。光臣くんにも作ってあげるね」
「ありがとう」
君は私が作ったものなんか使わないのは知ってる。
あの人からもらったマフラーをずっと大切に使ってる。
君が私を好きだと言うのは、自分に言い聞かせているから。
私が君を好きだと言う気持ちとは決定的な所が違っている。
私とあの人は少し似てるから、君は傍に置いて好きだと言ってくれてるだけ。
分かっていても離れられないくらい、光臣くんが好きなんだ。
でも好きでもつらい
苦しい
何度も好きだと言われる度、胸が痛いよ
「花蓮、クリスマスイヴは空いてるか?」
「うん」
「出かけないか?」
「良いの?」
「何遠慮してるんだ」
いつも人に奢らせてる癖にと笑って頭を撫でられた。
光臣くんが笑った時に、普段より顔が幼くなるのが好き。
男のくせにやたらと綺麗な顔してるのに口が悪くて、最初はケンカばっかりだったけど、いつの間にか好きになってた。
器用な癖に、へんな所が融通がきかなかったりして、お互い譲れなくて大ケンカした後に好きだと言われた。
「夏は部活で秋は課外詰め、冬は受験でますます構ってやれなくなるからな」
「私にはその気持ちわかんなーい」
既に大学の推薦が決まっている私の少しの皮肉に光臣くんは怒った顔をしてほっぺを抓られた。
「これだから推薦組は腹が立つんだよ」
「でも課題がいっぱいでたよ」
「絵を描くことはお前の趣味みたいなもんだろ。冬休みの間に終わらせてるくせに」
私は美大の推薦をもらったばかりだ。
他の大学受験より早く決まった分、絵の課題が山のように出された。
でも三分の二は終わってる。
お正月前には終わりそうだなと考えていると
「だからオレも息抜きしたいから、映画でも見に行こうぜ」
「うん。行く」
「じゃあ前の日に連絡するからな。ケータイチェックしておけよ」
「うん。分かった」
ケータイの必要性なんて光臣くんと付き合う前は考えても見なかった。
光臣くんとお揃いのケータイ。
ついている花のモチーフのストラップは私の宝物。私の誕生日プレゼントだった。
「明日、3時に駅の時計台の下の所で待ってろよ」
「うん。分かった」
電話でそう約束したはずなのに、1時間経っても光臣くんはまだこない。
連絡も来ない。
クリスマスイブに一人で突っ立ている私に冷やかすような目が向けられる。
何でクリスマスイヴが休みにぶつかるんだと文句を言いたくなった。
電話をしてもメールをしても光臣くんには繋がらない。
どうして…
約束したのに
寒い。
雪も降って来た。
ひらひら落ちてくる雪に埋もれて消えてしまいたい。
私が消えたら彼は探してくれるだろうか?
もしかしたら、あの人と一緒にいるのかもしれない。
千春先輩。私達の一つ上の先輩で、みんなから好かれている優しい人。
光臣くんとは幼なじみだと聞いた。
二人は付き合っていたけど千春先輩が大学に進学した頃に別れたと誰かが言っていた。
私と付き合い始めたのも千春先輩に似ているからだって、身代わりだって、彼を好きな女子に言われた。
光臣くんがそんにことをするわけないと信じたいけど信じられなくなってくる。
あれから3時間経っても光臣くんも来ないし、連絡もない。
手袋をしている指先も感覚がなくなってきている。
「色気づいてワンピースなんてはいて来るんじゃなかった。もう帰る。達久にお風呂ためておいてもらおう」
帰る決意を固めて弟に電話をかけようとケータイを開こうとしたら、指に感覚がなくて地面に落ちてしまった。
コンクリートの上に雪が積もっているせいか数メートル滑って行ってしまった。
「ケータイまで私をばかにしてんのかよ、このやろう」
滑舌もおかしくなってきている。
ケータイを拾おうと足を出すと同時に誰かが拾ってくれた。
「ありがとうございます」
お礼を言うと
「花蓮さん何してるんですか?せっかくのクリスマスイブに」
「高耶くん」
後輩の最上高耶くんが私のケータイを拾ってくれていた。
高耶くんは千春先輩の弟だ。
「明石さんはどうしたんですか?せっかくのクリスマスイブだってのに」
「連絡つかない。ドタキャンされたことにする」
「相変わらず最低なやろうですね」
高耶くんは光臣くんのことがあまり好きではないみたい。
部活とか委員会とか同じなのに。