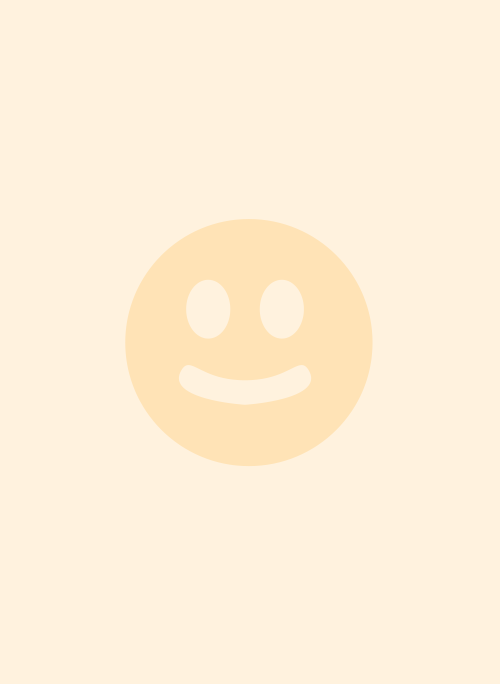終業式の時、花蓮の姿を見た。
一年ぶりぐらいじゃないかと思える程、距離感と懐かしさを覚えた。
髪を耳の上で結っているために白いうなじが見えた。
式の最中、眠いのか何度も欠伸をしているとこを見た。
校長の話しなんて聞くわけもなくオレは花蓮を見続けていた。
オレの視線に気づいたのか、花蓮がこっちを向いた。
あろうことか、欠伸を見せただけでまた前を向いてしまった。
情緒のかけらもあったもんじゃない。
自分の顔が眠たくなるようなものだと言われたような気がした。
一年ぶりぐらいじゃないかと思える程、距離感と懐かしさを覚えた。
髪を耳の上で結っているために白いうなじが見えた。
式の最中、眠いのか何度も欠伸をしているとこを見た。
校長の話しなんて聞くわけもなくオレは花蓮を見続けていた。
オレの視線に気づいたのか、花蓮がこっちを向いた。
あろうことか、欠伸を見せただけでまた前を向いてしまった。
情緒のかけらもあったもんじゃない。
自分の顔が眠たくなるようなものだと言われたような気がした。
ホームルームの後、急いで花蓮の教室に向かった。
花蓮は文系でオレは理系、教室は別棟で離れていたから、走った。
部活でもこんなペースで走ったことはなかった。
「いない?」
花蓮は既に教室にいないと言われた。
「うん。美術室に作品を取りに行くって。しばらく絵を描いてから帰る…」
みなまで聞く前に走った。
美術室の前に立って呼吸を整える。
ドアをゆっくり開けると美術室の奥、窓際に花蓮はいた。
キャンバスの前に座って、手を動かしている。
放課後、夕日のさす教室の中で絵を描いている姿が好きだった。
最初に見せてもらったのはオレ達が部活で走ってる絵だ。
「夢中になってたり真剣になってるとこは描いても楽しい」
と言っていた。
何がきっかけなんて忘れたけど、夢中になっている花蓮の姿をオレは好きになったんだ。
花蓮は文系でオレは理系、教室は別棟で離れていたから、走った。
部活でもこんなペースで走ったことはなかった。
「いない?」
花蓮は既に教室にいないと言われた。
「うん。美術室に作品を取りに行くって。しばらく絵を描いてから帰る…」
みなまで聞く前に走った。
美術室の前に立って呼吸を整える。
ドアをゆっくり開けると美術室の奥、窓際に花蓮はいた。
キャンバスの前に座って、手を動かしている。
放課後、夕日のさす教室の中で絵を描いている姿が好きだった。
最初に見せてもらったのはオレ達が部活で走ってる絵だ。
「夢中になってたり真剣になってるとこは描いても楽しい」
と言っていた。
何がきっかけなんて忘れたけど、夢中になっている花蓮の姿をオレは好きになったんだ。
けど、今日はそこにいたのは花蓮だけじゃなかった。
「花蓮さん何を描いているんですか?」
「んー?なんとなく描いてだけ」
「どこかの風景ですか?花が沢山だ」
「そうかも」
高耶が花蓮の後ろに張り付いている。
「花蓮さん、帰りに何か食っていきませんか?」
「良いよ〜」
「花蓮さんは何が好きですか?ケーキは好きですか?」
「大好き。苺のケーキ大好き」
「美味いケーキ屋知ってるんで、そこいきましょう」
「クリスマスの日はありがとう、タツがゲームもらったってはしゃいでたよ。でも良かったの?」
「構いませんよ。中古なんで」
恋人同士の会話に見えた。
オレの彼女なのに。
「花蓮さんの髪ひわふわしてますね。可愛い」
「纏めるのが大変なんだよ。からまるし、切った方が良いかな?」
「そんなことないですよ。くるくるのふわふわでオレはこの長さが好きです」
「花蓮さん何を描いているんですか?」
「んー?なんとなく描いてだけ」
「どこかの風景ですか?花が沢山だ」
「そうかも」
高耶が花蓮の後ろに張り付いている。
「花蓮さん、帰りに何か食っていきませんか?」
「良いよ〜」
「花蓮さんは何が好きですか?ケーキは好きですか?」
「大好き。苺のケーキ大好き」
「美味いケーキ屋知ってるんで、そこいきましょう」
「クリスマスの日はありがとう、タツがゲームもらったってはしゃいでたよ。でも良かったの?」
「構いませんよ。中古なんで」
恋人同士の会話に見えた。
オレの彼女なのに。
「花蓮さんの髪ひわふわしてますね。可愛い」
「纏めるのが大変なんだよ。からまるし、切った方が良いかな?」
「そんなことないですよ。くるくるのふわふわでオレはこの長さが好きです」
高耶の手が一束掬い、唇にあてた。
見ていられなかった。
教室の中に入って、花蓮から高耶を引き離した。
「あれ?何のようですか」
「光臣くん?」
花蓮は驚いた顔をしていたが、高耶はまるで気づいていたかのような顔をしている。
「花蓮、話しがある。高耶、お前帰れ」
「彼氏気取りですか?」
「気取ってねぇ。彼氏だ。オレの女に手を出すな」
「ドタキャンしたくせに?他の女といたくせに、それでも恋人だと言い切りますか?」
見ていられなかった。
教室の中に入って、花蓮から高耶を引き離した。
「あれ?何のようですか」
「光臣くん?」
花蓮は驚いた顔をしていたが、高耶はまるで気づいていたかのような顔をしている。
「花蓮、話しがある。高耶、お前帰れ」
「彼氏気取りですか?」
「気取ってねぇ。彼氏だ。オレの女に手を出すな」
「ドタキャンしたくせに?他の女といたくせに、それでも恋人だと言い切りますか?」
言い訳なんてしない。
事実だ。
だから謝り倒す。許して貰えるまで。
好きなんだとも何度も告げる。
「オレは花蓮が好きだ。美術バカな所も、料理が上手いとこも優しいとこ、ふわふわの髪もいがいと胸がでかいとこも全部好きだ」
「ぷっ、あははは、あんたバカですか?」
高耶は壊れた様に笑い出した。
「るせぇ、こっちはマジだ」
「分かってますよ。今回は退きますよ。でも次は全力で奪いますよ。オレだけじゃない、先輩の後釜を狙ってるやつは沢山いますよ」
女受けする笑顔と不適な台詞を残して高耶は出て行った。
事実だ。
だから謝り倒す。許して貰えるまで。
好きなんだとも何度も告げる。
「オレは花蓮が好きだ。美術バカな所も、料理が上手いとこも優しいとこ、ふわふわの髪もいがいと胸がでかいとこも全部好きだ」
「ぷっ、あははは、あんたバカですか?」
高耶は壊れた様に笑い出した。
「るせぇ、こっちはマジだ」
「分かってますよ。今回は退きますよ。でも次は全力で奪いますよ。オレだけじゃない、先輩の後釜を狙ってるやつは沢山いますよ」
女受けする笑顔と不適な台詞を残して高耶は出て行った。
「花蓮」
彼女の名前を呼ぶと返事はないが、花蓮は顔を上げてオレを見た。
二重の大きな目、黒目が少しだけ茶色がかっている。
リップだけ塗ってある化粧気のない綺麗な顔。
好きだ。
細くて小さい、どんなデカイもの作ってしまう手。
好きだ。
オレを優しく包んでくれて、直情的な心。
好きだ。
「光臣くん?」
オレを呼んでくれる声。
好きだ。
誘われるように口づけた。
彼女の名前を呼ぶと返事はないが、花蓮は顔を上げてオレを見た。
二重の大きな目、黒目が少しだけ茶色がかっている。
リップだけ塗ってある化粧気のない綺麗な顔。
好きだ。
細くて小さい、どんなデカイもの作ってしまう手。
好きだ。
オレを優しく包んでくれて、直情的な心。
好きだ。
「光臣くん?」
オレを呼んでくれる声。
好きだ。
誘われるように口づけた。
最初何をされてるか分からなかった。
とても久々なことだから。
高耶くんに聞いていた。光臣くんは約束の日に千春先輩と一緒にいたって。
やっぱり当たっていた。
こういう時の勘はよく当たる。
だから涙すらでなかった。
「知ってるよ。だって付き合ってから一度しかキスしてない。きっと唇の感触が千春先輩と似てるからだよ」
「それでもあいつが好きなんですか」
「多分」
「バカな人ですね」
「そうだね。覚悟はしてたよ」
高耶くんに絵をあの絵を見せた。
とても久々なことだから。
高耶くんに聞いていた。光臣くんは約束の日に千春先輩と一緒にいたって。
やっぱり当たっていた。
こういう時の勘はよく当たる。
だから涙すらでなかった。
「知ってるよ。だって付き合ってから一度しかキスしてない。きっと唇の感触が千春先輩と似てるからだよ」
「それでもあいつが好きなんですか」
「多分」
「バカな人ですね」
「そうだね。覚悟はしてたよ」
高耶くんに絵をあの絵を見せた。
ガラス越しの君と僕
付き合い出してからすぐに描いた絵。
毎日見ながら、自分に言い聞かせた。
すぐに終わりがくる。
自分はあの人にはなれない。
だから彼が私から離れて行くまでの毎日を大切にしようって。
「なら調度良いや。その誓いオレに下さい」
高耶くんの声が引くなった。マフラーを欲しいとねだられた時みたいだ。
付き合い出してからすぐに描いた絵。
毎日見ながら、自分に言い聞かせた。
すぐに終わりがくる。
自分はあの人にはなれない。
だから彼が私から離れて行くまでの毎日を大切にしようって。
「なら調度良いや。その誓いオレに下さい」
高耶くんの声が引くなった。マフラーを欲しいとねだられた時みたいだ。
「オレはあなたが好きです。あいつみたいに誰かを花蓮さんに重ねるあほなことはしない。だからいつかのための誓いをオレに下さい。あなたが死んでもあなたを好きでいますから」
クリスマスの日の告白に私は何も答えることは出来なかった。
「半永久的に有効なんでいつでも返事をください」
高耶くんは一方的に話して帰って行った。
クリスマスの日の告白に私は何も答えることは出来なかった。
「半永久的に有効なんでいつでも返事をください」
高耶くんは一方的に話して帰って行った。
この作品のキーワード
設定されていません
この作家の他の作品
表紙を見る
乙女ゲームってなんのこと?
悪役令嬢ってなんのこと?
婚約者の姉の奇行に毎日のように振り回させるようになってしまったマリーベル、彼女は平穏な日常を取り戻せるのか?
表紙を見る
誰かを好きになって、その人に自分を好きになってもらう、たったそれだけのことなのに
それが一番難しい。ってことを私達は思いしる。
表紙を見る
オレの妹は小さい頃から破天荒だった。
彼女の通った道には数々の伝説が出来上がっていった。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…