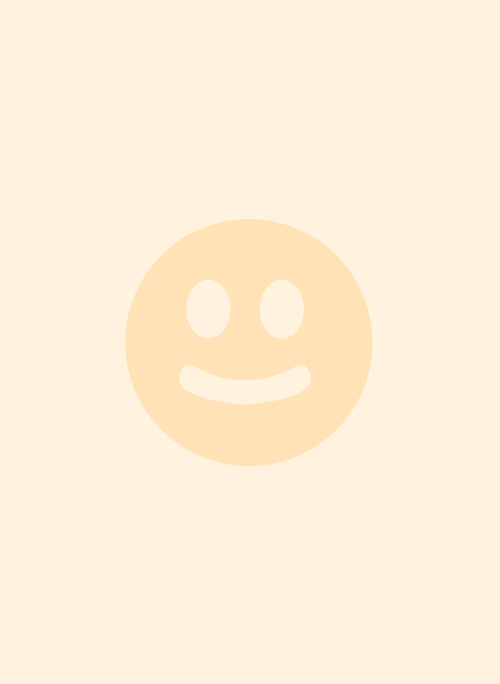「おい!花蓮はどこに行ったんだ?」
どんどんドアを叩くと達久はまた出て来て
「姉ちゃんは大学の先生と広島だって」
「広島!何で?」
「絵を描く仕事だって。じゃあね、これから高耶兄ちゃんたちとゲームするから」
高耶が何でいるんだ。
花蓮の絵を描く仕事ってなんだ?
昨日のうちに何が起きたんだ。
「達久!もっと詳しく言え!達久」
何度もインターホンを鳴らしたり、ドアを叩いたりしたが達久は出てこい。
そのかわりに…
「やかましい!」
花蓮の兄貴が出て来た。
目を合わせた瞬間殴られた。
「うるせぇんだよ、ちんこんちんこん卑猥な音鳴らし続けてんじゃねぇよ!猥褻物陳列罪でしょっぴいて貰うからな」
そんなのおのまとぺの表現の違いだろうが、インターホンがそういう風に聞こえてるあんたの耳が猥褻物だと言いたいが、高耶と同じ所を殴られて、痛みで声がでない。
どんどんドアを叩くと達久はまた出て来て
「姉ちゃんは大学の先生と広島だって」
「広島!何で?」
「絵を描く仕事だって。じゃあね、これから高耶兄ちゃんたちとゲームするから」
高耶が何でいるんだ。
花蓮の絵を描く仕事ってなんだ?
昨日のうちに何が起きたんだ。
「達久!もっと詳しく言え!達久」
何度もインターホンを鳴らしたり、ドアを叩いたりしたが達久は出てこい。
そのかわりに…
「やかましい!」
花蓮の兄貴が出て来た。
目を合わせた瞬間殴られた。
「うるせぇんだよ、ちんこんちんこん卑猥な音鳴らし続けてんじゃねぇよ!猥褻物陳列罪でしょっぴいて貰うからな」
そんなのおのまとぺの表現の違いだろうが、インターホンがそういう風に聞こえてるあんたの耳が猥褻物だと言いたいが、高耶と同じ所を殴られて、痛みで声がでない。
「花蓮とのことはとやかく言わん。花蓮はいつ帰ってくるかわからんし今日は帰れ。受験生なんだろ」
勉強しろと諭されるように言って彼はドアを閉めた。
高耶がいるなら昨日のことは知られているんだろう。
あの人は妹の花蓮を大切にしてるから腕一本ぐらい折られる覚悟だったのに。
いや彼ははらわたが煮え繰り返るくらい怒っているんだ。
冷静さを自分で言い聞かせていたんだろうな。
あの人が大人じゃなかったらオレは殺されてたんだろうな。
勉強しろと諭されるように言って彼はドアを閉めた。
高耶がいるなら昨日のことは知られているんだろう。
あの人は妹の花蓮を大切にしてるから腕一本ぐらい折られる覚悟だったのに。
いや彼ははらわたが煮え繰り返るくらい怒っているんだ。
冷静さを自分で言い聞かせていたんだろうな。
あの人が大人じゃなかったらオレは殺されてたんだろうな。
帰り道がやけに寒く感じられた。
昨日、花蓮はこんな中を待っていてくれたんだ。
今になって気づくなんて、最悪だ。
無くしてから初めて気がつくなんてベタ過ぎる。
過去の恋愛に夢中になって、本当に大切なことを見失うなんて。
昨日会いに行けば良かった。
謝り倒してクリスマスを祝えば良かった。
ポケットの中の花蓮のケータイが重く感じた。
開くと花蓮が描いた絵が待受画面になっていた。
ガラスの壁を挟んで寄り添う少女と少年。
手を重ね、お互いを見つめているはずなのに、幸せそうに見えない。
ガラス越しだからだろうか?
いや…
気持ちが通じてないからだ。
少年の目が少女を通り越しているんだ。
少女の目は少年を真っ直ぐ見ている。
少女は少年の心が自分にないことを気づいているんだ。
昨日、花蓮はこんな中を待っていてくれたんだ。
今になって気づくなんて、最悪だ。
無くしてから初めて気がつくなんてベタ過ぎる。
過去の恋愛に夢中になって、本当に大切なことを見失うなんて。
昨日会いに行けば良かった。
謝り倒してクリスマスを祝えば良かった。
ポケットの中の花蓮のケータイが重く感じた。
開くと花蓮が描いた絵が待受画面になっていた。
ガラスの壁を挟んで寄り添う少女と少年。
手を重ね、お互いを見つめているはずなのに、幸せそうに見えない。
ガラス越しだからだろうか?
いや…
気持ちが通じてないからだ。
少年の目が少女を通り越しているんだ。
少女の目は少年を真っ直ぐ見ている。
少女は少年の心が自分にないことを気づいているんだ。
花蓮は何を思ってこの絵を描いたんだろう。
自分ではない女を見ている男を思い続けるのはどれほど辛いのだろうか。
オレだったら発狂してるな…
現にオレの知らない男といることに苛立っている。
こんな男でも花蓮はまだ好きでいてくれているのか?
聞く術は残されてなくて、その事実が辛くてケータイを閉じた。
自分ではない女を見ている男を思い続けるのはどれほど辛いのだろうか。
オレだったら発狂してるな…
現にオレの知らない男といることに苛立っている。
こんな男でも花蓮はまだ好きでいてくれているのか?
聞く術は残されてなくて、その事実が辛くてケータイを閉じた。
花蓮は大学の課題優先を認められて、クリスマスの後から学校に来ていない。
学校もそんな異例を許している。
それだけ花蓮は特別な人間だったことを思い知るが、オレにとっては大事な女以外の何者でもなかった。
この思いを伝えたいが、会うことなく、終業式を向かえた。
「花蓮、学校きてるの?」
「やっぱり終業式はでないとね」
「なんか寝不足みたいな顔してて、課題多いって言ってたけど年が明ける前に終わらせてやるって張り切ってたよ。今度似顔絵描いてくれるって」
「ホントに?花蓮、おしるこ好きだったよね?山ほどおごってあげよ」
「その前にうちらも合格しないと」
「そうだね」
花蓮の友達の話しを盗み聞きするほど花蓮という単語に敏感になっている。
学校に来ているなら今日がチャンスだ。
いや、今日しかない!
学校もそんな異例を許している。
それだけ花蓮は特別な人間だったことを思い知るが、オレにとっては大事な女以外の何者でもなかった。
この思いを伝えたいが、会うことなく、終業式を向かえた。
「花蓮、学校きてるの?」
「やっぱり終業式はでないとね」
「なんか寝不足みたいな顔してて、課題多いって言ってたけど年が明ける前に終わらせてやるって張り切ってたよ。今度似顔絵描いてくれるって」
「ホントに?花蓮、おしるこ好きだったよね?山ほどおごってあげよ」
「その前にうちらも合格しないと」
「そうだね」
花蓮の友達の話しを盗み聞きするほど花蓮という単語に敏感になっている。
学校に来ているなら今日がチャンスだ。
いや、今日しかない!
終業式の時、花蓮の姿を見た。
一年ぶりぐらいじゃないかと思える程、距離感と懐かしさを覚えた。
髪を耳の上で結っているために白いうなじが見えた。
式の最中、眠いのか何度も欠伸をしているとこを見た。
校長の話しなんて聞くわけもなくオレは花蓮を見続けていた。
オレの視線に気づいたのか、花蓮がこっちを向いた。
あろうことか、欠伸を見せただけでまた前を向いてしまった。
情緒のかけらもあったもんじゃない。
自分の顔が眠たくなるようなものだと言われたような気がした。
一年ぶりぐらいじゃないかと思える程、距離感と懐かしさを覚えた。
髪を耳の上で結っているために白いうなじが見えた。
式の最中、眠いのか何度も欠伸をしているとこを見た。
校長の話しなんて聞くわけもなくオレは花蓮を見続けていた。
オレの視線に気づいたのか、花蓮がこっちを向いた。
あろうことか、欠伸を見せただけでまた前を向いてしまった。
情緒のかけらもあったもんじゃない。
自分の顔が眠たくなるようなものだと言われたような気がした。
ホームルームの後、急いで花蓮の教室に向かった。
花蓮は文系でオレは理系、教室は別棟で離れていたから、走った。
部活でもこんなペースで走ったことはなかった。
「いない?」
花蓮は既に教室にいないと言われた。
「うん。美術室に作品を取りに行くって。しばらく絵を描いてから帰る…」
みなまで聞く前に走った。
美術室の前に立って呼吸を整える。
ドアをゆっくり開けると美術室の奥、窓際に花蓮はいた。
キャンバスの前に座って、手を動かしている。
放課後、夕日のさす教室の中で絵を描いている姿が好きだった。
最初に見せてもらったのはオレ達が部活で走ってる絵だ。
「夢中になってたり真剣になってるとこは描いても楽しい」
と言っていた。
何がきっかけなんて忘れたけど、夢中になっている花蓮の姿をオレは好きになったんだ。
花蓮は文系でオレは理系、教室は別棟で離れていたから、走った。
部活でもこんなペースで走ったことはなかった。
「いない?」
花蓮は既に教室にいないと言われた。
「うん。美術室に作品を取りに行くって。しばらく絵を描いてから帰る…」
みなまで聞く前に走った。
美術室の前に立って呼吸を整える。
ドアをゆっくり開けると美術室の奥、窓際に花蓮はいた。
キャンバスの前に座って、手を動かしている。
放課後、夕日のさす教室の中で絵を描いている姿が好きだった。
最初に見せてもらったのはオレ達が部活で走ってる絵だ。
「夢中になってたり真剣になってるとこは描いても楽しい」
と言っていた。
何がきっかけなんて忘れたけど、夢中になっている花蓮の姿をオレは好きになったんだ。
けど、今日はそこにいたのは花蓮だけじゃなかった。
「花蓮さん何を描いているんですか?」
「んー?なんとなく描いてだけ」
「どこかの風景ですか?花が沢山だ」
「そうかも」
高耶が花蓮の後ろに張り付いている。
「花蓮さん、帰りに何か食っていきませんか?」
「良いよ〜」
「花蓮さんは何が好きですか?ケーキは好きですか?」
「大好き。苺のケーキ大好き」
「美味いケーキ屋知ってるんで、そこいきましょう」
「クリスマスの日はありがとう、タツがゲームもらったってはしゃいでたよ。でも良かったの?」
「構いませんよ。中古なんで」
恋人同士の会話に見えた。
オレの彼女なのに。
「花蓮さんの髪ひわふわしてますね。可愛い」
「纏めるのが大変なんだよ。からまるし、切った方が良いかな?」
「そんなことないですよ。くるくるのふわふわでオレはこの長さが好きです」
「花蓮さん何を描いているんですか?」
「んー?なんとなく描いてだけ」
「どこかの風景ですか?花が沢山だ」
「そうかも」
高耶が花蓮の後ろに張り付いている。
「花蓮さん、帰りに何か食っていきませんか?」
「良いよ〜」
「花蓮さんは何が好きですか?ケーキは好きですか?」
「大好き。苺のケーキ大好き」
「美味いケーキ屋知ってるんで、そこいきましょう」
「クリスマスの日はありがとう、タツがゲームもらったってはしゃいでたよ。でも良かったの?」
「構いませんよ。中古なんで」
恋人同士の会話に見えた。
オレの彼女なのに。
「花蓮さんの髪ひわふわしてますね。可愛い」
「纏めるのが大変なんだよ。からまるし、切った方が良いかな?」
「そんなことないですよ。くるくるのふわふわでオレはこの長さが好きです」
高耶の手が一束掬い、唇にあてた。
見ていられなかった。
教室の中に入って、花蓮から高耶を引き離した。
「あれ?何のようですか」
「光臣くん?」
花蓮は驚いた顔をしていたが、高耶はまるで気づいていたかのような顔をしている。
「花蓮、話しがある。高耶、お前帰れ」
「彼氏気取りですか?」
「気取ってねぇ。彼氏だ。オレの女に手を出すな」
「ドタキャンしたくせに?他の女といたくせに、それでも恋人だと言い切りますか?」
見ていられなかった。
教室の中に入って、花蓮から高耶を引き離した。
「あれ?何のようですか」
「光臣くん?」
花蓮は驚いた顔をしていたが、高耶はまるで気づいていたかのような顔をしている。
「花蓮、話しがある。高耶、お前帰れ」
「彼氏気取りですか?」
「気取ってねぇ。彼氏だ。オレの女に手を出すな」
「ドタキャンしたくせに?他の女といたくせに、それでも恋人だと言い切りますか?」
この作品のキーワード
設定されていません
この作家の他の作品
表紙を見る
乙女ゲームってなんのこと?
悪役令嬢ってなんのこと?
婚約者の姉の奇行に毎日のように振り回させるようになってしまったマリーベル、彼女は平穏な日常を取り戻せるのか?
表紙を見る
誰かを好きになって、その人に自分を好きになってもらう、たったそれだけのことなのに
それが一番難しい。ってことを私達は思いしる。
表紙を見る
オレの妹は小さい頃から破天荒だった。
彼女の通った道には数々の伝説が出来上がっていった。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…