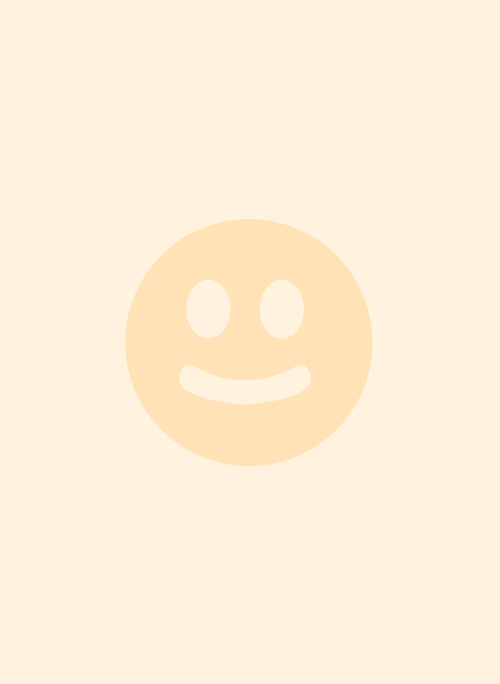「バカ、弟も兄ちゃんもいるよ」
「冗談ですよ」
家の中に入ると、弟が走ってきた。小学生4年生の達久は何度いっても、半袖とハーフパンツで真冬でも暮らしている。
「姉ちゃんお帰り。あれ?この間とは違う男だ」
「おう、坊主。初対面の相手にはまず挨拶だろ。こんばんわ」
高耶くんは達久の頭を掴んで挨拶をした。その手の力がよっぽど痛いのか、達久は高耶くんの手を掴みながら挨拶をかえした。
顔は笑顔だけど、目が笑ってない。
「可愛い弟さんですね」
「あんたが弟じゃなくて良かったよ。あがって」
「姉ちゃん。先生来てるよ」
「担任が?何しに?」
「違うよ。大学の先生って言ってた」
大学の先生が一体何のようだろう?入学取り消しとかじゃなければ良いが、と思いながらリビングに向かった。
「花蓮、遅いぞ。あ?誰だそいつ、この間とは違う男だな」
5つ上の兄の晋太郎は無遠慮に高耶くんを見ている。
「花蓮さんの兄弟ってストレートですね」
言葉も感情もストレートなうちの兄弟たちには思わず苦笑いをするしかなかった。
「冗談ですよ」
家の中に入ると、弟が走ってきた。小学生4年生の達久は何度いっても、半袖とハーフパンツで真冬でも暮らしている。
「姉ちゃんお帰り。あれ?この間とは違う男だ」
「おう、坊主。初対面の相手にはまず挨拶だろ。こんばんわ」
高耶くんは達久の頭を掴んで挨拶をした。その手の力がよっぽど痛いのか、達久は高耶くんの手を掴みながら挨拶をかえした。
顔は笑顔だけど、目が笑ってない。
「可愛い弟さんですね」
「あんたが弟じゃなくて良かったよ。あがって」
「姉ちゃん。先生来てるよ」
「担任が?何しに?」
「違うよ。大学の先生って言ってた」
大学の先生が一体何のようだろう?入学取り消しとかじゃなければ良いが、と思いながらリビングに向かった。
「花蓮、遅いぞ。あ?誰だそいつ、この間とは違う男だな」
5つ上の兄の晋太郎は無遠慮に高耶くんを見ている。
「花蓮さんの兄弟ってストレートですね」
言葉も感情もストレートなうちの兄弟たちには思わず苦笑いをするしかなかった。
「柚木さんこんにちは。急にお邪魔してすまないね。クリスマスイブなのに、お兄さんたちだけに伝言を伝えて帰ろうと思ったんだけど、調度良かった」
柔和な感じの30代後半ぐらいの男の人がソファから立ち上がった。
「藤原先生」
大学入試の時にお世話になった先生だ。私は来年から彼から色々教えてもらうことになっている。
「すみません。お待たせしちゃって」
「良いんだよ。こっちも連絡をしないで着てしまったからね。本題に入るけどね、明日
時間あるかな?君にやって欲しい仕事があるんだ」
「はい?」
行き成りそういわれても頭が付いていかない。
「僕の知り合いがね、君に絵を書いて欲しいそうなんだ。今度、喫茶店を開くに当って、メインの絵が欲しいそうなんだ。それを君にお願いしたいっていうんだ。どうかな?明日にでも、一緒に行って話しだけでも聞いてもらえないだろうか?」
「仕事ってことは、お金とかもらえるんですか?」
高耶くんが聞くと、藤原先生は頷いた。
「もちろんだよ。コレは仕事としてお願いするんだから、向うもそのつもりだといっていたよ」
「姉ちゃん凄い!もう絵描きさんになるの?」
柔和な感じの30代後半ぐらいの男の人がソファから立ち上がった。
「藤原先生」
大学入試の時にお世話になった先生だ。私は来年から彼から色々教えてもらうことになっている。
「すみません。お待たせしちゃって」
「良いんだよ。こっちも連絡をしないで着てしまったからね。本題に入るけどね、明日
時間あるかな?君にやって欲しい仕事があるんだ」
「はい?」
行き成りそういわれても頭が付いていかない。
「僕の知り合いがね、君に絵を書いて欲しいそうなんだ。今度、喫茶店を開くに当って、メインの絵が欲しいそうなんだ。それを君にお願いしたいっていうんだ。どうかな?明日にでも、一緒に行って話しだけでも聞いてもらえないだろうか?」
「仕事ってことは、お金とかもらえるんですか?」
高耶くんが聞くと、藤原先生は頷いた。
「もちろんだよ。コレは仕事としてお願いするんだから、向うもそのつもりだといっていたよ」
「姉ちゃん凄い!もう絵描きさんになるの?」
「夢が叶うんだぞ。やらせてもらえ、花蓮」
沢山の人に私の絵を見てもらいたい。
小さい頃、おじいちゃんが私の絵を見ると心が洗われる、死ぬ時はこれを棺に一緒に入れて欲しいと言ってくれたことがあった。
おじいちゃんは私の絵をずっと大切にしてくれて、死ぬ時も抱きしめるように逝ってしまった。
その顔はすごく穏やかなものだった。
それがきっかけだったかもしれない。私が絵を描き続けたのは、沢山絵の勉強して、絵の仕事に携われて、誰かの心に少しでも残っていけるのならばと思っていた。
こんな形で叶うなんて思っても見なかった。
「君の絵は人の心に残る。僕も君の絵を沢山の人に見てもらいたい」
「こんなチャンス滅多にないですよ。花蓮さん」
私の意志は決まっている。
「やります。やらせてください」
謙遜とかしり込みで引き受けないほど、お人よしでもないし、ヘタレでもない。
来たチャンスとはしっかり、がっちりとつかめ、女の手でもつかめるチャンスは男と同じ位にあるとおじいちゃんが言ってた。
だから私は怯まない。
沢山の人に私の絵を見てもらいたい。
小さい頃、おじいちゃんが私の絵を見ると心が洗われる、死ぬ時はこれを棺に一緒に入れて欲しいと言ってくれたことがあった。
おじいちゃんは私の絵をずっと大切にしてくれて、死ぬ時も抱きしめるように逝ってしまった。
その顔はすごく穏やかなものだった。
それがきっかけだったかもしれない。私が絵を描き続けたのは、沢山絵の勉強して、絵の仕事に携われて、誰かの心に少しでも残っていけるのならばと思っていた。
こんな形で叶うなんて思っても見なかった。
「君の絵は人の心に残る。僕も君の絵を沢山の人に見てもらいたい」
「こんなチャンス滅多にないですよ。花蓮さん」
私の意志は決まっている。
「やります。やらせてください」
謙遜とかしり込みで引き受けないほど、お人よしでもないし、ヘタレでもない。
来たチャンスとはしっかり、がっちりとつかめ、女の手でもつかめるチャンスは男と同じ位にあるとおじいちゃんが言ってた。
だから私は怯まない。
「じゃあ、明日の朝、迎えに来るから」
「はい。よろしくお願いします」
先生を見送ってから、4人で息を吐いた。
「凄いですね、先輩。画家デビューじゃないですか」
「大袈裟だよ。でも、頑張るよ」
「姉ちゃん、お金入ったらDS買っておくれ」
「「自分で買え」」
いつの間にか、高耶くんは内に馴染んで、遅い夕飯を一緒に食べた。
「そうか花蓮の後輩かぁ。女泣かせてそうな顔だな」
「嫌だなぁ。今日は折角のクリスマスイブだってのに、女にフラれたばっかりのブロークンハートのロンリーボーイなんですから」
「嘘付け。どうせ、やる気もなく出て行って、気の効いたプレゼントもなくて、もういい、知らないっって言われたんだろう。対して好きでもない女と付き合うから面倒くさくなるんだ」
小学生の前でそういうことを余り話さないで欲しいと思ったけど、達久はたまたま高耶くんが持っていたDSにすっかり夢中だ。
「仕方ないですよ。好きな人は、違う人と付き合ってるんですけど、諦められないんです。代用品でもないとやりきれない」
「思うだけでは辛すぎるか・・・。ガキの癖に大人みたいなこと言いやがって」
晋兄ちゃんはふぅっと煙を吐いた。
彼も片思いをしていることを私は知っている。けれど、それを彼は絶対に伝えることはしない。
相手の幸せを祈る。そんな好きの形を兄は選んだんだ。
「でも好きなんて気持ちがある限り、良いんじゃねぇか。頑張れよ青少年」
「好きな人に、好きになってもらうだけなんですけどね」
「一番簡単なことなのにね。難しいね」
「はい。よろしくお願いします」
先生を見送ってから、4人で息を吐いた。
「凄いですね、先輩。画家デビューじゃないですか」
「大袈裟だよ。でも、頑張るよ」
「姉ちゃん、お金入ったらDS買っておくれ」
「「自分で買え」」
いつの間にか、高耶くんは内に馴染んで、遅い夕飯を一緒に食べた。
「そうか花蓮の後輩かぁ。女泣かせてそうな顔だな」
「嫌だなぁ。今日は折角のクリスマスイブだってのに、女にフラれたばっかりのブロークンハートのロンリーボーイなんですから」
「嘘付け。どうせ、やる気もなく出て行って、気の効いたプレゼントもなくて、もういい、知らないっって言われたんだろう。対して好きでもない女と付き合うから面倒くさくなるんだ」
小学生の前でそういうことを余り話さないで欲しいと思ったけど、達久はたまたま高耶くんが持っていたDSにすっかり夢中だ。
「仕方ないですよ。好きな人は、違う人と付き合ってるんですけど、諦められないんです。代用品でもないとやりきれない」
「思うだけでは辛すぎるか・・・。ガキの癖に大人みたいなこと言いやがって」
晋兄ちゃんはふぅっと煙を吐いた。
彼も片思いをしていることを私は知っている。けれど、それを彼は絶対に伝えることはしない。
相手の幸せを祈る。そんな好きの形を兄は選んだんだ。
「でも好きなんて気持ちがある限り、良いんじゃねぇか。頑張れよ青少年」
「好きな人に、好きになってもらうだけなんですけどね」
「一番簡単なことなのにね。難しいね」
折角のクリスマスイブなのに、何で切ない恋話をしなくちゃいけなくなったんだろう。
「兄ちゃん、ケーキ食べないの?」
「はぁ?ケーキは明日だ!ガキはさっさと寝ろ」
「あっ、そうだ。サンタさん来るんだ」
まだサンタクロースを信じてる達久はDSを高耶くんに返して、部屋に戻って行った。
「あっ!歯を磨いてから寝ろ。またあの惨劇を繰り返すのか?網に入るのも、9歳までだぞ」
晋兄ちゃんは達久を追いかけてリビングから出て行った。
「惨劇ですか?」
「タツは歯医者が苦手なの?でもムシ歯は出来るから晋兄ちゃんが連れて行くんだけど、騒ぐ、泣く、逃げるのオンパレード。もう2度と行くかっ!って言ってるけど毎年ムシ歯は出来るんだよね」
私の時もそうだった。
うちは父子家庭で、忙しい父の変わりに兄が私たちの面倒を見てくれた。
「良い兄さんなんですね。ホストみたいな顔してますけど」
「あれでも立派な郵便局員なんだよ。休日のホストみたいな格好だけど」
「オレも兄貴が欲しかったな」
「立派なお姉さんがいるじゃない」
「兄ちゃん、ケーキ食べないの?」
「はぁ?ケーキは明日だ!ガキはさっさと寝ろ」
「あっ、そうだ。サンタさん来るんだ」
まだサンタクロースを信じてる達久はDSを高耶くんに返して、部屋に戻って行った。
「あっ!歯を磨いてから寝ろ。またあの惨劇を繰り返すのか?網に入るのも、9歳までだぞ」
晋兄ちゃんは達久を追いかけてリビングから出て行った。
「惨劇ですか?」
「タツは歯医者が苦手なの?でもムシ歯は出来るから晋兄ちゃんが連れて行くんだけど、騒ぐ、泣く、逃げるのオンパレード。もう2度と行くかっ!って言ってるけど毎年ムシ歯は出来るんだよね」
私の時もそうだった。
うちは父子家庭で、忙しい父の変わりに兄が私たちの面倒を見てくれた。
「良い兄さんなんですね。ホストみたいな顔してますけど」
「あれでも立派な郵便局員なんだよ。休日のホストみたいな格好だけど」
「オレも兄貴が欲しかったな」
「立派なお姉さんがいるじゃない」
晋兄ちゃんとは違うだろうけど、千春先輩は高耶くんにとって良いお姉さんのはずだ。
「花蓮さん、どうするんですか?」
「何を?」
「あの人とこのまま付き合い続けるんですか?」
「わかんない・・・」
そうわかんない。
彼とこれからどうなりたいのかなんて分からない。
「私の長所はね。絵を描くと、他のことは考えられなることなの。だから、今度の仕事も光臣くんのことで手につかなくなるくらいなら、最初から引き受けたりしない」
「そうですか。強いんですね」
「どうだろうね。鈍感、いや執着心が無いだけなのかもしれない。私には絵があるからって思っちゃうんだよね」
人としては最低なのかもと笑うと、高耶くんは力一杯否定してくれた。
「そんなこと無いですよ。花蓮さんは素敵ですよ。最低なんかじゃない。あいつのことずっと待ってた姿とか、恋する女そのもだったじゃないですか。不安で泣きそうになってた顔にオレがどんなにっ」
「おーい、高耶。そろそろ帰れ、親が心配するぞ」
晋兄ちゃんが戻ってきて、高耶くんの言葉が途中で遮られた。
「はいはい。帰りますよ。先輩お邪魔しました」
高耶くんを玄関まで送ると、ふいに手をつかまれた。
「花蓮さん、どうするんですか?」
「何を?」
「あの人とこのまま付き合い続けるんですか?」
「わかんない・・・」
そうわかんない。
彼とこれからどうなりたいのかなんて分からない。
「私の長所はね。絵を描くと、他のことは考えられなることなの。だから、今度の仕事も光臣くんのことで手につかなくなるくらいなら、最初から引き受けたりしない」
「そうですか。強いんですね」
「どうだろうね。鈍感、いや執着心が無いだけなのかもしれない。私には絵があるからって思っちゃうんだよね」
人としては最低なのかもと笑うと、高耶くんは力一杯否定してくれた。
「そんなこと無いですよ。花蓮さんは素敵ですよ。最低なんかじゃない。あいつのことずっと待ってた姿とか、恋する女そのもだったじゃないですか。不安で泣きそうになってた顔にオレがどんなにっ」
「おーい、高耶。そろそろ帰れ、親が心配するぞ」
晋兄ちゃんが戻ってきて、高耶くんの言葉が途中で遮られた。
「はいはい。帰りますよ。先輩お邪魔しました」
高耶くんを玄関まで送ると、ふいに手をつかまれた。
「高耶くん?」
「あれ、いらないならオレに下さい」
高耶くんが見ているのは、下駄箱の上においていた、光臣くんのプレゼントだった。
帰ってきたときに慌てて置いたままだった。
高耶くんの目は怖いほど真剣で、知らない人、知らない男の人みたいな目だった。
「花蓮さん」
先輩じゃなくてさん付けで呼ばれてるだけなのに、胸がドキドキする。
「送ってきたお礼貰っても良いですよね?」
高耶くんは袋を手に取ると中からマフラーと手袋を出して身につけた。
光臣くんのため作った、紺と紫と白のマフラーと黒の手袋。
「似合ってるね。送ってくれてありがとう」
「あったかいです。さよなら、仕事頑張ってください」
手放したはずなのに、光臣くんの気持ちだけはどうしても私から出て行かない。
あれからケータイはずっと鳴らない。
「あれ、いらないならオレに下さい」
高耶くんが見ているのは、下駄箱の上においていた、光臣くんのプレゼントだった。
帰ってきたときに慌てて置いたままだった。
高耶くんの目は怖いほど真剣で、知らない人、知らない男の人みたいな目だった。
「花蓮さん」
先輩じゃなくてさん付けで呼ばれてるだけなのに、胸がドキドキする。
「送ってきたお礼貰っても良いですよね?」
高耶くんは袋を手に取ると中からマフラーと手袋を出して身につけた。
光臣くんのため作った、紺と紫と白のマフラーと黒の手袋。
「似合ってるね。送ってくれてありがとう」
「あったかいです。さよなら、仕事頑張ってください」
手放したはずなのに、光臣くんの気持ちだけはどうしても私から出て行かない。
あれからケータイはずっと鳴らない。
おかしい。
花蓮のケータイに何度かけても通じない。
あいつまたマナーモードのままにしてんのか?
折角ケータイを持たせても、通じるのはごく僅かな回数だけだ。
「畜生。あいつ、ちゃんと家に帰ってれば良いけど」
いつもルーズなくせに、約束には敏感な奴で、意固地のようになって守ろうとする。
時計はもう8時を過ぎている。
雪も降っているのに、あそこにいたら手が悴んでしまう。
どうしてオレは、あそこに行かなかったんだろう。
「光臣くん、大丈夫?お友達に連絡ついたの?」
「いや。多分大丈夫だよ」
「ごめんね。無理言ってしまって」
大丈夫。あいつは絵のためならオレすら袖にした女だ。
最初のデート美術館に行った。あいつは美術部だったからあいつに合わせた。そうしたら、一度心を奪われた絵の前に立った途端、動かなくなった。
行こうと言っても聞かなくて、実力行使に出たら、腕を逆に取られてぶん投げられた。
そろって、美術館から追い出されたのは言うまでも無かった。
そういう女だ。花蓮は。
だから、大丈夫。
花蓮のケータイに何度かけても通じない。
あいつまたマナーモードのままにしてんのか?
折角ケータイを持たせても、通じるのはごく僅かな回数だけだ。
「畜生。あいつ、ちゃんと家に帰ってれば良いけど」
いつもルーズなくせに、約束には敏感な奴で、意固地のようになって守ろうとする。
時計はもう8時を過ぎている。
雪も降っているのに、あそこにいたら手が悴んでしまう。
どうしてオレは、あそこに行かなかったんだろう。
「光臣くん、大丈夫?お友達に連絡ついたの?」
「いや。多分大丈夫だよ」
「ごめんね。無理言ってしまって」
大丈夫。あいつは絵のためならオレすら袖にした女だ。
最初のデート美術館に行った。あいつは美術部だったからあいつに合わせた。そうしたら、一度心を奪われた絵の前に立った途端、動かなくなった。
行こうと言っても聞かなくて、実力行使に出たら、腕を逆に取られてぶん投げられた。
そろって、美術館から追い出されたのは言うまでも無かった。
そういう女だ。花蓮は。
だから、大丈夫。
好きな女を放ってオレは、千春の前にいる。
ちゃんと行くはずだった。
準備もしていた。
誕生日はストラップしかやれなかったから、クリスマスプレゼントも用意していた。
あいつに似合いそうな蝶のモチーフのペンダント。アクセサリーなんて持ってないだろうから、喜んでくれると嬉しいと思いながら選んだのに。
どうしてオレはここにいる。
「柚木さんとお付き合いしてるって聞いたわ」
「あぁ」
「私はきっと彼女に恨まれるわね。折角のクリスマスイブに恋人を盗ってしまったんだから」
「仕方なねぇよ。今日は・・・」
そう仕方ない。
千春が高校卒業してから、会っていなかった。家を出て大学に通っていたことを知っていた。
それが帰ってきていた、千春にばったりと会ってしまった。
「光臣くん久しぶり。また背が伸びたのね」
別れた時とと同じ優しい穏やかな声。
あの頃の記憶が戻ってきそうになった。
ちゃんと行くはずだった。
準備もしていた。
誕生日はストラップしかやれなかったから、クリスマスプレゼントも用意していた。
あいつに似合いそうな蝶のモチーフのペンダント。アクセサリーなんて持ってないだろうから、喜んでくれると嬉しいと思いながら選んだのに。
どうしてオレはここにいる。
「柚木さんとお付き合いしてるって聞いたわ」
「あぁ」
「私はきっと彼女に恨まれるわね。折角のクリスマスイブに恋人を盗ってしまったんだから」
「仕方なねぇよ。今日は・・・」
そう仕方ない。
千春が高校卒業してから、会っていなかった。家を出て大学に通っていたことを知っていた。
それが帰ってきていた、千春にばったりと会ってしまった。
「光臣くん久しぶり。また背が伸びたのね」
別れた時とと同じ優しい穏やかな声。
あの頃の記憶が戻ってきそうになった。
この作品のキーワード
設定されていません
この作家の他の作品
表紙を見る
乙女ゲームってなんのこと?
悪役令嬢ってなんのこと?
婚約者の姉の奇行に毎日のように振り回させるようになってしまったマリーベル、彼女は平穏な日常を取り戻せるのか?
表紙を見る
誰かを好きになって、その人に自分を好きになってもらう、たったそれだけのことなのに
それが一番難しい。ってことを私達は思いしる。
表紙を見る
オレの妹は小さい頃から破天荒だった。
彼女の通った道には数々の伝説が出来上がっていった。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…