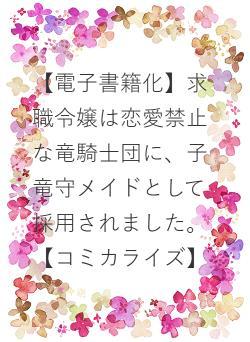「……ルシール・モートン! 君との婚約をここで、破棄させてもらう!」
「……っ……!」
突然の婚約破棄宣言を受け、私は目を見開いて驚いてしまった。
何故かというと、声高らかに私との婚約を破棄したカーター侯爵令息ロベルトは、先ほどまで談笑していた、ある程度良い関係が築けたと思っていた婚約者だったから。
いえ……だったのよ。
今夜の夜会だって共に入場もして来たし、私たち二人は良い関係を築けたと思っていた。
私が八歳の頃に婚約して今は、十七歳、つまり、私たち二人は、九年もの長い月日を婚約者同士として生きていた。
そろそろ結婚式の準備を……という話だって両親の口からは出ていたし、穏やかな性格のロベルトとの結婚には、私は何の不満もなかった。
だから、ロベルトと結婚して……カーター侯爵夫人となり、生きていくのだろうと思っていた。
けれど、婚約破棄をされてしまったとなると、どれほど言い訳を重ねたところで『あれは表向きの理由で、とんでもない女だったらしい』と、女性側に何か問題があったのだろうと勘繰られる。
それは酷過ぎるとなっても、これまでもそうだったということは、これからもきっとそうなのだろうし、ここでみっともなく喚き立ててもその結果は変わらない。
頭から冷や水を浴びせられたような思いだけれど、ロベルトが公式の場でこれを言い出したということは、私にそれだけの大きな不満があったということだ。
……それに自ら気がつけなかった、私への罰なのだわ。
「……かしこまりました。今まで、ありがとうございました」
私はせめても最後は笑顔で居ようと微笑み、カーテシーを彼に向けてした。
下がろうとして振り返るのと同時に顔を上げると、その時、一瞬だけ見えたロベルトの顔は悪戯を成功させた子どものような楽しげな表情だった。
何かしら。
ロベルトは……礼儀正しく親しげな態度を見せつつも、私を嫌っていて、こんな風に公の場で婚約破棄をしたんでしょう?
それにしては、不可解に思える微笑みだったような気がして、私は夜会会場から引き上げながら不思議に思い首を捻った。
――――さて、どうしようかしら。
いきなり婚約破棄された私は、とにかくあの場を去らなければと会場の扉から出て来たものの、ここからどうするべきか悩んだ。
だって、ロベルトに迎えに来てもらっていたので、カーター家の馬車に乗って城へとやって来たけれど、彼に婚約破棄されてしまった今の私には、カーター家の馬車に乗る資格はないもの。
だとすると……モートン家の馬車を呼ぶしかないわ。けれど、どうやって呼べば良いかしら。
まさか、今夜婚約破棄されるなんて思いもしなかったのだから、何も考えていなかったわ。
……いえ。
誰か好きな人が出来たからという婚約解消だとしても、私は何の条件も付けずに頷いたのに……今更だけどロベルトったら、何を考えているのかしら。
とは言え、何もかも、もう時既に遅しよ。
こんな風に婚約破棄されても、不都合があるのは女性側だけで、男性側であるロベルトは、今夜からでも誰かに求婚することが出来るのよ。
そして、私は何かに問題ある貴族令嬢とされてしまい、求婚者なんて現れるはずもない。
家庭教師などの職業婦人として生きていくか、教会に行って神に使えるシスターになるかの二択……いえ。運が良かったならば、妻を亡くされた貴族から後妻になる話は来るかもしれない。
……とても年齢差のある縁談になるとは思うけれど。
「……モートン伯爵令嬢」
とぼとぼと城の廊下を歩いていた時に不意に名前を呼ばれて振り返れば、そこにはご両親を亡くされ若くしてブライアント公爵となられたニコラス様の姿があった。
「まあ。ニコラス様ではありませんか」
立ち止まった私に駆けつけてくれたニコラス様は、金色の髪に薄い緑の瞳、それに、まるで芸術品のように整った容貌。
この国の貴族でも容姿端麗の貴公子として知られて、本来ならば男性側からのダンス誘いを待つのが通常の手順であるはずなのに、女性側からの熱い誘いがいくらでも来ていると、そんな噂でもっぱらな男性だった。
つまり、私などのように平凡な貴族令嬢からすると、どんなに手を伸ばしても届かない、きらめく星のようなお方だ。
確かロベルトとは同じ歳、共に通った貴族学校で仲が良かったということで、私も何度かご挨拶をさせていただいた。少々、お話もしたかもしれない。
……何を話したかは覚えていない。
友人ロベルトがしでかした突然の婚約破棄劇を見て、紳士的なニコラス様は、私を心配して追いかけて来てくれたのだろう。
「ルシール嬢。ロベルトは何故、あのような事を……信じられません」
眉を寄せて悩まれているお顔も流石に魅力的で、現在貴族社会で一番人気の未婚者だけあるわ。
冷静に考えて頷いた私だけど、それはここでの対応としては間違っていると気が付き、出来るだけ悲しそうに見える表情を浮かべた。
「それは……私にも、わからなくて」
ここでは私は、そう言うしかなかった。
だって、私は本当にロベルトとは、上手くいっていると思っていたのよ。
激しく求め合うような恋愛関係ではないけれど、お互いに信頼もして穏やかな友人関係の夫婦になっていくだろう。
そう思っていたのに。
ロベルトからの裏切りとも言えるあの行動については、まだ信じられない。
もっと、私にも早く話してくれればとは思う。
だって、私は別に彼を縛るつもりなんてなかった。もし、婚約を破棄したいくらい嫌っていたのだとしたら、解消したいと言ってくれれば、それで良かったのに。
ここからどう言えばわからずに俯いた私に、ニコラス様は心配そうな様子で声をかけてくれた。
「……良かったら、モートン伯爵邸まで、僕がお送りしてよろしいですか?」
「いえ! それは、あの……それは」
一瞬だけ……男性と二人きりで馬車には乗れないからと、断りかけてしまった。けれど、私にはもう将来を決められた婚約者は居ない。
つまり、別に未婚者のブライアント公爵と馬車に乗ったところで、誰にも非難されるいわれなかった。
「ええ。僕には、わかっておりますよ。ですが、困っているモートン伯爵令嬢を、ここで放っておくことは出来ません。お願いですから、送らせてください」
有能だと名の知られた彼は、言葉を失った私が何を言いかけて、何を言わなかったのかお見通しのようだ。
「……ありがとうございます」
確かに迎えの馬車を呼ばねばと悩んでいた私は、ニコラス様からの有り難い申し出に頷いた。