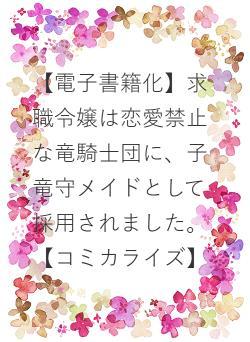そして、第二王子ジョセフに王位を継がせる。
現国王を含め、多くの貴族がその思惑で動いているはずだ……ウィリアムのことをずっと心配している、近親の一人の女性を除いて。
「姉上が俺をここから、出してくれようとしてくれているのか……?」
ウィリアムの真っ黒な瞳の中に、またひとつ、光が灯った……彼を絶望から救う、希望の光。
「ええ。父王陛下王妃陛下は、ウィリアム様を……この離宮に閉じ込めています。姉であるエレイン様はウィリアム様がどのような状態であるか、ずっと気にかけてくれていました。ここに唯一入ることの許されている私からの詳細な聞き取りが出来て、もし、危険性がないと証明出来るのなら、両陛下の誤解を解くことができると……」
これはエレインが、以前からそうしたいと考えていたことだ。
ウィリアムは危険人物でもなんでもない。ただ悲しい生い立ちを持つ孤独な男の子だった。
姉エレインは、それを知っていた。その時は彼女だって幼い子どもで……自分が守るべき弟の小さな手を、離さざるを得なかった。
今はもう違う。
現国王を含め、多くの貴族がその思惑で動いているはずだ……ウィリアムのことをずっと心配している、近親の一人の女性を除いて。
「姉上が俺をここから、出してくれようとしてくれているのか……?」
ウィリアムの真っ黒な瞳の中に、またひとつ、光が灯った……彼を絶望から救う、希望の光。
「ええ。父王陛下王妃陛下は、ウィリアム様を……この離宮に閉じ込めています。姉であるエレイン様はウィリアム様がどのような状態であるか、ずっと気にかけてくれていました。ここに唯一入ることの許されている私からの詳細な聞き取りが出来て、もし、危険性がないと証明出来るのなら、両陛下の誤解を解くことができると……」
これはエレインが、以前からそうしたいと考えていたことだ。
ウィリアムは危険人物でもなんでもない。ただ悲しい生い立ちを持つ孤独な男の子だった。
姉エレインは、それを知っていた。その時は彼女だって幼い子どもで……自分が守るべき弟の小さな手を、離さざるを得なかった。
今はもう違う。
聡明なエレインは周囲にそうと勘付かれないように着々と準備を進め、どうにかして弟ウィリアムを救い出そうと動いていた。
以前のモニカならば、彼女とて、こんな事を頼めなかった。
けれど、今の私……彼を幸せにしたいと願うモニカ・ラザルスならば、エレインが得たい証言を公的に述べることだって出来る。
「姉上……ご無理をなさらないのなら、良いのだが。俺はこのままでも、どうとでもなるのだし」
「まあ」
ウィリアムとエレインは、姉弟であるせいかよく似ている。お互いにお互いのことを、心配し合っている。
私も……彼ら二人を、会わせてあげたかった。
『君とみる夕焼け』という小説の中では、エレインは亡くなってしまい、それは絶対に叶わなかったことだから。
◇◆◇
本人の希望を聞き、弟を離宮から出すと決めてからのエレインの動きは、とても早かった。
彼女が優秀な王族である証拠でもあるし……これまでずっと、そうしたかったけれど、それが出来なかったという強い気持ちもそこには感じられた。
以前のモニカならば、彼女とて、こんな事を頼めなかった。
けれど、今の私……彼を幸せにしたいと願うモニカ・ラザルスならば、エレインが得たい証言を公的に述べることだって出来る。
「姉上……ご無理をなさらないのなら、良いのだが。俺はこのままでも、どうとでもなるのだし」
「まあ」
ウィリアムとエレインは、姉弟であるせいかよく似ている。お互いにお互いのことを、心配し合っている。
私も……彼ら二人を、会わせてあげたかった。
『君とみる夕焼け』という小説の中では、エレインは亡くなってしまい、それは絶対に叶わなかったことだから。
◇◆◇
本人の希望を聞き、弟を離宮から出すと決めてからのエレインの動きは、とても早かった。
彼女が優秀な王族である証拠でもあるし……これまでずっと、そうしたかったけれど、それが出来なかったという強い気持ちもそこには感じられた。
弟のウィリアムは危険人物でもなんでもないので、離宮から出すべきだというエレインの主張は、条件付きで認められることになった。
ウィリアムの傍には婚約者である私が付き添うこと……そして、もし彼が何かを仕出かしたならば、姉エレインが全ての責任を取ること。
エレインは迷わずに、その条件を受け入れた。
そして、私ととも離宮を出たウィリアムは、物々しい衛兵たちを引き連れて移動することのない廊下に戸惑っているようだ。
特別な機会でもなければ許可なく出られなかった、今までが異常だったのだけれど……。
「ウィリアム様。こうして、自由になった気分は、どうですか……?」
私が何気なく言った質問に、隣を歩くウィリアムは少し考えていた。
「自由か。ああ。条件付きの自由ではあるが、姉上が俺に与えてくれたものだ。大事にしたい」
頭上に広がる青い空を見て、ウィリアムがしみじみと呟いた言葉に、私は何も言えなくなった。
……産みの亡き母の身分が低かっただけで、それだけで、彼は世間から隔離されて、ずっと孤独に生きて来た。
色々と思うところはあるだろう。
ウィリアムの傍には婚約者である私が付き添うこと……そして、もし彼が何かを仕出かしたならば、姉エレインが全ての責任を取ること。
エレインは迷わずに、その条件を受け入れた。
そして、私ととも離宮を出たウィリアムは、物々しい衛兵たちを引き連れて移動することのない廊下に戸惑っているようだ。
特別な機会でもなければ許可なく出られなかった、今までが異常だったのだけれど……。
「ウィリアム様。こうして、自由になった気分は、どうですか……?」
私が何気なく言った質問に、隣を歩くウィリアムは少し考えていた。
「自由か。ああ。条件付きの自由ではあるが、姉上が俺に与えてくれたものだ。大事にしたい」
頭上に広がる青い空を見て、ウィリアムがしみじみと呟いた言葉に、私は何も言えなくなった。
……産みの亡き母の身分が低かっただけで、それだけで、彼は世間から隔離されて、ずっと孤独に生きて来た。
色々と思うところはあるだろう。
こうして自由に歩くことは、本来ならば、誰にだって制限されることはない。
けれど、ウィリアムはそんな自らの不遇を、誰かのせいだと、長い時を同じくした婚約者モニカにも言ったことはなかった。
なんともたとえようもない想いを抱えたままの私が、エレインの自室へとウィリアムを案内すると、彼女はひと目をはばからずに弟へと駆け寄った。
「ウィリアム……!」
えっ……!
エレイン。気持ちはわかるけれど、そんな対応を誰かに見られたら!
私は慌てて周囲を確認したけれど、既に人払いを済ませていたようだ。広い部屋の中には私たち三人しか居なかった。
エレインは政治的な問題で王妃である母と、弟ジョセフ側の人間であらねばならない。ウィリアムをこんな風に特別に大事に思っていると、誰にも知られてはならないのだ。
「……姉上」
部屋に入った途端に姉から抱きつかれたウィリアムは、両手を浮かせて戸惑っている。
私から『心配している』という話を聞いていたものの、姉エレインが自分へと、これだけの愛情を向けてくれていたと知って、とても驚いているのだろう。
けれど、ウィリアムはそんな自らの不遇を、誰かのせいだと、長い時を同じくした婚約者モニカにも言ったことはなかった。
なんともたとえようもない想いを抱えたままの私が、エレインの自室へとウィリアムを案内すると、彼女はひと目をはばからずに弟へと駆け寄った。
「ウィリアム……!」
えっ……!
エレイン。気持ちはわかるけれど、そんな対応を誰かに見られたら!
私は慌てて周囲を確認したけれど、既に人払いを済ませていたようだ。広い部屋の中には私たち三人しか居なかった。
エレインは政治的な問題で王妃である母と、弟ジョセフ側の人間であらねばならない。ウィリアムをこんな風に特別に大事に思っていると、誰にも知られてはならないのだ。
「……姉上」
部屋に入った途端に姉から抱きつかれたウィリアムは、両手を浮かせて戸惑っている。
私から『心配している』という話を聞いていたものの、姉エレインが自分へと、これだけの愛情を向けてくれていたと知って、とても驚いているのだろう。
「今まで……ごめんなさい。なかなか助けられなくて……本当にごめんなさいっ……っ」
エレインはこれまで堪えていた想いが爆発してしまったのか、むせび泣くようにして泣いていた。
「姉上……モニカから、いつも心配してくれていたと聞きました。ありがとうございます。姉上に心配をおかけしてしまい、何も返すことも出来ず、不甲斐ない弟で申し訳ありません」
そうして姉弟の二人は無言で抱き合い、お互いの存在を確かめるようにしていた。
ああ……なんて、嬉しい。
私は身体中から、無性にこみ上げるものを感じていた。
だって、小説の中ではウィリアムとエレインの二人は、わかり合うこともなく、死に別れてしまう。
ウィリアムがエレインの思いを知るのは、物語終盤で、もう何もかも終わってしまった後だった。
そんな切ないIFストーリーを知っている私には、二人がこうして面と向かって仲直りしている光景が、眩しすぎて……尊すぎて……ああなんて、美しいの。
やはり、この二人には、この先、絶対に幸せになってもらわなくては……いえ。私がそうしなければ。
「いや、泣きすぎだろう」
不意に私の方を見たウィリアムは、呆れたようにして言った。
こんな二人を見て……私が泣かない方が、おかしいんです。
だって、私はあなたたちのことが書かれた文章だけを読んだだけでも、号泣していたんですよ。
エレインはこれまで堪えていた想いが爆発してしまったのか、むせび泣くようにして泣いていた。
「姉上……モニカから、いつも心配してくれていたと聞きました。ありがとうございます。姉上に心配をおかけしてしまい、何も返すことも出来ず、不甲斐ない弟で申し訳ありません」
そうして姉弟の二人は無言で抱き合い、お互いの存在を確かめるようにしていた。
ああ……なんて、嬉しい。
私は身体中から、無性にこみ上げるものを感じていた。
だって、小説の中ではウィリアムとエレインの二人は、わかり合うこともなく、死に別れてしまう。
ウィリアムがエレインの思いを知るのは、物語終盤で、もう何もかも終わってしまった後だった。
そんな切ないIFストーリーを知っている私には、二人がこうして面と向かって仲直りしている光景が、眩しすぎて……尊すぎて……ああなんて、美しいの。
やはり、この二人には、この先、絶対に幸せになってもらわなくては……いえ。私がそうしなければ。
「いや、泣きすぎだろう」
不意に私の方を見たウィリアムは、呆れたようにして言った。
こんな二人を見て……私が泣かない方が、おかしいんです。
だって、私はあなたたちのことが書かれた文章だけを読んだだけでも、号泣していたんですよ。
感情が昂ぶり過ぎて泣いてしまっていたけれど、時間をかけてようやく落ち着けた私たち三人は、とりあえず涙を拭き、エレインに促されるままに応接用のソファへと腰掛けることにした。
王族の姫の部屋は、信じられないほどに豪華だった……本来ならば、王太子ウィリアムだって、こんな部屋で日々を過ごしていただろうと思うと心が痛む。
「姉上。信じられないと思いますが……ダスレイン大臣が、黒幕なのです。王位簒奪を」
ウィリアムはこれは真っ先に伝えねばと思っていたのか、エレインにダスレイン大臣のことを伝えた。
私もこれは早めに伝えねばと思っていたけれど、エレインは非常に警戒心が強い。下手に伝えると、私が遠ざけられる可能性もあった。
しかし、愛する弟ウィリアムの言葉となれば、用心深いエレインも話が違ってくるだろう。
王族の姫の部屋は、信じられないほどに豪華だった……本来ならば、王太子ウィリアムだって、こんな部屋で日々を過ごしていただろうと思うと心が痛む。
「姉上。信じられないと思いますが……ダスレイン大臣が、黒幕なのです。王位簒奪を」
ウィリアムはこれは真っ先に伝えねばと思っていたのか、エレインにダスレイン大臣のことを伝えた。
私もこれは早めに伝えねばと思っていたけれど、エレインは非常に警戒心が強い。下手に伝えると、私が遠ざけられる可能性もあった。
しかし、愛する弟ウィリアムの言葉となれば、用心深いエレインも話が違ってくるだろう。
「え。ダスレイン公爵が……黒幕ですって? 王家を陥れようとしても、あの人の継承権はかなり下の方でしょう? 王位簒奪となると、かなりの人数を殺すことになってしまうけれど……ああ」
エレインはそう言って非常に驚いた表情を見せていたけれど、私たちが何も言わずに大きく頷いたのを見てから、頭を手で押さえて息をついた。
切り替えが早い。
これまでにそんなことを考えもしなかったであろうエレインは、私たち二人が口を揃えてそう言うならば、確率が高いのだと踏んだろう。
沈着冷静で頭脳明晰。自分を律し遠い先にある目的のためには、自分の欲求などは抑えることが出来る。
この方が男子ならばと誰もが思い、エレインだってそういう言葉を、これまでに嫌になるくらい聞いていたはずだ。
けれど、シュレジエン王国は女王が許されない。
……ダスレイン大臣が、ウィリアムを閉じ込めて、王族ならびに自分より高い継承権を持つ者を殺そうと計画していることを、エレインはここで知った。
彼女が油断して暗殺される確率は、ここで減らすことが出来る。
エレインはそう言って非常に驚いた表情を見せていたけれど、私たちが何も言わずに大きく頷いたのを見てから、頭を手で押さえて息をついた。
切り替えが早い。
これまでにそんなことを考えもしなかったであろうエレインは、私たち二人が口を揃えてそう言うならば、確率が高いのだと踏んだろう。
沈着冷静で頭脳明晰。自分を律し遠い先にある目的のためには、自分の欲求などは抑えることが出来る。
この方が男子ならばと誰もが思い、エレインだってそういう言葉を、これまでに嫌になるくらい聞いていたはずだ。
けれど、シュレジエン王国は女王が許されない。
……ダスレイン大臣が、ウィリアムを閉じ込めて、王族ならびに自分より高い継承権を持つ者を殺そうと計画していることを、エレインはここで知った。
彼女が油断して暗殺される確率は、ここで減らすことが出来る。
ダスレイン大臣は彼女も欺けるほどに、上手くやっていた。人畜無害な演技で、なかなか尻尾を握らせなかった。
……けれど、私たちはここで真実を伝えることが出来た。
「そうね。もし、そうだったとすれば、理解出来ることが、たくさんあるわね……ああ。そうなの。あの人が私や家族を、誤解をさせて酷く苦しめたのね……」
エレインは無表情のまま、目を細めてそう言った。
誰が自分の敵であるか不確定であれば、彼女にも出来ることが少なかったはずだ。
けれど、今は敵が誰であるか、特定出来た。
「あの……エレイン様。貴女には、暗殺の危険があります。というのも、王族に亀裂を入れるためです。それに、不遇にあったウィリアム様をどうにかして庇おうとされていることも、おそらく……」
ダスレイン大臣は自分の思い通りにはならないエレインに、それまでの罪をなすりつけて殺した。そして、ウィリアムには、それを理由にすり寄ろうとした。
自分にとっての邪魔者であるエレインの死を、自分勝手に利用するだけ利用してしまう、とんでもない外道だったのだ。
……けれど、私たちはここで真実を伝えることが出来た。
「そうね。もし、そうだったとすれば、理解出来ることが、たくさんあるわね……ああ。そうなの。あの人が私や家族を、誤解をさせて酷く苦しめたのね……」
エレインは無表情のまま、目を細めてそう言った。
誰が自分の敵であるか不確定であれば、彼女にも出来ることが少なかったはずだ。
けれど、今は敵が誰であるか、特定出来た。
「あの……エレイン様。貴女には、暗殺の危険があります。というのも、王族に亀裂を入れるためです。それに、不遇にあったウィリアム様をどうにかして庇おうとされていることも、おそらく……」
ダスレイン大臣は自分の思い通りにはならないエレインに、それまでの罪をなすりつけて殺した。そして、ウィリアムには、それを理由にすり寄ろうとした。
自分にとっての邪魔者であるエレインの死を、自分勝手に利用するだけ利用してしまう、とんでもない外道だったのだ。
「ああ。そうね……私さえ排除すれば、ウィリアムを形だけでも守るものが居なくなり、お父様もお母様も、そして、ジョセフだって操作しやすい。ふふふ。そうなのね……まあ。ダスレイン公爵が」
余裕を持ってお茶を飲んだエレインは、艶やかに微笑み、対面に座っている私たち二人を見た。
「私のことは貴方たち二人は、心配しなくても良いわ。敵が誰かわかれば、私だって対処もしようがあるというもの。貴方たちは仲睦まじい婚約者同士の姿を、城中に振り撒きなさい」
エレイン側にも何か考えがあるのか、そう言って微笑んだ……聡明な彼女のすることならば間違いないと思うし、そういった思惑に口を挟む権利は私にはない。
始終見張っていないとハラハラさせてしまう、キャンディスさんとはまったく違うのだ。どっしりと安心感のある言葉だった。
「あの……姉上」
それまでエレインの様子を窺いつつ、黙っていたウィリアムは、真面目な表情で姉を呼んだ。
余裕を持ってお茶を飲んだエレインは、艶やかに微笑み、対面に座っている私たち二人を見た。
「私のことは貴方たち二人は、心配しなくても良いわ。敵が誰かわかれば、私だって対処もしようがあるというもの。貴方たちは仲睦まじい婚約者同士の姿を、城中に振り撒きなさい」
エレイン側にも何か考えがあるのか、そう言って微笑んだ……聡明な彼女のすることならば間違いないと思うし、そういった思惑に口を挟む権利は私にはない。
始終見張っていないとハラハラさせてしまう、キャンディスさんとはまったく違うのだ。どっしりと安心感のある言葉だった。
「あの……姉上」
それまでエレインの様子を窺いつつ、黙っていたウィリアムは、真面目な表情で姉を呼んだ。
この作家の他の作品
表紙を見る
夜会での婚約者からの、いきなりの婚約破棄!
けれど、伯爵令嬢ルシールには
婚約者ロベルトとは良い友人のような
おだやかな関係を築いていると思って居たし
、婚約破棄されてしまうような覚えもなかった。
しかし、されてしまったものは仕方ないと夜会からの帰り道、
ロベルトの友人若くして公爵位を継いだ
ニコラスに声を掛けられるのだが……。
現実主義ドライ令嬢がいつのまにか愛されていた公爵に
囲い込まれて一本道しか行けなくなる話。
表紙を見る
異世界恋愛が好き……そんな私、大好きだった小説『ドキデキ』の世界に転生してモブ令嬢になっていた!
主人公二人の素敵場面を観察していると、注意して来た美形の男性……あれ? これから陥れられて全てを奪われるラスボスになるはずの王弟ではない?
こっ、これって!! 転生者の醍醐味、救いたい不遇キャラを救って、私も一緒に幸せになります!
表紙を見る
グレンジャー伯爵令嬢ウェンディは父が友人に裏切られ、
社交界デビューを目前にして無一文になってしまった。
父は異国へと一人出稼ぎに行ってしまい、
行く宛てのない姉を心配する弟を安心させるために、
以前邸で働いていた竜騎士を頼ることに。
彼が働くアレイスター竜騎士団は『恋愛禁止』という厳格な規則があり、
そのため若い女性は働いていない。
しかし、ウェンディは竜力を持つ貴族の血を引く女性にしかなれないという
『子竜守』として特別に採用されることになり……。
子竜守として働くことになった没落貴族令嬢が、
不器用だけどとても優しい団長と恋愛禁止な竜騎士団で働くために
秘密の契約結婚をすることなってしまう、
ほのぼの子竜育てありな可愛い恋物語。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…