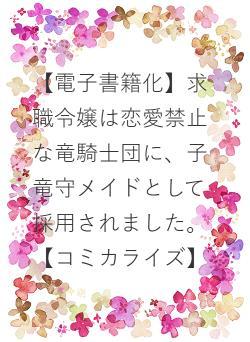何もかもをここでつまびらかにすることは出来ず、曖昧なことしか口に出来ない私に、ウィリアムは信じるときっぱりと言い切った。
いわば、いきなりくるりと手のひらを返した婚約者モニカを、純粋に信じてくれていた。
信頼に応えて……私はウィリアムを、必ず幸せにする。
彼には味方が今は私だけしか居ないけれど、これからは違う。
孤独で悲しみの中に堕ちるなんて、絶対にさせない。幽閉の身から解放されて自立することさえ出来れば、ウィリアムはどんな道でも……どんな相手でも、結婚相手に選ぶことが出来るのだから。
あら……? なんだか、たまに胸が痛くなるわね……?
小説の中では語られなかった設定だけれど、もしかしたら悪役令嬢モニカは、心疾患を患っていたのかもしれない。
いわば、いきなりくるりと手のひらを返した婚約者モニカを、純粋に信じてくれていた。
信頼に応えて……私はウィリアムを、必ず幸せにする。
彼には味方が今は私だけしか居ないけれど、これからは違う。
孤独で悲しみの中に堕ちるなんて、絶対にさせない。幽閉の身から解放されて自立することさえ出来れば、ウィリアムはどんな道でも……どんな相手でも、結婚相手に選ぶことが出来るのだから。
あら……? なんだか、たまに胸が痛くなるわね……?
小説の中では語られなかった設定だけれど、もしかしたら悪役令嬢モニカは、心疾患を患っていたのかもしれない。
「おい。大丈夫か……?」
不意に胸を押さえていた私を見て、体調でも悪くしたと思ったのか、ウィリアムは近付いて来た。
そんな彼を見て私はここで自分がすべき事を思い出したので、手を彼に向けて動かないように制した。
「ああ。そういえば、ちょうど良かったですわ。ウィリアム様。私も貴方にして欲しいことがあって……これは、時間的に急務です」
「……何をすれば良いんだ?」
「そこで服を脱いで、真っ直ぐに立っていてもらえますか?」
「はあぁ? ……お前はたまに、突拍子もないことを、いきなり言い出すな。まあ、良い。これで良いのか」
毛玉を取らせてくださいと言った事件を思い出したのか、顔を顰めながらウィリアムは着ていたシャツを脱いで下着姿になると、私のお願い通り真っ直ぐな姿勢でその場に立った。
「そのまま、動かないでください」
私は近くにあった紙とペンを机に置き、ポケットの中から、最近ようやく使い慣れてきた巻き尺を取りだした。
ウィリアムは本当に素直な良い子なので、私の指示に従って、手首や腕にテープを巻き付けられても、何も言わないでいた。
……こんな場所に長年幽閉されているから、筋肉もあまりないだろうと勝手に思って居たけれど、ウィリアムの身体はがっしりとしていて筋肉質だった。
あまり動かないはずの王子様だというのに、その意外性にときめいてしまう。
不意に胸を押さえていた私を見て、体調でも悪くしたと思ったのか、ウィリアムは近付いて来た。
そんな彼を見て私はここで自分がすべき事を思い出したので、手を彼に向けて動かないように制した。
「ああ。そういえば、ちょうど良かったですわ。ウィリアム様。私も貴方にして欲しいことがあって……これは、時間的に急務です」
「……何をすれば良いんだ?」
「そこで服を脱いで、真っ直ぐに立っていてもらえますか?」
「はあぁ? ……お前はたまに、突拍子もないことを、いきなり言い出すな。まあ、良い。これで良いのか」
毛玉を取らせてくださいと言った事件を思い出したのか、顔を顰めながらウィリアムは着ていたシャツを脱いで下着姿になると、私のお願い通り真っ直ぐな姿勢でその場に立った。
「そのまま、動かないでください」
私は近くにあった紙とペンを机に置き、ポケットの中から、最近ようやく使い慣れてきた巻き尺を取りだした。
ウィリアムは本当に素直な良い子なので、私の指示に従って、手首や腕にテープを巻き付けられても、何も言わないでいた。
……こんな場所に長年幽閉されているから、筋肉もあまりないだろうと勝手に思って居たけれど、ウィリアムの身体はがっしりとしていて筋肉質だった。
あまり動かないはずの王子様だというのに、その意外性にときめいてしまう。
もちろん小説の中のヒーローの体型がひょろながもやしだと決まらないので、そういう意味でのヒーロー補正もあるだろうけれど……あまり運動をしなくても筋肉がほどよく付き、努力しなくても維持したまま筋力が落ちない人も居るらしいので、ウィリアムもチートがかったそういう男性なのかもしれない。
あら。手首も細いと思っていたけれど、かなり太いわね……骨太だわ。
「いや……お前。いくらなんでも、やり過ぎだ。一体……これは、何をしているんだ?」
流れで下の服まで脱がされそうになって、ようやく抵抗感を示したウィリアムは、私の手を押さえていた。
「採寸ですわ。ウィリアム様だって、たまになさるでしょう」
既製品のように大衆向けの服ではなく、すべてをその顧客のために縫製する特注品(オーダーメイド)は、ぴっちりと身体に沿うように仕立てていく。
よって、顧客が不必要だと思えるまで細部にまで渡る採寸が、必要とされているのだ。
「いやいや。俺がたまにしているということは、その数値が、どこかに存在しているということだろう。お前がここで再度計測する必要がどこにある」
あら。手首も細いと思っていたけれど、かなり太いわね……骨太だわ。
「いや……お前。いくらなんでも、やり過ぎだ。一体……これは、何をしているんだ?」
流れで下の服まで脱がされそうになって、ようやく抵抗感を示したウィリアムは、私の手を押さえていた。
「採寸ですわ。ウィリアム様だって、たまになさるでしょう」
既製品のように大衆向けの服ではなく、すべてをその顧客のために縫製する特注品(オーダーメイド)は、ぴっちりと身体に沿うように仕立てていく。
よって、顧客が不必要だと思えるまで細部にまで渡る採寸が、必要とされているのだ。
「いやいや。俺がたまにしているということは、その数値が、どこかに存在しているということだろう。お前がここで再度計測する必要がどこにある」
確かにウィリアムのサイズについては、王室のお針子の元に行けば知ることが出来るだろう。
「けれど、ウィリアム様。少しでもサイズが違ってしまえば、大変なことになってしまいます」
「……あとひと月で、何がどう間違えば、サイズが大きく違えることになるんだ。とにかく、下は勘弁してくれ。どうしてもというのなら、お前以外が採寸するようにしてくれ」
「あの……私は気にしませんけど」
「俺が!! 気にするんだ!! ……わかれよ!!」
口を押さえて顔を赤くしたウィリアムに、私は気にならないと言えば、彼は慌てて叫ぶように言った。
「仕方ありません。仮縫いの時には、ちゃんと身体に沿って、調整させてもらいますからね」
私はふうっと息を吐いた。仮縫いの時に合わせるならば、二回ほどした方が良いかもしれない。
「何を仕方なさそうに、ため息をついて。訳も聞かずに、上半身だけでも測らせてやったんだぞ……」
いかにも面白くなさそうなウィリアムは置いていたシャツを羽織ると、椅子に座った。採寸は経験のある人にしかおそらくは理解は出来ないけれど、なかなかに体力を使う作業なのだ。
「けれど、ウィリアム様。少しでもサイズが違ってしまえば、大変なことになってしまいます」
「……あとひと月で、何がどう間違えば、サイズが大きく違えることになるんだ。とにかく、下は勘弁してくれ。どうしてもというのなら、お前以外が採寸するようにしてくれ」
「あの……私は気にしませんけど」
「俺が!! 気にするんだ!! ……わかれよ!!」
口を押さえて顔を赤くしたウィリアムに、私は気にならないと言えば、彼は慌てて叫ぶように言った。
「仕方ありません。仮縫いの時には、ちゃんと身体に沿って、調整させてもらいますからね」
私はふうっと息を吐いた。仮縫いの時に合わせるならば、二回ほどした方が良いかもしれない。
「何を仕方なさそうに、ため息をついて。訳も聞かずに、上半身だけでも測らせてやったんだぞ……」
いかにも面白くなさそうなウィリアムは置いていたシャツを羽織ると、椅子に座った。採寸は経験のある人にしかおそらくは理解は出来ないけれど、なかなかに体力を使う作業なのだ。
「あら。これは、言ってませんでしたね……ウィリアム様が王太子としての誓いを行う、立太子の儀式の、儀礼服を作るのですわ」
「……どういうことだ? 王室専属のお針子がそれは、作成するはずだろう?」
「いえいえ。ウィリアム様は何も心配することはありません……そう言ってあったでしょう?」
引き裂かれる運命にある儀礼服の代わりを、私は用意することにしていた。
密かに動くダスレイン大臣の手の者の犯行を完全に止めることは、使える人を限られている私には難しい。ならば、儀礼服は引き裂かれたと見せかけて、もう一着用意すれば良い。
彼らは自分たちの企みが上手くいったと思えば、こちらにその対策があるなんて思わずにすっかり油断してしまうだろう。
「まあ、お前がやりたいようにしてくれ……」
ウィリアムは私がサイズを書いた書き付けを整理しているのを見てから、ふてくされたように本を開いてソファへと寝っ転がった。
◇◆◇
「……モニカさんが入ってから、本当に助かっているよ。仕事の覚えも早いし、段取りも良いねえ。うちも初めての支店を作って、モニカさんに暖簾分けでも考えようかねえ」
「……どういうことだ? 王室専属のお針子がそれは、作成するはずだろう?」
「いえいえ。ウィリアム様は何も心配することはありません……そう言ってあったでしょう?」
引き裂かれる運命にある儀礼服の代わりを、私は用意することにしていた。
密かに動くダスレイン大臣の手の者の犯行を完全に止めることは、使える人を限られている私には難しい。ならば、儀礼服は引き裂かれたと見せかけて、もう一着用意すれば良い。
彼らは自分たちの企みが上手くいったと思えば、こちらにその対策があるなんて思わずにすっかり油断してしまうだろう。
「まあ、お前がやりたいようにしてくれ……」
ウィリアムは私がサイズを書いた書き付けを整理しているのを見てから、ふてくされたように本を開いてソファへと寝っ転がった。
◇◆◇
「……モニカさんが入ってから、本当に助かっているよ。仕事の覚えも早いし、段取りも良いねえ。うちも初めての支店を作って、モニカさんに暖簾分けでも考えようかねえ」
王都でも有名なメゾンキャローヒルのマダムは、彼女の職務上とても褒め上手で、入ったばかりの新人をその気にさせることなどお手の物らしい。
「まあ、そう言っていただけて、本当に嬉しいですわ。ですが、私にはまだまだ技術や経験が足りません。良き先輩方のおかげで、こうしてお仕事させていただいておりますもの。これからも技術向上に向けて頑張りますわ」
ふふふと二人で笑い合って、私は手に持っていた書き付けをしまった。
仕事を覚える上でメモは大事だ。一度聞いたことは完全に覚えられてしまう記憶力抜群の人はさておき、どんな仕事でも、何もかもすべて最初から上手く出来る人など存在しない。
失敗はしても良い。けれど、再度起こらないよう自分なりのやり方に落とし込むために、仕事中の覚え書きは必須だった。
私は記憶を取り戻してから、ウィリアムの悲劇回避に向けて、王都にある有名なメゾンでお針子見習いとして働いていた。
それは何故かというと、離宮に居るウィリアムには、婚約者である私一人しか近づけない。そういうことになっている。
「まあ、そう言っていただけて、本当に嬉しいですわ。ですが、私にはまだまだ技術や経験が足りません。良き先輩方のおかげで、こうしてお仕事させていただいておりますもの。これからも技術向上に向けて頑張りますわ」
ふふふと二人で笑い合って、私は手に持っていた書き付けをしまった。
仕事を覚える上でメモは大事だ。一度聞いたことは完全に覚えられてしまう記憶力抜群の人はさておき、どんな仕事でも、何もかもすべて最初から上手く出来る人など存在しない。
失敗はしても良い。けれど、再度起こらないよう自分なりのやり方に落とし込むために、仕事中の覚え書きは必須だった。
私は記憶を取り戻してから、ウィリアムの悲劇回避に向けて、王都にある有名なメゾンでお針子見習いとして働いていた。
それは何故かというと、離宮に居るウィリアムには、婚約者である私一人しか近づけない。そういうことになっている。
つまり、儀礼服の二着目を作成するならば、私自身が採寸や|仮縫い(フィッティング)の技術を身につける必要があった。
モニカは優雅に暮らす貴族令嬢なので、暇を持て余している。その時間を有効活用し平民と身分を偽り、メゾンでお針子として働くことに成功していた。
……そろそろ、マダムにもこういった事情を明かし、協力を仰ぐ必要があった。ここ二月ほど彼女の仕事ぶりを見ていたけれど、職人として秘密を守れ、信頼出来ると踏んだ。
立太子の儀式のための儀礼服など、これで何にしようするかと問われれば、それにしか使用するしかないほどに豪華である必要があるのだから。
しかし、これを必要であると明かすには、互いに信頼出来る関係性が出来てからでないと難しいと考えていたため、偶然選んだ勤め先のマダムである彼女が、信頼に足る人物で良かった。
さて、ウィリアムの立太子の儀式へ向けて……これで、準備は十分なようね。
モニカは優雅に暮らす貴族令嬢なので、暇を持て余している。その時間を有効活用し平民と身分を偽り、メゾンでお針子として働くことに成功していた。
……そろそろ、マダムにもこういった事情を明かし、協力を仰ぐ必要があった。ここ二月ほど彼女の仕事ぶりを見ていたけれど、職人として秘密を守れ、信頼出来ると踏んだ。
立太子の儀式のための儀礼服など、これで何にしようするかと問われれば、それにしか使用するしかないほどに豪華である必要があるのだから。
しかし、これを必要であると明かすには、互いに信頼出来る関係性が出来てからでないと難しいと考えていたため、偶然選んだ勤め先のマダムである彼女が、信頼に足る人物で良かった。
さて、ウィリアムの立太子の儀式へ向けて……これで、準備は十分なようね。
「……モニカ。お前は確か、生粋の貴族令嬢ではなかったのか」
「ええ。私の公式な身分は、ラザレス伯爵令嬢モニカ。仰るとおり、シュレジエン王国貴族でございます。ウィリアム様」
そもそも伯爵位以上の貴族令嬢でなければ、王族に嫁ぐことは許されず、王太子に嫁ぐならば、何代も前から続く『品行方正』な血筋であることが求められる。
王太子ウィリアムの婚約者モニカは、そういった厳しい基準を満たしている、選り抜きの伯爵令嬢ということになる。
ここでウィリアムが何を言いたいかは、理解出来る。社交を仕事とする貴族令嬢は、お茶会や夜会に出て優雅に暮らすのが、いわばお仕事。
今の私のように、お針子の真似事なんて、決してしないものなのである。
私は|仮縫い(フィッティング)のために持ち込んだ様々な布を当てて、彼の身体に沿うように取り付けていく。何人かで協力するような作業ではあるけれど、一人でも出来るように訓練して来た。
しかし、生けるマネキンとしての役目を果たすウィリアムには、長時間立ったままで居てもらうことになるけれど、これはもう仕方ない。
「ええ。私の公式な身分は、ラザレス伯爵令嬢モニカ。仰るとおり、シュレジエン王国貴族でございます。ウィリアム様」
そもそも伯爵位以上の貴族令嬢でなければ、王族に嫁ぐことは許されず、王太子に嫁ぐならば、何代も前から続く『品行方正』な血筋であることが求められる。
王太子ウィリアムの婚約者モニカは、そういった厳しい基準を満たしている、選り抜きの伯爵令嬢ということになる。
ここでウィリアムが何を言いたいかは、理解出来る。社交を仕事とする貴族令嬢は、お茶会や夜会に出て優雅に暮らすのが、いわばお仕事。
今の私のように、お針子の真似事なんて、決してしないものなのである。
私は|仮縫い(フィッティング)のために持ち込んだ様々な布を当てて、彼の身体に沿うように取り付けていく。何人かで協力するような作業ではあるけれど、一人でも出来るように訓練して来た。
しかし、生けるマネキンとしての役目を果たすウィリアムには、長時間立ったままで居てもらうことになるけれど、これはもう仕方ない。
この離宮に入ることの出来る、正当な理由を持つ婚約者である私は、一人しかない。出来るだけ短時間で、効率良く動くしかない。
無数にある布地を当てて、手際良くまち針を刺していく私に、ウィリアムは小さく息をついた。
「おい。お前。凄すぎないか……このまま、優秀なお針子にもなれそうだ。本当に、仕事が出来るんだな」
「まあ! ありがとうございます。嬉しいですわ。頑張って会得して得た技術を褒められることほど、嬉しいことはありませんわ」
さきほど、突然私に立ったままで居て欲しいと頼まれ、この前の反省を活かし私が持って来た|仮縫い(フィッティング)中に身につけていても、支障のない薄い下履きを身につけている彼は、呆然としたままでそう呟いた。
思わぬ褒め言葉をもらって笑顔になった私は、ある程度まで縫製されている布を重ね、必要な部分には無数のまち針を刺して、それを幾度となく繰り返す。
長時間かかる単調な作業にも関わらず、言われた通りに動いてくれるウィリアムは、文句の一言も言うこともなく私に付き合ってくれた。
無数にある布地を当てて、手際良くまち針を刺していく私に、ウィリアムは小さく息をついた。
「おい。お前。凄すぎないか……このまま、優秀なお針子にもなれそうだ。本当に、仕事が出来るんだな」
「まあ! ありがとうございます。嬉しいですわ。頑張って会得して得た技術を褒められることほど、嬉しいことはありませんわ」
さきほど、突然私に立ったままで居て欲しいと頼まれ、この前の反省を活かし私が持って来た|仮縫い(フィッティング)中に身につけていても、支障のない薄い下履きを身につけている彼は、呆然としたままでそう呟いた。
思わぬ褒め言葉をもらって笑顔になった私は、ある程度まで縫製されている布を重ね、必要な部分には無数のまち針を刺して、それを幾度となく繰り返す。
長時間かかる単調な作業にも関わらず、言われた通りに動いてくれるウィリアムは、文句の一言も言うこともなく私に付き合ってくれた。
この作家の他の作品
表紙を見る
夜会での婚約者からの、いきなりの婚約破棄!
けれど、伯爵令嬢ルシールには
婚約者ロベルトとは良い友人のような
おだやかな関係を築いていると思って居たし
、婚約破棄されてしまうような覚えもなかった。
しかし、されてしまったものは仕方ないと夜会からの帰り道、
ロベルトの友人若くして公爵位を継いだ
ニコラスに声を掛けられるのだが……。
現実主義ドライ令嬢がいつのまにか愛されていた公爵に
囲い込まれて一本道しか行けなくなる話。
表紙を見る
異世界恋愛が好き……そんな私、大好きだった小説『ドキデキ』の世界に転生してモブ令嬢になっていた!
主人公二人の素敵場面を観察していると、注意して来た美形の男性……あれ? これから陥れられて全てを奪われるラスボスになるはずの王弟ではない?
こっ、これって!! 転生者の醍醐味、救いたい不遇キャラを救って、私も一緒に幸せになります!
表紙を見る
グレンジャー伯爵令嬢ウェンディは父が友人に裏切られ、
社交界デビューを目前にして無一文になってしまった。
父は異国へと一人出稼ぎに行ってしまい、
行く宛てのない姉を心配する弟を安心させるために、
以前邸で働いていた竜騎士を頼ることに。
彼が働くアレイスター竜騎士団は『恋愛禁止』という厳格な規則があり、
そのため若い女性は働いていない。
しかし、ウェンディは竜力を持つ貴族の血を引く女性にしかなれないという
『子竜守』として特別に採用されることになり……。
子竜守として働くことになった没落貴族令嬢が、
不器用だけどとても優しい団長と恋愛禁止な竜騎士団で働くために
秘密の契約結婚をすることなってしまう、
ほのぼの子竜育てありな可愛い恋物語。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…