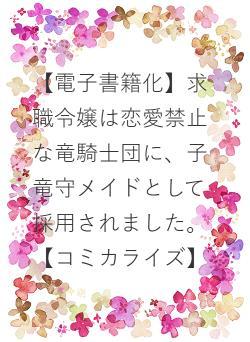私とウィリアムは久しぶりに同伴して夜会に出て、仲睦まじい婚約者らしく寄り添っていた。
舞踏会のはじまりに、二回ほど踊った。
これは、婚約している男女にしか許されないことだ。三回目は結婚している夫婦のみ。
それとなくダスレイン大臣を確認すると、これまでの親しみのある好々爺のような印象が一変。何も思い通りにならない苛立ちでか、人相がすっかり悪くなってしまっていた。
あのような様子では、とても近づきづらく、これまで懇意にしていた人たちも離れていってしまうと思うけれど、それはもうあの人の自業自得よね。
今もダスレイン大臣の周囲には円を描くように空間が出来ていて、ピリピリとした空気を身にまとう彼に話しかけようと思う者は居ないようだ。
対して、私のすぐ傍に居るウィリアムは、今までは幽閉されていた王太子だった。
けれど、成人の年齢になり、こうして表に顔を見せるようになっていまえば、これまで不遇だった派閥が目の色を変えて優秀な彼に近づきたがった。
今も現王とは距離を置いている権力の強い公爵が、ぜひ我が邸の夜会へと誘いに来たところだった。
舞踏会のはじまりに、二回ほど踊った。
これは、婚約している男女にしか許されないことだ。三回目は結婚している夫婦のみ。
それとなくダスレイン大臣を確認すると、これまでの親しみのある好々爺のような印象が一変。何も思い通りにならない苛立ちでか、人相がすっかり悪くなってしまっていた。
あのような様子では、とても近づきづらく、これまで懇意にしていた人たちも離れていってしまうと思うけれど、それはもうあの人の自業自得よね。
今もダスレイン大臣の周囲には円を描くように空間が出来ていて、ピリピリとした空気を身にまとう彼に話しかけようと思う者は居ないようだ。
対して、私のすぐ傍に居るウィリアムは、今までは幽閉されていた王太子だった。
けれど、成人の年齢になり、こうして表に顔を見せるようになっていまえば、これまで不遇だった派閥が目の色を変えて優秀な彼に近づきたがった。
今も現王とは距離を置いている権力の強い公爵が、ぜひ我が邸の夜会へと誘いに来たところだった。
……色々と、やんごとなき理由があるにせよ。
血が繋がった息子だというのに教育も授けずに幽閉していたなんて、良識ある人から見れば、臣下として忠誠を誓う国王陛下のなさったことだと言っても、納得しがたい部分は多かったと思う。
それもこれも、いずれ解決してしまう問題だけれどね。
金採掘を見事に大成功させた私たちは、頼りになるフランツを始めとするオブライエン一家を、護衛として雇うことに成功した。
あの金鉱山には途方もない量が埋蔵されていて、ウィリアムは一生お金に困ることはないだろう。
……それは、ウィリアムがシュレジエン王国の国王になったとしても同じことだ。
年々価値の上がり続ける金は、優良な投資対象としても大富豪たちに購入される。
彼らは金を『将来的に価値が上がり続けるもの』として、金庫に積み上げ貯めるだけ貯め込んでいるので、そうそうのことでは吐き出されない。
つまり、彼らに売った金が流通されなければ、価値は崩れない。
私たちには、いくらでも、売却先は見つかるのだ。
血が繋がった息子だというのに教育も授けずに幽閉していたなんて、良識ある人から見れば、臣下として忠誠を誓う国王陛下のなさったことだと言っても、納得しがたい部分は多かったと思う。
それもこれも、いずれ解決してしまう問題だけれどね。
金採掘を見事に大成功させた私たちは、頼りになるフランツを始めとするオブライエン一家を、護衛として雇うことに成功した。
あの金鉱山には途方もない量が埋蔵されていて、ウィリアムは一生お金に困ることはないだろう。
……それは、ウィリアムがシュレジエン王国の国王になったとしても同じことだ。
年々価値の上がり続ける金は、優良な投資対象としても大富豪たちに購入される。
彼らは金を『将来的に価値が上がり続けるもの』として、金庫に積み上げ貯めるだけ貯め込んでいるので、そうそうのことでは吐き出されない。
つまり、彼らに売った金が流通されなければ、価値は崩れない。
私たちには、いくらでも、売却先は見つかるのだ。
「……オブライエン一家は、本当に有能でしたわね。彼らをまとめて護衛として雇えることになったのは、本当に幸運なことでした」
実はダスレイン大臣は、自分の『王族たちを仲違いさせて王位簒奪する』という目的のため、なり振り構わずにエレインとウィリアムに定期的に暗殺者を送るようになった。
自分が狙っていたタイミングで、私たちから情報を得ていたエレインを、暗殺出来なかったと言うのも大きかっただろう。
既にエレインはダスレイン大臣の元へスパイを送り、彼の行動は彼女には筒抜けなのだ。
流石は有能過ぎる、ウィリアムの姉と言ったところ。
彼女が小説内で生きていたなら、この上ない味方で居てくれただろう……今、まさにそうなっている訳だけれど、そう思うと胸が熱くなる。
まだ、ダスレイン大臣が暗殺者を送った証拠が出揃ってもいない段階なので、自由に泳がせて捕らえていないけれど……それだってもう、時間の問題だわ。
「ん? ……モニカ!」
ウィリアムは誰かにぶつかられて、手に持っていたワインを私のドレスにこぼしてしまった。
あら……これは大変。
実はダスレイン大臣は、自分の『王族たちを仲違いさせて王位簒奪する』という目的のため、なり振り構わずにエレインとウィリアムに定期的に暗殺者を送るようになった。
自分が狙っていたタイミングで、私たちから情報を得ていたエレインを、暗殺出来なかったと言うのも大きかっただろう。
既にエレインはダスレイン大臣の元へスパイを送り、彼の行動は彼女には筒抜けなのだ。
流石は有能過ぎる、ウィリアムの姉と言ったところ。
彼女が小説内で生きていたなら、この上ない味方で居てくれただろう……今、まさにそうなっている訳だけれど、そう思うと胸が熱くなる。
まだ、ダスレイン大臣が暗殺者を送った証拠が出揃ってもいない段階なので、自由に泳がせて捕らえていないけれど……それだってもう、時間の問題だわ。
「ん? ……モニカ!」
ウィリアムは誰かにぶつかられて、手に持っていたワインを私のドレスにこぼしてしまった。
あら……これは大変。
淡い色のドレスだったから、もう使えないわね。染め替えしようかしら。
……その場はシーンと静まり返り、私たちの挙動を皆が注目していた。
「もう! ウィリアム様。ワインをこぼすなんて、駄目ですよ。お詫びに新しいドレス買って下さいね」
「ああ。悪かった。モニカ」
ウィリアムはそう言って謝罪してくれたので、私はにっこり微笑み甘えるように彼の腕にしがみ付いて小声で囁いた。
「わかっています……ダスレイン大臣の仕業ですね。ウィリアム様は気にしないでください。私たちの関係を確認しているのでしょう」
悪役令嬢モニカ・ラザルスの悪行は、オブライエン一家の件の通り広く知られていた。
短絡的な考えを持つ彼女は、王族に虐げられている王太子ウィリアムを虐めることで、貴族の中での自分の地位が上がると勘違いしていたのだ。
……そんな訳が、あるはずないでしょ。
臣下たる貴族には王族が絶対的権力を持っているとは言えど、全員が全員、その先のことを考えられないような愚かな人ばかりではない。
……その場はシーンと静まり返り、私たちの挙動を皆が注目していた。
「もう! ウィリアム様。ワインをこぼすなんて、駄目ですよ。お詫びに新しいドレス買って下さいね」
「ああ。悪かった。モニカ」
ウィリアムはそう言って謝罪してくれたので、私はにっこり微笑み甘えるように彼の腕にしがみ付いて小声で囁いた。
「わかっています……ダスレイン大臣の仕業ですね。ウィリアム様は気にしないでください。私たちの関係を確認しているのでしょう」
悪役令嬢モニカ・ラザルスの悪行は、オブライエン一家の件の通り広く知られていた。
短絡的な考えを持つ彼女は、王族に虐げられている王太子ウィリアムを虐めることで、貴族の中での自分の地位が上がると勘違いしていたのだ。
……そんな訳が、あるはずないでしょ。
臣下たる貴族には王族が絶対的権力を持っているとは言えど、全員が全員、その先のことを考えられないような愚かな人ばかりではない。
誰かを理由なく虐めているなら、同じようなことを好むような下劣な人たちにしか、そんな行動は認めてもらえないわよ。
「わかった。好きなドレスを買うと約束する……そろそろ帰ろうか」
ワインで汚れてしまったドレスで、舞踏会の会場に居るわけにはいかない。私たちは周囲の貴族に礼をして離宮へと帰ることになった。
私は離宮に帰ってすぐ、ここに置きっぱなしにしているお父様のオペラグラスを持って窓際に立った。
「ふふふ。これで、全て上手く行きましたね。ウィリアム様」
「……確認のため聞いておくが、今、お前は何をしているんだ。モニカ」
「現地確認です。物作りの現場も人材を使う仕事も、何事も現場が命なんです。この目で確認することが何よりも大事なのですよ」
私はオペラグラスを向けた先、執務棟の中のダスレイン大臣の部屋を見ていた。
私たちが貴族たちと歓談し、仲睦まじい様子を見せていたせいか、以前より多くの窓は割れ暴れ回っているようだった。
「あらあら。思惑と違ったから、執務室の中のものを破壊ですか……? いけませんね」
「わかった。好きなドレスを買うと約束する……そろそろ帰ろうか」
ワインで汚れてしまったドレスで、舞踏会の会場に居るわけにはいかない。私たちは周囲の貴族に礼をして離宮へと帰ることになった。
私は離宮に帰ってすぐ、ここに置きっぱなしにしているお父様のオペラグラスを持って窓際に立った。
「ふふふ。これで、全て上手く行きましたね。ウィリアム様」
「……確認のため聞いておくが、今、お前は何をしているんだ。モニカ」
「現地確認です。物作りの現場も人材を使う仕事も、何事も現場が命なんです。この目で確認することが何よりも大事なのですよ」
私はオペラグラスを向けた先、執務棟の中のダスレイン大臣の部屋を見ていた。
私たちが貴族たちと歓談し、仲睦まじい様子を見せていたせいか、以前より多くの窓は割れ暴れ回っているようだった。
「あらあら。思惑と違ったから、執務室の中のものを破壊ですか……? いけませんね」
もちろん。私は前世知識という彼から見れば異常なチートを手にしているから余裕を持ってそんな光景を見ていられるのかも知れない。
「おい。何が見えるんだ?」
ウィリアムが近づいて来たので、私はオペラグラスを渡した。
ダスレイン大臣は、まさか自室がこんな風に覗かれているなんて夢にも思っていないので、黒い影がわかりやすく暴れ回っているのが良く見えるはずだ。
何かに失敗したとて、怒ったり落ち込んだりは、せめて、邸に帰ってからにするべきだと思うわ。
ましてや、自らの職場で人や物に当たり散らすなどと……悪役の名に相応しいとても見事な暴れっぷりだけれど。
「ダスレイン大臣も自分の企みが上手くいかないからって、冷静さを保てないなんていけませんね」
「は? あれは、ダスレイン大臣なのか? あの、暴れ回っている賊のような影は。おい。あいつ、何かを割れた窓から投げたぞ」
あの影の正体が、彼を恨む賊の方がまだ良かったかも知れない。
大臣本人が暴れ回って、執務室を半壊させているなんて、とてもではないけれど笑えないもの。
「おい。何が見えるんだ?」
ウィリアムが近づいて来たので、私はオペラグラスを渡した。
ダスレイン大臣は、まさか自室がこんな風に覗かれているなんて夢にも思っていないので、黒い影がわかりやすく暴れ回っているのが良く見えるはずだ。
何かに失敗したとて、怒ったり落ち込んだりは、せめて、邸に帰ってからにするべきだと思うわ。
ましてや、自らの職場で人や物に当たり散らすなどと……悪役の名に相応しいとても見事な暴れっぷりだけれど。
「ダスレイン大臣も自分の企みが上手くいかないからって、冷静さを保てないなんていけませんね」
「は? あれは、ダスレイン大臣なのか? あの、暴れ回っている賊のような影は。おい。あいつ、何かを割れた窓から投げたぞ」
あの影の正体が、彼を恨む賊の方がまだ良かったかも知れない。
大臣本人が暴れ回って、執務室を半壊させているなんて、とてもではないけれど笑えないもの。
「ウィリアム様。このように、何か上手くいかないことがあっても、あのようなメンタルの悪化は、ただの時間の無駄です。良い見本になりましたわね。それに、お金の無駄遣いとも言えます。あ……ふふふ。あらあら。国王陛下がそろそろ、ダスレイン大臣の執務室へと辿り着きそうですね」
明るい廊下を歩く仰々しい人数の影は、オペラグラスを使わなくても、そうと知ることが出来た。
国王の移動には、多くの側近は侍従が付きそうものなのだ。
「え? ああ。もしかして、さっき姉上の宮に寄っていたのは……」
ウィリアムは呆れたように言ったので、私はにっこり微笑んで頷いた。
実は私はエレインに頼んで、国王陛下をダスレイン大臣の執務室へと向かってもらうようにしていたのだ。
以前に見た彼の姿を国王が見られたなら、どうなるかしらとは思ったのだけれど、実際のところ、私の想像よりも酷いことになってしまっていた。
あんな……言い訳のしようもない、思い通りにならないと暴れ回るとんでもない姿を国王に見られて、ダスレイン大臣はどれだけ焦ってしまうのかしら。
明るい廊下を歩く仰々しい人数の影は、オペラグラスを使わなくても、そうと知ることが出来た。
国王の移動には、多くの側近は侍従が付きそうものなのだ。
「え? ああ。もしかして、さっき姉上の宮に寄っていたのは……」
ウィリアムは呆れたように言ったので、私はにっこり微笑んで頷いた。
実は私はエレインに頼んで、国王陛下をダスレイン大臣の執務室へと向かってもらうようにしていたのだ。
以前に見た彼の姿を国王が見られたなら、どうなるかしらとは思ったのだけれど、実際のところ、私の想像よりも酷いことになってしまっていた。
あんな……言い訳のしようもない、思い通りにならないと暴れ回るとんでもない姿を国王に見られて、ダスレイン大臣はどれだけ焦ってしまうのかしら。
「どんな表情になってしまうか、私も近くで見たかったです。なんだか、とっても面白いことになりそうですね」
「……俺はお前が仕事が出来すぎて、少々怖くなる時がある」
ウィリアムはそう言ったので、私は嬉しくなって頭を下げた。
「まあ……それは、私にとって一番の褒め言葉ですわ。ウィリアム様。ありがとうございます」
「いや……まったく褒めてない。俺が言いたかったのは、そういった意味ではない」
困ったように微笑むウィリアムに私は肩を竦めて、彼に貸していたオペラグラスを受け取った。
「……俺はお前が仕事が出来すぎて、少々怖くなる時がある」
ウィリアムはそう言ったので、私は嬉しくなって頭を下げた。
「まあ……それは、私にとって一番の褒め言葉ですわ。ウィリアム様。ありがとうございます」
「いや……まったく褒めてない。俺が言いたかったのは、そういった意味ではない」
困ったように微笑むウィリアムに私は肩を竦めて、彼に貸していたオペラグラスを受け取った。
「……見事な手際だったわね。モニカ。ダスレイン大臣は執務室を破壊しているところを目撃したお父様を怒らせて、一時的とは言え謹慎処分。政治的には、立派な失脚よ。みんな貴女のおかげね。私と弟を守ってくれてありがとう」
「まあ。エレイン様。お褒めいただき、ありがとうございます。私にとって何よりのお言葉にございます」
エレイン様の宮でのお茶会に呼ばれた私とウィリアムは、異国から特別に取り寄せたというお茶を頂きながら、ダスレイン大臣がその後どうなったのかという話をお聞きしていた。
……とは言え、あの時の私が何をしたかと言うと、エレイン様に『国王陛下をダスレイン大臣の執務室に向かうように働きかけてください』と、お願いしたことだけ。
まさかここまで思惑通りに上手くいってしまうなんて、私自身も驚いている。
空き時間を見て度々観察していたところ、ダスレイン大臣は何か気に入らないことがあれば、執務室で暴れ散らす悪癖があったようだ。
けれど、それは人の居ない深夜にだいたい行われ、側近たちは朝までに、必死でそれを元通りにしていたらしい。
人が良い温厚そうな外見とは違い、とてもとても性格の悪い悪役なので、ダスレイン大臣の側近は彼に弱みを握られ、絶対的な忠誠を誓わされた者ばかり。
つまり、逆らうことが許されないし、情報漏洩などしようものなら、奈落の底に突き落とされてしまうだろう。
「まあ。エレイン様。お褒めいただき、ありがとうございます。私にとって何よりのお言葉にございます」
エレイン様の宮でのお茶会に呼ばれた私とウィリアムは、異国から特別に取り寄せたというお茶を頂きながら、ダスレイン大臣がその後どうなったのかという話をお聞きしていた。
……とは言え、あの時の私が何をしたかと言うと、エレイン様に『国王陛下をダスレイン大臣の執務室に向かうように働きかけてください』と、お願いしたことだけ。
まさかここまで思惑通りに上手くいってしまうなんて、私自身も驚いている。
空き時間を見て度々観察していたところ、ダスレイン大臣は何か気に入らないことがあれば、執務室で暴れ散らす悪癖があったようだ。
けれど、それは人の居ない深夜にだいたい行われ、側近たちは朝までに、必死でそれを元通りにしていたらしい。
人が良い温厚そうな外見とは違い、とてもとても性格の悪い悪役なので、ダスレイン大臣の側近は彼に弱みを握られ、絶対的な忠誠を誓わされた者ばかり。
つまり、逆らうことが許されないし、情報漏洩などしようものなら、奈落の底に突き落とされてしまうだろう。
この作家の他の作品
表紙を見る
夜会での婚約者からの、いきなりの婚約破棄!
けれど、伯爵令嬢ルシールには
婚約者ロベルトとは良い友人のような
おだやかな関係を築いていると思って居たし
、婚約破棄されてしまうような覚えもなかった。
しかし、されてしまったものは仕方ないと夜会からの帰り道、
ロベルトの友人若くして公爵位を継いだ
ニコラスに声を掛けられるのだが……。
現実主義ドライ令嬢がいつのまにか愛されていた公爵に
囲い込まれて一本道しか行けなくなる話。
表紙を見る
異世界恋愛が好き……そんな私、大好きだった小説『ドキデキ』の世界に転生してモブ令嬢になっていた!
主人公二人の素敵場面を観察していると、注意して来た美形の男性……あれ? これから陥れられて全てを奪われるラスボスになるはずの王弟ではない?
こっ、これって!! 転生者の醍醐味、救いたい不遇キャラを救って、私も一緒に幸せになります!
表紙を見る
グレンジャー伯爵令嬢ウェンディは父が友人に裏切られ、
社交界デビューを目前にして無一文になってしまった。
父は異国へと一人出稼ぎに行ってしまい、
行く宛てのない姉を心配する弟を安心させるために、
以前邸で働いていた竜騎士を頼ることに。
彼が働くアレイスター竜騎士団は『恋愛禁止』という厳格な規則があり、
そのため若い女性は働いていない。
しかし、ウェンディは竜力を持つ貴族の血を引く女性にしかなれないという
『子竜守』として特別に採用されることになり……。
子竜守として働くことになった没落貴族令嬢が、
不器用だけどとても優しい団長と恋愛禁止な竜騎士団で働くために
秘密の契約結婚をすることなってしまう、
ほのぼの子竜育てありな可愛い恋物語。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…