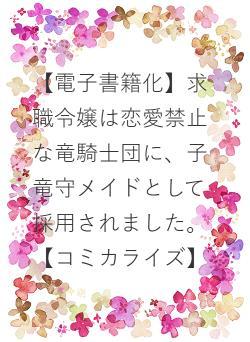何なの……物語の進行上で、キャンディスと出会う前のウィリアムは不幸でないといけないとは言え、あまりにこれは辛すぎない?
私は王太子ウィリアムには、とりあえず婚約者が居なければと定められた令嬢だから、宮に入ることは許されているけど、話すことと言えば彼自身を常に否定し続け罵る言葉しか口から出なかった。
いくらヒロインキャンディスが彼の前に現れれば助けて貰えるとは言っても、これではあんまりだと思うわ。
……少しくらい、彼の環境改善をしてあげても、良いと思うの。
「え。お前……本当に戻って来たのか……?」
髪を切るための鋏を持って戻って来た私を見て、大きなソファで寝転がりくつろいでいたウィリアムは、非常に驚いて身を起こした。
私がウィリアムに『毛玉を取らせてください』と言ったことを、白昼夢で見た夢幻(ゆめまぼろし)だと思っているのかもしれない。
これは現実なのよ。申し訳ないけど、頭にある毛玉は取らせてもらうわ。
「もうっ……お待ちくださいと、言ったではないですか。ほら、ここに座ってください」
私は彼の座っているソファの座面を指差すと、ウィリアムは不思議なくらい素直に指示に従ってくれた。
髪を整えるために切っても散らばらないようにと、私は彼にここに来る前に物色していた適当な白いテーブルクロスを被せて首のあたりで括った。
私はその姿を見て、ふふっと微笑んだ。
ずいぶんと可愛らしい、大きなてるてる坊主の出来上がり。
「……もう良い。よくわからないが、お前の好きにしろ。髪はまた生えてくるし、どうとでもしてくれ」
モニカの思惑がわからずに投げやりに言ったウィリアムに、私は大丈夫と肩をとんと叩いた。
「はい。仕事はちゃんとしますよ。ほら……」
私は王太子ウィリアムには、とりあえず婚約者が居なければと定められた令嬢だから、宮に入ることは許されているけど、話すことと言えば彼自身を常に否定し続け罵る言葉しか口から出なかった。
いくらヒロインキャンディスが彼の前に現れれば助けて貰えるとは言っても、これではあんまりだと思うわ。
……少しくらい、彼の環境改善をしてあげても、良いと思うの。
「え。お前……本当に戻って来たのか……?」
髪を切るための鋏を持って戻って来た私を見て、大きなソファで寝転がりくつろいでいたウィリアムは、非常に驚いて身を起こした。
私がウィリアムに『毛玉を取らせてください』と言ったことを、白昼夢で見た夢幻(ゆめまぼろし)だと思っているのかもしれない。
これは現実なのよ。申し訳ないけど、頭にある毛玉は取らせてもらうわ。
「もうっ……お待ちくださいと、言ったではないですか。ほら、ここに座ってください」
私は彼の座っているソファの座面を指差すと、ウィリアムは不思議なくらい素直に指示に従ってくれた。
髪を整えるために切っても散らばらないようにと、私は彼にここに来る前に物色していた適当な白いテーブルクロスを被せて首のあたりで括った。
私はその姿を見て、ふふっと微笑んだ。
ずいぶんと可愛らしい、大きなてるてる坊主の出来上がり。
「……もう良い。よくわからないが、お前の好きにしろ。髪はまた生えてくるし、どうとでもしてくれ」
モニカの思惑がわからずに投げやりに言ったウィリアムに、私は大丈夫と肩をとんと叩いた。
「はい。仕事はちゃんとしますよ。ほら……」
頭の上にあった大きな毛玉を、ザンっと音をさせて鋏で切り取り払うと、綺麗な黒髪がふさっと彼の襟足にかかった。
身繕いする物だけは、王族として最高級のものを使っているのか、高級石けんの良い匂いがした。
……いいえ。それだって当たり前のことよ。だって、ウィリアムは間違いなく王の血を受け継ぐ王族なのだから。
それも……将来は王位を受け継ぐ権利を持つ王太子よ。
「軽い」
ウィリアムは毛玉のなくなった自分の頭を触って、呆然として呟いた。
髪の一本一本は羽根のように軽いとは言え、あれだけ寄り集まれば重かったのかも知れない。
「ええ。そうでしょうね。あんなにも大きな毛玉があったのですもの。けれど、ウィリアム様の髪は柔らかくて癖があって、季節的に空気が乾燥しているので、香油を付けないとまた毛玉が出来てしまうと思います。一度、お風呂に入りましょう。私がこういった髪の手入れを基本から、教えてあげますから」
身繕いする物だけは、王族として最高級のものを使っているのか、高級石けんの良い匂いがした。
……いいえ。それだって当たり前のことよ。だって、ウィリアムは間違いなく王の血を受け継ぐ王族なのだから。
それも……将来は王位を受け継ぐ権利を持つ王太子よ。
「軽い」
ウィリアムは毛玉のなくなった自分の頭を触って、呆然として呟いた。
髪の一本一本は羽根のように軽いとは言え、あれだけ寄り集まれば重かったのかも知れない。
「ええ。そうでしょうね。あんなにも大きな毛玉があったのですもの。けれど、ウィリアム様の髪は柔らかくて癖があって、季節的に空気が乾燥しているので、香油を付けないとまた毛玉が出来てしまうと思います。一度、お風呂に入りましょう。私がこういった髪の手入れを基本から、教えてあげますから」
母の死後、立場が一気に悪くなり何年も身支度などの世話をしてくれる使用人が居ずに、これまで身支度を見よう見まねでするしかなかったウィリアムは、自分の髪の適切な手入れ法を知らないだけなのだ。
私は誰かに何かを教えることには慣れているし、なんなら優秀なウィリアムは誰にも教わることなく本を読んだだけで、すべてを学んだ人だ。
きっと、すぐに自ら出来る手入れ方法を、すぐに習得してしまうはずだ。
私が彼の髪の毛の長さを整えつつそう言うと、ウィリアムは驚いた表情で私を見た。
「えっ……待ってくれ。お前が俺と風呂に一緒に入るのか?」
「あ。そうですね! その方が、やり方を伝えやすいし、わかりやすいかも知れないです。普段から、乾燥させないように香油を桶に一滴だけ垂らす方法もあるんですよ。付けすぎては、逆効果になってしまうかもしれないですけど……」
髪に香油を付けすぎて海藻みたいなベタベタ髪な王子様を脳内で想像してしまって、私はそれは絶対に嫌だと思ってしまった。
周囲から勝手な期待をされてはガッカリされて、美形の王子様も何かと大変だわ。
私は誰かに何かを教えることには慣れているし、なんなら優秀なウィリアムは誰にも教わることなく本を読んだだけで、すべてを学んだ人だ。
きっと、すぐに自ら出来る手入れ方法を、すぐに習得してしまうはずだ。
私が彼の髪の毛の長さを整えつつそう言うと、ウィリアムは驚いた表情で私を見た。
「えっ……待ってくれ。お前が俺と風呂に一緒に入るのか?」
「あ。そうですね! その方が、やり方を伝えやすいし、わかりやすいかも知れないです。普段から、乾燥させないように香油を桶に一滴だけ垂らす方法もあるんですよ。付けすぎては、逆効果になってしまうかもしれないですけど……」
髪に香油を付けすぎて海藻みたいなベタベタ髪な王子様を脳内で想像してしまって、私はそれは絶対に嫌だと思ってしまった。
周囲から勝手な期待をされてはガッカリされて、美形の王子様も何かと大変だわ。
「待て待て待て……何を言っている。流石にそれは……嫌だ! ……というか、無理だ。言葉で聞いても覚えられるから、口で教えてくれ」
何故かその時、ウィリアムは涙目になって訴えたので、私は幼い弟のお世話もし慣れているのだし、特に気にしないのにと不思議に思いつつも頷いた。
「そうですか……? そうですね。これから私が言ったことを、毎日してみてください。ろくなお手入れしていなくても、こんなにも綺麗な髪なのです! ちゃんと手入れをすれば、もっともっと艶めいて輝くでしょう……」
ウィリアムは小説のヒーローに相応しく、異性の目を惹くような美しい容姿を持っている。
お飾りの王太子ウィリアムの抱えている問題は、彼が少々幸せになってもなくならないもの。
不遇を耐える悲壮な表情も魅力的だろうけれど、ヒロインキャンディスと出会う前に、少々幸せだったとしても何の問題もないはずだ。
何故かその時、ウィリアムは涙目になって訴えたので、私は幼い弟のお世話もし慣れているのだし、特に気にしないのにと不思議に思いつつも頷いた。
「そうですか……? そうですね。これから私が言ったことを、毎日してみてください。ろくなお手入れしていなくても、こんなにも綺麗な髪なのです! ちゃんと手入れをすれば、もっともっと艶めいて輝くでしょう……」
ウィリアムは小説のヒーローに相応しく、異性の目を惹くような美しい容姿を持っている。
お飾りの王太子ウィリアムの抱えている問題は、彼が少々幸せになってもなくならないもの。
不遇を耐える悲壮な表情も魅力的だろうけれど、ヒロインキャンディスと出会う前に、少々幸せだったとしても何の問題もないはずだ。
「ああ……しかし……どういうことなんだ。何がしたいんだ。お前。いきなり、言っていることが真逆になったぞ! あの時に、悪魔でも憑いたのか? いや、状況的には天使か? どうか何を思って、いきなり親切にしてくれるのか、理由を率直に教えてくれ。正直に言って、俺には何が起こっているのか良くわからない」
短くなった髪を心配そうに触ったウィリアムは、私が急に自分に親身になったことに戸惑いを隠せない。私は掛けていたテーブルクロスを彼から外して、切った髪を包んで纏めると、にっこり笑って言った。
「ええ。お任せください。私が、貴方をきっと幸せにします!!」
きっと幸せにしてみせるわ。これから先のことなら、熱心な読者である私が一番に理解しているもの。
「……はぁあ? 何を言い出す……なんなんだ? もう、本当に良くわからない」
思いも寄らないだろう宣言に呆気に取られたウィリアムは、自分がやるべき仕事を見つけいきいきした顔の私を見て顔を顰めた。
短くなった髪を心配そうに触ったウィリアムは、私が急に自分に親身になったことに戸惑いを隠せない。私は掛けていたテーブルクロスを彼から外して、切った髪を包んで纏めると、にっこり笑って言った。
「ええ。お任せください。私が、貴方をきっと幸せにします!!」
きっと幸せにしてみせるわ。これから先のことなら、熱心な読者である私が一番に理解しているもの。
「……はぁあ? 何を言い出す……なんなんだ? もう、本当に良くわからない」
思いも寄らないだろう宣言に呆気に取られたウィリアムは、自分がやるべき仕事を見つけいきいきした顔の私を見て顔を顰めた。
「モニカ。あの子は……今日は、何をしていたの?」
王女の身分に相応しく豪華なドレスに身を包んだ美しいエレイン様は、彼女の取り巻きである私の隣を通り抜けようとしたその時に、さりげなく質問をした。
「つつがなく、過ごされております……体調なども良く食事も三食、きちんと食べられております。エレイン様」
以前までの悪役令嬢モニカは、こういった時に嬉々として、今日はどれだけ酷い言葉を使って彼を虐めたとエレイン様に報告をしていた。
そうすれば、彼女に喜んで貰えると思い込んでいたからだ……本当に、大きな勘違いだった訳だけれど。
「……そう」
取り巻きの一人である私へ耳打ちをした後で、感情のない返事をし立ち去る、素っ気ない態度の第一王女エレイン様。
けれど、小説を読んでいる私は知っているのだ……今のままでは何も出来ない彼女が、幽閉されている弟ウィリアムを、心から心配しているのを。
私は記憶を取り戻してからというもの、彼へ暴言を吐くだけのために、たまにしか行かなかったウィリアムの宮へと日参するようになった。
王女の身分に相応しく豪華なドレスに身を包んだ美しいエレイン様は、彼女の取り巻きである私の隣を通り抜けようとしたその時に、さりげなく質問をした。
「つつがなく、過ごされております……体調なども良く食事も三食、きちんと食べられております。エレイン様」
以前までの悪役令嬢モニカは、こういった時に嬉々として、今日はどれだけ酷い言葉を使って彼を虐めたとエレイン様に報告をしていた。
そうすれば、彼女に喜んで貰えると思い込んでいたからだ……本当に、大きな勘違いだった訳だけれど。
「……そう」
取り巻きの一人である私へ耳打ちをした後で、感情のない返事をし立ち去る、素っ気ない態度の第一王女エレイン様。
けれど、小説を読んでいる私は知っているのだ……今のままでは何も出来ない彼女が、幽閉されている弟ウィリアムを、心から心配しているのを。
私は記憶を取り戻してからというもの、彼へ暴言を吐くだけのために、たまにしか行かなかったウィリアムの宮へと日参するようになった。
今日も今日とて彼の元へ向かえば、ウィリアムは私がスカートの裾に隠して何冊も持ち込んだ本を、お気に入りのソファへと腰掛けて読んでいた。
こうして実在の人物として目の当たりにするとわかりやすいけれど、ウィリアムは非常に頭が良い。
彼の抱える事情も事情なので教育はほとんど受けられていないはずなのに、私が軽く基本を教えれば、易々と応用まで幾通りか思いついてしまう。
頭が良すぎる上に、記憶力だって、良すぎている。教えているはずの私の覚え間違いや記憶違いを、あの時はこう言っていたと指摘されることだってある。
この短期間に、貴族学院を卒業出来るほどの学力は身につけてしまっていた。流石は、小説の中でのヒーローというものである。
主人公チートとは、かくあるものかと思ったり。
「お前。姉上には……この状況を、どう説明するんだよ。大丈夫なのか」
これまでウィリアムに対し散々『この私には、エレイン様が後ろ盾に付いている』とモニカが毒づいていたせいか、エレインの意向に逆らったように見える私の立場を心配してくれているようだ。
なんて、優しいの。
こうして実在の人物として目の当たりにするとわかりやすいけれど、ウィリアムは非常に頭が良い。
彼の抱える事情も事情なので教育はほとんど受けられていないはずなのに、私が軽く基本を教えれば、易々と応用まで幾通りか思いついてしまう。
頭が良すぎる上に、記憶力だって、良すぎている。教えているはずの私の覚え間違いや記憶違いを、あの時はこう言っていたと指摘されることだってある。
この短期間に、貴族学院を卒業出来るほどの学力は身につけてしまっていた。流石は、小説の中でのヒーローというものである。
主人公チートとは、かくあるものかと思ったり。
「お前。姉上には……この状況を、どう説明するんだよ。大丈夫なのか」
これまでウィリアムに対し散々『この私には、エレイン様が後ろ盾に付いている』とモニカが毒づいていたせいか、エレインの意向に逆らったように見える私の立場を心配してくれているようだ。
なんて、優しいの。
そんな酷いことをした張本人であるモニカの身体で思い出してしまうのも悲しいけれど、名前付きでSNSで書き込めば即時開示請求が裁判所を通るような暴言を、いくつも目の前で吐かれていたというのに。
ウィリアムは、人としての器が大きいのよ……誰にだって、出来ることではないわ。
「良いんです。エレイン様は、弟のウィリアム様をいつも心配しているので……実は私がここに来ていたのも、お姉様からの意向ですよ。意地悪されるとはわかっていても、貴方が何か困っていないか、ご飯は食べているか……どうしているのかを、少しでも知りたかったのです」
これは小説の後半で明かされる事実なのだけど、姉エレインは政治的な問題で幽閉されてしまった腹違いの弟を心配して、それとなく便宜を図っていたのだ。
使用人の中にも、彼女の息の掛かった者も居る。けれど、他の人の手前、私のようにウィリアムとは話せないけれど、何か困ったことがあれば、さりげなく助けているはずだ。
……けれど、悪役令嬢だったモニカは、エレインの本当の意図など知るよしもなかった。
ウィリアムは、人としての器が大きいのよ……誰にだって、出来ることではないわ。
「良いんです。エレイン様は、弟のウィリアム様をいつも心配しているので……実は私がここに来ていたのも、お姉様からの意向ですよ。意地悪されるとはわかっていても、貴方が何か困っていないか、ご飯は食べているか……どうしているのかを、少しでも知りたかったのです」
これは小説の後半で明かされる事実なのだけど、姉エレインは政治的な問題で幽閉されてしまった腹違いの弟を心配して、それとなく便宜を図っていたのだ。
使用人の中にも、彼女の息の掛かった者も居る。けれど、他の人の手前、私のようにウィリアムとは話せないけれど、何か困ったことがあれば、さりげなく助けているはずだ。
……けれど、悪役令嬢だったモニカは、エレインの本当の意図など知るよしもなかった。
エレインは意地悪い性格で短絡的な思考をする弟の婚約者モニカを、信用ならないと疑い、それでもモニカを使って弟のために何が出来るかと試行錯誤していたのだ。
ウィリアムがそんな優しい姉の思いを知ったその時には、エレインは暗殺されて故人になっている。彼は『お礼も言えなかった』と、悲しみに打ちひしがれ涙を流すしかなかった。
もちろん。私のここ最近の頑張りから身ぎれいになって、すっかり可愛くなったウィリアムに、そんな重い悲しみを与える訳にはいかないので、エレインの死については私が事前に回避しておこうと思っている。
……というか、ウィリアムに関する悲劇はすべて。
「はっ……姉上が……? そのようなことがあるはずがないだろう。俺は嫌われている……姉上の立場を思えば、それは無理もない話だ。あの人を恨んではいない」
まさか。ウィリアムを嫌っているなんて、そんな訳がない。エレインも可哀想なウィリアムになんとか優しくしてあげたかったけど、彼も知っての通り彼女の状況がそれを許さなかった。
ウィリアムがそんな優しい姉の思いを知ったその時には、エレインは暗殺されて故人になっている。彼は『お礼も言えなかった』と、悲しみに打ちひしがれ涙を流すしかなかった。
もちろん。私のここ最近の頑張りから身ぎれいになって、すっかり可愛くなったウィリアムに、そんな重い悲しみを与える訳にはいかないので、エレインの死については私が事前に回避しておこうと思っている。
……というか、ウィリアムに関する悲劇はすべて。
「はっ……姉上が……? そのようなことがあるはずがないだろう。俺は嫌われている……姉上の立場を思えば、それは無理もない話だ。あの人を恨んではいない」
まさか。ウィリアムを嫌っているなんて、そんな訳がない。エレインも可哀想なウィリアムになんとか優しくしてあげたかったけど、彼も知っての通り彼女の状況がそれを許さなかった。
この作家の他の作品
表紙を見る
夜会での婚約者からの、いきなりの婚約破棄!
けれど、伯爵令嬢ルシールには
婚約者ロベルトとは良い友人のような
おだやかな関係を築いていると思って居たし
、婚約破棄されてしまうような覚えもなかった。
しかし、されてしまったものは仕方ないと夜会からの帰り道、
ロベルトの友人若くして公爵位を継いだ
ニコラスに声を掛けられるのだが……。
現実主義ドライ令嬢がいつのまにか愛されていた公爵に
囲い込まれて一本道しか行けなくなる話。
表紙を見る
異世界恋愛が好き……そんな私、大好きだった小説『ドキデキ』の世界に転生してモブ令嬢になっていた!
主人公二人の素敵場面を観察していると、注意して来た美形の男性……あれ? これから陥れられて全てを奪われるラスボスになるはずの王弟ではない?
こっ、これって!! 転生者の醍醐味、救いたい不遇キャラを救って、私も一緒に幸せになります!
表紙を見る
グレンジャー伯爵令嬢ウェンディは父が友人に裏切られ、
社交界デビューを目前にして無一文になってしまった。
父は異国へと一人出稼ぎに行ってしまい、
行く宛てのない姉を心配する弟を安心させるために、
以前邸で働いていた竜騎士を頼ることに。
彼が働くアレイスター竜騎士団は『恋愛禁止』という厳格な規則があり、
そのため若い女性は働いていない。
しかし、ウェンディは竜力を持つ貴族の血を引く女性にしかなれないという
『子竜守』として特別に採用されることになり……。
子竜守として働くことになった没落貴族令嬢が、
不器用だけどとても優しい団長と恋愛禁止な竜騎士団で働くために
秘密の契約結婚をすることなってしまう、
ほのぼの子竜育てありな可愛い恋物語。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…