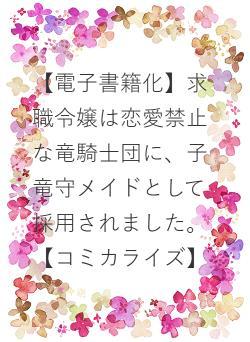私たちはこれまで固く閉ざされていた鉄扉を抜けて、奥の部屋へと通された。
オブライエン家のアジトは、私がなんとなく頭で想像していたよりも、かなり広い空間だった。部屋に至るまでの通路も長いし、何個も曲がり角があった。
私は記憶力がそこまで悪い方でもないけれど、初見であの道筋を覚えられる人は、なかなか少ないかもしれない。
だから、ここに住んで居れば、どんなに騎士団などが人数を揃えたとしても、土地勘のある彼らが捕らえられる可能性は低い。
それに地下街になんて、大人数揃えて侵入しても、すぐに勘付かれてしまう。裏稼業の住人たちが、協力し合えればもっとだろう。
だから、彼らは『暗殺一家』として有名なのに、アジトだと堂々と公表して地下街に住んでいるという訳なのね。
ふかふかのソファが並ぶ応接室へと座り、向かいには私たちと交渉するためのオブライエン一家側代表として、一人残ったフランツが座った。
「……実は、俺たち、オブライエン一家は、暗殺者を引退したいんです。それは、先代の祖父が先日亡くなってから、家族で話し合って……代々続く稼業だからと、別に続けなくて良いではないかという、話になっていて」
神妙な表情のフランツから想像つきもしなかった、とんでもない事を切り出された。
「え。オブライエン一家が……暗殺稼業を、引退したいと考えているのか……?」
ウィリアムはポカンとした表情で驚き、私の顔を嬉しそうに見たけれど……もしそうならば、彼らには渡りに船のはずの、私たちの護衛の依頼を受けていない理由がわからない。
もしかしたら……彼らには私たちの知らない、何かあるということなのかしら。
オブライエン家のアジトは、私がなんとなく頭で想像していたよりも、かなり広い空間だった。部屋に至るまでの通路も長いし、何個も曲がり角があった。
私は記憶力がそこまで悪い方でもないけれど、初見であの道筋を覚えられる人は、なかなか少ないかもしれない。
だから、ここに住んで居れば、どんなに騎士団などが人数を揃えたとしても、土地勘のある彼らが捕らえられる可能性は低い。
それに地下街になんて、大人数揃えて侵入しても、すぐに勘付かれてしまう。裏稼業の住人たちが、協力し合えればもっとだろう。
だから、彼らは『暗殺一家』として有名なのに、アジトだと堂々と公表して地下街に住んでいるという訳なのね。
ふかふかのソファが並ぶ応接室へと座り、向かいには私たちと交渉するためのオブライエン一家側代表として、一人残ったフランツが座った。
「……実は、俺たち、オブライエン一家は、暗殺者を引退したいんです。それは、先代の祖父が先日亡くなってから、家族で話し合って……代々続く稼業だからと、別に続けなくて良いではないかという、話になっていて」
神妙な表情のフランツから想像つきもしなかった、とんでもない事を切り出された。
「え。オブライエン一家が……暗殺稼業を、引退したいと考えているのか……?」
ウィリアムはポカンとした表情で驚き、私の顔を嬉しそうに見たけれど……もしそうならば、彼らには渡りに船のはずの、私たちの護衛の依頼を受けていない理由がわからない。
もしかしたら……彼らには私たちの知らない、何かあるということなのかしら。
「はい。ですが、こういう裏稼業を営むには、それなりに仁義を通さねばならず……裏社会の元締めから足抜け料に、法外な金額を要求されています。ですが、人を殺して金銭を得るような暗殺はもうしたくないというのが、俺たち家族の共通した意見なんです」
やはり、改まって話をするからには何かあると思って居たけれど、彼らが困窮してまで暗殺の仕事を受けられなくなっていたのは、こういう理由があったからだった。
確かに、現代社会でも裏稼業を足抜けする時には小指を……という話があるくらいだもの、彼らだって普通の家族に戻りたいけど戻れないから……だから、暗殺もせずに、飢えていたのね。
「仕事を選んでいた……というのは?」
「とんでもないことをした犯罪者でも、悪どい方法で、罪を逃れる汚い奴らも居ます。そういった奴らを片付ける依頼は受けるようにしています……ですが、そういう依頼の依頼人から、高額な金額は取れません」
暗殺一家でも仕事を選んでいるというのは、そういう事だったのね。
もし、そういう基準で仕事を選んでいたならば、悪役令嬢モニカからの依頼なんて、とんでもないと思うわよね。
やはり、改まって話をするからには何かあると思って居たけれど、彼らが困窮してまで暗殺の仕事を受けられなくなっていたのは、こういう理由があったからだった。
確かに、現代社会でも裏稼業を足抜けする時には小指を……という話があるくらいだもの、彼らだって普通の家族に戻りたいけど戻れないから……だから、暗殺もせずに、飢えていたのね。
「仕事を選んでいた……というのは?」
「とんでもないことをした犯罪者でも、悪どい方法で、罪を逃れる汚い奴らも居ます。そういった奴らを片付ける依頼は受けるようにしています……ですが、そういう依頼の依頼人から、高額な金額は取れません」
暗殺一家でも仕事を選んでいるというのは、そういう事だったのね。
もし、そういう基準で仕事を選んでいたならば、悪役令嬢モニカからの依頼なんて、とんでもないと思うわよね。
ここまで不思議だった事の流れは、納得出来たわ。
「……わかりました。私たちがその金額を用意すれば、王太子ウィリアム様とエレイン様の護衛として雇われてくださる……そういった認識で、よろしいですか?」
「おっ……おいっ。モニカ」
何か言いたそうなウィリアムには、右手を挙げてそれを制し、私はフランツを見つめた。
……おそらく、小説の中ではオブライエン一家はウィリアム一行を襲うために現れるけれど、それは撃退される。
けれど、あの時は激戦になり、ウィリアム側も多くの犠牲も出し、彼らは一定の成果も出した。
それゆえオブライエン一家はダスレイン大臣から、法外な足抜け料を前金で貰っていたとすれば……その後に、フランツがウィリアムの元に現れるのも、わかるわ。
彼はもうあの時に暗殺者ではなかったから、元盗賊と身分を偽りウィリアムと合流したのね……献身的といえるまでのフランツの活躍ぶりには、多少の罪悪感も含まれていたのかもしれない。
ああ……フランツったら、そんな切ない過去を持っていたのね。
「……わかりました。私たちがその金額を用意すれば、王太子ウィリアム様とエレイン様の護衛として雇われてくださる……そういった認識で、よろしいですか?」
「おっ……おいっ。モニカ」
何か言いたそうなウィリアムには、右手を挙げてそれを制し、私はフランツを見つめた。
……おそらく、小説の中ではオブライエン一家はウィリアム一行を襲うために現れるけれど、それは撃退される。
けれど、あの時は激戦になり、ウィリアム側も多くの犠牲も出し、彼らは一定の成果も出した。
それゆえオブライエン一家はダスレイン大臣から、法外な足抜け料を前金で貰っていたとすれば……その後に、フランツがウィリアムの元に現れるのも、わかるわ。
彼はもうあの時に暗殺者ではなかったから、元盗賊と身分を偽りウィリアムと合流したのね……献身的といえるまでのフランツの活躍ぶりには、多少の罪悪感も含まれていたのかもしれない。
ああ……フランツったら、そんな切ない過去を持っていたのね。
「俺たち一家が足抜け出来るような……その金さえあれば、そちらの護衛を引き受ける。しかし、護衛など表の職業だ。俺たちには転職することは、今は……許されないんだ」
フランツはその時、私たちの背後に立つ護衛騎士たちを見た。本来なら彼らはそういう職業に就きたいけれど、裏社会のルールで許されないだけだった。
「それでは、いくら足抜け料が必要なのですか」
私の言葉に暗い表情でぽつりとフランツが返した金額は、途方もないものだった。
……隣のウィリアムも、息を呑んで居たようだ。
裏社会の元締めというのから、オブライエン一家からもみかじめ料のようなものを取っていたということよね。
彼らは腕も良く、依頼料も高額で知られていた。それならば、元締めはこれまでにオブライエン一家から何もせずとも、相当な金額を貰っていたはずだ。
それがなくなるのだから、足抜け料に法外な高額をふっかけてきたというところね。悪党たちのボスは真の悪党なのだわ。
……けれど、前世記憶チートで色々とこの世界のことを知っている私には、出せない金額でもなかった。
フランツはその時、私たちの背後に立つ護衛騎士たちを見た。本来なら彼らはそういう職業に就きたいけれど、裏社会のルールで許されないだけだった。
「それでは、いくら足抜け料が必要なのですか」
私の言葉に暗い表情でぽつりとフランツが返した金額は、途方もないものだった。
……隣のウィリアムも、息を呑んで居たようだ。
裏社会の元締めというのから、オブライエン一家からもみかじめ料のようなものを取っていたということよね。
彼らは腕も良く、依頼料も高額で知られていた。それならば、元締めはこれまでにオブライエン一家から何もせずとも、相当な金額を貰っていたはずだ。
それがなくなるのだから、足抜け料に法外な高額をふっかけてきたというところね。悪党たちのボスは真の悪党なのだわ。
……けれど、前世記憶チートで色々とこの世界のことを知っている私には、出せない金額でもなかった。
「ええ。それでは、その額、前金としてご用意します。お二人の護衛費用については、また期間ごとにお支払いさせて頂きます」
「モニカ!?」
「本当ですか!?」
ウィリアムは非常に驚いた表情で私の名前を呼び、この金額は流石に無理と思っていたのか、諦めムードで暗い表情を浮かべていたフランツは思わず立ち上がっていた。
「落ち着いてください。これは、正式な取引です。私たちはオブライエン一家、つまり、貴方たちの力を必要としています……良いですね?」
フランツははっとした表情になり、恥ずかしそうに、もう一度座り直した。
「もちろんです。それが叶えられたなら、私たちはウィリアム王太子殿下の護衛として……臣下として忠実な働きを見せるとお約束します」
「……わかりました。それでは、またこちらから、ご連絡します」
「はい」
「おい。モニカ……」
「あ……ご確認しておきたいんですけど、フランツさんとの連絡方法って、手紙になりますか……?」
これが、私は良く忘れてしまうのだ。
会社員時代にも、交渉成立! と舞い上がり、握手をして機嫌良く建物を出て自社に戻れば、紹介された担当者の名刺をもらい忘れ、連絡先がわからない……という失敗が過去に良くあった。
ええ。良いことに浮かれて失敗してしまうのは、人の性(さが)なのよ。
オブライエン一家との交渉窓口フランツは、王都に懇意の酒場があるらしく、そこのオーナーに待ち合わせの日取りなどの手紙を渡せば伝わるから、お互いに連絡方法は、そこで伝え合おうということになった。
「モニカ!?」
「本当ですか!?」
ウィリアムは非常に驚いた表情で私の名前を呼び、この金額は流石に無理と思っていたのか、諦めムードで暗い表情を浮かべていたフランツは思わず立ち上がっていた。
「落ち着いてください。これは、正式な取引です。私たちはオブライエン一家、つまり、貴方たちの力を必要としています……良いですね?」
フランツははっとした表情になり、恥ずかしそうに、もう一度座り直した。
「もちろんです。それが叶えられたなら、私たちはウィリアム王太子殿下の護衛として……臣下として忠実な働きを見せるとお約束します」
「……わかりました。それでは、またこちらから、ご連絡します」
「はい」
「おい。モニカ……」
「あ……ご確認しておきたいんですけど、フランツさんとの連絡方法って、手紙になりますか……?」
これが、私は良く忘れてしまうのだ。
会社員時代にも、交渉成立! と舞い上がり、握手をして機嫌良く建物を出て自社に戻れば、紹介された担当者の名刺をもらい忘れ、連絡先がわからない……という失敗が過去に良くあった。
ええ。良いことに浮かれて失敗してしまうのは、人の性(さが)なのよ。
オブライエン一家との交渉窓口フランツは、王都に懇意の酒場があるらしく、そこのオーナーに待ち合わせの日取りなどの手紙を渡せば伝わるから、お互いに連絡方法は、そこで伝え合おうということになった。
「おい。モニカ。あれほどの金額を用意するなど簡単に言っていたが、本当に大丈夫なのか……?」
私たちは離宮へと戻り、ウィリアムは変装を解いてソファに座っていた。
ここに閉じ込められていた彼も、今では外出に慣れてしまっていて、物珍しく周囲を見まわし観察することもなくなった。
そんな慣れない様子も、それはそれで可愛かったのだけれど、すぐさま溶け込めるような振る舞いを身に付けたウィリアムは本当に覚えが良い。
成長スピードが異常なのだ。そういった優秀な人に対し、自ら教えられるということに、私は大きな喜びを覚えていた。
これまでに幾度となく、新人教育の経験を積んでいたのは、そのためにあったのではないかと思うほどだ。
「ええ。大丈夫ですわ……これは、内密にしていただきたいのですが、まだ見つかっていない、とある金山の在処を私は知っているのです」
小説の中でウィリアムとキャンディスの窮地(ピンチ)を救う、金山は王都近くにある。
それも、とてもわかりやすい目印があるのだけれど、いまだに誰かに見つかっていないのは、金策に困った主人公のために用意されているという奇跡的な物語補正のせいだと思う。
「……お前のその、よく分からない知識を持っている話は、俺ももう既に慣れた。それで、これからどうするんだ。ラザルス伯爵家に仕える騎士でも、場所の確認のために送り込むのか」
ウィリアムはそう聞いたので、私は首を横に振った。
「いえ。私がこの目で、実在するのか、どれほどの埋蔵量があるのか。現地を確認して来ます!」
別にラザルス家に使える護衛騎士たちを、私は信用していないと言う訳ではない。
私たちは離宮へと戻り、ウィリアムは変装を解いてソファに座っていた。
ここに閉じ込められていた彼も、今では外出に慣れてしまっていて、物珍しく周囲を見まわし観察することもなくなった。
そんな慣れない様子も、それはそれで可愛かったのだけれど、すぐさま溶け込めるような振る舞いを身に付けたウィリアムは本当に覚えが良い。
成長スピードが異常なのだ。そういった優秀な人に対し、自ら教えられるということに、私は大きな喜びを覚えていた。
これまでに幾度となく、新人教育の経験を積んでいたのは、そのためにあったのではないかと思うほどだ。
「ええ。大丈夫ですわ……これは、内密にしていただきたいのですが、まだ見つかっていない、とある金山の在処を私は知っているのです」
小説の中でウィリアムとキャンディスの窮地(ピンチ)を救う、金山は王都近くにある。
それも、とてもわかりやすい目印があるのだけれど、いまだに誰かに見つかっていないのは、金策に困った主人公のために用意されているという奇跡的な物語補正のせいだと思う。
「……お前のその、よく分からない知識を持っている話は、俺ももう既に慣れた。それで、これからどうするんだ。ラザルス伯爵家に仕える騎士でも、場所の確認のために送り込むのか」
ウィリアムはそう聞いたので、私は首を横に振った。
「いえ。私がこの目で、実在するのか、どれほどの埋蔵量があるのか。現地を確認して来ます!」
別にラザルス家に使える護衛騎士たちを、私は信用していないと言う訳ではない。
現に変装した王太子ウィリアムを連れてオブライエン一家に日参していても、情報が漏れることはなかった。
代々、忠実にラザルス家に仕えていた騎士の家系の者たちなので、忠誠心は高い。
けれど、小説の中ではモニカに利用されてしまうけれど。
あの場所は間違いないと確信は持てていても、自分の目での現地確認は必須なのだ。
これから私が採掘のことは差配することになるので、金鉱山の実態を知らなければ、影響が出てしまう。
遠方過ぎて時間の関係で行けないなどなら諦めもつくけれど、金鉱山は王都すぐ近くにある。
――――百聞は一見にしかず。これは、私の経験上、真実なのだ。
「……は? おい。待て。モニカ。お前は自分が貴族令嬢だということを、忘れているだろう?」
「ですから……私は、生まれた時からラザルス伯爵令嬢ですわ。それは、王太子ウィリアム様の婚約者であることで、証明されていると思うのですが……」
彼に何度か貴族令嬢であることを忘れていないか確認された覚えのある私はそう言い、ウィリアムはそれにイラッとした態度で返した。
代々、忠実にラザルス家に仕えていた騎士の家系の者たちなので、忠誠心は高い。
けれど、小説の中ではモニカに利用されてしまうけれど。
あの場所は間違いないと確信は持てていても、自分の目での現地確認は必須なのだ。
これから私が採掘のことは差配することになるので、金鉱山の実態を知らなければ、影響が出てしまう。
遠方過ぎて時間の関係で行けないなどなら諦めもつくけれど、金鉱山は王都すぐ近くにある。
――――百聞は一見にしかず。これは、私の経験上、真実なのだ。
「……は? おい。待て。モニカ。お前は自分が貴族令嬢だということを、忘れているだろう?」
「ですから……私は、生まれた時からラザルス伯爵令嬢ですわ。それは、王太子ウィリアム様の婚約者であることで、証明されていると思うのですが……」
彼に何度か貴族令嬢であることを忘れていないか確認された覚えのある私はそう言い、ウィリアムはそれにイラッとした態度で返した。
「だから、普通の貴族令嬢は、現地確認が必要だとしても、鉱山になんて、絶対に近付かないんだ! 危険だろう!!」
「まあ、それでは……私は普通の貴族令嬢ではありません。ここからは、特別な貴族令嬢になりますわ。この目で現場を確認したいです。諦めることは、絶対に嫌です」
金鉱山の現地確認は譲れないと言い張り、ウィリアムも引き下がらないと強気の姿勢を見せたけれど、私だってここは引き下がらない。
鉱山に金があると言っても、ちゃんとそこにあるのか、埋蔵量はどの程度なのか。
それすらも下調べもせずに、他人任せにすることなんて私には出来ない。
……というのも、私は会社員時代に、何度も大失敗を重ねたからだ。
しかし、それは私がそれから失敗をする可能性を低くしてくれた貴重な経験とも言える。
手痛い失敗をしなければ『これは必須でしなければ』という、大事な前提条件の必要性に気がつけないものだ。
「……わかった。俺も一緒に行く。それなら良い。そうでなければ、姉上に頼んで、お前を止めてもらうからな」
指さして言い切ったウィリアムは、じっと見つめた。ここで私は、反論出来なくなった。
「まあ、それでは……私は普通の貴族令嬢ではありません。ここからは、特別な貴族令嬢になりますわ。この目で現場を確認したいです。諦めることは、絶対に嫌です」
金鉱山の現地確認は譲れないと言い張り、ウィリアムも引き下がらないと強気の姿勢を見せたけれど、私だってここは引き下がらない。
鉱山に金があると言っても、ちゃんとそこにあるのか、埋蔵量はどの程度なのか。
それすらも下調べもせずに、他人任せにすることなんて私には出来ない。
……というのも、私は会社員時代に、何度も大失敗を重ねたからだ。
しかし、それは私がそれから失敗をする可能性を低くしてくれた貴重な経験とも言える。
手痛い失敗をしなければ『これは必須でしなければ』という、大事な前提条件の必要性に気がつけないものだ。
「……わかった。俺も一緒に行く。それなら良い。そうでなければ、姉上に頼んで、お前を止めてもらうからな」
指さして言い切ったウィリアムは、じっと見つめた。ここで私は、反論出来なくなった。
……流石、優秀なウィリアムだわ。私にとって最も効果的な方法を知っているわね。
ウィリアムは私が姉エレインに絶対に逆らえないと知っているので、ここで念を押した。
そうすると、私が後日『ウィリアムを、危険な目に遭わせた』と、お叱りを受けることになるのだけど……ここはもう仕方ない。
私が引くしかなさそうだ。
金鉱山が必ず実在するとしても、私はその目で見たいという強い気持ちがあるのだから。
「……わかりました。ですが、危険だと判断したら、即お帰りくださいね」
この前に受けたウィリアムの腕の傷は、すぐに治っていたようだけれど、それでも本来ならば護衛の首が飛ぶようなことだったのだ。
今回はお忍び中で軽傷、しかも本人が動いて婚約者を庇った傷ということもあり、エレイン様が私を叱る程度で済んだ。
王太子、いえ、王族という身分は、それほどまでに重要視されるものなのだ。
「おい……危険だとわかればお前も帰るんだ。モニカは俺の婚約者で、未来の王太子妃。かよわい貴族令嬢なんだぞ。本当にわかってないな……」
ウィリアムは私が姉エレインに絶対に逆らえないと知っているので、ここで念を押した。
そうすると、私が後日『ウィリアムを、危険な目に遭わせた』と、お叱りを受けることになるのだけど……ここはもう仕方ない。
私が引くしかなさそうだ。
金鉱山が必ず実在するとしても、私はその目で見たいという強い気持ちがあるのだから。
「……わかりました。ですが、危険だと判断したら、即お帰りくださいね」
この前に受けたウィリアムの腕の傷は、すぐに治っていたようだけれど、それでも本来ならば護衛の首が飛ぶようなことだったのだ。
今回はお忍び中で軽傷、しかも本人が動いて婚約者を庇った傷ということもあり、エレイン様が私を叱る程度で済んだ。
王太子、いえ、王族という身分は、それほどまでに重要視されるものなのだ。
「おい……危険だとわかればお前も帰るんだ。モニカは俺の婚約者で、未来の王太子妃。かよわい貴族令嬢なんだぞ。本当にわかってないな……」
この作家の他の作品
表紙を見る
夜会での婚約者からの、いきなりの婚約破棄!
けれど、伯爵令嬢ルシールには
婚約者ロベルトとは良い友人のような
おだやかな関係を築いていると思って居たし
、婚約破棄されてしまうような覚えもなかった。
しかし、されてしまったものは仕方ないと夜会からの帰り道、
ロベルトの友人若くして公爵位を継いだ
ニコラスに声を掛けられるのだが……。
現実主義ドライ令嬢がいつのまにか愛されていた公爵に
囲い込まれて一本道しか行けなくなる話。
表紙を見る
異世界恋愛が好き……そんな私、大好きだった小説『ドキデキ』の世界に転生してモブ令嬢になっていた!
主人公二人の素敵場面を観察していると、注意して来た美形の男性……あれ? これから陥れられて全てを奪われるラスボスになるはずの王弟ではない?
こっ、これって!! 転生者の醍醐味、救いたい不遇キャラを救って、私も一緒に幸せになります!
表紙を見る
グレンジャー伯爵令嬢ウェンディは父が友人に裏切られ、
社交界デビューを目前にして無一文になってしまった。
父は異国へと一人出稼ぎに行ってしまい、
行く宛てのない姉を心配する弟を安心させるために、
以前邸で働いていた竜騎士を頼ることに。
彼が働くアレイスター竜騎士団は『恋愛禁止』という厳格な規則があり、
そのため若い女性は働いていない。
しかし、ウェンディは竜力を持つ貴族の血を引く女性にしかなれないという
『子竜守』として特別に採用されることになり……。
子竜守として働くことになった没落貴族令嬢が、
不器用だけどとても優しい団長と恋愛禁止な竜騎士団で働くために
秘密の契約結婚をすることなってしまう、
ほのぼの子竜育てありな可愛い恋物語。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…