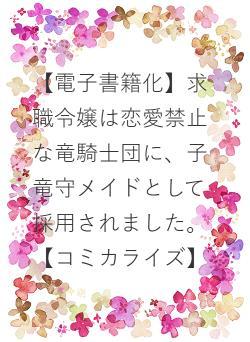ウィリアムは王太子としてのプライドもあったのだろうけれど、自分の気持ちは収めてくれたようだ。
私はほっとして、息をついた。
「ええ。誰かを尊重すれば、私たちも尊重されます。とにかく、何度も通って依頼を受けてくれる条件を聞き出しましょう」
私の言葉を聞いてから、ウィリアムはなんとも言えない表情になった。
「……ああ。そういえば、モニカ。俺はあの……キャンディスというメイドに、少々話があるんだが、仕事終わりに離宮に来るように伝えてくれないか」
「……はい? ああ。キャンディスさんに、そう伝えておきますわね」
唐突にこれまで避けてきたキャンディスに話があると言ったウィリアムに、少々戸惑いつつ私は頷いた。
ウィリアムと話す相手は彼が選ぶ訳なのだから、婚約者だからと私が口を出すことはないし、これからもしない。
あら……なんだか、胸が痛い。
どうしたのかしら。おかしいわ。
慌てて胸を押さえても、心臓がどくどくと高鳴っている。
「なあ。モニカ。この後、王都を歩きたい。駄目か?」
私はほっとして、息をついた。
「ええ。誰かを尊重すれば、私たちも尊重されます。とにかく、何度も通って依頼を受けてくれる条件を聞き出しましょう」
私の言葉を聞いてから、ウィリアムはなんとも言えない表情になった。
「……ああ。そういえば、モニカ。俺はあの……キャンディスというメイドに、少々話があるんだが、仕事終わりに離宮に来るように伝えてくれないか」
「……はい? ああ。キャンディスさんに、そう伝えておきますわね」
唐突にこれまで避けてきたキャンディスに話があると言ったウィリアムに、少々戸惑いつつ私は頷いた。
ウィリアムと話す相手は彼が選ぶ訳なのだから、婚約者だからと私が口を出すことはないし、これからもしない。
あら……なんだか、胸が痛い。
どうしたのかしら。おかしいわ。
慌てて胸を押さえても、心臓がどくどくと高鳴っている。
「なあ。モニカ。この後、王都を歩きたい。駄目か?」
「……ウィリアム様。これは必要がある外出だからと、特別にしているのです。もし、ウィリアム様が王都を歩きたいなら、それなりに護衛の準備も必要ですし……」
「はああ。変装だってしていると言うのに、面倒な身分だな……まあ、今日のところは大人しく帰るか……」
せっかく外出したのだし、町歩きもしたいと思ったらしいウィリアムは私からすげなく断られると、前を向いてやけに綺麗な横顔を見せた。
この王子様がやけに美しい外見を持っていることは、最初からそうなのだけれど……。
あ。まだ……胸が痛い。
この前に医者に胸が痛くなる状況の話をしたら『いたって全身健康です』と、けんもほろろな対応だったのだけれど……その筋では有名な方だったのに、やぶ医者だったのかしら。
……やっぱり、モニカは先天性の心疾患を、患っているのではないかしら。
「はああ。変装だってしていると言うのに、面倒な身分だな……まあ、今日のところは大人しく帰るか……」
せっかく外出したのだし、町歩きもしたいと思ったらしいウィリアムは私からすげなく断られると、前を向いてやけに綺麗な横顔を見せた。
この王子様がやけに美しい外見を持っていることは、最初からそうなのだけれど……。
あ。まだ……胸が痛い。
この前に医者に胸が痛くなる状況の話をしたら『いたって全身健康です』と、けんもほろろな対応だったのだけれど……その筋では有名な方だったのに、やぶ医者だったのかしら。
……やっぱり、モニカは先天性の心疾患を、患っているのではないかしら。
それから、私たち二人は一週間ほどオブライエン一家のアジトへと通った。
……けれど、彼らはたまに『帰れ』と繰り返すばかりで、話は一向に進展しなかった。
「今日は、どうだろうか……何かを言ってくれれば良いけどな」
「ええ。そうですね……」
実は私は会社員時代に、ある会社に平日三ヶ月間通い詰めて、契約をもぎ取ったことがあった。
それは、その会社の経営者がそういう営業方法が好んでいたからという情報を、先んじて知っていたから出来たことだった。
けれど、今回はいくら通い詰めても、難しい可能性もあった。
オブライエン一家ほどの暗殺者でなければ、既に隙なく警備を固めているエレインを暗殺することは難しいだろう。
しかも、彼らは複数居る家族も、全員暗殺者。こういった家族で営む稼業であれば、たった一人の強い個人よりも、目的をひとつとするチーム戦で威力を発揮する。
だから、もし彼らが私たちではなく……ダスレイン大臣に雇われてしまうと、致命傷にもなりかねない。私たちにとってはオブライエン一家は換えの利かない存在だけれど、あちらにとってはそうではない。
そして、直近の彼らの情報と、これまで訪問する中で、私にはひとつ気になることがあった。
「ええ……このままだと、先方の対応に変化は見込めなさそうですね。今回は、彼らに高価な贈り物を届けましょう」
「え? どういうことだ?」
……けれど、彼らはたまに『帰れ』と繰り返すばかりで、話は一向に進展しなかった。
「今日は、どうだろうか……何かを言ってくれれば良いけどな」
「ええ。そうですね……」
実は私は会社員時代に、ある会社に平日三ヶ月間通い詰めて、契約をもぎ取ったことがあった。
それは、その会社の経営者がそういう営業方法が好んでいたからという情報を、先んじて知っていたから出来たことだった。
けれど、今回はいくら通い詰めても、難しい可能性もあった。
オブライエン一家ほどの暗殺者でなければ、既に隙なく警備を固めているエレインを暗殺することは難しいだろう。
しかも、彼らは複数居る家族も、全員暗殺者。こういった家族で営む稼業であれば、たった一人の強い個人よりも、目的をひとつとするチーム戦で威力を発揮する。
だから、もし彼らが私たちではなく……ダスレイン大臣に雇われてしまうと、致命傷にもなりかねない。私たちにとってはオブライエン一家は換えの利かない存在だけれど、あちらにとってはそうではない。
そして、直近の彼らの情報と、これまで訪問する中で、私にはひとつ気になることがあった。
「ええ……このままだと、先方の対応に変化は見込めなさそうですね。今回は、彼らに高価な贈り物を届けましょう」
「え? どういうことだ?」
私の提案を聞いて、ウィリアムは変な表情になっていた。
彼の生い立ちを知れば、世間知らずは仕方ないことなのだけれど、依頼料を払って雇うと言っているのに客側であるこちらがへりくだる必要があるのかと、いまだ腑に落ちないのかもしれない。
「話を聞きたくないという拒否状態に、敢えて話を聞いて貰おうというのです。私たちも相応の何かを用意する必要がありますし……それに、私には少しだけ確認したいことがありまして……」
「ああ。わかった……余計なことはもう言わない。モニカの作戦が上手くいくように、俺も協力するようにする」
私が苦笑してそう言えば、ウィリアムは少し考えるような間を取り、眉を顰めながらも言った。
まあ……本当にウィリアムは、優秀な王子様だわ。
ついこの前まで世間と隔絶された生活を送っていたというのに、少ない情報量だけでも自分の中で咀嚼して学習して、ここで私に何故それをするのかと質問するよりも、彼らの対応を見た方が早いと思ったのね。
けれど、少々……成長速度が速すぎて、怖い気もする。
彼の生い立ちを知れば、世間知らずは仕方ないことなのだけれど、依頼料を払って雇うと言っているのに客側であるこちらがへりくだる必要があるのかと、いまだ腑に落ちないのかもしれない。
「話を聞きたくないという拒否状態に、敢えて話を聞いて貰おうというのです。私たちも相応の何かを用意する必要がありますし……それに、私には少しだけ確認したいことがありまして……」
「ああ。わかった……余計なことはもう言わない。モニカの作戦が上手くいくように、俺も協力するようにする」
私が苦笑してそう言えば、ウィリアムは少し考えるような間を取り、眉を顰めながらも言った。
まあ……本当にウィリアムは、優秀な王子様だわ。
ついこの前まで世間と隔絶された生活を送っていたというのに、少ない情報量だけでも自分の中で咀嚼して学習して、ここで私に何故それをするのかと質問するよりも、彼らの対応を見た方が早いと思ったのね。
けれど、少々……成長速度が速すぎて、怖い気もする。
だって、こんなにも短期間でこれだけ伸びるのだから、ウィリアムがどんな風に成長するのか、私には想像もつかないもの。
そういえば、ウィリアムはどんな逆境不遇にあっても、キャンディスさえ居てくれればそれで良いと言い切ってしまうようなヒーローだった……もし、キャンディスが悪い人間だったなら、彼はどうなっていたんだろう。
いいえ。そんなことあり得ないのだから……考えるだけ、無駄だったわ。
ウィリアムの傍には、この先もずっと私が付いているのだから、この先も彼は絶対に大丈夫よ。
◇◆◇
「……失礼します。私はモニカ・ラザルスです。オブライエン一家にどうしても依頼したい事があり、訪問しました」
ここまでは訪問の手土産として菓子箱を持参していたのだけれど、今回はわかりやすく高級な代物。人里離れた高山に住むという珍味、コモンシカの高級肉を贈り物とすることにした。
「こちらに、コモンシカの肉を置いておきます。もし、よろしかったら、ご家族でお楽しみください……それでは」
そういえば、ウィリアムはどんな逆境不遇にあっても、キャンディスさえ居てくれればそれで良いと言い切ってしまうようなヒーローだった……もし、キャンディスが悪い人間だったなら、彼はどうなっていたんだろう。
いいえ。そんなことあり得ないのだから……考えるだけ、無駄だったわ。
ウィリアムの傍には、この先もずっと私が付いているのだから、この先も彼は絶対に大丈夫よ。
◇◆◇
「……失礼します。私はモニカ・ラザルスです。オブライエン一家にどうしても依頼したい事があり、訪問しました」
ここまでは訪問の手土産として菓子箱を持参していたのだけれど、今回はわかりやすく高級な代物。人里離れた高山に住むという珍味、コモンシカの高級肉を贈り物とすることにした。
「こちらに、コモンシカの肉を置いておきます。もし、よろしかったら、ご家族でお楽しみください……それでは」
私は言いたいことはこれでもう終えたとばかりに、身を翻しその場を去ろうとした。その時、ヒュッと風を切る音がして、私は温かな何かに包まれた。
「っ……ウィリアム!」
狙われた私を庇ったらしいウィリアムの腕には、一筋の傷。地面を見れば、小さなナイフが突き刺さっている。
「おい。何をする」
ウィリアムの怒りが籠った声……まさか、オブライエン一家が今まで開かれなかった扉を開けてくれたというの!?
「……お前。モニカ・ラザルスだろう。噂は聞いている。婚約者である王太子ウィリアム様を、虐げ酷く虐めているとか。そのような者の依頼は、絶対に受けない」
初めて空いた扉の中には、黒い影があり顔は見えない……出て来たのは、若い男性のようだ。
「それは、誤解だ。俺がその、王太子ウィリアムだ」
庇ってくれたウィリアムはあろうことか、変装用に被っていたフードを取り、暗殺一家の一人と対峙していた。
彼の高貴な育ちの良さは、どうしても隠しきれない。王の血統を引く人物であると、ひと目見ればわかってしまう。
「ウィリアム様……!」
「っ……ウィリアム!」
狙われた私を庇ったらしいウィリアムの腕には、一筋の傷。地面を見れば、小さなナイフが突き刺さっている。
「おい。何をする」
ウィリアムの怒りが籠った声……まさか、オブライエン一家が今まで開かれなかった扉を開けてくれたというの!?
「……お前。モニカ・ラザルスだろう。噂は聞いている。婚約者である王太子ウィリアム様を、虐げ酷く虐めているとか。そのような者の依頼は、絶対に受けない」
初めて空いた扉の中には、黒い影があり顔は見えない……出て来たのは、若い男性のようだ。
「それは、誤解だ。俺がその、王太子ウィリアムだ」
庇ってくれたウィリアムはあろうことか、変装用に被っていたフードを取り、暗殺一家の一人と対峙していた。
彼の高貴な育ちの良さは、どうしても隠しきれない。王の血統を引く人物であると、ひと目見ればわかってしまう。
「ウィリアム様……!」
思わぬ事態に彼の名前を不用意に口にした私は、しまったと口を押さえた。そして、この私の焦った動きさえも王太子ウィリアムが、彼であることを示していた。
……しまった。
王太子本人がこのような地下街に暗殺者に依頼に来ていることなど、絶対に知られてはいけないのに。
しかも、私が元々行いの悪過ぎた悪役令嬢だったから、婚約者を虐げている話を聞かれてオブライエン一家にこれまで話もしてもらえずに断られていたんだわ!
よく考えたら誰だって、そんな評判の悪い人間からの依頼なんて、絶対に受けたくないわよね。
……悪役令嬢に生まれ変わっていたのに、これまでにあまり生活に支障が無かったから、そんなことも全く思いつきもしなかったわ。
……しまった。
王太子本人がこのような地下街に暗殺者に依頼に来ていることなど、絶対に知られてはいけないのに。
しかも、私が元々行いの悪過ぎた悪役令嬢だったから、婚約者を虐げている話を聞かれてオブライエン一家にこれまで話もしてもらえずに断られていたんだわ!
よく考えたら誰だって、そんな評判の悪い人間からの依頼なんて、絶対に受けたくないわよね。
……悪役令嬢に生まれ変わっていたのに、これまでにあまり生活に支障が無かったから、そんなことも全く思いつきもしなかったわ。
「では……モニカ・ラザルスについての悪い噂は、あくまで噂であると?」
扉は開かれていても、顔が陰になったまま見えないオブライエン一家の一人は、慎重に聞き返した。
……いえ。
モニカの悪行については、噂ではなくその通りなのだけれど、中身が変わってしまっているから、私ではないとも言えるし。
……複雑だわ。ここで彼らを真実を話すことは、絶対に出来ないもの。
「ああ。その通りだ。王城での噂を知るならば、これも知っているだろう。俺たち二人は熱烈に愛し合っている婚約者同士なんだ。何故、彼女にナイフを向けた? その回答次第では、俺にも考えがある」
ウィリアムは真剣な表情でそう言ったので、私は緊迫した場面にも関わらず、彼の凜とした格好良さに見惚れてしまっていた。
そうだった……ウィリアムは、最初からなんでも生まれ持ったチート級ヒーロー。
さっき私を庇う時の動きだって、まるで訓練された戦闘員のように、しなやかで素早かった。
これは、ウィリアムの存在自体が、そもそも格好良いもの。こうした場面で彼に見惚れてしまうのも、無理はないと思うわ。
「……それは知らない。しかし、確かに先ほど聞いた情報は、俺たちは知らなかった。真偽を調べさせてもらう。一週間後に、また来い」
彼はそう言い放ち、両開きの扉はまた、隙間なくきっちりと閉められた。
オブライエン一家がそう判断したのならば、私たちはここで用はない。
扉は開かれていても、顔が陰になったまま見えないオブライエン一家の一人は、慎重に聞き返した。
……いえ。
モニカの悪行については、噂ではなくその通りなのだけれど、中身が変わってしまっているから、私ではないとも言えるし。
……複雑だわ。ここで彼らを真実を話すことは、絶対に出来ないもの。
「ああ。その通りだ。王城での噂を知るならば、これも知っているだろう。俺たち二人は熱烈に愛し合っている婚約者同士なんだ。何故、彼女にナイフを向けた? その回答次第では、俺にも考えがある」
ウィリアムは真剣な表情でそう言ったので、私は緊迫した場面にも関わらず、彼の凜とした格好良さに見惚れてしまっていた。
そうだった……ウィリアムは、最初からなんでも生まれ持ったチート級ヒーロー。
さっき私を庇う時の動きだって、まるで訓練された戦闘員のように、しなやかで素早かった。
これは、ウィリアムの存在自体が、そもそも格好良いもの。こうした場面で彼に見惚れてしまうのも、無理はないと思うわ。
「……それは知らない。しかし、確かに先ほど聞いた情報は、俺たちは知らなかった。真偽を調べさせてもらう。一週間後に、また来い」
彼はそう言い放ち、両開きの扉はまた、隙間なくきっちりと閉められた。
オブライエン一家がそう判断したのならば、私たちはここで用はない。
怪我をしているウィリアムの腕に素早くハンカチを巻くと、私は彼に頷き腕を取って歩き出した。
――――私たち一行は無言のままで、地下街へ出入り口へと向かった。
そして、夕暮れの赤い光が広がる空を見て、ほっと息をついた。
ああ。良かった。
思わぬ展開ではあったけれど、一週間後に再び訪問すれば、オブライエン一家の助力は得られるかもしれない。
「……とりあえず、会ってもらえることになったな。話も聞いてくれるだろう」
私と同じことを考えていただろうウィリアムもなんだか、にっこり笑って満足そうにしている。
「あの、ウィリアム様。怪我は大丈夫ですか?」
王太子の彼が怪我をするなど、本来絶対にあってはならないことなのだけれど、既にそうなってしまったのなら仕方ない。
今まで無反応に近かったから、脅しでナイフを投げられるなどと、想定出来なかった私の考えが甘かったのだかわ。
「ああ。気にするな。かすり傷だ。もっとも、これは脅しのつもりだったんだろう。この時間が過ぎても何もなければ、薬や毒なども塗られていない」
――――私たち一行は無言のままで、地下街へ出入り口へと向かった。
そして、夕暮れの赤い光が広がる空を見て、ほっと息をついた。
ああ。良かった。
思わぬ展開ではあったけれど、一週間後に再び訪問すれば、オブライエン一家の助力は得られるかもしれない。
「……とりあえず、会ってもらえることになったな。話も聞いてくれるだろう」
私と同じことを考えていただろうウィリアムもなんだか、にっこり笑って満足そうにしている。
「あの、ウィリアム様。怪我は大丈夫ですか?」
王太子の彼が怪我をするなど、本来絶対にあってはならないことなのだけれど、既にそうなってしまったのなら仕方ない。
今まで無反応に近かったから、脅しでナイフを投げられるなどと、想定出来なかった私の考えが甘かったのだかわ。
「ああ。気にするな。かすり傷だ。もっとも、これは脅しのつもりだったんだろう。この時間が過ぎても何もなければ、薬や毒なども塗られていない」
この作家の他の作品
表紙を見る
夜会での婚約者からの、いきなりの婚約破棄!
けれど、伯爵令嬢ルシールには
婚約者ロベルトとは良い友人のような
おだやかな関係を築いていると思って居たし
、婚約破棄されてしまうような覚えもなかった。
しかし、されてしまったものは仕方ないと夜会からの帰り道、
ロベルトの友人若くして公爵位を継いだ
ニコラスに声を掛けられるのだが……。
現実主義ドライ令嬢がいつのまにか愛されていた公爵に
囲い込まれて一本道しか行けなくなる話。
表紙を見る
異世界恋愛が好き……そんな私、大好きだった小説『ドキデキ』の世界に転生してモブ令嬢になっていた!
主人公二人の素敵場面を観察していると、注意して来た美形の男性……あれ? これから陥れられて全てを奪われるラスボスになるはずの王弟ではない?
こっ、これって!! 転生者の醍醐味、救いたい不遇キャラを救って、私も一緒に幸せになります!
表紙を見る
グレンジャー伯爵令嬢ウェンディは父が友人に裏切られ、
社交界デビューを目前にして無一文になってしまった。
父は異国へと一人出稼ぎに行ってしまい、
行く宛てのない姉を心配する弟を安心させるために、
以前邸で働いていた竜騎士を頼ることに。
彼が働くアレイスター竜騎士団は『恋愛禁止』という厳格な規則があり、
そのため若い女性は働いていない。
しかし、ウェンディは竜力を持つ貴族の血を引く女性にしかなれないという
『子竜守』として特別に採用されることになり……。
子竜守として働くことになった没落貴族令嬢が、
不器用だけどとても優しい団長と恋愛禁止な竜騎士団で働くために
秘密の契約結婚をすることなってしまう、
ほのぼの子竜育てありな可愛い恋物語。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…