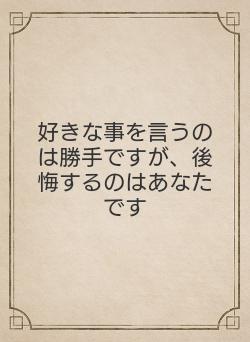ティアトレイには取り扱い説明書があったけど、そう、難しいことが書かれているわけではなかった。
対象年齢は十五歳以上であること。
自分を守るためだけに使うことが強調されていた。
ミリー様も寮生活なので、仕事が終わったあと、夕食を共にすることが多い。
だから、すでにティアトレイを使ったことのある、ミリー様に体験談を聞いてみた。
「ティアトレイはどういう時に使うものなんでしょうか」
「私の場合は話が通じない相手に使っていますね。あ、自分から先に手を出してはいけませんよ。向こうから手を出してこようとしたり、手を出してきた時に使うようにしてくださいね。先に手を出すと、相手と同じレベルになりますから。それに世間はどんな理由があろうとも暴力をふるったほうが悪いと言います。たとえ、先に言葉の暴力を受けたとしても駄目です」
「わかりました。使う機会がないことが一番良いのでしょうけど、その時が来れば使ってみます」
「でも、リファルド様はどうしてそこまでサブリナ様の世話を焼くんですかね」
不思議そうにするミリー様に苦笑して答える。
「強くなる私を見たいと教えてもらいましたが、それとは違うのかなって。……いじめられていた記憶って、中々、忘れられないものなんですよ。だから、私が良くない道を選ぶのではないかと心配してくれているのかなと思っています」
「体の傷も残るものはありますが、言葉の暴力は心の傷ですから、本人がどう気持ちを切りかえられるかですものね。心の綺麗な人ほど、自分を責めてしまいますし」
ミリー様は頷いてから続ける。
「実際、そんな人達は、たとえサブリナ様が死を選んでも、そんな気はなかったで終わります。気にしているだけ無駄ですよ。仲良くしたいと思ってくれる人と仲良くしたら良いと思います」
「ありがとうございます。そうすることにします」
今まで、同年代の人と、こんな風に真面目な話をすることはなかった。
友達ってこういうものなんだろうか。
勝手に友達だと思ってしまっても良いのか、そちらも気になっていると、ミリー様が笑顔で話しかけてきた。
「私とは仲良くしてくれると嬉しいです。悲しいことにお友達がいないもので」
「私もです! よろしくお願いいたします!」
「こちらこそ、よろしくお願いいたします」
ミリー様と私はお互いに頭を下げた。
*****
次の日から、早速、ティアトレイに慣れることに決めた。
一時期はティアトレイで素振りをしていたと、ミリー様から教えてもらったので、私も毎日、やってみることにする。
思ったよりも重いので、腕の筋肉がつけば良いなと思う。
ここ最近は顔色も良くなってきたし、自分が生きているのだと感じられる気がした。
ティアトレイの必要性を感じずにいられないのは、リファルド様に会った時に、両親のことを教えてもらったからだ。
なんと、お父様はお母様と離婚すると言い出した。
領地の管理が自分ではできないから、子爵の座を放棄したくなったのだ。
現在、お母様は泣き縋って止めているんだそうだ。
あんな人のどこが良いのか、私にはさっぱりわからない。
でも、私があの人の血を引いていることは確かだ。
どす黒い感情が、どうしても湧き上がるのは、そのせいなんだろうか。
とにかく、今日は良い日だった。
幸せな気持ちを思い出して眠りについた次の日、リファルド様から手紙が届いた。
内容はお父様とお母様の離婚が成立したことと、なぜ、成立したかの理由が書いてあった。
リファルド様は子爵家にスパイを入れてくれているから、早くにわかった話だった。
離婚成立が衝撃だったこともあるけど、その後の話にも驚いた。
お父様はお母様にも暴力をふるい、無理やり、離婚を認めさせたというのだ。
そんな酷い目にあっても、お母様はお父様のことが好きなんだそうだ。
きっと、今までの私もアキーム様に対して、そんな気持ちだったんだろう。
目を覚ませて本当に良かった。
そう思った次の日に、伯父様から連絡が来た。
お母様が爵位を返上し、お父様の所へ向かったこと。お父様が私を逆恨みしているようだと書かれていた。
この様子だとティアトレイはアキーム様よりも先に、お父様に使うことになりそうだわ。
対象年齢は十五歳以上であること。
自分を守るためだけに使うことが強調されていた。
ミリー様も寮生活なので、仕事が終わったあと、夕食を共にすることが多い。
だから、すでにティアトレイを使ったことのある、ミリー様に体験談を聞いてみた。
「ティアトレイはどういう時に使うものなんでしょうか」
「私の場合は話が通じない相手に使っていますね。あ、自分から先に手を出してはいけませんよ。向こうから手を出してこようとしたり、手を出してきた時に使うようにしてくださいね。先に手を出すと、相手と同じレベルになりますから。それに世間はどんな理由があろうとも暴力をふるったほうが悪いと言います。たとえ、先に言葉の暴力を受けたとしても駄目です」
「わかりました。使う機会がないことが一番良いのでしょうけど、その時が来れば使ってみます」
「でも、リファルド様はどうしてそこまでサブリナ様の世話を焼くんですかね」
不思議そうにするミリー様に苦笑して答える。
「強くなる私を見たいと教えてもらいましたが、それとは違うのかなって。……いじめられていた記憶って、中々、忘れられないものなんですよ。だから、私が良くない道を選ぶのではないかと心配してくれているのかなと思っています」
「体の傷も残るものはありますが、言葉の暴力は心の傷ですから、本人がどう気持ちを切りかえられるかですものね。心の綺麗な人ほど、自分を責めてしまいますし」
ミリー様は頷いてから続ける。
「実際、そんな人達は、たとえサブリナ様が死を選んでも、そんな気はなかったで終わります。気にしているだけ無駄ですよ。仲良くしたいと思ってくれる人と仲良くしたら良いと思います」
「ありがとうございます。そうすることにします」
今まで、同年代の人と、こんな風に真面目な話をすることはなかった。
友達ってこういうものなんだろうか。
勝手に友達だと思ってしまっても良いのか、そちらも気になっていると、ミリー様が笑顔で話しかけてきた。
「私とは仲良くしてくれると嬉しいです。悲しいことにお友達がいないもので」
「私もです! よろしくお願いいたします!」
「こちらこそ、よろしくお願いいたします」
ミリー様と私はお互いに頭を下げた。
*****
次の日から、早速、ティアトレイに慣れることに決めた。
一時期はティアトレイで素振りをしていたと、ミリー様から教えてもらったので、私も毎日、やってみることにする。
思ったよりも重いので、腕の筋肉がつけば良いなと思う。
ここ最近は顔色も良くなってきたし、自分が生きているのだと感じられる気がした。
ティアトレイの必要性を感じずにいられないのは、リファルド様に会った時に、両親のことを教えてもらったからだ。
なんと、お父様はお母様と離婚すると言い出した。
領地の管理が自分ではできないから、子爵の座を放棄したくなったのだ。
現在、お母様は泣き縋って止めているんだそうだ。
あんな人のどこが良いのか、私にはさっぱりわからない。
でも、私があの人の血を引いていることは確かだ。
どす黒い感情が、どうしても湧き上がるのは、そのせいなんだろうか。
とにかく、今日は良い日だった。
幸せな気持ちを思い出して眠りについた次の日、リファルド様から手紙が届いた。
内容はお父様とお母様の離婚が成立したことと、なぜ、成立したかの理由が書いてあった。
リファルド様は子爵家にスパイを入れてくれているから、早くにわかった話だった。
離婚成立が衝撃だったこともあるけど、その後の話にも驚いた。
お父様はお母様にも暴力をふるい、無理やり、離婚を認めさせたというのだ。
そんな酷い目にあっても、お母様はお父様のことが好きなんだそうだ。
きっと、今までの私もアキーム様に対して、そんな気持ちだったんだろう。
目を覚ませて本当に良かった。
そう思った次の日に、伯父様から連絡が来た。
お母様が爵位を返上し、お父様の所へ向かったこと。お父様が私を逆恨みしているようだと書かれていた。
この様子だとティアトレイはアキーム様よりも先に、お父様に使うことになりそうだわ。
順調に日々を過ごしていたある日、城でメイドとして働いている女性から、私と同じ名前の女性が家出人として平民の間で捜索されているという話を聞いた。
しかも、見つけた人には謝礼金を出すというのだ。
私は平民どころか、この国の貴族にもあまり知られていない。
だから、もし、居場所がバレてしまうのなら、城内で働いている人が教えたということになる。
城内でのことは、城外で話すことは許されていないから見つかることはないと思うので安心だ。
でも、そんな手配を出したのは、一体、誰なのかしら。
考えられるとしたら、私の両親かアキーム様だ。
お母様はそんなことをする性格には思えない。
でも、お父様に私を連れ戻すことができれば、再婚しても良いなどと言われていたら、必死に私を捜すでしょう。
ただ、お父様と長く離れることによって冷静になることができるかもしれない。
私だって、アキーム様が家を離れることが多かったから疑いを持てたのだ。
今日は仕事の日だということで、このことを考えるのは終わりにして、気持ちを切り替えた。
******
何も動きがないまま日にちは過ぎた。
結局、私を捜しているのはお母様だとわかった。
お父様に再婚条件として、私とアキーム様の再婚を求められたらしい。
全てを捨てたお母様は、今はお父様に付きまとっていると聞いた。
お父様は新たな領地の人間との折り合いが悪く、逃げ回っているらしいから、お母様の存在は本当は邪魔なはずだ。
お父様がお母様を見捨てないのは、お母様になら、私が連絡するのではないかと思っているからだった。
お母様に叱られることはあっても、暴力をふるわれたことはない。
でも、お母さまを見ていると、昔の私を思い出して嫌な気分になる。
会いたくないという気持ちが強い。
「サブリナさんはやさしいので、いざというときにしんぱいです。ティアトレイにまほうをふよしてもらいましょう」
お母様が私を捜しているという話を聞いたラシル様が、ミリー様の婚約者のキール様に頼んで、ティアトレイに魔法を付与してくれることになった。
そして、数日後、預けていたティアトレイが返ってきた。
「キールさんがいっていましたが、かれのかけたまほうは、そのひとのせいかくによってこうりょくがかわるそうです。ミリアーナさんのばあいは、わるい人がふれると、やけどするそうです。サブリナさんのばあいは、どうなるかわかりません」
「そうなんですね」
ラシル様から返してもらったティアトレイは、特に何かが変わったようには見えない。
ロシノアール王国は王族や公爵家の血筋を引く人は魔法が使える。
でも、私が住んでいた国は魔法を使える人は誰一人いない。
だから、魔法を付与されたと言われても、なんだかピンとこなかった。
何にしても魔法の付与は大変なものだと聞くし、キール様にはお礼を言わなくちゃいけないわ。
大事にティアトレイを抱きしめて寮に帰ると、ロビーにリファルド様がいた。
「ど、どうしてこちらに!?」
「君の母親が罪を犯して警察に捕まった」
「……はい?」
「警察を使って、君を引きずり出そうとしている」
「……母は何をしたのでしょうか」
「平民がよく通う店で食い逃げをしようとしたらしい。すぐに捕まったが、その時に自分の名前をサブリナだと名乗ったそうだ」
「どうせすぐに嘘だとわかるのに、どうしてそんな嘘をついたのでしょうか」
「警察なら本人確認をするために、君の居場所を特定すると思ったんだろうな」
リファルド様は難しい顔をして続ける。
「君とコンタクトを取ろうとしていたが、君の身元保証はワイズ家がしているから先に連絡がきた」
「迷惑をおかけしてしまって申し訳ございません!」
「気にするな。どうする? 警察は君に話を聞きたいが、王城内には入れないから、外に出れるかと聞いてきている」
「ありがとうございます。これ以上、迷惑をかけられませんし行ってこようと思います」
「そうか。なら、一人では心配だ。俺も行く」
「え、あ、大丈夫です! 一人では行かないようにしますから」
気持ちは嬉しいので、丁重にお断りしてから続ける。
「きっと、お父様が私に近づいてくるでしょう。ティアトレイがどんな効果を発揮してくれるのか、試してみようと思います」
リファルド様は一瞬、驚いた顔をしたけど、すぐに笑顔になって頷く。
「やっぱり俺も行く。君がどう変わったのか見たいからな」
昔よりも強くなっているはず。
その姿を見てもらわなくちゃ。
しかも、見つけた人には謝礼金を出すというのだ。
私は平民どころか、この国の貴族にもあまり知られていない。
だから、もし、居場所がバレてしまうのなら、城内で働いている人が教えたということになる。
城内でのことは、城外で話すことは許されていないから見つかることはないと思うので安心だ。
でも、そんな手配を出したのは、一体、誰なのかしら。
考えられるとしたら、私の両親かアキーム様だ。
お母様はそんなことをする性格には思えない。
でも、お父様に私を連れ戻すことができれば、再婚しても良いなどと言われていたら、必死に私を捜すでしょう。
ただ、お父様と長く離れることによって冷静になることができるかもしれない。
私だって、アキーム様が家を離れることが多かったから疑いを持てたのだ。
今日は仕事の日だということで、このことを考えるのは終わりにして、気持ちを切り替えた。
******
何も動きがないまま日にちは過ぎた。
結局、私を捜しているのはお母様だとわかった。
お父様に再婚条件として、私とアキーム様の再婚を求められたらしい。
全てを捨てたお母様は、今はお父様に付きまとっていると聞いた。
お父様は新たな領地の人間との折り合いが悪く、逃げ回っているらしいから、お母様の存在は本当は邪魔なはずだ。
お父様がお母様を見捨てないのは、お母様になら、私が連絡するのではないかと思っているからだった。
お母様に叱られることはあっても、暴力をふるわれたことはない。
でも、お母さまを見ていると、昔の私を思い出して嫌な気分になる。
会いたくないという気持ちが強い。
「サブリナさんはやさしいので、いざというときにしんぱいです。ティアトレイにまほうをふよしてもらいましょう」
お母様が私を捜しているという話を聞いたラシル様が、ミリー様の婚約者のキール様に頼んで、ティアトレイに魔法を付与してくれることになった。
そして、数日後、預けていたティアトレイが返ってきた。
「キールさんがいっていましたが、かれのかけたまほうは、そのひとのせいかくによってこうりょくがかわるそうです。ミリアーナさんのばあいは、わるい人がふれると、やけどするそうです。サブリナさんのばあいは、どうなるかわかりません」
「そうなんですね」
ラシル様から返してもらったティアトレイは、特に何かが変わったようには見えない。
ロシノアール王国は王族や公爵家の血筋を引く人は魔法が使える。
でも、私が住んでいた国は魔法を使える人は誰一人いない。
だから、魔法を付与されたと言われても、なんだかピンとこなかった。
何にしても魔法の付与は大変なものだと聞くし、キール様にはお礼を言わなくちゃいけないわ。
大事にティアトレイを抱きしめて寮に帰ると、ロビーにリファルド様がいた。
「ど、どうしてこちらに!?」
「君の母親が罪を犯して警察に捕まった」
「……はい?」
「警察を使って、君を引きずり出そうとしている」
「……母は何をしたのでしょうか」
「平民がよく通う店で食い逃げをしようとしたらしい。すぐに捕まったが、その時に自分の名前をサブリナだと名乗ったそうだ」
「どうせすぐに嘘だとわかるのに、どうしてそんな嘘をついたのでしょうか」
「警察なら本人確認をするために、君の居場所を特定すると思ったんだろうな」
リファルド様は難しい顔をして続ける。
「君とコンタクトを取ろうとしていたが、君の身元保証はワイズ家がしているから先に連絡がきた」
「迷惑をおかけしてしまって申し訳ございません!」
「気にするな。どうする? 警察は君に話を聞きたいが、王城内には入れないから、外に出れるかと聞いてきている」
「ありがとうございます。これ以上、迷惑をかけられませんし行ってこようと思います」
「そうか。なら、一人では心配だ。俺も行く」
「え、あ、大丈夫です! 一人では行かないようにしますから」
気持ちは嬉しいので、丁重にお断りしてから続ける。
「きっと、お父様が私に近づいてくるでしょう。ティアトレイがどんな効果を発揮してくれるのか、試してみようと思います」
リファルド様は一瞬、驚いた顔をしたけど、すぐに笑顔になって頷く。
「やっぱり俺も行く。君がどう変わったのか見たいからな」
昔よりも強くなっているはず。
その姿を見てもらわなくちゃ。
次の日がちょうどお休みだったことと、リファルド様の都合もついたため、一緒に警察署に向かうことになった。
警察署の奥にある留置所にお母様は入れられていて、鉄柵の向こう側に私が立つと笑顔を見せた。
「サブリナちゃん、やっと顔を見せてくれたのね!」
「……お母様、どうして嫌がらせをするんですか」
「嫌がらせをしているのはあなたじゃないの! わたしはただ、幸せに暮らしたいだけなの。どうして協力してくれないの?」
「私がいなくても幸せに暮らせますよ。ですからもう、私のことはもう捜さないでください。アキーム様と再婚なんて絶対にしませんから!」
強い口調で言うと、お母様はショックを受けたような顔をした。
「一体、どうしちゃったの。あなたは言い返すような子じゃなかったじゃないの」
「言うことを聞いていれば、嫌われないと思っていたからです」
「なら、わたしのお願いを聞いてちょうだい!」
お母様は震えながら訴えてきた。
実の娘に言い返されることも怖いらしい。
それなのに、よく、お父様を追いかけていけたものだわ。
世間なんて、私よりももっと冷たい人が多いのに。
「お母様、聞いてください。私はアキーム様のことはもう好きではありません」
「……どうして? 彼が浮気をしたから? バンディが言っていたけど、貴族の男性は愛人を持つことは当たり前のことだそうよ。妻は一人だけだから良いじゃないかと言っていたわ」
「お母様は、その話を聞いて納得できたんですか?」
「……どういうこと?」
「自分を放って、お父様が他の女性に会いに行くことは許せることなんですか」
「……それは嫌だけど、一緒にいられなくなるくらいなら我慢するわ!」
お母様は顔を手で覆って叫んだ。
依存してしまうと恐ろしいことになるのね。
そして、自分がそうなっているとはわからないから困ったものだ。
「お母様、私は私の人生を歩みます。お父様にも邪魔はさせません。お母様が私を諦めてくれないのであれば、会えないようにするしかありません」
「そ、そんな。サブリナちゃん、あなた、本当にどうしちゃったの」
久しぶりに会うお母様は服や肌は薄汚れているし、十歳以上老けているように見える。
苦労したのでしょうけど、どうして、お母様は私よりもお父様を選ぶのかしら。
私では頼りにならないから?
同族嫌悪だから?
……もう、どうでもいいわね。
「私はもう、お母様達の前には現れません。今回の件で、お母様達は強制送還になり、二度と入国出来なくなるでしょう」
「……サブリナちゃん。どうして、そんな酷いことを言う子になっちゃったの」
「私はきっと、最初から冷たい人間なんです。では、さようなら、お母様。今までありがとうございました」
深々とお辞儀をすると、お母様が叫ぶ。
「サブリナちゃん! 待って! あなたがアキーム様と再婚してくれないと駄目なのよ! バンディに捨てられたら、わたしはどうやって生きていったらいいの!?」
「お父様のために全てを投げ捨てる強さがあるなら、他に素敵な何かを見つけて生きていけるはずだと私は思います。自分の人生です。他人に何を言われようと、迷惑をかけずに自分が楽しく生きていけるなら、それが一番ですから」
「バンディと一緒にいることがわたしの幸せなの!」
お母様は必死に訴えてくる。
親というものは、子供を第一に考えるものだと思っていた。
でも、実際は全ての人がそうというわけではないのね。
そして、これがお母様の生き方なんだわ。
「ごめんなさい、お母様。私はあなたのために自分を犠牲にすることはできません」
親不孝者だと言われても、絶対にアキーム様と再婚なんてしない。
はっきりと告げてから、私はその場をあとにした。
お母様が泣きわめいていたけど気にしない。
このあとが本番だからだ。
待っていてくれたリファルド様と合流したところで、警察の担当者がやって来たので、お母様についての話をした。
そして、必要なことを話し終え、警察署を出ると、案の定、お父様が待っていたのだった。
今度こそ、お父様と決着をつけるわ。
警察署の奥にある留置所にお母様は入れられていて、鉄柵の向こう側に私が立つと笑顔を見せた。
「サブリナちゃん、やっと顔を見せてくれたのね!」
「……お母様、どうして嫌がらせをするんですか」
「嫌がらせをしているのはあなたじゃないの! わたしはただ、幸せに暮らしたいだけなの。どうして協力してくれないの?」
「私がいなくても幸せに暮らせますよ。ですからもう、私のことはもう捜さないでください。アキーム様と再婚なんて絶対にしませんから!」
強い口調で言うと、お母様はショックを受けたような顔をした。
「一体、どうしちゃったの。あなたは言い返すような子じゃなかったじゃないの」
「言うことを聞いていれば、嫌われないと思っていたからです」
「なら、わたしのお願いを聞いてちょうだい!」
お母様は震えながら訴えてきた。
実の娘に言い返されることも怖いらしい。
それなのに、よく、お父様を追いかけていけたものだわ。
世間なんて、私よりももっと冷たい人が多いのに。
「お母様、聞いてください。私はアキーム様のことはもう好きではありません」
「……どうして? 彼が浮気をしたから? バンディが言っていたけど、貴族の男性は愛人を持つことは当たり前のことだそうよ。妻は一人だけだから良いじゃないかと言っていたわ」
「お母様は、その話を聞いて納得できたんですか?」
「……どういうこと?」
「自分を放って、お父様が他の女性に会いに行くことは許せることなんですか」
「……それは嫌だけど、一緒にいられなくなるくらいなら我慢するわ!」
お母様は顔を手で覆って叫んだ。
依存してしまうと恐ろしいことになるのね。
そして、自分がそうなっているとはわからないから困ったものだ。
「お母様、私は私の人生を歩みます。お父様にも邪魔はさせません。お母様が私を諦めてくれないのであれば、会えないようにするしかありません」
「そ、そんな。サブリナちゃん、あなた、本当にどうしちゃったの」
久しぶりに会うお母様は服や肌は薄汚れているし、十歳以上老けているように見える。
苦労したのでしょうけど、どうして、お母様は私よりもお父様を選ぶのかしら。
私では頼りにならないから?
同族嫌悪だから?
……もう、どうでもいいわね。
「私はもう、お母様達の前には現れません。今回の件で、お母様達は強制送還になり、二度と入国出来なくなるでしょう」
「……サブリナちゃん。どうして、そんな酷いことを言う子になっちゃったの」
「私はきっと、最初から冷たい人間なんです。では、さようなら、お母様。今までありがとうございました」
深々とお辞儀をすると、お母様が叫ぶ。
「サブリナちゃん! 待って! あなたがアキーム様と再婚してくれないと駄目なのよ! バンディに捨てられたら、わたしはどうやって生きていったらいいの!?」
「お父様のために全てを投げ捨てる強さがあるなら、他に素敵な何かを見つけて生きていけるはずだと私は思います。自分の人生です。他人に何を言われようと、迷惑をかけずに自分が楽しく生きていけるなら、それが一番ですから」
「バンディと一緒にいることがわたしの幸せなの!」
お母様は必死に訴えてくる。
親というものは、子供を第一に考えるものだと思っていた。
でも、実際は全ての人がそうというわけではないのね。
そして、これがお母様の生き方なんだわ。
「ごめんなさい、お母様。私はあなたのために自分を犠牲にすることはできません」
親不孝者だと言われても、絶対にアキーム様と再婚なんてしない。
はっきりと告げてから、私はその場をあとにした。
お母様が泣きわめいていたけど気にしない。
このあとが本番だからだ。
待っていてくれたリファルド様と合流したところで、警察の担当者がやって来たので、お母様についての話をした。
そして、必要なことを話し終え、警察署を出ると、案の定、お父様が待っていたのだった。
今度こそ、お父様と決着をつけるわ。
「サブリナ、久しぶりだな。メイリーナから話は聞いたか」
「聞きましたよ。ちゃんとお断りしておきました」
お父様とアキーム様は繋がっているらしいのだけど、ここにいるのはお父様しかいない。
どうせなら、一緒に来てくれるほうが手間が省けて済むんだけど、そう上手くはいかなかった。
リファルド様が少し心配そうな顔で私を見ていることに気がついたので笑顔で話しかける。
「大丈夫です。昔よりは強くなれていますから。それに、今はティアトレイもありますし!」
警察署を出る前に護衛騎士からティアトレイを返してもらっていた。
だから、ティアトレイを掲げて言うと、リファルド様は口元に笑みを浮かべた。
何も口には出さないけど、わかってくれたのだと思う。
私が目を向けると、お父様は話しかけてくる。
「シルバートレイなんて持ってどうしたんだ」
「必要な時に使おうと思いまして」
「意味がわからない。オルドリン伯爵と再婚して、メイドにでもなるつもりか? それとも、前々からやらされてたのか?」
「どちらもいいえです。お父様、もう私はあなたに用事はないんです。ですので、これで最後にしていただけますでしょうか。本来ならば、先日にお会いした時に最後にするはずだったんです」
「サブリナ、本当にお前は偉そうな口をきくようになったな。お前は俺の娘なんだ。子供は親の言うことを黙ってきいていればいいんだよ!」
「子供といっても、私はもう成人しています。それに、子供だからといって、何でもかんでも親の言うことをきく必要はないと思います」
シルバートレイを握り直して続ける。
「だって、親が間違っていることだってありますから」
「オレが間違っているわけがないだろう!」
「何度も間違っていましたよ! それにお父様の言う通りにやったとしても、トラブルになった時に責任は取らずに知らんぷりじゃないですか! お父様は私のことを考えているんじゃありません! 自分の感情を優先にしているだけです! お父様にとって私の生き方がおかしくても、私は私の思う道を行くだけです! 理解してくれなんて望みません! ですから、お父様も私とわかり合おうとすることは諦めてください」
「生意気なことを言いやがって! そんな甘い考えで世の中生きていけると思うなよ!」
「生きていってみせます。それに望み通りに生きていない私は悪い娘なんでしょう。それなら、関わり合いにならないことが一番です。お互いに不快な気持ちになるだけですからね。お父様は私のこれからの人生に必要ありません」
「いい加減にしろ! 大人しく、オレの言うことをきくんだ! お前がオルドリン伯爵と再婚しなきゃ、オレの命が危ないんだよ!」
意味がわからないわ。
もしかして、アキーム様に脅されているの?
「とにかく一緒に行くぞ!」
お父様がティアトレイを持っていないほうの腕を掴む。
これはわざと掴ませた。
相手から手を出されたなら、正当防衛が成り立つ。
――過剰防衛だと言われかねないけど。
その手を振り払ってから叫ぶ。
「また私に触れたら容赦しませんから」
「何が容赦しないだ。お前に何ができるって言うんだ!」
「できますよ! もう、私は昔の私ではありませんから!」
あざ笑うお父様の額に向けて、私はシルバートレイの角を両手で叩きつけた。
ガツンという音のあと「ぎゃあああああ」という断末魔のような叫び声が上がった。
驚いて後ろに下がると、お父様はその場に崩れ落ちた。
お父様は地面に寝転ぶようにして倒れ、額を押さえて転げ回っている。
私のティアトレイに付与された魔法は、触れた人を痺れさせるものだった。
「聞きましたよ。ちゃんとお断りしておきました」
お父様とアキーム様は繋がっているらしいのだけど、ここにいるのはお父様しかいない。
どうせなら、一緒に来てくれるほうが手間が省けて済むんだけど、そう上手くはいかなかった。
リファルド様が少し心配そうな顔で私を見ていることに気がついたので笑顔で話しかける。
「大丈夫です。昔よりは強くなれていますから。それに、今はティアトレイもありますし!」
警察署を出る前に護衛騎士からティアトレイを返してもらっていた。
だから、ティアトレイを掲げて言うと、リファルド様は口元に笑みを浮かべた。
何も口には出さないけど、わかってくれたのだと思う。
私が目を向けると、お父様は話しかけてくる。
「シルバートレイなんて持ってどうしたんだ」
「必要な時に使おうと思いまして」
「意味がわからない。オルドリン伯爵と再婚して、メイドにでもなるつもりか? それとも、前々からやらされてたのか?」
「どちらもいいえです。お父様、もう私はあなたに用事はないんです。ですので、これで最後にしていただけますでしょうか。本来ならば、先日にお会いした時に最後にするはずだったんです」
「サブリナ、本当にお前は偉そうな口をきくようになったな。お前は俺の娘なんだ。子供は親の言うことを黙ってきいていればいいんだよ!」
「子供といっても、私はもう成人しています。それに、子供だからといって、何でもかんでも親の言うことをきく必要はないと思います」
シルバートレイを握り直して続ける。
「だって、親が間違っていることだってありますから」
「オレが間違っているわけがないだろう!」
「何度も間違っていましたよ! それにお父様の言う通りにやったとしても、トラブルになった時に責任は取らずに知らんぷりじゃないですか! お父様は私のことを考えているんじゃありません! 自分の感情を優先にしているだけです! お父様にとって私の生き方がおかしくても、私は私の思う道を行くだけです! 理解してくれなんて望みません! ですから、お父様も私とわかり合おうとすることは諦めてください」
「生意気なことを言いやがって! そんな甘い考えで世の中生きていけると思うなよ!」
「生きていってみせます。それに望み通りに生きていない私は悪い娘なんでしょう。それなら、関わり合いにならないことが一番です。お互いに不快な気持ちになるだけですからね。お父様は私のこれからの人生に必要ありません」
「いい加減にしろ! 大人しく、オレの言うことをきくんだ! お前がオルドリン伯爵と再婚しなきゃ、オレの命が危ないんだよ!」
意味がわからないわ。
もしかして、アキーム様に脅されているの?
「とにかく一緒に行くぞ!」
お父様がティアトレイを持っていないほうの腕を掴む。
これはわざと掴ませた。
相手から手を出されたなら、正当防衛が成り立つ。
――過剰防衛だと言われかねないけど。
その手を振り払ってから叫ぶ。
「また私に触れたら容赦しませんから」
「何が容赦しないだ。お前に何ができるって言うんだ!」
「できますよ! もう、私は昔の私ではありませんから!」
あざ笑うお父様の額に向けて、私はシルバートレイの角を両手で叩きつけた。
ガツンという音のあと「ぎゃあああああ」という断末魔のような叫び声が上がった。
驚いて後ろに下がると、お父様はその場に崩れ落ちた。
お父様は地面に寝転ぶようにして倒れ、額を押さえて転げ回っている。
私のティアトレイに付与された魔法は、触れた人を痺れさせるものだった。
お父様の絶叫が聞こえたのか、警察署の中から人が出てきた。
リファルド様と一緒に簡単に経緯を説明すると、護衛の兵士が捕まえていた、お父様の身柄を引き取ってくれることになった。
「うああ」
お父様は痛みに弱いのか、額を押さえて未だに喚いている。
もしくは、ティアトレイの効力がよっぽどすごいのでしょうね。
足がしびれたりすると動けなくなるけど、頭の近くだから、脳に支障をきたしているのかもしれない。
下手をすると死んでしまうかもしれないわ。
キール様は殺意が強ければ、効力が強いと言っていた。
お父様がまだ動けるということは、私の殺意はそう強くない。
どちらかというと、かかわりたくないという思いなんだろう。
人を殺める勇気は私にはないし、そこまでする権利はない。
だって、私は殺されていないもの。
やっても良いのは精神的に追い詰めることくらいだろうか。
されたことをやり返すことも良くないと言われているし、死刑制度もいろんな国でどんどん廃止されていっている。
私がお父様を殴ったことも警察の人からは注意された。
警察署の前でだから余計によね。
もっと、違う場所にすれば良かったかしら。
……って、そんな問題ではないわね。
しばらくすると、お父様は額の痛みはなくなったようだけど、上手く話せないとのことで、聴取に時間がかかると警察の人は教えてくれた。
「父はどうなるのでしょうか」
「あなたの御母上に命令した罪で改めて捕まえます。実行犯よりも命令したほうが罪が重いんですよ」
「それは聞いたことがあります」
実行犯よりも指示を出した人間のほうが罪が重くなる。
他国はどうかわからないが、私が住んでいた国やロシノアール王国では、そういうことになっている。
警察との話を終えたあと、リファルド様がティアトレイを見て話しかけてくる。
「それにしても、すごい効力なんだな」
「はい。魔法ってすごいですね」
「そうだな。他の国では平民も簡単な魔法を使える国もあるというから、使えない俺にしてみれば羨ましいもんだ」
「戦争で魔法を使うことはあるんですか?」
「ある。だから、俺達は戦場近くに行っても参加はしない」
「最初から勝ち目のない戦いには挑まないということですね」
「ああ。だから、同盟国が必要なんだ」
魔法を使える人が多い国から攻められたら、使えない国の人はどうしようもない。
だから魔法を使える国と同盟を結んでいて、それが各国への抑止力になっている。
それにしても、私の物理的な攻撃力はまだまだ弱い。
もっと力をつけないといけないわ。
私にはまだ、最大の敵が残っている。
力には力で対抗する。
ティアトレイももっと上手く扱えるようにならないと駄目ね。
初めて人を殴ったから、未だに胸がドキドキしている。
「大丈夫か?」
今までやったことのないことをしたせいか、かなり胸がドキドキしている。
そのことがわかるのか、リファルド様が顔を覗き込んできた。
「はい。そう簡単に強くはなれませんが、まずは、お父様の言いなりにならなくなった私は少し変われたかなと思うのですが、どうでしょうか」
「そうだな。君の母親のような状態から今の君になったのなら、かなり変われたと思う」
「あとは、自分で自分を好きだと思えるようになりたいです」
「そう思えることは良いことだ。自分なんか嫌いだと言う人もいる。でも、俺は生きている以上、誰かの望み通りに生きるのではなく、自分で選んだ人生を歩む人を応援したくなる」
リファルド様が優しい笑みを浮かべて言った。
こんな素敵なリファルド様を見れたのは、なんだかご褒美をもらった気分だわ。
今の私は前向きな気持ちになっている。
でも、お母様は前に進むどころか後退しようとしている。
今回の件で目を覚ましてくれるだろうか。
私は私で小さな一歩でしかないけど、今は良しとしよう。
お父様はこのまま、国外退去させられるはずだ。
アキーム様はどう動くかしら。
リファルド様と一緒にいるところを見られているから、きっと連絡するでしょうね。
「あの、リファルド様」
「俺のことは心配するな。次が本番だぞ」
「はい。アキーム様だけでなく、エレファーナ様も出てくる可能性もありますから」
「そのとおりだ」
顔を見合わせると、リファルド様は話題を変える。
「立ち話もなんだし、レストランにでも行くか。予約をしているんだ」
遠慮しようかと思ったけどれ、予約をしているのなら断るほうが迷惑だと思い、快くお誘いを受けることにした。
リファルド様と一緒に簡単に経緯を説明すると、護衛の兵士が捕まえていた、お父様の身柄を引き取ってくれることになった。
「うああ」
お父様は痛みに弱いのか、額を押さえて未だに喚いている。
もしくは、ティアトレイの効力がよっぽどすごいのでしょうね。
足がしびれたりすると動けなくなるけど、頭の近くだから、脳に支障をきたしているのかもしれない。
下手をすると死んでしまうかもしれないわ。
キール様は殺意が強ければ、効力が強いと言っていた。
お父様がまだ動けるということは、私の殺意はそう強くない。
どちらかというと、かかわりたくないという思いなんだろう。
人を殺める勇気は私にはないし、そこまでする権利はない。
だって、私は殺されていないもの。
やっても良いのは精神的に追い詰めることくらいだろうか。
されたことをやり返すことも良くないと言われているし、死刑制度もいろんな国でどんどん廃止されていっている。
私がお父様を殴ったことも警察の人からは注意された。
警察署の前でだから余計によね。
もっと、違う場所にすれば良かったかしら。
……って、そんな問題ではないわね。
しばらくすると、お父様は額の痛みはなくなったようだけど、上手く話せないとのことで、聴取に時間がかかると警察の人は教えてくれた。
「父はどうなるのでしょうか」
「あなたの御母上に命令した罪で改めて捕まえます。実行犯よりも命令したほうが罪が重いんですよ」
「それは聞いたことがあります」
実行犯よりも指示を出した人間のほうが罪が重くなる。
他国はどうかわからないが、私が住んでいた国やロシノアール王国では、そういうことになっている。
警察との話を終えたあと、リファルド様がティアトレイを見て話しかけてくる。
「それにしても、すごい効力なんだな」
「はい。魔法ってすごいですね」
「そうだな。他の国では平民も簡単な魔法を使える国もあるというから、使えない俺にしてみれば羨ましいもんだ」
「戦争で魔法を使うことはあるんですか?」
「ある。だから、俺達は戦場近くに行っても参加はしない」
「最初から勝ち目のない戦いには挑まないということですね」
「ああ。だから、同盟国が必要なんだ」
魔法を使える人が多い国から攻められたら、使えない国の人はどうしようもない。
だから魔法を使える国と同盟を結んでいて、それが各国への抑止力になっている。
それにしても、私の物理的な攻撃力はまだまだ弱い。
もっと力をつけないといけないわ。
私にはまだ、最大の敵が残っている。
力には力で対抗する。
ティアトレイももっと上手く扱えるようにならないと駄目ね。
初めて人を殴ったから、未だに胸がドキドキしている。
「大丈夫か?」
今までやったことのないことをしたせいか、かなり胸がドキドキしている。
そのことがわかるのか、リファルド様が顔を覗き込んできた。
「はい。そう簡単に強くはなれませんが、まずは、お父様の言いなりにならなくなった私は少し変われたかなと思うのですが、どうでしょうか」
「そうだな。君の母親のような状態から今の君になったのなら、かなり変われたと思う」
「あとは、自分で自分を好きだと思えるようになりたいです」
「そう思えることは良いことだ。自分なんか嫌いだと言う人もいる。でも、俺は生きている以上、誰かの望み通りに生きるのではなく、自分で選んだ人生を歩む人を応援したくなる」
リファルド様が優しい笑みを浮かべて言った。
こんな素敵なリファルド様を見れたのは、なんだかご褒美をもらった気分だわ。
今の私は前向きな気持ちになっている。
でも、お母様は前に進むどころか後退しようとしている。
今回の件で目を覚ましてくれるだろうか。
私は私で小さな一歩でしかないけど、今は良しとしよう。
お父様はこのまま、国外退去させられるはずだ。
アキーム様はどう動くかしら。
リファルド様と一緒にいるところを見られているから、きっと連絡するでしょうね。
「あの、リファルド様」
「俺のことは心配するな。次が本番だぞ」
「はい。アキーム様だけでなく、エレファーナ様も出てくる可能性もありますから」
「そのとおりだ」
顔を見合わせると、リファルド様は話題を変える。
「立ち話もなんだし、レストランにでも行くか。予約をしているんだ」
遠慮しようかと思ったけどれ、予約をしているのなら断るほうが迷惑だと思い、快くお誘いを受けることにした。
お父様のしびれはいつまで経っても消えないらしく、限界がくるまで眠ることもできないそうだ。
お父様とお母様は、二度とロシノアール王国に入国することができなくなった。
そして、二人のせいでロシノアール王国は他国の人が入国する時の条件を厳しくしたため、多くの人から恨まれることになった。
特に裏取引をしていた人間には大打撃だったようだ。
取り締まりが厳しくなり、多くの人間が捕まった。
悪いことをしていたのだから捕まるのはしょうがない。
でも、そういう人達は、私のような考えにはならない。
お父様のせいで、仲間が捕まったと怒り、お父様は今までよりも多くの人から命を狙われることになった。
お母様は最初はお父様に付いていっていた。
でも、ある時、捕まりそうになったお父様はお母様を囮にして自分だけ逃げた。
お母様は悪い人間に捕まり、暴行されそうになったけれど、お父様達を監視している人達はそんな状況を黙って見ているわけにもいかず、警察に連絡をしたため、事なきを得た。
現在のお母様は怯えていて、何も話せる状態ではないらしい。
暴漢に襲われそうになったことなんて、普通の人でもかなりのショックのはずだ。
しかも、お父様に裏切られたのだから、心が弱いお母様にはかなりのダメージだと思う。
ただ、この出来事でやっと、お母様はお父様から離れる決意をした。
問題だったのが、行くあてもないために私にすり寄ろうとしてきたことだ。
私が住んでいた国の警察から連絡があり、身柄を引き取ってほしいと言われた。
でも、お断りした。
保釈金を払うつもりもないと伝えると、無料の就職支援施設に送られることになった。
就職支援施設といっても色々とあって、お母様が行くところはホームレスの人ばかりが集まっている、寮が完備されている施設だった。
一人にしておくと危険だと判断され、状態が落ち着くまでは監視されることになる。
できれば、そこまで心が弱ってしまう前に、お父様から逃げるという道を選んでほしかった。
逃げることは良くないと思う人もいるだろうけれど、私は逃げても良いと思っている。
だって、自分の人生なんだもの。
逃げて新たな道を探せばいい。
人にどうこう言われる筋合いはない。
自分の考えは相手が親であろうがなんだろうが、他の人に強いられるべきものではないのだから。
――といっても、他人のことを気にして我慢してしまう人が多いのよね。
*****
今日は戦地に赴いていたリファルド様が戻られる日で、キール様も戻って来るから一緒にお出迎えをしようと、ミリー様に誘われて、デファン公爵家にお邪魔していた。
「ミリー様はキール様の婚約者だからお出迎えはわかりますが、私はどうなんでしょうか。お世話になっていますから、何かしなければならないのは確かですが、お出迎えされても喜んでもらえるかどうか心配です」
「キール様からの手紙では、リファルド様はオフの時はサブリナ様のことをいつも気にしているようですし、出迎えたら喜ばれると思いますよ」
「そう思うようにします」
私が頷くと、ミリー様は話題を変えてくる。
「そういえば、サブリナ様の元夫のアキーム様は今は大人しくしているんですか?」
「ええ。私がロシノアール王国にいることがわかったので、接触しようとしているようですが、お父様のせいで入国審査が厳しいため時間がかかっているみたいです」
「問題の国でもありますから、何日もかけているんでしょうね」
「はい。しかも、ワイズ公爵家と折り合いの悪い公爵家にすり寄ったみたいです。今の段階ですと、アキーム様は罪を犯していませんから、公爵家の力も働いて入国はできてしまうでしょう」
「そういえば、サブリナさんとリファルド様は婚約しないのですか?」
ミリー様が不思議そうな顔で聞いてくるので、慌てて首を横に振る。
「私は平民ですから、公爵家の嫡男の婚約者になるなんて不可能です。しかも、一度、結婚までしてますから」
「再婚する人なんてたくさんいますよ。それに、元夫が酷い人だったことは他の人も知っているのでしょう?」
「それはそうですが、どう考えても難しいはずです」
「偉いからこそ、無理がきくというのもありますよ。元夫が入国できるかもしれないんですから」
ミリー様が苦笑した時、応接室の扉がノックされた。
リファルド様たちが帰ってきたのかと思ったら違った。
訪ねて来たのは情報屋だった。
情報屋というのは、その名の通り、情報を売り買いする人間のことで、リファルド様が雇った若い男性だった。
緊急の話だと言うので聞いてみると、アキーム様と彼の母親のエレファーナ様のロシノアール王国への入国が認められたという話だった。
いよいよ、本番といったところだわ。
お父様とお母様は、二度とロシノアール王国に入国することができなくなった。
そして、二人のせいでロシノアール王国は他国の人が入国する時の条件を厳しくしたため、多くの人から恨まれることになった。
特に裏取引をしていた人間には大打撃だったようだ。
取り締まりが厳しくなり、多くの人間が捕まった。
悪いことをしていたのだから捕まるのはしょうがない。
でも、そういう人達は、私のような考えにはならない。
お父様のせいで、仲間が捕まったと怒り、お父様は今までよりも多くの人から命を狙われることになった。
お母様は最初はお父様に付いていっていた。
でも、ある時、捕まりそうになったお父様はお母様を囮にして自分だけ逃げた。
お母様は悪い人間に捕まり、暴行されそうになったけれど、お父様達を監視している人達はそんな状況を黙って見ているわけにもいかず、警察に連絡をしたため、事なきを得た。
現在のお母様は怯えていて、何も話せる状態ではないらしい。
暴漢に襲われそうになったことなんて、普通の人でもかなりのショックのはずだ。
しかも、お父様に裏切られたのだから、心が弱いお母様にはかなりのダメージだと思う。
ただ、この出来事でやっと、お母様はお父様から離れる決意をした。
問題だったのが、行くあてもないために私にすり寄ろうとしてきたことだ。
私が住んでいた国の警察から連絡があり、身柄を引き取ってほしいと言われた。
でも、お断りした。
保釈金を払うつもりもないと伝えると、無料の就職支援施設に送られることになった。
就職支援施設といっても色々とあって、お母様が行くところはホームレスの人ばかりが集まっている、寮が完備されている施設だった。
一人にしておくと危険だと判断され、状態が落ち着くまでは監視されることになる。
できれば、そこまで心が弱ってしまう前に、お父様から逃げるという道を選んでほしかった。
逃げることは良くないと思う人もいるだろうけれど、私は逃げても良いと思っている。
だって、自分の人生なんだもの。
逃げて新たな道を探せばいい。
人にどうこう言われる筋合いはない。
自分の考えは相手が親であろうがなんだろうが、他の人に強いられるべきものではないのだから。
――といっても、他人のことを気にして我慢してしまう人が多いのよね。
*****
今日は戦地に赴いていたリファルド様が戻られる日で、キール様も戻って来るから一緒にお出迎えをしようと、ミリー様に誘われて、デファン公爵家にお邪魔していた。
「ミリー様はキール様の婚約者だからお出迎えはわかりますが、私はどうなんでしょうか。お世話になっていますから、何かしなければならないのは確かですが、お出迎えされても喜んでもらえるかどうか心配です」
「キール様からの手紙では、リファルド様はオフの時はサブリナ様のことをいつも気にしているようですし、出迎えたら喜ばれると思いますよ」
「そう思うようにします」
私が頷くと、ミリー様は話題を変えてくる。
「そういえば、サブリナ様の元夫のアキーム様は今は大人しくしているんですか?」
「ええ。私がロシノアール王国にいることがわかったので、接触しようとしているようですが、お父様のせいで入国審査が厳しいため時間がかかっているみたいです」
「問題の国でもありますから、何日もかけているんでしょうね」
「はい。しかも、ワイズ公爵家と折り合いの悪い公爵家にすり寄ったみたいです。今の段階ですと、アキーム様は罪を犯していませんから、公爵家の力も働いて入国はできてしまうでしょう」
「そういえば、サブリナさんとリファルド様は婚約しないのですか?」
ミリー様が不思議そうな顔で聞いてくるので、慌てて首を横に振る。
「私は平民ですから、公爵家の嫡男の婚約者になるなんて不可能です。しかも、一度、結婚までしてますから」
「再婚する人なんてたくさんいますよ。それに、元夫が酷い人だったことは他の人も知っているのでしょう?」
「それはそうですが、どう考えても難しいはずです」
「偉いからこそ、無理がきくというのもありますよ。元夫が入国できるかもしれないんですから」
ミリー様が苦笑した時、応接室の扉がノックされた。
リファルド様たちが帰ってきたのかと思ったら違った。
訪ねて来たのは情報屋だった。
情報屋というのは、その名の通り、情報を売り買いする人間のことで、リファルド様が雇った若い男性だった。
緊急の話だと言うので聞いてみると、アキーム様と彼の母親のエレファーナ様のロシノアール王国への入国が認められたという話だった。
いよいよ、本番といったところだわ。
お出迎えを無事に終えて少し落ち着いたところで、アキーム様が入国できてしまったことを、リファルド様に伝えた。
すると、難しい顔で尋ねてくる。
「どうしてそこまで君にこだわるのか、理由はわかるのか」
「こうだと確信しているわけではありませんが、支配できる人が好きなのではないかと思います。あと、母親からそう教わってきたのかもしれません」
「人の意見と自分の意見が違っていたら攻撃してくるような母親のようだからな」
眉根を寄せるリファルド様に頷く。
「自分の言っていることだけが正しくて、それ以外の意見を言う人は認められないというような人です」
「迷っているならまだしも、こうだと決めた人間に口を出す必要性はないと思うがな。考え方なんて人によって色々とあるだろう」
「普通の人はそう思うと思いますが、エレファーナ様は自分の意見が正しいと思い込んでいる人ですから話になりません。感じ方が違うと怒り始めて暴言を吐きます。言われた人が不快になることなんてどうでも良いんです」
「そんな奴と話をして決着がつくのか? 人を誹謗中傷することは罪だが、考えたことを言うのは罪ではない」
「最悪の場合は、ティアトレイを使うしかないかと思っています」
話し合いで解決しないのであれば、物理的に対抗するしか無い。
あの人は今の私よりも力は弱い。
できれば、距離を取ることで解決したかったけど、追いかけてくるのだからしょうがない。
自分に危害を加えられる前に対処するしかないのだ。
「一人にならないようにすることと、私がティアトレイを使ったとしても罪に問われないような状況に持って行くつもりです。彼らのせいで暴行罪で捕まるなんて馬鹿らしいですから」
「そうだな。俺も裏で手を回すようにするが、相手も黙ってはいないだろう」
相手というのはアキーム様たちのことではなく、敵対している公爵家のことを言っているのだとわかった。
「ご迷惑をおかけして申し訳ございません」
「気にするな。好きでやってると言ってるだろ。それにしても、君は本当に変な人間に好かれるんだな」
「……前にも似たようなことを言われた気がしますね。アキーム様達は別として、普通の人から見たら変な人間であっても、常識を持っていて、人を思いやる気持ちを持っている人であれば、その人が人と変わった考えを持っていて変な人間と言われていても、私は気にならないと思います。だから、そういう変な人に好かれたいです」
「自分の言いたいことを言うだけじゃなく、相手の話も聞ける人だということだな」
リファルド様は納得したように頷いた。
「はい。あの、お疲れのところに嫌な話をして申し訳ございません」
「いや。俺も気になっていたから、教えてくれて助かる」
「……ありがとうございます」
ミリー様に言われて、再確認したことがある。
アキーム様の件が終わったら、リファルド様とはお別れだ。
寂しいし悲しいけれど、今までが異常だったのだ。
平民になった私に、何から何まで面倒を見てくれる公爵令息なんて、リファルド様しかいない。
このままでは、私との変な噂がたてられてしまうかもしれない。
私からちゃんと身を引かないとならない。
そのためには、私がリファルド様に頼らなくても生きていけるということを見せないと駄目だわ。
決意を新たにしたその数日後の朝、アキーム様から手紙が届いたのだった。
すると、難しい顔で尋ねてくる。
「どうしてそこまで君にこだわるのか、理由はわかるのか」
「こうだと確信しているわけではありませんが、支配できる人が好きなのではないかと思います。あと、母親からそう教わってきたのかもしれません」
「人の意見と自分の意見が違っていたら攻撃してくるような母親のようだからな」
眉根を寄せるリファルド様に頷く。
「自分の言っていることだけが正しくて、それ以外の意見を言う人は認められないというような人です」
「迷っているならまだしも、こうだと決めた人間に口を出す必要性はないと思うがな。考え方なんて人によって色々とあるだろう」
「普通の人はそう思うと思いますが、エレファーナ様は自分の意見が正しいと思い込んでいる人ですから話になりません。感じ方が違うと怒り始めて暴言を吐きます。言われた人が不快になることなんてどうでも良いんです」
「そんな奴と話をして決着がつくのか? 人を誹謗中傷することは罪だが、考えたことを言うのは罪ではない」
「最悪の場合は、ティアトレイを使うしかないかと思っています」
話し合いで解決しないのであれば、物理的に対抗するしか無い。
あの人は今の私よりも力は弱い。
できれば、距離を取ることで解決したかったけど、追いかけてくるのだからしょうがない。
自分に危害を加えられる前に対処するしかないのだ。
「一人にならないようにすることと、私がティアトレイを使ったとしても罪に問われないような状況に持って行くつもりです。彼らのせいで暴行罪で捕まるなんて馬鹿らしいですから」
「そうだな。俺も裏で手を回すようにするが、相手も黙ってはいないだろう」
相手というのはアキーム様たちのことではなく、敵対している公爵家のことを言っているのだとわかった。
「ご迷惑をおかけして申し訳ございません」
「気にするな。好きでやってると言ってるだろ。それにしても、君は本当に変な人間に好かれるんだな」
「……前にも似たようなことを言われた気がしますね。アキーム様達は別として、普通の人から見たら変な人間であっても、常識を持っていて、人を思いやる気持ちを持っている人であれば、その人が人と変わった考えを持っていて変な人間と言われていても、私は気にならないと思います。だから、そういう変な人に好かれたいです」
「自分の言いたいことを言うだけじゃなく、相手の話も聞ける人だということだな」
リファルド様は納得したように頷いた。
「はい。あの、お疲れのところに嫌な話をして申し訳ございません」
「いや。俺も気になっていたから、教えてくれて助かる」
「……ありがとうございます」
ミリー様に言われて、再確認したことがある。
アキーム様の件が終わったら、リファルド様とはお別れだ。
寂しいし悲しいけれど、今までが異常だったのだ。
平民になった私に、何から何まで面倒を見てくれる公爵令息なんて、リファルド様しかいない。
このままでは、私との変な噂がたてられてしまうかもしれない。
私からちゃんと身を引かないとならない。
そのためには、私がリファルド様に頼らなくても生きていけるということを見せないと駄目だわ。
決意を新たにしたその数日後の朝、アキーム様から手紙が届いたのだった。
アキーム様からの手紙には、宿屋に返事を送ってくれと書かれていたので、こちらが指定した場所と日時でなら、会っても良いと返した。
私がすんなりと会うことを認めたことに警戒しているような返事がきたけれど、断ってはこなかった。
現在、ラファイ伯爵令嬢がエレファーナ様のターゲットだから、彼女も連れてきているようだ。
自分も私と同じ目に遭ってみて、彼女はどう感じているんだろうか。
そのうち恐ろしいことになる気もする。
でも、そうなったとしても、自業自得だと思ってしまう私は冷たい人間なのかもしれない。
******
当日、私達はレストランで会うことにした。
個室にすべきか迷ったけど、護衛を入れたがらない可能性があるため、店を貸し切ってもらった。
キール様のお家が経営するところだったので、融通が利いたのだ。
店の中に集まってくれるお客様は全て関係者で、証人になってくれる人ばかりだ。
警察関係者も紛れ込んでいるというので、もし、アキーム様達が悪事を働いていたことを暴露したら、彼らの人生はそれで終了ということになる。
「久しぶりね、サブリナさん」
案内された席に着くと、エレファーナ様が顔で話しかけてきた。
周りに人がいるから、よそゆきの顔をしているみたいだ。
エレファーナ様の隣にはアキーム様が座っている。
ラファイ伯爵令嬢の姿は見えない。
ここには彼女を連れてこなかったみたいだ。
「お久しぶりです、エレファーナ様。あの時の約束を守っていただけなくて残念です」
「しょうがないじゃないの。アキームがこの状態なんだもの」
エレファーナ様は少しふっくらしたように見えるけれど、アキーム様は以前よりも痩せていて憔悴しているように見える。
「何かあったんですか」
「あなたのせいよ。あなたがいなくなってから、アキームは誹謗中傷に悩まされているの!」
「誹謗中傷?」
聞き返すと、エレファーナ様が話し始める。
「そうよ。彼があなたにひどい対応をしていたことに対して、最低な男性だとか言われるようになったのよ」
「酷いことをしたというのは間違ってはいないでしょう。それに誹謗中傷をしている人達がやっているようなことをエレファーナ様はしていますよね」
「私のことはどうでもいいのよ! アキームは人の悪口は言っていないわ! だから、他の人間がアキームの悪口を言うことは許せない!」
エレファーナ様がすごい剣幕で叫んだ。
「アキーム様のことは可哀相だと思えるのに、あなたが攻撃した人のことは可哀想とは思えないのですか」
「当たり前でしょう。おかしなことを言うほうが悪いのよ!」
「めちゃくちゃなことを言っていることを、自分でわからないのですか?」
「めちゃくちゃなことなんて言っていないわ。劣っている人間が偉そうにするんじゃないわよ!」
エレファーナ様は立ち上がり、私を睨みつけて続ける。
「私のように賢い人間は、あなたのような人間をクズだと思っているの」
「別にあなたにどう思われてもかまいません。ところで、どうしてクズである私と関わろうとするんですか? それが不思議です。嫌なら関わらなければ良いでしょう。そんなこともわからないんですか?」
「クズだと認識しろと言っているだけよ! 教えてあげているんだから親切でしょう!」
「余計な御世話です。自己満足にも程があるでしょう」
「なんですって!?」
エレファーナ様がテーブルに手を叩きつけた時、アキーム様が叫ぶ。
「もうやめてくれ!」
立ち上がったアキーム様は、私に訴えかける。
「僕が悪かった! 謝るから帰ってきてくれ! ベルと君なら、君のほうが僕には合うんだよ!」
「はあ?」
あまりの勝手な言い分に、思わず間抜けな声が出てしまった。
「ベルはワガママばっかりで口うるさいんだ。あれも駄目、これも駄目って心が安らぐ日がないんだよ。やっぱり、僕には君しかいないって気がついた。失って気が付くものがあるって言うだろう? 僕はそのタイプなんだ!」
「無理です。あなたの元には戻りません。大体、こうやって会うこと自体もおかしいんです」
「でも、君は会ってくれた。まだ、僕に未練があるということだろう?」
「そう取られてしまったのであれば、私の態度に問題があるのだと思います。申し訳ございません。私はあなたとよりを戻すつもりはありません」
「サブリナ! 言うことを聞くんだ!」
声を荒らげるアキーム様を見て、エレファーナ様と彼はやっぱり親子だと確信した時、ウエイターがやって来ると私に話しかけてきた。
「ご注文の品をお持ちいたしました」
私の目の前に置かれたのは、私専用のティアトレイだった。
どうしてシルバートレイが?
そんな疑問と聞き覚えのある声に驚いて見上げてみると、ウエイターだと思った彼は、髪型を変え、化粧までしたゼノンだった。
私がすんなりと会うことを認めたことに警戒しているような返事がきたけれど、断ってはこなかった。
現在、ラファイ伯爵令嬢がエレファーナ様のターゲットだから、彼女も連れてきているようだ。
自分も私と同じ目に遭ってみて、彼女はどう感じているんだろうか。
そのうち恐ろしいことになる気もする。
でも、そうなったとしても、自業自得だと思ってしまう私は冷たい人間なのかもしれない。
******
当日、私達はレストランで会うことにした。
個室にすべきか迷ったけど、護衛を入れたがらない可能性があるため、店を貸し切ってもらった。
キール様のお家が経営するところだったので、融通が利いたのだ。
店の中に集まってくれるお客様は全て関係者で、証人になってくれる人ばかりだ。
警察関係者も紛れ込んでいるというので、もし、アキーム様達が悪事を働いていたことを暴露したら、彼らの人生はそれで終了ということになる。
「久しぶりね、サブリナさん」
案内された席に着くと、エレファーナ様が顔で話しかけてきた。
周りに人がいるから、よそゆきの顔をしているみたいだ。
エレファーナ様の隣にはアキーム様が座っている。
ラファイ伯爵令嬢の姿は見えない。
ここには彼女を連れてこなかったみたいだ。
「お久しぶりです、エレファーナ様。あの時の約束を守っていただけなくて残念です」
「しょうがないじゃないの。アキームがこの状態なんだもの」
エレファーナ様は少しふっくらしたように見えるけれど、アキーム様は以前よりも痩せていて憔悴しているように見える。
「何かあったんですか」
「あなたのせいよ。あなたがいなくなってから、アキームは誹謗中傷に悩まされているの!」
「誹謗中傷?」
聞き返すと、エレファーナ様が話し始める。
「そうよ。彼があなたにひどい対応をしていたことに対して、最低な男性だとか言われるようになったのよ」
「酷いことをしたというのは間違ってはいないでしょう。それに誹謗中傷をしている人達がやっているようなことをエレファーナ様はしていますよね」
「私のことはどうでもいいのよ! アキームは人の悪口は言っていないわ! だから、他の人間がアキームの悪口を言うことは許せない!」
エレファーナ様がすごい剣幕で叫んだ。
「アキーム様のことは可哀相だと思えるのに、あなたが攻撃した人のことは可哀想とは思えないのですか」
「当たり前でしょう。おかしなことを言うほうが悪いのよ!」
「めちゃくちゃなことを言っていることを、自分でわからないのですか?」
「めちゃくちゃなことなんて言っていないわ。劣っている人間が偉そうにするんじゃないわよ!」
エレファーナ様は立ち上がり、私を睨みつけて続ける。
「私のように賢い人間は、あなたのような人間をクズだと思っているの」
「別にあなたにどう思われてもかまいません。ところで、どうしてクズである私と関わろうとするんですか? それが不思議です。嫌なら関わらなければ良いでしょう。そんなこともわからないんですか?」
「クズだと認識しろと言っているだけよ! 教えてあげているんだから親切でしょう!」
「余計な御世話です。自己満足にも程があるでしょう」
「なんですって!?」
エレファーナ様がテーブルに手を叩きつけた時、アキーム様が叫ぶ。
「もうやめてくれ!」
立ち上がったアキーム様は、私に訴えかける。
「僕が悪かった! 謝るから帰ってきてくれ! ベルと君なら、君のほうが僕には合うんだよ!」
「はあ?」
あまりの勝手な言い分に、思わず間抜けな声が出てしまった。
「ベルはワガママばっかりで口うるさいんだ。あれも駄目、これも駄目って心が安らぐ日がないんだよ。やっぱり、僕には君しかいないって気がついた。失って気が付くものがあるって言うだろう? 僕はそのタイプなんだ!」
「無理です。あなたの元には戻りません。大体、こうやって会うこと自体もおかしいんです」
「でも、君は会ってくれた。まだ、僕に未練があるということだろう?」
「そう取られてしまったのであれば、私の態度に問題があるのだと思います。申し訳ございません。私はあなたとよりを戻すつもりはありません」
「サブリナ! 言うことを聞くんだ!」
声を荒らげるアキーム様を見て、エレファーナ様と彼はやっぱり親子だと確信した時、ウエイターがやって来ると私に話しかけてきた。
「ご注文の品をお持ちいたしました」
私の目の前に置かれたのは、私専用のティアトレイだった。
どうしてシルバートレイが?
そんな疑問と聞き覚えのある声に驚いて見上げてみると、ウエイターだと思った彼は、髪型を変え、化粧までしたゼノンだった。
「一体、それは何なの?」
エレファーナ様はティアトレイのことを知らないようで、訝しげな顔をした。
「ちゃんとした商品名はありますが、シルバートレイです」
「どうして、そんなものをレストランで注文するのよ」
エレファーナ様は去っていくウエイター、ではなく、ゼノンを呼び止める。
「ちょっとあなた! 一体、何を考えているの!」
「申し訳ございません。わたくしはオーダーされたものを持ってきただけでございます」
ご丁寧に裏声まで使っているから、かなり楽しんでいるように見える。
ゼノンが来るなんて聞いていなかった。
きっと、リファルド様が今日のことをゼノンに話をして、私に内緒で計画を進めたんでしょう。
私が呆れた顔をすると、ゼノンは微かに微笑み、この場を離れる。
眉毛の書き方を変えるだけで、本当にイメージが違うわ。
「信じられない! 何なのよ、一体! 無礼だわ!」
エレファーナ様は怒り狂っているけど、アキーム様は違った。
「もしかして、家に帰ってきてメイドをするつもりなのか?」
「どうしたら、そんな前向きな気持ちになれるのか知りたいです」
「前向きとかそういうものじゃない。本当のことを言ってるんだよ」
ここまでポジティブだと、生きていくことに疲れることなんてないんでしょうね。
生きづらい世の中だと思っている私には、少しだけ羨ましい。
かといって、アキーム様のようになりたいと思うことは絶対にない。
繊細すぎても生きていくことは辛い。
だけど、人の気持ちに無神経になれば、知らない内に多くの人から嫌われることになる。
アキーム様はやっと、自分がそういう状態になっていることに気がついたんだろう。
問題は、自分に原因があることに気づいていないことだ。
駄目元で伝えてみることにする。
「これはメイドが使う普通のシルバートレイとは違います」
「……どういうことかな」
「これは言葉ではわかってもらえず、暴力をふるってくる人から身を守るものです」
「……どうして君がそんなものを持っているんだ?」
「いただいたんです。アキーム様達のような人から身を守るために」
「僕は君に暴力をふるったことなんて一度もないじゃないか!」
「精神的に追い詰めることだって、言葉の暴力になるんです」
アキーム様を睨みつけると、焦った顔をして尋ねてくる。
「君は今まで幸せだと思っていただろ?」
「結婚する前はそうでしたが、あなたが領地の視察に頻繁に出かけるようになってからは違います。そして、私があなたからの支配に気付けたのは、あなたとラファイ伯爵令嬢との話を聞いたからです」
「……リファルド様から聞いたのか? 彼が嘘をついているんだ!」
「いいえ。私もあの場にいたんです」
「……なんだって?」
あの時の出来事を話すと、アキーム様は青ざめた。
「いや、その、あれは、ベルの前だから言ったことであって」
「あんなことを嘘でも話す人のことを好きでいられるはずがありません」
「そ、そんな……」
アキーム様は助けを求めるかのようにエレファーナ様を見た。
エレファーナ様はそんなアキーム様に優しい目を向けて声をかける。
「本当にしょうがない子ね。だから、彼女はやめておきなさいと言ったでしょう」
「で、ですが、盗み聞きをするような人だとは思っていなかったんです!」
「それが彼女の本性ですよ」
どう思われても良いけど、一応、伝えておく。
「あの時のアキーム様は小声で話しているわけじゃありませんでしたし、あの場に他の誰かがいたら話し声が丸聞こえでしたので、聞かれたくない話をあんな所でするほうが間違っています。しかも、話をしていただけではないようですし」
「しょ、しょうがないじゃないか。あの時はベルのことを魅力的に思えていたんだよ。それに、君と別れる気もなかった」
「それはあなたの勝手な考えじゃないですか。それを私に押し付けないでください!」
アキーム様のことが本当に好きだった。
それなのに、今は全く魅力を感じない。
まるで、魔法がとけたみたいだわ。
「サブリナは僕のことが可哀相だとは思わないのか?」
「……何を言っているんですか?」
「世間から冷たい目で見られて、妻にも見捨てられるなんて最悪な人生じゃないか! せめて、君だけでも人生を僕に捧げて尽くしてくれよ!」
「お断りします。私の人生は私のものです。あなたに捧げるものではありません」
「この生意気な!」
エレファーナ様が手を出してきたので、ティアトレイで防御した。
「きゃあっ!」
ティアトレイに手をぶつけただけでなく、しびれが全身を駆け巡ったのか、エレファーナ様は悲鳴をあげ、呆然とした表情で椅子に崩れ落ちる。
「い、一体、それはなんなんだよ!?」
アキーム様がティアトレイを奪おうと私に手を伸ばした。
エレファーナ様はティアトレイのことを知らないようで、訝しげな顔をした。
「ちゃんとした商品名はありますが、シルバートレイです」
「どうして、そんなものをレストランで注文するのよ」
エレファーナ様は去っていくウエイター、ではなく、ゼノンを呼び止める。
「ちょっとあなた! 一体、何を考えているの!」
「申し訳ございません。わたくしはオーダーされたものを持ってきただけでございます」
ご丁寧に裏声まで使っているから、かなり楽しんでいるように見える。
ゼノンが来るなんて聞いていなかった。
きっと、リファルド様が今日のことをゼノンに話をして、私に内緒で計画を進めたんでしょう。
私が呆れた顔をすると、ゼノンは微かに微笑み、この場を離れる。
眉毛の書き方を変えるだけで、本当にイメージが違うわ。
「信じられない! 何なのよ、一体! 無礼だわ!」
エレファーナ様は怒り狂っているけど、アキーム様は違った。
「もしかして、家に帰ってきてメイドをするつもりなのか?」
「どうしたら、そんな前向きな気持ちになれるのか知りたいです」
「前向きとかそういうものじゃない。本当のことを言ってるんだよ」
ここまでポジティブだと、生きていくことに疲れることなんてないんでしょうね。
生きづらい世の中だと思っている私には、少しだけ羨ましい。
かといって、アキーム様のようになりたいと思うことは絶対にない。
繊細すぎても生きていくことは辛い。
だけど、人の気持ちに無神経になれば、知らない内に多くの人から嫌われることになる。
アキーム様はやっと、自分がそういう状態になっていることに気がついたんだろう。
問題は、自分に原因があることに気づいていないことだ。
駄目元で伝えてみることにする。
「これはメイドが使う普通のシルバートレイとは違います」
「……どういうことかな」
「これは言葉ではわかってもらえず、暴力をふるってくる人から身を守るものです」
「……どうして君がそんなものを持っているんだ?」
「いただいたんです。アキーム様達のような人から身を守るために」
「僕は君に暴力をふるったことなんて一度もないじゃないか!」
「精神的に追い詰めることだって、言葉の暴力になるんです」
アキーム様を睨みつけると、焦った顔をして尋ねてくる。
「君は今まで幸せだと思っていただろ?」
「結婚する前はそうでしたが、あなたが領地の視察に頻繁に出かけるようになってからは違います。そして、私があなたからの支配に気付けたのは、あなたとラファイ伯爵令嬢との話を聞いたからです」
「……リファルド様から聞いたのか? 彼が嘘をついているんだ!」
「いいえ。私もあの場にいたんです」
「……なんだって?」
あの時の出来事を話すと、アキーム様は青ざめた。
「いや、その、あれは、ベルの前だから言ったことであって」
「あんなことを嘘でも話す人のことを好きでいられるはずがありません」
「そ、そんな……」
アキーム様は助けを求めるかのようにエレファーナ様を見た。
エレファーナ様はそんなアキーム様に優しい目を向けて声をかける。
「本当にしょうがない子ね。だから、彼女はやめておきなさいと言ったでしょう」
「で、ですが、盗み聞きをするような人だとは思っていなかったんです!」
「それが彼女の本性ですよ」
どう思われても良いけど、一応、伝えておく。
「あの時のアキーム様は小声で話しているわけじゃありませんでしたし、あの場に他の誰かがいたら話し声が丸聞こえでしたので、聞かれたくない話をあんな所でするほうが間違っています。しかも、話をしていただけではないようですし」
「しょ、しょうがないじゃないか。あの時はベルのことを魅力的に思えていたんだよ。それに、君と別れる気もなかった」
「それはあなたの勝手な考えじゃないですか。それを私に押し付けないでください!」
アキーム様のことが本当に好きだった。
それなのに、今は全く魅力を感じない。
まるで、魔法がとけたみたいだわ。
「サブリナは僕のことが可哀相だとは思わないのか?」
「……何を言っているんですか?」
「世間から冷たい目で見られて、妻にも見捨てられるなんて最悪な人生じゃないか! せめて、君だけでも人生を僕に捧げて尽くしてくれよ!」
「お断りします。私の人生は私のものです。あなたに捧げるものではありません」
「この生意気な!」
エレファーナ様が手を出してきたので、ティアトレイで防御した。
「きゃあっ!」
ティアトレイに手をぶつけただけでなく、しびれが全身を駆け巡ったのか、エレファーナ様は悲鳴をあげ、呆然とした表情で椅子に崩れ落ちる。
「い、一体、それはなんなんだよ!?」
アキーム様がティアトレイを奪おうと私に手を伸ばした。
この作家の他の作品
表紙を見る
彼が浮気をしたのは全て私のせいらしい…。
悪いのは本当に私なの…?
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…