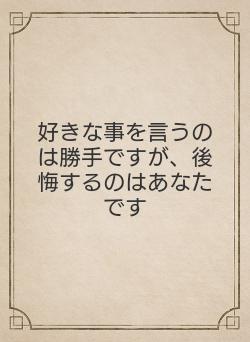「り、理解していますわよ! なんて失礼なことを言うのですか!」
「そんなことを言い返してくるあなたに驚きです。今まで私にあれだけ失礼なことをしてきておいて、よく言えますね!」
興奮してはいけないとわかっているのに抑えられない。
椅子から立ち上がり、感情的になって叫ぶ。
「私の学生時代がどれだけ辛いものだったか想像がつきますか!?」
「つくわよ!」
ラファイ伯爵令嬢も興奮しているのか、媚びることを忘れて言い返してくる。
「それでも学園に来ていたということは耐えられるほどの辛さだったのよ! 今の私はあなたと違うの! 家を追い出されたのよ!? あなたには住む家があったんだから、わたしのほうが辛いに決まっているでしょう!」
「あの時の私はオルドリン伯爵のためだと思って耐えられていました! だけど、無駄だった! この気持ちがあなたにわかるわけがありません!」
何のためにあんな辛い思いを我慢して、学園に行っていたんだろう。
アキーム様のためだけに頑張っていたのに――
アキーム様のことがなければ、家を追い出されても良かった。
あんな辛い環境にいるくらいなら、どこかで野垂れ死んだほうが良いと思った。
それでも、踏みとどまれたのは――
「あの人の傍にいたいと思ったからなのに」
涙があふれてきて止まらなかった。
慌てて立ち上がったゼノンを、リファルド様が制する。
「まだ、サブリナ嬢は終わってない。そうだろ」
リファルド様が挑戦的な笑みを浮かべて尋ねてきたので、大きく首を縦に振る。
そうよ。
これくらいで終わらせられない。
「……ありがとうございます」
涙をハンカチで拭ったあと、ラファイ伯爵令嬢に告げる。
「今の涙で完全に吹っ切れました。オルドリン伯爵を許すこともないし、ラファイ伯爵令嬢、あなたのことも絶対に許しません。過去のことは、あなたのお父様に報告させていただきます」
「やめて!」
ラファイ伯爵令嬢は涙目で訴えてくる。
「オルドリン伯爵との離婚理由はどんなものかは知らないけど、あなた、今までは幸せだったのでしょう? それで良いじゃないの! わたしは結婚の夢を絶たれたのよ!?」
「あなたの婚約が駄目になったことは、私のせいではありませんし、私はあなたとオルドリン伯爵が浮気していたことを責めているんじゃありません。あなたが過去にしてきたことを問題にしているんです。それは、あなたのお父様も同じなのでしょう?」
「そ、それは……」
ラファイ伯爵令嬢は地面に座り込んで頭を下げる。
「申し訳ございませんでした。謝りますからお許しください」
「……これからする質問に正直に話をしていただけるなら考えます」
「なんでしょうか!?」
ラファイ伯爵令嬢は頭を上げて、明るい表情を見せた。
喜んでも無駄なのに。
そんな言葉を口に出さないように堪えて、質問をする。
「どうしてあなたは、私に嫌なことをしたんですか。オルドリン伯爵に頼まれたからですか?」
「い、いいえ、その、たまたま、目の前にあなたがいたからで」
ラファイ伯爵令嬢は笑みを消して目を泳がせながら答える。
たまたま、目の前にいたからですって?
「では、他の人に同じことをしなかったのはなぜですか? 目の前には他にも人がたくさんいましたよね」
「……苛立たしく思わなかったからです。その、あの時のわたしはストレスが溜まっていたんです!」
「私のせいでストレスが溜まっていたとでも言うのですか?」
「いいえ。他のことでです! だから、誰かを傷つけることでストレス発散をしようとしていたんです!」
堂々と言っているけれど、言っていることは普通の人なら考えないことだ。
たとえ、考えたとしても実行には移さないし、八つ当たりしてしまったとしても、すぐに後悔するものだ。
ラファイ伯爵令嬢のように開き直ったりなんかしない。
「あなたの考えはわかりました」
「では、許していただけるんですね!?」
「そんなわけがないでしょう。やはり、過去の話はラファイ伯爵にお話をしなければならない内容だと思います」
「や、やめて、そんな! わたしのお父様がどんな人かわかって言っているの!?」
「ラファイ伯爵がどんな人であろうとも、あなたの過去の話をするつもりです」
「やめてって言っているじゃないですか! そんなことになったら、わたしはもう社交場にも呼ばれなくなってしまうわ!」
「呼ばれなくなるのはオルドリン伯爵も同じでしょう。二人仲良く暮らしてはどうでしょうか」
そうだわ。
住む家がないのなら、それこそ、アキーム様と静養地で大人しく暮らしていれば良いのよ。
「嫌よ! 私には華やかな世界が似合うの! どうしてよ! そんなに嫌ならもっと早くに言ってくれれば良かったじゃないの!」
「嫌だと言えば嫌がらせをエスカレートさせたのはあなたじゃないですか。そんなことまで忘れているようでしたら、反省する気はないとみなします。お帰りください」
「謝ります! 謝りますから許してください!」
私の所へ駆け寄ろうとしたラファイ伯爵令嬢を、周りを取り囲んでいた兵士が止めた。
「サブリナさん、ごめんなさい! あなたがそこまで苦しんでいるとは思わなかったの! 正直に話すわ! 実は、あなたを攻撃しろと言ったのはアキーム様なのよ!」
「だからって言いなりになる必要はないでしょう」
「あの時のわたしは子供だったの!」
「なら、その責任はご両親に取ってもらいましょう」
「そんなっ!」
兵士に押さえつけられたラファイ伯爵令嬢は、悲鳴のような甲高い声を上げた。
彼女にはアキーム様と一緒に苦しんでもらう。
人を傷つけるという行為がどれだけ駄目なものなのか。
安易な気持ちで浮気をしたのだから、そんなことをしたらどうなるのか。
ちゃんと知ってもらわなければならない。
というか、大人なんだから知っていて当たり前なんだけどね。
「さようなら、ラファイ伯爵令嬢。もう二度と私に近づかないでください」
「そんな! あなたが許してくれないと、わたしは家に帰れないのに!」
「あなたは自分のことしか考えていないのですね」
「……少しいいか?」
リファルド様が手を挙げたので頷くと、彼は口元に笑みを浮かべて話す。
「もし、サブリナ嬢に近づけば、ワイズ公爵家が相手になる。言っておくが、こちらはそっちに馬鹿な真似をされて腹を立ててるんだ。次も許してもらえると思うなよ」
「……う、あ……っ」
ラファイ伯爵令嬢の目から大粒の涙が溢れ出した。
「そんなことを言い返してくるあなたに驚きです。今まで私にあれだけ失礼なことをしてきておいて、よく言えますね!」
興奮してはいけないとわかっているのに抑えられない。
椅子から立ち上がり、感情的になって叫ぶ。
「私の学生時代がどれだけ辛いものだったか想像がつきますか!?」
「つくわよ!」
ラファイ伯爵令嬢も興奮しているのか、媚びることを忘れて言い返してくる。
「それでも学園に来ていたということは耐えられるほどの辛さだったのよ! 今の私はあなたと違うの! 家を追い出されたのよ!? あなたには住む家があったんだから、わたしのほうが辛いに決まっているでしょう!」
「あの時の私はオルドリン伯爵のためだと思って耐えられていました! だけど、無駄だった! この気持ちがあなたにわかるわけがありません!」
何のためにあんな辛い思いを我慢して、学園に行っていたんだろう。
アキーム様のためだけに頑張っていたのに――
アキーム様のことがなければ、家を追い出されても良かった。
あんな辛い環境にいるくらいなら、どこかで野垂れ死んだほうが良いと思った。
それでも、踏みとどまれたのは――
「あの人の傍にいたいと思ったからなのに」
涙があふれてきて止まらなかった。
慌てて立ち上がったゼノンを、リファルド様が制する。
「まだ、サブリナ嬢は終わってない。そうだろ」
リファルド様が挑戦的な笑みを浮かべて尋ねてきたので、大きく首を縦に振る。
そうよ。
これくらいで終わらせられない。
「……ありがとうございます」
涙をハンカチで拭ったあと、ラファイ伯爵令嬢に告げる。
「今の涙で完全に吹っ切れました。オルドリン伯爵を許すこともないし、ラファイ伯爵令嬢、あなたのことも絶対に許しません。過去のことは、あなたのお父様に報告させていただきます」
「やめて!」
ラファイ伯爵令嬢は涙目で訴えてくる。
「オルドリン伯爵との離婚理由はどんなものかは知らないけど、あなた、今までは幸せだったのでしょう? それで良いじゃないの! わたしは結婚の夢を絶たれたのよ!?」
「あなたの婚約が駄目になったことは、私のせいではありませんし、私はあなたとオルドリン伯爵が浮気していたことを責めているんじゃありません。あなたが過去にしてきたことを問題にしているんです。それは、あなたのお父様も同じなのでしょう?」
「そ、それは……」
ラファイ伯爵令嬢は地面に座り込んで頭を下げる。
「申し訳ございませんでした。謝りますからお許しください」
「……これからする質問に正直に話をしていただけるなら考えます」
「なんでしょうか!?」
ラファイ伯爵令嬢は頭を上げて、明るい表情を見せた。
喜んでも無駄なのに。
そんな言葉を口に出さないように堪えて、質問をする。
「どうしてあなたは、私に嫌なことをしたんですか。オルドリン伯爵に頼まれたからですか?」
「い、いいえ、その、たまたま、目の前にあなたがいたからで」
ラファイ伯爵令嬢は笑みを消して目を泳がせながら答える。
たまたま、目の前にいたからですって?
「では、他の人に同じことをしなかったのはなぜですか? 目の前には他にも人がたくさんいましたよね」
「……苛立たしく思わなかったからです。その、あの時のわたしはストレスが溜まっていたんです!」
「私のせいでストレスが溜まっていたとでも言うのですか?」
「いいえ。他のことでです! だから、誰かを傷つけることでストレス発散をしようとしていたんです!」
堂々と言っているけれど、言っていることは普通の人なら考えないことだ。
たとえ、考えたとしても実行には移さないし、八つ当たりしてしまったとしても、すぐに後悔するものだ。
ラファイ伯爵令嬢のように開き直ったりなんかしない。
「あなたの考えはわかりました」
「では、許していただけるんですね!?」
「そんなわけがないでしょう。やはり、過去の話はラファイ伯爵にお話をしなければならない内容だと思います」
「や、やめて、そんな! わたしのお父様がどんな人かわかって言っているの!?」
「ラファイ伯爵がどんな人であろうとも、あなたの過去の話をするつもりです」
「やめてって言っているじゃないですか! そんなことになったら、わたしはもう社交場にも呼ばれなくなってしまうわ!」
「呼ばれなくなるのはオルドリン伯爵も同じでしょう。二人仲良く暮らしてはどうでしょうか」
そうだわ。
住む家がないのなら、それこそ、アキーム様と静養地で大人しく暮らしていれば良いのよ。
「嫌よ! 私には華やかな世界が似合うの! どうしてよ! そんなに嫌ならもっと早くに言ってくれれば良かったじゃないの!」
「嫌だと言えば嫌がらせをエスカレートさせたのはあなたじゃないですか。そんなことまで忘れているようでしたら、反省する気はないとみなします。お帰りください」
「謝ります! 謝りますから許してください!」
私の所へ駆け寄ろうとしたラファイ伯爵令嬢を、周りを取り囲んでいた兵士が止めた。
「サブリナさん、ごめんなさい! あなたがそこまで苦しんでいるとは思わなかったの! 正直に話すわ! 実は、あなたを攻撃しろと言ったのはアキーム様なのよ!」
「だからって言いなりになる必要はないでしょう」
「あの時のわたしは子供だったの!」
「なら、その責任はご両親に取ってもらいましょう」
「そんなっ!」
兵士に押さえつけられたラファイ伯爵令嬢は、悲鳴のような甲高い声を上げた。
彼女にはアキーム様と一緒に苦しんでもらう。
人を傷つけるという行為がどれだけ駄目なものなのか。
安易な気持ちで浮気をしたのだから、そんなことをしたらどうなるのか。
ちゃんと知ってもらわなければならない。
というか、大人なんだから知っていて当たり前なんだけどね。
「さようなら、ラファイ伯爵令嬢。もう二度と私に近づかないでください」
「そんな! あなたが許してくれないと、わたしは家に帰れないのに!」
「あなたは自分のことしか考えていないのですね」
「……少しいいか?」
リファルド様が手を挙げたので頷くと、彼は口元に笑みを浮かべて話す。
「もし、サブリナ嬢に近づけば、ワイズ公爵家が相手になる。言っておくが、こちらはそっちに馬鹿な真似をされて腹を立ててるんだ。次も許してもらえると思うなよ」
「……う、あ……っ」
ラファイ伯爵令嬢の目から大粒の涙が溢れ出した。
その後、ラファイ伯爵令嬢は兵士によって門の外に追い出された。
少しは反省してくれるといいけど、彼女のあの様子だとどうなるかはわからない。
姿が見えなくなったところで、メイドがお茶を淹れ直してくれた。
甘い花の匂いがふわりと香る温かなお茶を飲むと、心が穏やかになった気がした。
「落ち着いたか」
リファルド様に尋ねられて、カップをソーサーに戻してから頷く。
「はい。興奮してしまって申し訳ございませんでした」
「気にするな。言い返せずに泣いているだけよりも俺は良いと思うしな」
「それはリファルドが公爵令息だから言えることなんだよ。普通の貴族はそういうの無理だって」
「お前は言いたいことを言っているだろ」
呆れた顔をしているリファルド様にゼノンが笑う。
「僕の場合は何かあれば君に頼れるから」
「人を何だと思ってるんだ。俺はお前なんぞ助けないからな」
「そんなこと言って、いつだってフォローしてくれるじゃん。照れるなって」
「鼻を潰されたくなかったら黙れ」
「ああ、こわ」
おどけるゼノンを一睨みしたあと、リファルド様は私に目を向ける。
「本題に入るが、慰謝料の件はどうする? もう関わりたくないだろうから、間に俺が入ってもいい」
「リファルド様にご迷惑をおかけするわけにはいきませんし、慰謝料は諦めようと思います。あの様子ですと、ラファイ伯爵令嬢からお金が取れるとは思えません」
「オルドリン家から取ろうと思ったら、元夫と関わらないといけなくなるから、それも嫌だということだな」
「そうです。それに、二人はこれから一緒に住むのではないでしょうか」
ラファイ伯爵令嬢は助けを求めてアキーム様の所に行くんじゃないかしら。
だって、彼女には他に頼れる人がいないはずだから。
街の人たちはワイズ公爵領の人だから、私に同情してくれる人が多いのだろうと思っていた。
でも、ゼノンが言うには、あの当時、見ないふりをしていた人たちも大人になって、考え方が変わった人が多いのだと言う。
私を馬鹿にしている人もまだいるのは確かだけど、多くの人はわざと人を嫌な気持ちにさせることをするという行為は許されるものではないし、そのようなことをする人と付き合いたくないという本音を口に出せるようになっているそうだ。
ラファイ伯爵令嬢がワイズ公爵家を敵にまわしたとわかったら、彼女と仲が良かった人達も手のひらを返すんでしょう。
それはそれでどうかと思うけどね。
友人なら悪いことは悪いと言うべきだし、何も言わずに見捨てるのは違うと思うわ。
……友人が一人もいない私が言うのもなんだけど。
「君に連絡を取るには、ゼノンの実家であるジーリン家に連絡を入れれば良いんだな?」
「迷惑をかけると思うので早い内に出ていくつもりです。その時には、こちらから連絡を入れさせていただきます」
「出ていくって言っても当てなんてないんだろ」
ゼノンが眉根を寄せるので苦笑して答える。
「あなたの家にいたら、両親が来るに決まってるもの」
「クズ叔父なんて気にしなくていいって」
「そのクズ叔父以外にも彼女には気がかりがあるだろう」
「ああ、オルドリン伯爵か」
ゼノンが眉根を寄せて舌打ちをした。
「……そうなの。あの人にしてみれば、私は所有物みたいなもののようだから」
私がどう生きるかは、アキーム様次第というようなことを言っていた。
そんなの絶対に嫌だ。
私の人生はわたしのものだ。
自分で望むならまだしも、自分が納得していないのに彼の望むように生きたくなんかない。
「君の人生は君のものだろう。誰かに助言を受けるのは良いが、最終的な判断は君がすべきだ。誰かに決められたものなんて納得できるかどうかわからない」
私が考えていたことと同じことを、リファルド様が言ったので驚いた。
この考えがやっぱり普通の考え方なのね。
「……そうですよね。それは私も思います。ですから、私は私の生きたいように生きようと思います」
「それでいいと思う」
満足したように頷くと、リファルド様は今度はゼノンに話しかける。
「お前はどうするんだ」
「サブリナを僕の家まで送り届けたら、また向こうに戻るよ。仕事が忙しくてさ」
「ゼノン、迷惑をかけてごめんなさい。それから、本当にありがとう」
「どういたしまして。僕は強くなったサブリナが見れて満足だから気にしなくていいよ」
ゼノンは満面の笑みを浮かべて言った。
私が頑なじゃなければ、もっと早くにアキーム様の本性を知ることができたのかもしれない。
恋は盲目と言うけれど、本当にそうだったわ。
さようなら、旦那様。
そして、改めてさようなら、オリンドル伯爵。
私はあなたがいなくても、必ず幸せになってみせます。
あなたは、ラファイ伯爵令嬢、または他の浮気相手の方と、どうぞお幸せに。
少しは反省してくれるといいけど、彼女のあの様子だとどうなるかはわからない。
姿が見えなくなったところで、メイドがお茶を淹れ直してくれた。
甘い花の匂いがふわりと香る温かなお茶を飲むと、心が穏やかになった気がした。
「落ち着いたか」
リファルド様に尋ねられて、カップをソーサーに戻してから頷く。
「はい。興奮してしまって申し訳ございませんでした」
「気にするな。言い返せずに泣いているだけよりも俺は良いと思うしな」
「それはリファルドが公爵令息だから言えることなんだよ。普通の貴族はそういうの無理だって」
「お前は言いたいことを言っているだろ」
呆れた顔をしているリファルド様にゼノンが笑う。
「僕の場合は何かあれば君に頼れるから」
「人を何だと思ってるんだ。俺はお前なんぞ助けないからな」
「そんなこと言って、いつだってフォローしてくれるじゃん。照れるなって」
「鼻を潰されたくなかったら黙れ」
「ああ、こわ」
おどけるゼノンを一睨みしたあと、リファルド様は私に目を向ける。
「本題に入るが、慰謝料の件はどうする? もう関わりたくないだろうから、間に俺が入ってもいい」
「リファルド様にご迷惑をおかけするわけにはいきませんし、慰謝料は諦めようと思います。あの様子ですと、ラファイ伯爵令嬢からお金が取れるとは思えません」
「オルドリン家から取ろうと思ったら、元夫と関わらないといけなくなるから、それも嫌だということだな」
「そうです。それに、二人はこれから一緒に住むのではないでしょうか」
ラファイ伯爵令嬢は助けを求めてアキーム様の所に行くんじゃないかしら。
だって、彼女には他に頼れる人がいないはずだから。
街の人たちはワイズ公爵領の人だから、私に同情してくれる人が多いのだろうと思っていた。
でも、ゼノンが言うには、あの当時、見ないふりをしていた人たちも大人になって、考え方が変わった人が多いのだと言う。
私を馬鹿にしている人もまだいるのは確かだけど、多くの人はわざと人を嫌な気持ちにさせることをするという行為は許されるものではないし、そのようなことをする人と付き合いたくないという本音を口に出せるようになっているそうだ。
ラファイ伯爵令嬢がワイズ公爵家を敵にまわしたとわかったら、彼女と仲が良かった人達も手のひらを返すんでしょう。
それはそれでどうかと思うけどね。
友人なら悪いことは悪いと言うべきだし、何も言わずに見捨てるのは違うと思うわ。
……友人が一人もいない私が言うのもなんだけど。
「君に連絡を取るには、ゼノンの実家であるジーリン家に連絡を入れれば良いんだな?」
「迷惑をかけると思うので早い内に出ていくつもりです。その時には、こちらから連絡を入れさせていただきます」
「出ていくって言っても当てなんてないんだろ」
ゼノンが眉根を寄せるので苦笑して答える。
「あなたの家にいたら、両親が来るに決まってるもの」
「クズ叔父なんて気にしなくていいって」
「そのクズ叔父以外にも彼女には気がかりがあるだろう」
「ああ、オルドリン伯爵か」
ゼノンが眉根を寄せて舌打ちをした。
「……そうなの。あの人にしてみれば、私は所有物みたいなもののようだから」
私がどう生きるかは、アキーム様次第というようなことを言っていた。
そんなの絶対に嫌だ。
私の人生はわたしのものだ。
自分で望むならまだしも、自分が納得していないのに彼の望むように生きたくなんかない。
「君の人生は君のものだろう。誰かに助言を受けるのは良いが、最終的な判断は君がすべきだ。誰かに決められたものなんて納得できるかどうかわからない」
私が考えていたことと同じことを、リファルド様が言ったので驚いた。
この考えがやっぱり普通の考え方なのね。
「……そうですよね。それは私も思います。ですから、私は私の生きたいように生きようと思います」
「それでいいと思う」
満足したように頷くと、リファルド様は今度はゼノンに話しかける。
「お前はどうするんだ」
「サブリナを僕の家まで送り届けたら、また向こうに戻るよ。仕事が忙しくてさ」
「ゼノン、迷惑をかけてごめんなさい。それから、本当にありがとう」
「どういたしまして。僕は強くなったサブリナが見れて満足だから気にしなくていいよ」
ゼノンは満面の笑みを浮かべて言った。
私が頑なじゃなければ、もっと早くにアキーム様の本性を知ることができたのかもしれない。
恋は盲目と言うけれど、本当にそうだったわ。
さようなら、旦那様。
そして、改めてさようなら、オリンドル伯爵。
私はあなたがいなくても、必ず幸せになってみせます。
あなたは、ラファイ伯爵令嬢、または他の浮気相手の方と、どうぞお幸せに。
◇◆◇◆◇
(アキーム(元夫視点))
オルドリン伯爵邸を出た次の日に、僕は貸別荘に着いた。
僕はその土地ごとで、期間限定のメイドを雇っている。
今回もこの静養地でメイドを探すことにした。
給料は良いので、いつもならばすぐに見つかる。
それなのに、今回は面接に来る人がいなかった。
「本当についてないな」
ため息を吐くと、いつも一緒に旅をしている御者が話しかけてきた。
「旦那様、サブリナ様との離婚が原因で人が来ないのではないでしょうか」
「……なんだって? サブリナとの離婚というのはどういうことなんだ!?」
僕はサブリナとの離婚を認めていないのに、どうして離婚したことになってるんだよ!?
僕は何も聞いてないぞ!?
「旦那様が離婚されたことは、小さなものではありましたが新聞の記事になっておりました」
「そ、そんな……!」
その時、誰かが訪ねてきたのか、玄関の呼び鈴が鳴った。
とにかく、面接だ。
身の回りの世話をしてくれる人がほしい。
落ち着いてから状況を整理しよう。
そう思って自ら出迎えると、ポーチに立っていたのは、僕の不幸の原因を作った女性、ベル・ラファイが化粧の落ちた醜い顔をして立っていた。
「ど、どうして君が……」
僕は幽霊でも見るような恐怖を感じながら、彼女を見つめた。
(アキーム(元夫視点))
オルドリン伯爵邸を出た次の日に、僕は貸別荘に着いた。
僕はその土地ごとで、期間限定のメイドを雇っている。
今回もこの静養地でメイドを探すことにした。
給料は良いので、いつもならばすぐに見つかる。
それなのに、今回は面接に来る人がいなかった。
「本当についてないな」
ため息を吐くと、いつも一緒に旅をしている御者が話しかけてきた。
「旦那様、サブリナ様との離婚が原因で人が来ないのではないでしょうか」
「……なんだって? サブリナとの離婚というのはどういうことなんだ!?」
僕はサブリナとの離婚を認めていないのに、どうして離婚したことになってるんだよ!?
僕は何も聞いてないぞ!?
「旦那様が離婚されたことは、小さなものではありましたが新聞の記事になっておりました」
「そ、そんな……!」
その時、誰かが訪ねてきたのか、玄関の呼び鈴が鳴った。
とにかく、面接だ。
身の回りの世話をしてくれる人がほしい。
落ち着いてから状況を整理しよう。
そう思って自ら出迎えると、ポーチに立っていたのは、僕の不幸の原因を作った女性、ベル・ラファイが化粧の落ちた醜い顔をして立っていた。
「ど、どうして君が……」
僕は幽霊でも見るような恐怖を感じながら、彼女を見つめた。
伯父様の家に来てから、十日が経った。
この家には昔から何度か訪れてはいたけど、この屋敷に長く滞在したことはなかった。
お母様は知らない人に会うことが苦手だったし、お父様は伯父様の前で私に辛く当たることができない。
だから、招待されてもすぐに帰ることが多かった。
両親は本当は来たくもなかったみたいだけど、断る理由もないし、断り続けても怪しまれると思ったみたいだ。
ここでの暮らしは慣れない環境で戸惑うことも多い。
でも、困ったら誰かが助けてくれるので不安な気持ちになることはなかった。
辛かった時の気持ちを知っているから、人の優しさを知って、自分も優しくなれるのだということを実感した。
伯父様達は今まで頑張ってきたのだから、ここではゆっくりすれば良いと言ってくれる。
でも、お世話になる以上は何かせずにはいられないし、出ていくためにはお金が必要だと話すと、屋敷内での雑用を頼まれた。
頼まれる雑用もそう大変なものでもないし、衣食住も保証されて、お給料までもらえるのだから恵まれた環境だと言える。
今日は書斎に置かれていた古い新聞を整理する作業を任されていたので、黙々と作業を進めていると、メイドがやって来た。
「サブリナ様、ワイズ公爵家からお手紙が届いております」
「ありがとう」
作業の手を止めて、メイドから手紙を受け取る。
差出人を確認するとリファルド様からだった。
言葉遣いや態度は俺様といった感じなのに、文字はとても繊細で綺麗だった。
……というか、手紙を私みたいに自分で書いたりしないわよね。
きっと、誰かに代筆を頼んでるに決まっている。
どうでも良いことを考えながら、封が切られた封筒の中から手紙を取り出した。
そこには、ラファイ伯爵令嬢のことだけでなく、アキーム様や私の両親の動きが詳しく書かれていた。
両親は近い内に私に会いに来る予定を立てているらしい。
これは、伯父様からも話は聞いていた。
伯父様は来るなと言ってくれているけど、お父様のことだもの。
勝手にやって来て、私に会わせろとうるさく言ってくる可能性が高い。
今までは、私が悪くなくても、怒られれば言い返さずに謝るだけだった。
だけど、今の私は違うわ。
自分自身が悪かったと思わない限り、絶対に謝らない。
そう心に決めて、数枚ある報告書のような手紙を読み進めていくと、アキーム様が私との離婚を認めないと言っているという文章を読んでしまった。
どうして、そんなことを言うのよ。
アキーム様は私のことを自分のおもちゃか何かだと勘違いしているんじゃないだろうか。
私はアキーム様のおもちゃなんかじゃない。
離婚に異議を申し立てないようにお願いしているんだから、エレファーナ様にはしっかり管理してもらわないといけないわ。
もし、放置しているだけなら、こっちにも考えがある。
黒い感情が渦巻いてきたことに気がついて、慌ててアキーム様のことを考えるのはやめた。
手紙の最後には、伯父様にも、同じことを連絡をすると書かれていた。
リファルド様は、一見、近づきにくい人に見えるけど、根は優しい人なのかもしれない。
曲がったことが嫌いなのかもしれないわね。
だから、私のことも見捨てられないのかも。
……いや、ゼノンのせいかしらね。
でも、それだけで動いてくれる人でもないと思っている。
ラファイ伯爵令嬢はリファルド様に不満はなかった。
なのに、浮気をした。
たとえ、リファルド様の態度が冷たかったとしても、それは浮気をしても良い理由にはならない。
リファルド様がラファイ伯爵令嬢に怒って、婚約を破棄する気持ちはわかるわ。
公爵家のメンツというものもあるしね。
そういえば、どうして、リファルド様の婚約者はラファイ伯爵令嬢だったのかしら。
もっと、爵位が上の女性でも良かった気がする。
ラファイ伯爵家って、そんなにも権力がある家なのかしら。
あとで詳しく話を聞いてみようと考えてから、止めていた作業を再開した。
******
「オルドリン伯爵が君に会いたいと手紙を送ってきているんだがどうする?」
昼食時に伯父様から尋ねられて驚いた。
手紙を送らせるだなんて、本当にエレファーナ様は役に立たないわ。
アキーム様が勝手に送っているのかも知れないけど、それって結局は、息子を止められていないじゃないの。
「……何と書いてきているんですか?」
「自分は離婚を認めていない。サブリナのことを本当に大事にするから、離婚が決まってしまったのなら再婚したいというような内容かな」
「再婚ですって?」
「ああ。信じられないよな。自分の知らない所で話が進められたにしたって、やり直せると思える根性がすごい」
「お断りの手紙を出してもらえますか」
「もちろんだよ。僕宛の手紙だから僕が返す。目先の問題として気になるのは、愚弟の件だ」
「……お父様はしつこい性格ですからね」
中肉中背で温和な雰囲気を醸し出す、紳士の伯父様はため息を吐いてから答える。
「3日後にはこちらに着くそうだ。来るなと言っても無駄だろうね。来てほしくないなら条件をのめと言ってきている」
「どんな条件でしょうか」
「オルドリン伯爵との再婚だ」
「お父様はどうしても私を不幸にさせたいみたいですね」
「本当に親かと疑ってしまうよ。来るとわかっているんだから、こちらも対策はしておく。それから、ゼノンがこのことをリファルド様に話すと言っていたが、それはいいかな?」
「リファルド様のご迷惑にならなければ結構です」
「わかった。そう伝えておくよ」
伯父様達に早速、迷惑をかけてしまうことが本当に申し訳なかった。
大体、お父様もアキーム様も再婚だなんて、どうしてそんな信じられない話を考えることができるのかしら。
絶対にお断りだわ!
この家には昔から何度か訪れてはいたけど、この屋敷に長く滞在したことはなかった。
お母様は知らない人に会うことが苦手だったし、お父様は伯父様の前で私に辛く当たることができない。
だから、招待されてもすぐに帰ることが多かった。
両親は本当は来たくもなかったみたいだけど、断る理由もないし、断り続けても怪しまれると思ったみたいだ。
ここでの暮らしは慣れない環境で戸惑うことも多い。
でも、困ったら誰かが助けてくれるので不安な気持ちになることはなかった。
辛かった時の気持ちを知っているから、人の優しさを知って、自分も優しくなれるのだということを実感した。
伯父様達は今まで頑張ってきたのだから、ここではゆっくりすれば良いと言ってくれる。
でも、お世話になる以上は何かせずにはいられないし、出ていくためにはお金が必要だと話すと、屋敷内での雑用を頼まれた。
頼まれる雑用もそう大変なものでもないし、衣食住も保証されて、お給料までもらえるのだから恵まれた環境だと言える。
今日は書斎に置かれていた古い新聞を整理する作業を任されていたので、黙々と作業を進めていると、メイドがやって来た。
「サブリナ様、ワイズ公爵家からお手紙が届いております」
「ありがとう」
作業の手を止めて、メイドから手紙を受け取る。
差出人を確認するとリファルド様からだった。
言葉遣いや態度は俺様といった感じなのに、文字はとても繊細で綺麗だった。
……というか、手紙を私みたいに自分で書いたりしないわよね。
きっと、誰かに代筆を頼んでるに決まっている。
どうでも良いことを考えながら、封が切られた封筒の中から手紙を取り出した。
そこには、ラファイ伯爵令嬢のことだけでなく、アキーム様や私の両親の動きが詳しく書かれていた。
両親は近い内に私に会いに来る予定を立てているらしい。
これは、伯父様からも話は聞いていた。
伯父様は来るなと言ってくれているけど、お父様のことだもの。
勝手にやって来て、私に会わせろとうるさく言ってくる可能性が高い。
今までは、私が悪くなくても、怒られれば言い返さずに謝るだけだった。
だけど、今の私は違うわ。
自分自身が悪かったと思わない限り、絶対に謝らない。
そう心に決めて、数枚ある報告書のような手紙を読み進めていくと、アキーム様が私との離婚を認めないと言っているという文章を読んでしまった。
どうして、そんなことを言うのよ。
アキーム様は私のことを自分のおもちゃか何かだと勘違いしているんじゃないだろうか。
私はアキーム様のおもちゃなんかじゃない。
離婚に異議を申し立てないようにお願いしているんだから、エレファーナ様にはしっかり管理してもらわないといけないわ。
もし、放置しているだけなら、こっちにも考えがある。
黒い感情が渦巻いてきたことに気がついて、慌ててアキーム様のことを考えるのはやめた。
手紙の最後には、伯父様にも、同じことを連絡をすると書かれていた。
リファルド様は、一見、近づきにくい人に見えるけど、根は優しい人なのかもしれない。
曲がったことが嫌いなのかもしれないわね。
だから、私のことも見捨てられないのかも。
……いや、ゼノンのせいかしらね。
でも、それだけで動いてくれる人でもないと思っている。
ラファイ伯爵令嬢はリファルド様に不満はなかった。
なのに、浮気をした。
たとえ、リファルド様の態度が冷たかったとしても、それは浮気をしても良い理由にはならない。
リファルド様がラファイ伯爵令嬢に怒って、婚約を破棄する気持ちはわかるわ。
公爵家のメンツというものもあるしね。
そういえば、どうして、リファルド様の婚約者はラファイ伯爵令嬢だったのかしら。
もっと、爵位が上の女性でも良かった気がする。
ラファイ伯爵家って、そんなにも権力がある家なのかしら。
あとで詳しく話を聞いてみようと考えてから、止めていた作業を再開した。
******
「オルドリン伯爵が君に会いたいと手紙を送ってきているんだがどうする?」
昼食時に伯父様から尋ねられて驚いた。
手紙を送らせるだなんて、本当にエレファーナ様は役に立たないわ。
アキーム様が勝手に送っているのかも知れないけど、それって結局は、息子を止められていないじゃないの。
「……何と書いてきているんですか?」
「自分は離婚を認めていない。サブリナのことを本当に大事にするから、離婚が決まってしまったのなら再婚したいというような内容かな」
「再婚ですって?」
「ああ。信じられないよな。自分の知らない所で話が進められたにしたって、やり直せると思える根性がすごい」
「お断りの手紙を出してもらえますか」
「もちろんだよ。僕宛の手紙だから僕が返す。目先の問題として気になるのは、愚弟の件だ」
「……お父様はしつこい性格ですからね」
中肉中背で温和な雰囲気を醸し出す、紳士の伯父様はため息を吐いてから答える。
「3日後にはこちらに着くそうだ。来るなと言っても無駄だろうね。来てほしくないなら条件をのめと言ってきている」
「どんな条件でしょうか」
「オルドリン伯爵との再婚だ」
「お父様はどうしても私を不幸にさせたいみたいですね」
「本当に親かと疑ってしまうよ。来るとわかっているんだから、こちらも対策はしておく。それから、ゼノンがこのことをリファルド様に話すと言っていたが、それはいいかな?」
「リファルド様のご迷惑にならなければ結構です」
「わかった。そう伝えておくよ」
伯父様達に早速、迷惑をかけてしまうことが本当に申し訳なかった。
大体、お父様もアキーム様も再婚だなんて、どうしてそんな信じられない話を考えることができるのかしら。
絶対にお断りだわ!
3日後、両親がジーリン伯爵家にやって来た。
伯父様達と一緒にエントランスホールで出迎えた私に、お父様は無言で近寄ってくると、私に向かって手を伸ばしてきた。
でも、隣にいた伯父様が睨みをきかしてくれたので、行き場をなくしたかのように手は下ろされる。
「何をしようとしていたのかは知らないが、あれだけ娘に会いたいと言っていたのに不満そうだな」
「兄さん、あまり、サブリナを甘やかさないでくださいよ。離婚なんて恥ですよ、恥」
一般的な体型の伯父様とは違い、お父様の体格は大柄で筋骨隆々といった感じだ。
同じような体型をしている騎士隊長を見たことがあるけど、その人は爽やかに見えたのに、お父様だとむさくるしく感じてしまうのはなぜなのかしら。
表向きは護身だとか言いながら、人を殴るために格闘技を習っていたというのだから、考えが理解できない。
子供の頃の私には死なない程度に加減をしていたのだから恐ろしい。
伯父様が厳しい表情で口を開く。
「サブリナと話をするのは良いが、二人きりでは駄目だ」
「……兄さんが横にいるんですか」
「いや、ゼノンに任せるつもりだ」
伯父様がそう言うと、後ろに控えていたゼノンが笑顔で手を振る。
「久しぶりですね、クソ叔父……じゃなくて、叔父上」
「おい、聞こえたからな。まったく、兄さんはどんな躾をしてるんだか」
お父様が叔父様を睨む。
「お前に言われたくないよ。躾と言うよりも、お前の場合は虐待だからな」
「そんなことはありませんよ。サブリナだってそう思わないだろう?」
お父様は憎たらしい笑みを浮かべた。
私が頷くと思っているのね。
残念でした。
今の私はあなたのことなんて怖くない。
「……いいえ」
「え? なんだって? 聞こえない! お前はいつだって声が小さい」
「いいえと言ったんです! 前々から思っていたのですが言えなかったことを言わせていただきます。あなたは最低な父親です!」
「なんだと?」
話を遮った上に、口にした言葉が予想外だったのか、お父様は訝しげな様子で私を見つめてきた。
「子供の頃に私にしたこと忘れてませんから。捨てようとしたり、暴力をふるってましたよね」
「おい。馬鹿なことを言うな!」
お父様が声を荒らげた時、お母様が叫ぶ。
「バンディ様! やめてください!」
「うるさいな! お前は黙っていろ!」
お父様はお母様の小柄で細い体を突き飛ばすと、私のブラウスの襟首を掴む。
「誰のおかげで嫁にいけたと思っているんだ」
「最低な旦那様のところに嫁がせていただき、ありがとうございました。勉強になりました」
「クソ叔父上、立ち話もなんですから、応接にご案内しましょう」
ゼノンがお父様の腕を掴んで言うと、お父様は不満そうにしながらも私から離れて頷く。
「まったくむかつく甥っ子だ」
「ありがとうございまーす。褒め言葉入りましたぁ!」
ゼノンは馬鹿にした調子で言うと、上機嫌で歩き出す。
そんな彼を追いかけて小声で話しかける。
「助けてくれたことには感謝するけど、ちょっとやりすぎよ」
「堪えてないから大丈夫だよ。これからが楽しみだな。サブリナの予想通りに《《お願いして》》くるだろうか」
「……私はそう思うわ」
掴まれた部分を直しながら頷く。
お父様のことが怖かった分、どうすれば機嫌を損ねずに済むか知りたくて、気付かれないように観察していた時期がある。
その時にわかったのは、お父様は権力者に弱いということだ。
応接室の前に着くと、お父様はゼノンに話しかける。
「まずは家族だけで話をさせてくれ」
「第三者がいないと危険ですから無理です」
「じゃあ、ゼノンでは駄目だ。他の奴にしろ」
予想していたような反応をしてきたので、私とゼノンは顔を見合わせる。
その様子が困っているように見えたのか、お父様は笑みを隠さない。
「ゼノン、私は他の人でもかまわないわ」
「……わかった」
ゼノンは神妙な面持ちで頷くと、お父様に話しかける。
「僕や両親以外なら良いようなので、先に中で待っている人に任せることにします」
「……中で待っている?」
「ええ。叔父上が来るのを待っていた人がいるんです」
「オレを?」
「お父様、とにかく中に入りましょう」
下手に怪しまれても困るので、強引にお父様を部屋の中に入れた。
お母様は何も言わずに無言で一緒に入ってくる。
談話室には、木のローテーブルとワインレッド色の三人用が二つ、真正面に一人用のソファが一つだけある。
待っているはずの人物は窓際にいて、私達に背を向けていた。
わざとそこに立っているのね。
こんなことを言うのもなんだけど、ゼノンと仲が良い理由がわかるわ。
「気にせずに話をしてくれ」
窓際に立っている人物は裏声で言うだけで、こちらを振り向こうとはしない。
余計に気になるけど、ここは私が何とかすれば良いわよね。
そう思った時、お父様が私の胸ぐらを掴んで叫ぶ。
「この生意気な女め! 勝手に離婚なんてしやがって! クズは大人しくあの腐った家にいればいいんだよ!」
「嫌です! 何があってもオルドリン伯爵家には戻りませんし、実家にも戻りません!」
「お前が嫁げたのは誰のおかげだと思ってるんだ!」
「サブリナ、お父様の言うことをきかないと駄目よ」
小柄で猫背のお母様は体を震わせて続ける。
「お父様はいつだって、サブリナの幸せを考えてるんだからっ! あなたはお父様の言うことを聞いていれば幸せになれるの!」
「私の幸せ? そうじゃないでしょう。私の幸せはあなた達やオリンドル伯爵家と二度と関わらないことです」
「まったく、生意気な口を! 殴られないとわからないようだなぁ!」
「それはこっちのセリフだ。馬鹿者が」
「……は?」
お父様は振り上げた腕をおろして、言葉を発した人物に罵声を浴びせる。
「なんだ、文句があんのか、この野郎!」
「ある」
彼はこちらに振り返って続ける。
「俺に喧嘩を売るとは良い度胸だ」
「な、な、な!」
相手がリファルド様だとわかった瞬間、お父様の顔色が一気に悪くなった。
伯父様達と一緒にエントランスホールで出迎えた私に、お父様は無言で近寄ってくると、私に向かって手を伸ばしてきた。
でも、隣にいた伯父様が睨みをきかしてくれたので、行き場をなくしたかのように手は下ろされる。
「何をしようとしていたのかは知らないが、あれだけ娘に会いたいと言っていたのに不満そうだな」
「兄さん、あまり、サブリナを甘やかさないでくださいよ。離婚なんて恥ですよ、恥」
一般的な体型の伯父様とは違い、お父様の体格は大柄で筋骨隆々といった感じだ。
同じような体型をしている騎士隊長を見たことがあるけど、その人は爽やかに見えたのに、お父様だとむさくるしく感じてしまうのはなぜなのかしら。
表向きは護身だとか言いながら、人を殴るために格闘技を習っていたというのだから、考えが理解できない。
子供の頃の私には死なない程度に加減をしていたのだから恐ろしい。
伯父様が厳しい表情で口を開く。
「サブリナと話をするのは良いが、二人きりでは駄目だ」
「……兄さんが横にいるんですか」
「いや、ゼノンに任せるつもりだ」
伯父様がそう言うと、後ろに控えていたゼノンが笑顔で手を振る。
「久しぶりですね、クソ叔父……じゃなくて、叔父上」
「おい、聞こえたからな。まったく、兄さんはどんな躾をしてるんだか」
お父様が叔父様を睨む。
「お前に言われたくないよ。躾と言うよりも、お前の場合は虐待だからな」
「そんなことはありませんよ。サブリナだってそう思わないだろう?」
お父様は憎たらしい笑みを浮かべた。
私が頷くと思っているのね。
残念でした。
今の私はあなたのことなんて怖くない。
「……いいえ」
「え? なんだって? 聞こえない! お前はいつだって声が小さい」
「いいえと言ったんです! 前々から思っていたのですが言えなかったことを言わせていただきます。あなたは最低な父親です!」
「なんだと?」
話を遮った上に、口にした言葉が予想外だったのか、お父様は訝しげな様子で私を見つめてきた。
「子供の頃に私にしたこと忘れてませんから。捨てようとしたり、暴力をふるってましたよね」
「おい。馬鹿なことを言うな!」
お父様が声を荒らげた時、お母様が叫ぶ。
「バンディ様! やめてください!」
「うるさいな! お前は黙っていろ!」
お父様はお母様の小柄で細い体を突き飛ばすと、私のブラウスの襟首を掴む。
「誰のおかげで嫁にいけたと思っているんだ」
「最低な旦那様のところに嫁がせていただき、ありがとうございました。勉強になりました」
「クソ叔父上、立ち話もなんですから、応接にご案内しましょう」
ゼノンがお父様の腕を掴んで言うと、お父様は不満そうにしながらも私から離れて頷く。
「まったくむかつく甥っ子だ」
「ありがとうございまーす。褒め言葉入りましたぁ!」
ゼノンは馬鹿にした調子で言うと、上機嫌で歩き出す。
そんな彼を追いかけて小声で話しかける。
「助けてくれたことには感謝するけど、ちょっとやりすぎよ」
「堪えてないから大丈夫だよ。これからが楽しみだな。サブリナの予想通りに《《お願いして》》くるだろうか」
「……私はそう思うわ」
掴まれた部分を直しながら頷く。
お父様のことが怖かった分、どうすれば機嫌を損ねずに済むか知りたくて、気付かれないように観察していた時期がある。
その時にわかったのは、お父様は権力者に弱いということだ。
応接室の前に着くと、お父様はゼノンに話しかける。
「まずは家族だけで話をさせてくれ」
「第三者がいないと危険ですから無理です」
「じゃあ、ゼノンでは駄目だ。他の奴にしろ」
予想していたような反応をしてきたので、私とゼノンは顔を見合わせる。
その様子が困っているように見えたのか、お父様は笑みを隠さない。
「ゼノン、私は他の人でもかまわないわ」
「……わかった」
ゼノンは神妙な面持ちで頷くと、お父様に話しかける。
「僕や両親以外なら良いようなので、先に中で待っている人に任せることにします」
「……中で待っている?」
「ええ。叔父上が来るのを待っていた人がいるんです」
「オレを?」
「お父様、とにかく中に入りましょう」
下手に怪しまれても困るので、強引にお父様を部屋の中に入れた。
お母様は何も言わずに無言で一緒に入ってくる。
談話室には、木のローテーブルとワインレッド色の三人用が二つ、真正面に一人用のソファが一つだけある。
待っているはずの人物は窓際にいて、私達に背を向けていた。
わざとそこに立っているのね。
こんなことを言うのもなんだけど、ゼノンと仲が良い理由がわかるわ。
「気にせずに話をしてくれ」
窓際に立っている人物は裏声で言うだけで、こちらを振り向こうとはしない。
余計に気になるけど、ここは私が何とかすれば良いわよね。
そう思った時、お父様が私の胸ぐらを掴んで叫ぶ。
「この生意気な女め! 勝手に離婚なんてしやがって! クズは大人しくあの腐った家にいればいいんだよ!」
「嫌です! 何があってもオルドリン伯爵家には戻りませんし、実家にも戻りません!」
「お前が嫁げたのは誰のおかげだと思ってるんだ!」
「サブリナ、お父様の言うことをきかないと駄目よ」
小柄で猫背のお母様は体を震わせて続ける。
「お父様はいつだって、サブリナの幸せを考えてるんだからっ! あなたはお父様の言うことを聞いていれば幸せになれるの!」
「私の幸せ? そうじゃないでしょう。私の幸せはあなた達やオリンドル伯爵家と二度と関わらないことです」
「まったく、生意気な口を! 殴られないとわからないようだなぁ!」
「それはこっちのセリフだ。馬鹿者が」
「……は?」
お父様は振り上げた腕をおろして、言葉を発した人物に罵声を浴びせる。
「なんだ、文句があんのか、この野郎!」
「ある」
彼はこちらに振り返って続ける。
「俺に喧嘩を売るとは良い度胸だ」
「な、な、な!」
相手がリファルド様だとわかった瞬間、お父様の顔色が一気に悪くなった。
お父様は今は田舎に住む子爵だが、元々は伯爵令息だ。
だから、公爵令息の顔を知らないはずがない。
後ろ姿だけで気がつかなかったのは、親しい間柄ではないからだろう。
お父様は私から距離を取って、部屋の奥にいるリファルド様に話しかける。
「ワイズ公爵令息がどうしてここにいるんですか!?」
「ゼノンから胸糞な気持ちになる人物がいると聞いて、どんなものか見に来た」
「ゼ、ゼノンから……? そんな! ゼノンと仲が良いことは存じ上げていましたが、今までは私に興味などなかったではないですか!」
「興味などあるわけないだろう。ゼノンは今までお前のことなど話題にしなかったからな」
「なら、どうして!?」
「知らないのか?」
リファルド様は嘲笑とも取れる笑みを浮かべた。
「知らないとはどういうことでしょうか」
お父様は理由がわからないようなので、私が教えてあげる。
「お父様、アキーム様と浮気していたのは、どなたかご存知ないのですか」
「あっ!」
お父様は焦った顔になると、リファルド様には聞こえないように呟く。
「クソ。どうして、よりにもよって公爵家の婚約者なんかに手を出すんだ、あいつは!」
「何か言ったか?」
リファルド様が尋ねると、お父様は「なんでもありません」と首を横に振った。
なんでもないことはないので、私が代わりに答える。
「よりにもよって公爵家の婚約者なんかに手を出すんだ、あいつは、と言ってました」
「おい! サブリナ!」
「触るな!」
リファルド様が一喝すると、お父様は私に向かって伸ばしていた手を引っ込めた。
応接室の入り口付近に立っている、私達に近寄りながら、リファルド様がお父様に尋ねる。
「何をしようとした」
「な、何を……って、その、娘が余計なことを言うものですから」
「言うものですからの続きはなんだ」
「も、申し訳ございませんでした」
お父様は謝ったあと手をすり合わせながら、リファルド様を見つめる。
「ワイズ公爵令息には大変申し訳ございませんが、家族だけで話をしたいんです。部屋から出ていってもらっても良いでしょうか」
「断る」
「こ、断ると言われましても、ここは私の実家です。いくら公爵令息といえども好き勝手に行動できるものではありません」
「実家だからって好き勝手しても良いわけではないだろう。俺はここの主人から許可を得てるんだ。お前に文句を言われる筋合いはない」
「それはそうかもしれませんが、そこを何とかお願いできませんか」
お父様は両手を合わせて頼み込む。
「しつこいな。断ると言っただろう。長い言葉じゃないんだ。すぐに理解してくれ」
「どうかお願いします。家族だけで話をさせてください」
「お願いいたします」
お父様はカーペットに額をつけて懇願し、お母様も同じようにしゃがんで頭を下げる。
お父様はこうやって低姿勢になって、酷いことをするような人間には思えないと、相手に思わせようとする。
でも、私や弱いものの前では偉そうにするのだ。
このことは、リファルド様に伝えているし、そんな演技に騙される人でもなかった。
「断ると言っているだろ。どうしてそんなに嫌がるんだ」
「プライベートな話だからです!」
「俺が他言するとでも思うのか?」
「そういうわけではございません! ただ、娘が可哀想かと思いまして」
「公爵令息の望みを娘のために断ると言うんだな。まあ、いいだろう」
リファルド様は頷くと、私に尋ねる。
「では、本人に聞こう。サブリナ、君は俺に話を聞かれたくないか」
「いいえ。その逆です。一緒に聞いていただきたいです」
「サブリナ、お前!」
床に膝をつけたまま、お父様が私を睨みつけてきた。
あの目をしたお父様に、何度か殴られたことがあるし、罵声を浴びせられたことは数え切れない。
その恐怖を思い出して、一瞬、怯みそうになった。
でも、お父様よりも強い視線を感じて横を見た。
そうだわ。
力では敵わない。
だから、殺されてしまうのではないかと思って、今までは怖くてしょうがなかった。
今の私にはリファルド様が付いている。
ゼノンじゃないけど、リファルド様の権力を貸してもらうわ。
大きく息を吸ってから、お父様に話しかける。
「リファルド様に聞かれたくないことを言うつもりなんですか」
「そ、そういうわけじゃない! ただ、再婚の話はお前にとっては恥だろうから!」
「今のところ、再婚の予定はありませんので、ご心配なく。そんな気もありません」
冷たく言うと、お父様は悔しそうな顔をした。
私に反抗されるだなんて夢にも思っていなかったんでしょう。
「別れたばかりの娘に、もう再婚相手を考えてるのか。でも、もう話をしなくても良くなったな。彼女にその気はないんだから」
「今回の離婚はオルドリン伯爵の浮気です! ですが、彼はとても反省しています! 許してあげるべきではないでしょうか!」
「お父様、その理屈ですと、何をやっても反省すれば良いになりませんか」
「俺もそう感じた。浮気は罪が軽いとでも言いたいのか」
私とリファルド様が反論すると、お父様は立ち上がって訴える。
「貴族の多くの男性は浮気をしています!」
「ふざけるな。お前の周りに多いだけで、してない奴のほうが多いに決まっているだろ。現に俺だってしてない。お前は浮気してない奴が悪だとでも言いたいのか」
「そ、そういうわけではありません! ですが、その、珍しいことではないですから!」
……というか、その言い方だと、もしかして。
「お父様、もしかして、あなたも浮気しているんですか」
まさか、義母だったエレファーナ様と浮気しているとかじゃないわよね!?
だから、公爵令息の顔を知らないはずがない。
後ろ姿だけで気がつかなかったのは、親しい間柄ではないからだろう。
お父様は私から距離を取って、部屋の奥にいるリファルド様に話しかける。
「ワイズ公爵令息がどうしてここにいるんですか!?」
「ゼノンから胸糞な気持ちになる人物がいると聞いて、どんなものか見に来た」
「ゼ、ゼノンから……? そんな! ゼノンと仲が良いことは存じ上げていましたが、今までは私に興味などなかったではないですか!」
「興味などあるわけないだろう。ゼノンは今までお前のことなど話題にしなかったからな」
「なら、どうして!?」
「知らないのか?」
リファルド様は嘲笑とも取れる笑みを浮かべた。
「知らないとはどういうことでしょうか」
お父様は理由がわからないようなので、私が教えてあげる。
「お父様、アキーム様と浮気していたのは、どなたかご存知ないのですか」
「あっ!」
お父様は焦った顔になると、リファルド様には聞こえないように呟く。
「クソ。どうして、よりにもよって公爵家の婚約者なんかに手を出すんだ、あいつは!」
「何か言ったか?」
リファルド様が尋ねると、お父様は「なんでもありません」と首を横に振った。
なんでもないことはないので、私が代わりに答える。
「よりにもよって公爵家の婚約者なんかに手を出すんだ、あいつは、と言ってました」
「おい! サブリナ!」
「触るな!」
リファルド様が一喝すると、お父様は私に向かって伸ばしていた手を引っ込めた。
応接室の入り口付近に立っている、私達に近寄りながら、リファルド様がお父様に尋ねる。
「何をしようとした」
「な、何を……って、その、娘が余計なことを言うものですから」
「言うものですからの続きはなんだ」
「も、申し訳ございませんでした」
お父様は謝ったあと手をすり合わせながら、リファルド様を見つめる。
「ワイズ公爵令息には大変申し訳ございませんが、家族だけで話をしたいんです。部屋から出ていってもらっても良いでしょうか」
「断る」
「こ、断ると言われましても、ここは私の実家です。いくら公爵令息といえども好き勝手に行動できるものではありません」
「実家だからって好き勝手しても良いわけではないだろう。俺はここの主人から許可を得てるんだ。お前に文句を言われる筋合いはない」
「それはそうかもしれませんが、そこを何とかお願いできませんか」
お父様は両手を合わせて頼み込む。
「しつこいな。断ると言っただろう。長い言葉じゃないんだ。すぐに理解してくれ」
「どうかお願いします。家族だけで話をさせてください」
「お願いいたします」
お父様はカーペットに額をつけて懇願し、お母様も同じようにしゃがんで頭を下げる。
お父様はこうやって低姿勢になって、酷いことをするような人間には思えないと、相手に思わせようとする。
でも、私や弱いものの前では偉そうにするのだ。
このことは、リファルド様に伝えているし、そんな演技に騙される人でもなかった。
「断ると言っているだろ。どうしてそんなに嫌がるんだ」
「プライベートな話だからです!」
「俺が他言するとでも思うのか?」
「そういうわけではございません! ただ、娘が可哀想かと思いまして」
「公爵令息の望みを娘のために断ると言うんだな。まあ、いいだろう」
リファルド様は頷くと、私に尋ねる。
「では、本人に聞こう。サブリナ、君は俺に話を聞かれたくないか」
「いいえ。その逆です。一緒に聞いていただきたいです」
「サブリナ、お前!」
床に膝をつけたまま、お父様が私を睨みつけてきた。
あの目をしたお父様に、何度か殴られたことがあるし、罵声を浴びせられたことは数え切れない。
その恐怖を思い出して、一瞬、怯みそうになった。
でも、お父様よりも強い視線を感じて横を見た。
そうだわ。
力では敵わない。
だから、殺されてしまうのではないかと思って、今までは怖くてしょうがなかった。
今の私にはリファルド様が付いている。
ゼノンじゃないけど、リファルド様の権力を貸してもらうわ。
大きく息を吸ってから、お父様に話しかける。
「リファルド様に聞かれたくないことを言うつもりなんですか」
「そ、そういうわけじゃない! ただ、再婚の話はお前にとっては恥だろうから!」
「今のところ、再婚の予定はありませんので、ご心配なく。そんな気もありません」
冷たく言うと、お父様は悔しそうな顔をした。
私に反抗されるだなんて夢にも思っていなかったんでしょう。
「別れたばかりの娘に、もう再婚相手を考えてるのか。でも、もう話をしなくても良くなったな。彼女にその気はないんだから」
「今回の離婚はオルドリン伯爵の浮気です! ですが、彼はとても反省しています! 許してあげるべきではないでしょうか!」
「お父様、その理屈ですと、何をやっても反省すれば良いになりませんか」
「俺もそう感じた。浮気は罪が軽いとでも言いたいのか」
私とリファルド様が反論すると、お父様は立ち上がって訴える。
「貴族の多くの男性は浮気をしています!」
「ふざけるな。お前の周りに多いだけで、してない奴のほうが多いに決まっているだろ。現に俺だってしてない。お前は浮気してない奴が悪だとでも言いたいのか」
「そ、そういうわけではありません! ですが、その、珍しいことではないですから!」
……というか、その言い方だと、もしかして。
「お父様、もしかして、あなたも浮気しているんですか」
まさか、義母だったエレファーナ様と浮気しているとかじゃないわよね!?
動揺する素振りを見せたお父様は、すぐに平静を装う。
「そんなわけがないだろう! オレは浮気なんてしてない! サブリナ! 今日のお前はどうかしているぞ! 浮気されたショックでおかしくなったんじゃないのか!?」
「おかしいのはお父様のほうです! お父様の場合は今日だけじゃなく昔からですけど!」
「サブリナちゃん! お父様になんてことを言うの!」
お母様は甲高い声を上げて立ち上がると、私の頬に向かって手を振り上げた。
叩かれるという恐怖で身がすくんだ時、腕をリファルド様に引っ張られた。
「きゃっ!」
私が横に避けたから、お母様は勢い余って前のめりになって床に体を打ち付ける。
「悪い男に盲目になっているところは、昔の君と同じじゃないか」
ふうと息を吐くリファルド様に慌てて謝る。
「申し訳ございません!」
「謝らなくても良い。君のせいじゃないだろう。それに、君はちゃんと目を覚ましている」
「あの、では、助けていただき、ありがとうございました」
「気にするな」
頷いたあと、リファルド様は倒れているお母様を見下ろして尋ねる。
「娘が実の父親をおかしいと言うのは良いことではない。だから、叱ろうとしたという行動は理解できる。だが、どうして頬を叩く必要がある? 暴力をふるわなくても、サブリナはあなたの話を聞くことができるだろうに」
「も、申し訳ございません!」
ガタガタと震えながら、お母様は床に額をつけて謝罪する。
「申し訳ございません、申し訳ございません!」
「わかったから何度も謝罪するな。それに謝るならサブリナに謝れ」
「あ、あの、お願いです! サブリナを再婚させてやってください!」
お母様までわけのわからないことを言い出した。
お母様はお父様のどこが良くて結婚したんだろう。
「何を言っているのかわからん。俺は再婚を反対するとは一言も言っていないだろう。大体、再婚するかどうかはサブリナが決めることだ」
リファルド様は呆れた顔をしたまま、私に目を向ける。
「どうでも良いことだが、ちゃん付けされてるのか」
「やめてほしいとお願いしましたが、呼び捨てにできないんだそうです」
「意味がわからん」
「それは私も同意見です。人前では絶対に呼ばないでほしいとお願いしていたんですが無理でしたね」
「ちゃんを付けることが愛称ならまだしも、そうじゃなさそうだしな」
貴族の間では、このような呼び方をすると子供扱いされているということで馬鹿にされてしまう。
だから、家庭内で呼ぶことはあっても、他人の前で口にすることはない。
でも、お母様はそんなことは気にしていなかった。
それで私が馬鹿にされても、お母様は痛みを感じることなどなかったからだ。
「サブリナ!」
二人を無視して話をしていたからか、お父様は私を指差して叫ぶ。
「今日はここで泊まることにしている! だから、あとで改めて話をするからな!」
「わかった」
リファルド様が返事をしたので、お父様は焦った顔をする。
「あの、ワイズ公爵令息に言ったわけでは」
「しばらく、ここで仕事をすることになったんだ。だから、いくらでも話を聞いてやれるぞ」
「ど、どうして、そんな」
リファルド様に笑顔で言われた、お父様の間抜けな顔を見て笑い出しそうになった。
「それから、次にサブリナに手を出したら、俺に手を出したとみなす。暴言も同じだ」
「……え、あ、どうして、どうしてそうなるのですか! 大体、あなたにそんな権利はあるんですか!?」
「俺はまだ公爵ではないが、次期、公爵だと決まっている。それでも気に食わないなら、父に話をして、お前に対する処理は俺に一任させてもらうことにする」
リファルド様は、お母様や私にはお前という言い方はしないのに、お父様には言うのね。
ゼノンのことをそう呼ぶのは親しいからだと思うけど、お父様に対しては明らかに馬鹿にしているといった感じだわ。
しかも、処理と言っていたしね。
お母様は立ち上がると、私に涙目で訴える。
「サブリナちゃん。あなたが幸せになるにはお父様の言うことに従わなければ駄目なの」
「従ったら不幸になりましたが?」
「違うわ。離婚せずに一緒に暮らし続ければ、いつかは幸せになれていたのよ」
「そうとは思えません」
「……ああ、もううるさい! 二人共やめろ! 今日はもういい! また、改めて来ることにするから帰るぞ!」
お父様が促すと、お母様は身を縮こまらせて頷いた。
「次があれば良いな」
リファルド様が笑顔で手を振ると、両親はびくりと身体を震わせて足を止めた。
「どうした。帰らないのか」
「……ええ、ああ、はい。帰ります」
大きい体を縮こまらせて、お父様は逃げるように部屋を出ていく。
お母様も一緒に出ていこうとしたけど、振り返って話しかけてきた。
「サブリナちゃん。あなたの幸せはアキーム様と一緒にいることだからね。昔のあなたもそう言っていたわ。そのことを思い出して。それにアキーム様も幸せに思える瞬間は家に帰った時にあなたが出迎えてくれることだと言っていたわ」
アキーム様のことはもうどうでもいいわ。
「昔の私と今の私は違うんです。私の幸せをお母様が勝手に決めないでください。私はお母様のようになりたくないんです」
「……わたしは幸せなのよ。あなたにはがっかりだわ」
お母様は私にそう言うと、リファルド様には一礼して部屋を出ていった。
「君は悪い人間を引き寄せる力でもあるのかもな。非常に興味深い」
「……うう。そんな嫌なことを言わないでくださいませ。好きで引き寄せているわけではないんです。しかも、相手は両親ですよ」
「両親の話は別として、元夫やその家族などのことを言っている。まあ、それだけ心が綺麗なんだろう。あの親と一緒に暮らして、よく悪の道に染まらずに済んだな」
「お母様に似て臆病なだけだと思います」
「でも、君は踏み出すことができただろう。君の母は夫が正義だと思い込んでいるようだし、重ねた年月を考えると、目を覚ますのは難しいだろうな」
「もしかしたら、きっかけは私と同じように騙されたのかもしれません」
私にとってアキーム様がヒーローだったように、お母様にとって、お父様はヒーローなんでしょうね。
「君は両親が好きか」
「……こんなことは言いたくないですが、いいえ、です」
「ならいい。さて、まずは君の両親に今回のお礼をせねばならないな」
お礼って、絶対に嫌な意味のほうよね。
笑顔のリファルド様を見て、敵にまわしたくないなとつくづく思った。
でも、今の私が過去よりも幸せだと思うことは間違いないと思った。
「そんなわけがないだろう! オレは浮気なんてしてない! サブリナ! 今日のお前はどうかしているぞ! 浮気されたショックでおかしくなったんじゃないのか!?」
「おかしいのはお父様のほうです! お父様の場合は今日だけじゃなく昔からですけど!」
「サブリナちゃん! お父様になんてことを言うの!」
お母様は甲高い声を上げて立ち上がると、私の頬に向かって手を振り上げた。
叩かれるという恐怖で身がすくんだ時、腕をリファルド様に引っ張られた。
「きゃっ!」
私が横に避けたから、お母様は勢い余って前のめりになって床に体を打ち付ける。
「悪い男に盲目になっているところは、昔の君と同じじゃないか」
ふうと息を吐くリファルド様に慌てて謝る。
「申し訳ございません!」
「謝らなくても良い。君のせいじゃないだろう。それに、君はちゃんと目を覚ましている」
「あの、では、助けていただき、ありがとうございました」
「気にするな」
頷いたあと、リファルド様は倒れているお母様を見下ろして尋ねる。
「娘が実の父親をおかしいと言うのは良いことではない。だから、叱ろうとしたという行動は理解できる。だが、どうして頬を叩く必要がある? 暴力をふるわなくても、サブリナはあなたの話を聞くことができるだろうに」
「も、申し訳ございません!」
ガタガタと震えながら、お母様は床に額をつけて謝罪する。
「申し訳ございません、申し訳ございません!」
「わかったから何度も謝罪するな。それに謝るならサブリナに謝れ」
「あ、あの、お願いです! サブリナを再婚させてやってください!」
お母様までわけのわからないことを言い出した。
お母様はお父様のどこが良くて結婚したんだろう。
「何を言っているのかわからん。俺は再婚を反対するとは一言も言っていないだろう。大体、再婚するかどうかはサブリナが決めることだ」
リファルド様は呆れた顔をしたまま、私に目を向ける。
「どうでも良いことだが、ちゃん付けされてるのか」
「やめてほしいとお願いしましたが、呼び捨てにできないんだそうです」
「意味がわからん」
「それは私も同意見です。人前では絶対に呼ばないでほしいとお願いしていたんですが無理でしたね」
「ちゃんを付けることが愛称ならまだしも、そうじゃなさそうだしな」
貴族の間では、このような呼び方をすると子供扱いされているということで馬鹿にされてしまう。
だから、家庭内で呼ぶことはあっても、他人の前で口にすることはない。
でも、お母様はそんなことは気にしていなかった。
それで私が馬鹿にされても、お母様は痛みを感じることなどなかったからだ。
「サブリナ!」
二人を無視して話をしていたからか、お父様は私を指差して叫ぶ。
「今日はここで泊まることにしている! だから、あとで改めて話をするからな!」
「わかった」
リファルド様が返事をしたので、お父様は焦った顔をする。
「あの、ワイズ公爵令息に言ったわけでは」
「しばらく、ここで仕事をすることになったんだ。だから、いくらでも話を聞いてやれるぞ」
「ど、どうして、そんな」
リファルド様に笑顔で言われた、お父様の間抜けな顔を見て笑い出しそうになった。
「それから、次にサブリナに手を出したら、俺に手を出したとみなす。暴言も同じだ」
「……え、あ、どうして、どうしてそうなるのですか! 大体、あなたにそんな権利はあるんですか!?」
「俺はまだ公爵ではないが、次期、公爵だと決まっている。それでも気に食わないなら、父に話をして、お前に対する処理は俺に一任させてもらうことにする」
リファルド様は、お母様や私にはお前という言い方はしないのに、お父様には言うのね。
ゼノンのことをそう呼ぶのは親しいからだと思うけど、お父様に対しては明らかに馬鹿にしているといった感じだわ。
しかも、処理と言っていたしね。
お母様は立ち上がると、私に涙目で訴える。
「サブリナちゃん。あなたが幸せになるにはお父様の言うことに従わなければ駄目なの」
「従ったら不幸になりましたが?」
「違うわ。離婚せずに一緒に暮らし続ければ、いつかは幸せになれていたのよ」
「そうとは思えません」
「……ああ、もううるさい! 二人共やめろ! 今日はもういい! また、改めて来ることにするから帰るぞ!」
お父様が促すと、お母様は身を縮こまらせて頷いた。
「次があれば良いな」
リファルド様が笑顔で手を振ると、両親はびくりと身体を震わせて足を止めた。
「どうした。帰らないのか」
「……ええ、ああ、はい。帰ります」
大きい体を縮こまらせて、お父様は逃げるように部屋を出ていく。
お母様も一緒に出ていこうとしたけど、振り返って話しかけてきた。
「サブリナちゃん。あなたの幸せはアキーム様と一緒にいることだからね。昔のあなたもそう言っていたわ。そのことを思い出して。それにアキーム様も幸せに思える瞬間は家に帰った時にあなたが出迎えてくれることだと言っていたわ」
アキーム様のことはもうどうでもいいわ。
「昔の私と今の私は違うんです。私の幸せをお母様が勝手に決めないでください。私はお母様のようになりたくないんです」
「……わたしは幸せなのよ。あなたにはがっかりだわ」
お母様は私にそう言うと、リファルド様には一礼して部屋を出ていった。
「君は悪い人間を引き寄せる力でもあるのかもな。非常に興味深い」
「……うう。そんな嫌なことを言わないでくださいませ。好きで引き寄せているわけではないんです。しかも、相手は両親ですよ」
「両親の話は別として、元夫やその家族などのことを言っている。まあ、それだけ心が綺麗なんだろう。あの親と一緒に暮らして、よく悪の道に染まらずに済んだな」
「お母様に似て臆病なだけだと思います」
「でも、君は踏み出すことができただろう。君の母は夫が正義だと思い込んでいるようだし、重ねた年月を考えると、目を覚ますのは難しいだろうな」
「もしかしたら、きっかけは私と同じように騙されたのかもしれません」
私にとってアキーム様がヒーローだったように、お母様にとって、お父様はヒーローなんでしょうね。
「君は両親が好きか」
「……こんなことは言いたくないですが、いいえ、です」
「ならいい。さて、まずは君の両親に今回のお礼をせねばならないな」
お礼って、絶対に嫌な意味のほうよね。
笑顔のリファルド様を見て、敵にまわしたくないなとつくづく思った。
でも、今の私が過去よりも幸せだと思うことは間違いないと思った。
(アキーム視点)
「どうして離婚が成立しているんだ!」
離婚に納得できなかった僕は、役所に行って文句を言ってみた。
でも、離婚届はサブリナが提出したものであり、オルドリン家に確認したところ、母上が離婚することは間違いないと答えたそうで、今更、破棄はできないと言われた。
「ねえ、アキーム様。もういいじゃないの。このままわたしを養ってよ」
ベルはあれだけサブリナを攻撃することに必死だったのに、ワイズ公爵家を敵にまわしたくないからか、今は僕からサブリナに近づけないようにしてくる。
「君は勝手だよ。勝手すぎる。僕はサブリナに情が湧いていたんだ! あんなに僕の思い通りに動く女性はいない! 別れるつもりはなかったんだ!」
「サブリナの代わりならわたしにだってなれるわよ! だから、もう、屋敷に帰りましょうよ」
ベルが僕の腕を掴んで言った。
「簡単に言ってくれるが、君はサブリナのように従順な女性になれるのか?」
「なるわ! なってみせるわよ!」
「それなら、僕のやろうとしていることを邪魔するな。サブリナはこんなことで文句を言わなかったよ」
「文句じゃないわ! あなたのためを思って言っているのよ!」
「僕のため? 違うだろ。君自身のためだ」
役所の出入り口で喧嘩をしていたからか、多くの人の視線が集まっていることに気づいた僕は、彼女の言う通り、屋敷に戻ることにした。
サブリナがどこにいるかはわかっている。
だから、迎えに行くための準備を整えないとならない。
それに、母上に確認しなければならないこともある。
馬車を停めている場所に向かっている途中で、見知った顔に出会ったので声をかけようとすると、なぜか、背を向けて元来た道を戻っていく。
どういうことだ。
僕に気づかなかったんだろうか。
一人目はそう思ったが、二人目に声をかけようとした時、その人物から言われた。
「今、君と仲良くしているところを見られたい奴なんていないよ。だから、悪いけど、話しかけないでくれないか」
そう言った男は、逃げるように僕から離れていく。
「そんな……、おかしいだろう。 僕は離婚されたんだぞ!?」
逃げる男の背中に向かって叫ぶと、彼は振り返らずに答える。
「離婚されるようなことをしたんだから当たり前だろう! 君は多くの女性の憧れの的だったが、今ではただの浮気男扱いだ」
「う、浮気なんて僕はしていない!」
「もう諦めろ。そちらのお嬢さんと仲良くやればいいだろう!」
「ち、違う。僕は離婚するつもりはないんだ!」
信じられない。
どうして、こんなことになるんだよ!?
「アキーム様はわたしに自分のことしか考えていないとおっしゃいましたけど、それはあなたもよね?」
ベルはそう言うと、僕の腕にしがみついた。
「どうして離婚が成立しているんだ!」
離婚に納得できなかった僕は、役所に行って文句を言ってみた。
でも、離婚届はサブリナが提出したものであり、オルドリン家に確認したところ、母上が離婚することは間違いないと答えたそうで、今更、破棄はできないと言われた。
「ねえ、アキーム様。もういいじゃないの。このままわたしを養ってよ」
ベルはあれだけサブリナを攻撃することに必死だったのに、ワイズ公爵家を敵にまわしたくないからか、今は僕からサブリナに近づけないようにしてくる。
「君は勝手だよ。勝手すぎる。僕はサブリナに情が湧いていたんだ! あんなに僕の思い通りに動く女性はいない! 別れるつもりはなかったんだ!」
「サブリナの代わりならわたしにだってなれるわよ! だから、もう、屋敷に帰りましょうよ」
ベルが僕の腕を掴んで言った。
「簡単に言ってくれるが、君はサブリナのように従順な女性になれるのか?」
「なるわ! なってみせるわよ!」
「それなら、僕のやろうとしていることを邪魔するな。サブリナはこんなことで文句を言わなかったよ」
「文句じゃないわ! あなたのためを思って言っているのよ!」
「僕のため? 違うだろ。君自身のためだ」
役所の出入り口で喧嘩をしていたからか、多くの人の視線が集まっていることに気づいた僕は、彼女の言う通り、屋敷に戻ることにした。
サブリナがどこにいるかはわかっている。
だから、迎えに行くための準備を整えないとならない。
それに、母上に確認しなければならないこともある。
馬車を停めている場所に向かっている途中で、見知った顔に出会ったので声をかけようとすると、なぜか、背を向けて元来た道を戻っていく。
どういうことだ。
僕に気づかなかったんだろうか。
一人目はそう思ったが、二人目に声をかけようとした時、その人物から言われた。
「今、君と仲良くしているところを見られたい奴なんていないよ。だから、悪いけど、話しかけないでくれないか」
そう言った男は、逃げるように僕から離れていく。
「そんな……、おかしいだろう。 僕は離婚されたんだぞ!?」
逃げる男の背中に向かって叫ぶと、彼は振り返らずに答える。
「離婚されるようなことをしたんだから当たり前だろう! 君は多くの女性の憧れの的だったが、今ではただの浮気男扱いだ」
「う、浮気なんて僕はしていない!」
「もう諦めろ。そちらのお嬢さんと仲良くやればいいだろう!」
「ち、違う。僕は離婚するつもりはないんだ!」
信じられない。
どうして、こんなことになるんだよ!?
「アキーム様はわたしに自分のことしか考えていないとおっしゃいましたけど、それはあなたもよね?」
ベルはそう言うと、僕の腕にしがみついた。
お父様が管理する領地が増えたと知らされたのは、尻尾を巻いて帰った次の日のことだった。
しかも、お父様は喜んでいるとの話だったので、最初はリファルド様が本当にお礼をしたのかと焦ったけれど、すぐにそうではないことがわかった。
お父様が新たに任された土地は、多くの貴族が管理を放棄した土地で、治安がとても悪い上に、作物が育ちにくい場所だった。
私達が住んでいる国、エスコルン王国は領地の広さによって貴族に課される税金の額が変わる。
だから、お父様は支払う税金が莫大に増えたのだ。
しかも、治安が悪く、その場所を管理しようとした貴族が何人か不審の死を遂げている。
明らかに他殺なのに、証拠がなくて捕まえられない。
それだけ、悪が蔓延っている場所だ。
普通の人がその状態なら、気の毒に思うかもしれない。
でも、お父様の場合はそんな気持ちにならないのはなぜなのかしらね。
薄情な娘だと言われるかもしれないけど、お父様がどうなろうが別にかまわないと思ってしまう。
殺されろとは思わない。
というか、そんな人間にはなりたくない。
だって、私は生きている。
辛い思いを味わってほしいだけだ。
……って、この考えでも酷いわね。
とにかく、仕事が増えたお父様はかなり忙しくなり、私の所へ来る余裕などなくなるでしょう。
お母様も一緒に働くことになるだろうし、私にかまっている時間もないはず。
考えてみたら、夫婦揃って、ここまで何度も来ようとするなんて暇だと言っているようなものだし、仕事を増やされてもしょうがないわね。
いきなり領地が増えるだなんておかしいと思わなかった、お父様が悪いわ。
お父様は執念深いから、これで終わるかはわからない。
でも、なんとかなるでしょう。
お父様達が仕事に追われている間に、私が移動してしまえば良いのだから。
私はゼノンが働いている国で働くことが決まった。
リファルド様が仕事を見つけてくれたのだ。
他国までは、お父様もさすがに追いかけては来れないはず。
税金を納めるためにはお金がいる。
増えた領地の税金を支払うためのお金を工面するためには、他国に行く旅費なんてない。
居場所を知らせる気はないし、私が会いに行かない限りは、もう二度と会うことはないでしょう。
伯父様達とも中々会えなくなるのは寂しいけど、幸せになるためには両親との縁切りが必要だ。
私が離婚してから跡取り問題でも揉めているみたいだから、エイトン子爵家は没落する可能性が高いわね。
あんな人を跡取りにしたから潰れてしまうんだわ。
気持ちを切り替えて、隣国に住むための基礎知識が書かれた本を読んでいると、メイドが部屋にやって来た。
「サブリナ様、オルドリン伯爵からプレゼントが届きましたので返しておきました」
「ありがとう。いつも、ごめんなさい」
頭を下げると、メイドは「それも仕事でございます」と言って微笑んだ。
普通ならばやらなくても良い仕事をしてもらっているんだから、お言葉に甘えているわけにもいかないわ。
そう思っていたところに伯父様がやって来た。
「オルドリン伯爵が自分の姉と一緒に訪ねて来ている」
「……とうとう押しかけてきたんですね」
ため息を吐いた時、屋敷の外から声が聞こえてきた。
「サブリナ! 本当に悪かったよ! 反省してるんだ! 話を聞いてほしい! このとおりだ!」
最悪だわ。
アキーム様は私が彼と会わないとわかっているから、その場で叫ぶことにしたみたいね。
本当に迷惑!
「何なんだ一体」
どうしようか迷っていると、リファルド様が眉間に皺を寄せて、私のところへやって来たのだった。
この作家の他の作品
表紙を見る
彼が浮気をしたのは全て私のせいらしい…。
悪いのは本当に私なの…?
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…